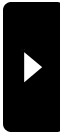2013年04月13日
『未来の住職塾』を終えて(後編:覚悟)
あらら、気がついたら『住職塾』第二期が始まってました。急いでアップしなきゃ・・・。
前編・中編からの続き、最後の後編です。
さて、1年の住職塾を通して、実は最後まで通奏低音のように私に鳴り響いていたのは「お寺とは何か?」「僧侶とは何か?」という問いでした。
もう少し詳しく申し上げるのならば「お寺とは、そもそもどのような起源を持ち、どのような機能を持ってきたのか?」ということと「曹洞宗の僧侶として生きるという事は自分にとってどのようなことになるのか?」ということです。
はずかしながら、今、その2つながらはっきりと答えが出ているわけではありません。(まぁ一生掛かっても出ないかもしれない)
今から一年少し前、この住職塾が始まる前、最初のプレセミナー@光明寺に参加したときのこと。
セミナー冒頭で、真宗学の泰斗 金子大榮先生が書かれた『住職道』による住職の心得が紹介されました。(余談ですが、近代の眼蔵家として夙に有名な岸澤惟安老師と親交があったようです)
即ち、住職とは「仏祖崇敬>学問>教化」であると。
私は、心から「その通り」とは思ったものの、覚悟(=道心と言い換えてもいいかもしれません)が脆弱なばかりに、理念としては受け入れることができるのですが、「じゃあ実際どうしたらよいのか?」「やっぱりイベントとかやるべきでは?」とか、要するに表層的なことばかりが気になっておりました。
しかしながら、やや逆説的に聞こえますが、この住職塾を通して、一見、横文字の経営に於けるテクニカルタームやフレームワークを学ばせてもらったことが、結局はこの2つへの「覚悟」を浮き彫りにした結果となりました。
ここでいう覚悟、というのはつまり、お寺や僧侶ということに「深入する」、「受容する」という覚悟。
あるいは「菩提心」というようなニュアンスもあるかもしれません。要は「どんな状況におかれても、やはり曹洞宗の僧侶でいる」という覚悟。
・・・「え?これって当たり前のことじゃない?」「そんな覚悟もなくて、よく坊さんやっていられるね?」
まぁ確かに、そうかもしれません。
ただ、これって口で言うほど簡単なことでもないのかも。少なくとも私にとっては。
「いやいや、それってあんたがお寺の生まれだからでしょ?」
これも確かにそうかもしれません。
では、自ら出家した方が全て良くて、お寺生まれの僧侶は全て悪いのでしょうか?
『正法眼蔵』「袈裟功徳」巻に、戯れでお袈裟をつけた遊女が、ついには発心し得道するという話もあります。
菩提心を発して出家することを誠に尊いことです。
では、菩提心を発すことだけで良いのでしょうか?1回発動することで完了でしょうか?
その観点から行くと、お寺生まれの人間には、一生掛かっても「まともな僧侶」になれない、と言われているような気がしてしまいます。
また、世俗的な”やる気”に満ちあふれているのが、理想の僧侶でしょうか?
私自身は、「自分が僧侶としてやりたいこと」を大見得切って言うことに、ちょっと違和感があります。
別に悪いことではないと思うのです。
ただ、「お坊さんとしてやりたいこと」を大きく言うと、「自分が”お坊さん”という虎の皮を借りて、やりたいことを正当化しているだけ」という、自分のいやらしさが目についてしまうのです。(これは私だけだと思うけど・・・)
何故こんな風に思えてしまうのか・・・。たぶん、次の話にヒントがあるんだと思います。

+++
いきなり話は変わります。
今年のお正月くらいだったと記憶しておりますが、NHK『プロフェッショナル-仕事の流儀-』で、楽焼の当代 楽吉左右衛門さんが特集されていました。私個人的に(詳しくはありませんが)その歴代の作品、もちろん当代も含めて、が、とても好きなので食い入るように見ておりました。
その中で、非常に印象的な言葉がありました。
曰く「自分の焼き物は、”伝統”と”革新”とが振り子のようになっている。両方があることで、進んでいる」
つまり、吉左右衛門さんの作品って、東京芸大の彫刻科出身ということもあってか、非常に屹立とした感じ、空間を拒絶するような孤高の造形があります。一方で、伝統的な楽焼も見事に踏襲されている。どちらかだけではダメで、どちらもあるから進化している。
まったく、この通りかもしれません。
付言すれば、もし振り子のようなら、実は伝統と革新には境界線があまり意味をなさず、もしかしたら、その概念すらも”とりたたて騒ぐほどのことでもなくなる”のかもしれません。
さりとて僅かにでも軌跡外れれば、振り子の運動ではなくなる。一毫でも外れれば、すでに「楽焼」ではなくなる。
肝要なのは、”振り子になること”。
まさに、以心伝心というか、師や仏祖の行履(あんり=生き様)をそっくり受け継いだとき、そして歩みを始めたときに、好むと好まざると「革新」がはじまる。
じゃあ、”革新”ばかりが目に入り、心にちらつく自分に、はたして”伝統”はあったのか・・・?
すなわち、僧侶の生き方、祖師の行履を学んでいたのか?
本当に偶然ですが、住職塾と同時に『正法眼蔵』の講義を東京に受けに行き始めました。
当時は言語化できなくても、漠然としたイメージがあったのかもしれません。
結果的に自分にとって誠にラッキーだったと思います。もしこれを受けていなければ、住職塾での学びも、もっと表層的なものになっていたかもしれない。また、逆に「一生の学び」を気付かせてくれたのが『正法眼蔵』だったと思います。
+++
で、さっきの話に戻ります。
あまりに有名な一節なので、ご存知の方も多いと思います。
『正法眼蔵』「現成公案」の中に、
「自己をはこびて万法を修証するを迷とす、万法すすみて自己を修証するはさとりなり。」
あるいはまた
「仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己をわするるなり。・・・」
+++
と言うことで、これは自分への戒めと、もしかしたらこれから受講されるされる方にとってお役に立てるかもしれないので、最後のまとめを書いておきます。
1.仏祖崇敬、道心、彼岸寺風にいえば「菩提心に火をつけろ!」は必須アイテム(笑)
2.自らの頭で考えましょう。実は教えてくれること以上に、考えさせられることの方が多いです(涙)
特に「当たり前」のこととしていることこそ、一番危険な罠です。また、学んだことがそのまま”寺業興隆”に繋がる訳ではありません。お金になるとか人が集まるとか、それ以前に”なぜそうしなければならないのか”を考えないといけません。
3.終わりは始まりです。セミナーは終われど、お寺の、そして僧侶としての歩みはこれからです。実行してはじめて意味をなします。共に学ぶ仲間です。そのご縁と行動が何より尊いことです。
・・・口では偉そうなことばっかり言って、実際何にもできてない泰明・・・猛省です
(未来の住職塾に関しての感想は以上です。本当に乱文を最後までお読み下さり、誠にありがとうございました。これはあくまで小原泰明個人の意見ですので、どうぞその点だけご了解ください。このセミナーで出逢えた全ての方に感謝です。 南無帰依仏 南無帰依法 南無帰依僧 合掌)
前編・中編からの続き、最後の後編です。
さて、1年の住職塾を通して、実は最後まで通奏低音のように私に鳴り響いていたのは「お寺とは何か?」「僧侶とは何か?」という問いでした。
もう少し詳しく申し上げるのならば「お寺とは、そもそもどのような起源を持ち、どのような機能を持ってきたのか?」ということと「曹洞宗の僧侶として生きるという事は自分にとってどのようなことになるのか?」ということです。
はずかしながら、今、その2つながらはっきりと答えが出ているわけではありません。(まぁ一生掛かっても出ないかもしれない)
今から一年少し前、この住職塾が始まる前、最初のプレセミナー@光明寺に参加したときのこと。
セミナー冒頭で、真宗学の泰斗 金子大榮先生が書かれた『住職道』による住職の心得が紹介されました。(余談ですが、近代の眼蔵家として夙に有名な岸澤惟安老師と親交があったようです)
即ち、住職とは「仏祖崇敬>学問>教化」であると。
私は、心から「その通り」とは思ったものの、覚悟(=道心と言い換えてもいいかもしれません)が脆弱なばかりに、理念としては受け入れることができるのですが、「じゃあ実際どうしたらよいのか?」「やっぱりイベントとかやるべきでは?」とか、要するに表層的なことばかりが気になっておりました。
しかしながら、やや逆説的に聞こえますが、この住職塾を通して、一見、横文字の経営に於けるテクニカルタームやフレームワークを学ばせてもらったことが、結局はこの2つへの「覚悟」を浮き彫りにした結果となりました。
ここでいう覚悟、というのはつまり、お寺や僧侶ということに「深入する」、「受容する」という覚悟。
あるいは「菩提心」というようなニュアンスもあるかもしれません。要は「どんな状況におかれても、やはり曹洞宗の僧侶でいる」という覚悟。
・・・「え?これって当たり前のことじゃない?」「そんな覚悟もなくて、よく坊さんやっていられるね?」
まぁ確かに、そうかもしれません。
ただ、これって口で言うほど簡単なことでもないのかも。少なくとも私にとっては。
「いやいや、それってあんたがお寺の生まれだからでしょ?」
これも確かにそうかもしれません。
では、自ら出家した方が全て良くて、お寺生まれの僧侶は全て悪いのでしょうか?
『正法眼蔵』「袈裟功徳」巻に、戯れでお袈裟をつけた遊女が、ついには発心し得道するという話もあります。
菩提心を発して出家することを誠に尊いことです。
では、菩提心を発すことだけで良いのでしょうか?1回発動することで完了でしょうか?
その観点から行くと、お寺生まれの人間には、一生掛かっても「まともな僧侶」になれない、と言われているような気がしてしまいます。
また、世俗的な”やる気”に満ちあふれているのが、理想の僧侶でしょうか?
私自身は、「自分が僧侶としてやりたいこと」を大見得切って言うことに、ちょっと違和感があります。
別に悪いことではないと思うのです。
ただ、「お坊さんとしてやりたいこと」を大きく言うと、「自分が”お坊さん”という虎の皮を借りて、やりたいことを正当化しているだけ」という、自分のいやらしさが目についてしまうのです。(これは私だけだと思うけど・・・)
何故こんな風に思えてしまうのか・・・。たぶん、次の話にヒントがあるんだと思います。

+++
いきなり話は変わります。
今年のお正月くらいだったと記憶しておりますが、NHK『プロフェッショナル-仕事の流儀-』で、楽焼の当代 楽吉左右衛門さんが特集されていました。私個人的に(詳しくはありませんが)その歴代の作品、もちろん当代も含めて、が、とても好きなので食い入るように見ておりました。
その中で、非常に印象的な言葉がありました。
曰く「自分の焼き物は、”伝統”と”革新”とが振り子のようになっている。両方があることで、進んでいる」
つまり、吉左右衛門さんの作品って、東京芸大の彫刻科出身ということもあってか、非常に屹立とした感じ、空間を拒絶するような孤高の造形があります。一方で、伝統的な楽焼も見事に踏襲されている。どちらかだけではダメで、どちらもあるから進化している。
まったく、この通りかもしれません。
付言すれば、もし振り子のようなら、実は伝統と革新には境界線があまり意味をなさず、もしかしたら、その概念すらも”とりたたて騒ぐほどのことでもなくなる”のかもしれません。
さりとて僅かにでも軌跡外れれば、振り子の運動ではなくなる。一毫でも外れれば、すでに「楽焼」ではなくなる。
肝要なのは、”振り子になること”。
まさに、以心伝心というか、師や仏祖の行履(あんり=生き様)をそっくり受け継いだとき、そして歩みを始めたときに、好むと好まざると「革新」がはじまる。
じゃあ、”革新”ばかりが目に入り、心にちらつく自分に、はたして”伝統”はあったのか・・・?
すなわち、僧侶の生き方、祖師の行履を学んでいたのか?
本当に偶然ですが、住職塾と同時に『正法眼蔵』の講義を東京に受けに行き始めました。
当時は言語化できなくても、漠然としたイメージがあったのかもしれません。
結果的に自分にとって誠にラッキーだったと思います。もしこれを受けていなければ、住職塾での学びも、もっと表層的なものになっていたかもしれない。また、逆に「一生の学び」を気付かせてくれたのが『正法眼蔵』だったと思います。
+++
で、さっきの話に戻ります。
あまりに有名な一節なので、ご存知の方も多いと思います。
『正法眼蔵』「現成公案」の中に、
「自己をはこびて万法を修証するを迷とす、万法すすみて自己を修証するはさとりなり。」
あるいはまた
「仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己をわするるなり。・・・」
+++
と言うことで、これは自分への戒めと、もしかしたらこれから受講されるされる方にとってお役に立てるかもしれないので、最後のまとめを書いておきます。
1.仏祖崇敬、道心、彼岸寺風にいえば「菩提心に火をつけろ!」は必須アイテム(笑)
2.自らの頭で考えましょう。実は教えてくれること以上に、考えさせられることの方が多いです(涙)
特に「当たり前」のこととしていることこそ、一番危険な罠です。また、学んだことがそのまま”寺業興隆”に繋がる訳ではありません。お金になるとか人が集まるとか、それ以前に”なぜそうしなければならないのか”を考えないといけません。
3.終わりは始まりです。セミナーは終われど、お寺の、そして僧侶としての歩みはこれからです。実行してはじめて意味をなします。共に学ぶ仲間です。そのご縁と行動が何より尊いことです。
・・・口では偉そうなことばっかり言って、実際何にもできてない泰明・・・猛省です

(未来の住職塾に関しての感想は以上です。本当に乱文を最後までお読み下さり、誠にありがとうございました。これはあくまで小原泰明個人の意見ですので、どうぞその点だけご了解ください。このセミナーで出逢えた全ての方に感謝です。 南無帰依仏 南無帰依法 南無帰依僧 合掌)
2013年04月08日
今日は坊さんの「クリスマス」?!
今日は僧侶にとっての「クリスマス」!!
・・・え?!何のこと?と訝しげられましたか?
今日は、ブッダ、つまりお釈迦様のお誕生日とされる日です。
西光寺でも、花御堂(はなみどう)という”赤ちゃんのお釈迦さんをまつる”お堂をたてて、お祝いします。
お像には甘茶をかけてお参りします。
で、先週末。花まつりを記念して、特にお子さんに楽しんで頂けるように「甘茶のディーバッグ+ぬりえセット」を準備し、お持ち頂けるようにセットしたのですが・・・↓

そう、あの天気でお参りの方はほとんど来られず(涙)ですから、たくさ~~~~~ん余っています。
まだお参り頂いていない方は是非!!
いつも同じ事を書いていますが、この「花まつり」(誕生日)と12/8の「成道会」(悟りを開いた日)と2/15の「涅槃会」(亡くなった日)の3つの日は「三仏忌」(さんぶっき)といい、大切な日です。
西光寺では、この三仏忌に『大佛頂萬行首楞嚴陀羅尼』(略して楞嚴咒)というお経を読むのですが・・・泰明はおよそ年に3回しか読まないので、舌カミカミ・・・。永平寺時代は夏の特別修行期間(夏安居、といいます)にて毎日読んでいたので、何とも思わなかったんですが・・・
まったく、修行が足りん!!!
・・・え?!何のこと?と訝しげられましたか?
今日は、ブッダ、つまりお釈迦様のお誕生日とされる日です。
西光寺でも、花御堂(はなみどう)という”赤ちゃんのお釈迦さんをまつる”お堂をたてて、お祝いします。
お像には甘茶をかけてお参りします。
で、先週末。花まつりを記念して、特にお子さんに楽しんで頂けるように「甘茶のディーバッグ+ぬりえセット」を準備し、お持ち頂けるようにセットしたのですが・・・↓

そう、あの天気でお参りの方はほとんど来られず(涙)ですから、たくさ~~~~~ん余っています。
まだお参り頂いていない方は是非!!
いつも同じ事を書いていますが、この「花まつり」(誕生日)と12/8の「成道会」(悟りを開いた日)と2/15の「涅槃会」(亡くなった日)の3つの日は「三仏忌」(さんぶっき)といい、大切な日です。
西光寺では、この三仏忌に『大佛頂萬行首楞嚴陀羅尼』(略して楞嚴咒)というお経を読むのですが・・・泰明はおよそ年に3回しか読まないので、舌カミカミ・・・。永平寺時代は夏の特別修行期間(夏安居、といいます)にて毎日読んでいたので、何とも思わなかったんですが・・・
まったく、修行が足りん!!!
2013年03月28日
『未来の住職塾』を終えて(中編:京都・東京あじくらべ)
前編からのつづきです。
さて中編は、「京都・東京あじくらべ」と題しまして、京都会場の最終回と、翌日の東京第一クラス@光明寺の比較を。
運良く、東京第一の最終回にもお邪魔しましたので、その時の印象を少し。
まず、何というか志が同じ、ということもあるのか、東京会場にもすんなりなじめました(たぶん・・・汗。自分調べ)
たとえ場所や宗派が違っても、気持ちは共有できるのが「住職塾」の良い所。
また、メンバー同士も和気あいあいとしていて、好感が持てます。東京会場でご縁をいただいた方に感謝です。中には、私が以前より拝見していたブログの、当のご本人に偶然お会いできたり、うれしいサプライズもありました。
あ、あと、うれしかったのは、かの有名な光明寺オープンテラスでの昼食。しかも門外漢の私も快く受け入れてくれて、みんなで楽しくランチ。寒かったけど・・・(笑)
ちなみに京都会場のあるメンバーが東京会場を振替受講されたとき「東京会場、飲み会もなしでメッチャ冷たい感じがするわ~(笑)」と仰ってましたが・・・そんなことないですよ!!(>Kさんへ)
余談はさておき、両会場ともに、最終回でありますので、同じように「寺業計画書」の発表があります。
一番思ったのが・・・
「やっぱり人柄が出るわ(笑)」ということ。
もちろん、京都は自分のクラスだから何度も会っているし、ディスカッションとかもしているメンバーなので、みなさんそれぞれのご性格とか、早い話、キャラが分かるんですが、それが計画書にも如実に表れています。
なので、東京会場の方々を拝見していても、はじめてお目に掛かるのに、計画書を拝見していると何となく分かる。しかもその計画をご本人が発表されるわけですので、書いてある文章とか話しぶりとか所作とか、そういうのでもお人柄がにじみ出ているような気がします。これは結構面白い発見でした。
あ、あと東京会場には永平寺の後輩がいらっしゃいました。がんばっている後輩の姿を見られて、なんかうれしかったです

それでですね、ここからが本題です。
これはもしかしたら地域差なのかもしれないし、同じ東京会場でも第一と第二では違うのかもしれないので、一般論化はできません。あくまで私が見た限り、という限定でお願いします。
それは「供養、お参り」に対する考え方の濃淡です。
簡単に言えば、京都会場を受講している方は、割に”供養、お参り”(含む永代供養墓)ということを寺業計画書に多く入れられています。(ちなみに京都市内のお寺の方はいらっしゃいません。メンバーは京都・大阪・兵庫・和歌山・愛知・佐賀など)
逆に、東京会場の方で”供養”を中心に持ってきている方は京都に比して少ない印象を受けました。(東京、静岡、神奈川、秋田など)逆に、イベントが多いような気がしました。
これは決して批判でもなんでもなく、ただ”そうだった”、ということなのですが、私個人的に僧侶としての生き方を考えたときに、大きな、そして避けては通れない問題ではなかろうかと思いました。
もちろん、これはあくまで”寺業計画”であり”僧侶としての人生設計や指針”とは違います。
それから、あえてそんなことを書く必要もないだろう、という考えもあるかもしれません。曰く当たり前なんだから、と。
もしくは、「自分としては供養について現状、ベストの状態だと思っている」と言われた方もいらっしゃったように、それもまた真なり、かもしれません。(ちなみに東京会場でお一方いらっしゃいました)
ただ、少し気になったのが、東京会場のみなさん、けっこう檀家数が多いんですね。(明言は避けますが、京都会場はその10分の1以下の規模のお寺をやり繰りされている方も皆無ではありません。)
そうであれば、供養ってとっても大事なことだと思うんです。だって数(法事や葬儀の件数)が違えば、人々への影響力も違ってくると思うので。(地域差もありましょうから、同じ線上には並べられないとしても)
とは言え、やはり”葬式や法事だけ”というお寺のイメージを払拭したい!そのお気持ちも分かります。何年も前は私もそうでした。
でも、思ったんですが、なんで葬式や法事のイメージを払拭しなければいけないのでしょうか?
やましいことをしている気になる?自信が無いから?何故自信がないのでしょうか?
檀家さんにとって”素晴らしい葬式や法事”を提供し、故人様にも、残された遺族(生者)にも共に安心を与えることができているのなら、感謝されこそすれ、否定される筋合いはありません。
(ただ、”つねに安心を与えられるように儀礼の質を上げる”とか、”自身の信心を涵養する”とか”檀家さんにとって「良い葬儀」とは?”、そうしたことを考え続けることは必要ではないかとは思います。)
それから”ネガティブイメージを払拭したらどうなるのか?”という観点もまた考えるべきかと思います。
「何故僧侶が葬式をするのか?」という意味、そして「どのように僧侶が葬式を担ってきたのか?」という歴史を学ぶことなくしては、これに答えることはできないだろうと思うのです。
ちょっと脱線します。過去に何度も書いたとおり、私には心から尊敬でき、かつ楽しく一緒にお酒を飲める(笑)牧師さんがいらっしゃいます。
その方にもある時、申し上げたのですが、「キリスト教ほど熱心に布教し、かつ葬儀のイメージがない(クリスマスの、単純に言えばポジティブなイメージ)宗教が、これだけ活動されて、結果、日本では人口の1%しか信者さんがいないのはどうしてでしょうか?これは単純に布教の仕方云々ではないはずです。
振り返って、うちのお檀家さんでも、例えばお寺の宗派の名前、宗祖の名前、本山、住職の名前、およその経典と内容など言える人は極めてまれです。もしかしたら、それは1%なのかもしれない。だとしたら、もしかしたら、それが日本人の宗教に対する本質ではないでしょうか?」と。
牧師さんも「う~ん」と仰っていましたが(笑)、これは日本人の思考(=日本人論)に直結し、なおかつ歴史を紐解かないと答えられない難しい問題ですね。それから、また更に別の問題もあります。果たして、一つの宗教のみの信仰を持たなければならないとする信仰感は、日本で古来からあったものでしょうか?ついでに、本当に本当に「今、この時代の人々が一番信仰心がないのか?」ということも慎重に見ていかなければなりません。
やや脱線してきましたが、私の言いたいことは”現状を具に見る”ことです。お寺も、周りの関係も、自分自身も。
そこからでしか始まらないし、始められない。(自戒の意味で)
そうしたとき、自分にはお寺や仏教や宗派や宗教や日本の歴史や伝播の過程など、あらゆる面で知っていることがほとんどないことに、愕然としました。自分は何も知らない、ということに気がつかされました。
で、実は最後「後編-覚悟-」に続いていきます。
・・・あっ、その前にスピンオフ記事として、名古屋東別院で行われた『住職塾セミナー』(単回のプレセミナー)についてをアップします。
さて中編は、「京都・東京あじくらべ」と題しまして、京都会場の最終回と、翌日の東京第一クラス@光明寺の比較を。
運良く、東京第一の最終回にもお邪魔しましたので、その時の印象を少し。
まず、何というか志が同じ、ということもあるのか、東京会場にもすんなりなじめました(たぶん・・・汗。自分調べ)
たとえ場所や宗派が違っても、気持ちは共有できるのが「住職塾」の良い所。
また、メンバー同士も和気あいあいとしていて、好感が持てます。東京会場でご縁をいただいた方に感謝です。中には、私が以前より拝見していたブログの、当のご本人に偶然お会いできたり、うれしいサプライズもありました。
あ、あと、うれしかったのは、かの有名な光明寺オープンテラスでの昼食。しかも門外漢の私も快く受け入れてくれて、みんなで楽しくランチ。寒かったけど・・・(笑)
ちなみに京都会場のあるメンバーが東京会場を振替受講されたとき「東京会場、飲み会もなしでメッチャ冷たい感じがするわ~(笑)」と仰ってましたが・・・そんなことないですよ!!(>Kさんへ)
余談はさておき、両会場ともに、最終回でありますので、同じように「寺業計画書」の発表があります。
一番思ったのが・・・
「やっぱり人柄が出るわ(笑)」ということ。
もちろん、京都は自分のクラスだから何度も会っているし、ディスカッションとかもしているメンバーなので、みなさんそれぞれのご性格とか、早い話、キャラが分かるんですが、それが計画書にも如実に表れています。
なので、東京会場の方々を拝見していても、はじめてお目に掛かるのに、計画書を拝見していると何となく分かる。しかもその計画をご本人が発表されるわけですので、書いてある文章とか話しぶりとか所作とか、そういうのでもお人柄がにじみ出ているような気がします。これは結構面白い発見でした。
あ、あと東京会場には永平寺の後輩がいらっしゃいました。がんばっている後輩の姿を見られて、なんかうれしかったです


それでですね、ここからが本題です。
これはもしかしたら地域差なのかもしれないし、同じ東京会場でも第一と第二では違うのかもしれないので、一般論化はできません。あくまで私が見た限り、という限定でお願いします。
それは「供養、お参り」に対する考え方の濃淡です。
簡単に言えば、京都会場を受講している方は、割に”供養、お参り”(含む永代供養墓)ということを寺業計画書に多く入れられています。(ちなみに京都市内のお寺の方はいらっしゃいません。メンバーは京都・大阪・兵庫・和歌山・愛知・佐賀など)
逆に、東京会場の方で”供養”を中心に持ってきている方は京都に比して少ない印象を受けました。(東京、静岡、神奈川、秋田など)逆に、イベントが多いような気がしました。
これは決して批判でもなんでもなく、ただ”そうだった”、ということなのですが、私個人的に僧侶としての生き方を考えたときに、大きな、そして避けては通れない問題ではなかろうかと思いました。
もちろん、これはあくまで”寺業計画”であり”僧侶としての人生設計や指針”とは違います。
それから、あえてそんなことを書く必要もないだろう、という考えもあるかもしれません。曰く当たり前なんだから、と。
もしくは、「自分としては供養について現状、ベストの状態だと思っている」と言われた方もいらっしゃったように、それもまた真なり、かもしれません。(ちなみに東京会場でお一方いらっしゃいました)
ただ、少し気になったのが、東京会場のみなさん、けっこう檀家数が多いんですね。(明言は避けますが、京都会場はその10分の1以下の規模のお寺をやり繰りされている方も皆無ではありません。)
そうであれば、供養ってとっても大事なことだと思うんです。だって数(法事や葬儀の件数)が違えば、人々への影響力も違ってくると思うので。(地域差もありましょうから、同じ線上には並べられないとしても)
とは言え、やはり”葬式や法事だけ”というお寺のイメージを払拭したい!そのお気持ちも分かります。何年も前は私もそうでした。
でも、思ったんですが、なんで葬式や法事のイメージを払拭しなければいけないのでしょうか?
やましいことをしている気になる?自信が無いから?何故自信がないのでしょうか?
檀家さんにとって”素晴らしい葬式や法事”を提供し、故人様にも、残された遺族(生者)にも共に安心を与えることができているのなら、感謝されこそすれ、否定される筋合いはありません。
(ただ、”つねに安心を与えられるように儀礼の質を上げる”とか、”自身の信心を涵養する”とか”檀家さんにとって「良い葬儀」とは?”、そうしたことを考え続けることは必要ではないかとは思います。)
それから”ネガティブイメージを払拭したらどうなるのか?”という観点もまた考えるべきかと思います。
「何故僧侶が葬式をするのか?」という意味、そして「どのように僧侶が葬式を担ってきたのか?」という歴史を学ぶことなくしては、これに答えることはできないだろうと思うのです。
ちょっと脱線します。過去に何度も書いたとおり、私には心から尊敬でき、かつ楽しく一緒にお酒を飲める(笑)牧師さんがいらっしゃいます。
その方にもある時、申し上げたのですが、「キリスト教ほど熱心に布教し、かつ葬儀のイメージがない(クリスマスの、単純に言えばポジティブなイメージ)宗教が、これだけ活動されて、結果、日本では人口の1%しか信者さんがいないのはどうしてでしょうか?これは単純に布教の仕方云々ではないはずです。
振り返って、うちのお檀家さんでも、例えばお寺の宗派の名前、宗祖の名前、本山、住職の名前、およその経典と内容など言える人は極めてまれです。もしかしたら、それは1%なのかもしれない。だとしたら、もしかしたら、それが日本人の宗教に対する本質ではないでしょうか?」と。
牧師さんも「う~ん」と仰っていましたが(笑)、これは日本人の思考(=日本人論)に直結し、なおかつ歴史を紐解かないと答えられない難しい問題ですね。それから、また更に別の問題もあります。果たして、一つの宗教のみの信仰を持たなければならないとする信仰感は、日本で古来からあったものでしょうか?ついでに、本当に本当に「今、この時代の人々が一番信仰心がないのか?」ということも慎重に見ていかなければなりません。
やや脱線してきましたが、私の言いたいことは”現状を具に見る”ことです。お寺も、周りの関係も、自分自身も。
そこからでしか始まらないし、始められない。(自戒の意味で)
そうしたとき、自分にはお寺や仏教や宗派や宗教や日本の歴史や伝播の過程など、あらゆる面で知っていることがほとんどないことに、愕然としました。自分は何も知らない、ということに気がつかされました。
で、実は最後「後編-覚悟-」に続いていきます。
・・・あっ、その前にスピンオフ記事として、名古屋東別院で行われた『住職塾セミナー』(単回のプレセミナー)についてをアップします。
2013年03月26日
『未来の住職塾』を終えて(前編:感想)
昨年(H24)5月に開講した、超宗派のセミナー「未来の住職塾」の第一期が全ての会場で終わりました。松本さんはじめ、講師の方々、スタッフの方、受講生のみなさん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
また、第二期募集も、今日で締め切りですね。
「”未来の住職塾”って何?」って方はここをクリック
当初は東京と京都会場のみ、それも一クラス5~7人くらい集まればいいや、くらいに思っていらしたそうなのですが、このセミナー、ふたを開けてみたら全国5会場に展開し、一期生は70名を超える人数だったようです。
私は京都会場を受講していたのですが、第一期の最初に始まり、そして最初に終わりました。
さて、これから2~3回にわたってこの『未来の住職塾』に対する総括的な記事を書いていこうと思います。いままで受講された方はどうぞ忌憚のないご意見を頂戴したく、またこれから受講される方(二期生)には拙い文章ですが、ほんの少しでもお役に立てれば、と思って記します。
で、泰明にしては珍しく、すでに構想が決まっておりまして(笑)以下のように記します。

と言うことで、まず<前編>です。
得たものや、感想ですが、既にいろんなところで書いているので、端的に行きたいと思います。
1.素晴らしい仲間
・・・これはもう、得たものの筆頭です。
と言うか、私のこの感想文が第二期のパンフレットに載っているくらいでして・・・。
例えば、「お寺ってどういうところなのかな。坊さんの生き方ってどういうものだと思う?」とか「●●って法要があるんだけど、もっと認知度を上げて、宗祖の教えを敷衍するためにはどうしたらいいかな?」とか、そんな話(相談)が気軽に出来る僧侶の仲間っていますか?僕はほとんどいません。申し訳ないけど・・・。
本気で腹を割って話せる仲間ができました。宗派が違うとか同じとか、殆ど意味をなさない。
本気でお寺のこと、仏教のことを考えている仲間がいる。それで充分。
ちなみに・・・泰明は、全6回、毎度講義後にクラスメイトと飲んでました!
1回目と最後6回目の講義後は、事務局主催で懇親会が行われましたが、中4回は”自主的に”(笑)
講義後、終電まで4時間くらいずっと語り合ってました。6時間あまりの講義を受けて、その後で飲み会。自分でもよく体力が保つと思うけど、それでも語り足りなかったよね?(←って誰に言ってんでしょうか)
あ、あと、”同級生のウチに遊びにいく”じゃないけど、クラスメイトのお寺に遊びに行く予定も既にあります★楽しみ!
2.らせん的成長
・・・ちょっと抽象的。実は、これ松本塾長の談。
すなわち、それこそ円を描くように、住職塾を受ける前の自分と、今の自分は、本当のところ表立って何かが変わったわけではありません。やっていることと言えば、相も変わらず、お葬式に法事、役員会に掃除・坐禅、青年会の活動やら何やら。
でも、表だっては変化がないかもしれません。しかし、お寺の事業や在り方一つ一つ具に見直し、本当に悩んで考えて、或いは見つめてきたことなので、同じ事をやっていても実は感覚的には”何かが違う”気がします。もしかしたら、気のせいかもしれませんが・・・(汗)
で、このらせんの意味はこうです。
つまり前段の”同じ事をやってる”のはらせんを上からみたところ。一年経って円を描くが如く、また同じ場所に戻ってきた。
しかしながら、後段”何かが違う”のは、らせんを横から見たところ。一回り成長している(ような気が・・・)ということです。
これは言い得て妙だと、ひどく得心したのですが、その通りかと思います。
3.相手に気持ちや考えを伝えること
・・・これ、私は結構苦手だったりします。今でもそうだけど。でも住職塾のお蔭で、ググッと成長したような気がします。
私の感想って、セミナーの内容にあまり触れていません。
まぁ有料講座だから(笑)ってのも有るんですが、書きませんでした。
テキストとかワークとか、ディスカッションとか、すごいクオリティだと思うし、次々現れる課題に対して、楽しく、どきどきしながら打ち込めました。
ちなみに来期から講座を担当されるあるスタッフの方曰く「日本広しといえども、大企業ですらこれだけのクオリティを保ったセミナーはそうそうない」とのこと。私はこのスタッフの方にお会いして、心底感激したのですが、その話はまた今度。
で、何が言いたいかというと、ある意味、住職塾は”マネジメントに関する、何か最新の、イノヴェイティブな理論とか、やり方”を教えてくれるのではありません。もちろん、そういう側面も多分にあります。
ただ、それって畢竟、「いかにして考え(=教え、=安心)や気持ちを、上手に、深く相手に伝えていくか」ということに集約されるかもしれません。だからこそ、どうしたら伝えられるかを考えるためのフレームワークだったと思う。(もちろん、それだけじゃないですけどね)
これは、既にウチのお寺の護持会活動や、酉の市にも活かされていると実感しております。
4.覚悟・・・最後になります。
これが一番、書きづらいです。上手く表現できるかどうか。
詳しくは、<後編>とも大きくリンクするので、そこで述べたいと思います。
ごく簡単に言えば「おまえは坊さんとして生きていく覚悟があるのか?」ということです。
その覚悟を何度も確かめられ、問われたような講義でした。そうする中で、確かとは言い難いけれど、何ものかを掴んだ、そんなニュアンスです。
・・・とりあえず、前編はここまでにします。
また、第二期募集も、今日で締め切りですね。
「”未来の住職塾”って何?」って方はここをクリック
当初は東京と京都会場のみ、それも一クラス5~7人くらい集まればいいや、くらいに思っていらしたそうなのですが、このセミナー、ふたを開けてみたら全国5会場に展開し、一期生は70名を超える人数だったようです。
私は京都会場を受講していたのですが、第一期の最初に始まり、そして最初に終わりました。
さて、これから2~3回にわたってこの『未来の住職塾』に対する総括的な記事を書いていこうと思います。いままで受講された方はどうぞ忌憚のないご意見を頂戴したく、またこれから受講される方(二期生)には拙い文章ですが、ほんの少しでもお役に立てれば、と思って記します。
で、泰明にしては珍しく、すでに構想が決まっておりまして(笑)以下のように記します。
<前編>
【得たもの】
・・・住職塾を通して何を得られたのか&感想
<中編>
【京都・東京あじくらべ】
・・・京都の翌日行われた東京第一での最終講座との比較
<後編>
【覚悟 -そして第二期へ-】
・・・う~ん、何だろ。第二期の方へってことくらいでしょうか

と言うことで、まず<前編>です。
得たものや、感想ですが、既にいろんなところで書いているので、端的に行きたいと思います。
1.素晴らしい仲間
・・・これはもう、得たものの筆頭です。
と言うか、私のこの感想文が第二期のパンフレットに載っているくらいでして・・・。
例えば、「お寺ってどういうところなのかな。坊さんの生き方ってどういうものだと思う?」とか「●●って法要があるんだけど、もっと認知度を上げて、宗祖の教えを敷衍するためにはどうしたらいいかな?」とか、そんな話(相談)が気軽に出来る僧侶の仲間っていますか?僕はほとんどいません。申し訳ないけど・・・。
本気で腹を割って話せる仲間ができました。宗派が違うとか同じとか、殆ど意味をなさない。
本気でお寺のこと、仏教のことを考えている仲間がいる。それで充分。
ちなみに・・・泰明は、全6回、毎度講義後にクラスメイトと飲んでました!
1回目と最後6回目の講義後は、事務局主催で懇親会が行われましたが、中4回は”自主的に”(笑)
講義後、終電まで4時間くらいずっと語り合ってました。6時間あまりの講義を受けて、その後で飲み会。自分でもよく体力が保つと思うけど、それでも語り足りなかったよね?(←って誰に言ってんでしょうか)
あ、あと、”同級生のウチに遊びにいく”じゃないけど、クラスメイトのお寺に遊びに行く予定も既にあります★楽しみ!
2.らせん的成長
・・・ちょっと抽象的。実は、これ松本塾長の談。
すなわち、それこそ円を描くように、住職塾を受ける前の自分と、今の自分は、本当のところ表立って何かが変わったわけではありません。やっていることと言えば、相も変わらず、お葬式に法事、役員会に掃除・坐禅、青年会の活動やら何やら。
でも、表だっては変化がないかもしれません。しかし、お寺の事業や在り方一つ一つ具に見直し、本当に悩んで考えて、或いは見つめてきたことなので、同じ事をやっていても実は感覚的には”何かが違う”気がします。もしかしたら、気のせいかもしれませんが・・・(汗)
で、このらせんの意味はこうです。
つまり前段の”同じ事をやってる”のはらせんを上からみたところ。一年経って円を描くが如く、また同じ場所に戻ってきた。
しかしながら、後段”何かが違う”のは、らせんを横から見たところ。一回り成長している(ような気が・・・)ということです。
これは言い得て妙だと、ひどく得心したのですが、その通りかと思います。
3.相手に気持ちや考えを伝えること
・・・これ、私は結構苦手だったりします。今でもそうだけど。でも住職塾のお蔭で、ググッと成長したような気がします。
私の感想って、セミナーの内容にあまり触れていません。
まぁ有料講座だから(笑)ってのも有るんですが、書きませんでした。
テキストとかワークとか、ディスカッションとか、すごいクオリティだと思うし、次々現れる課題に対して、楽しく、どきどきしながら打ち込めました。
ちなみに来期から講座を担当されるあるスタッフの方曰く「日本広しといえども、大企業ですらこれだけのクオリティを保ったセミナーはそうそうない」とのこと。私はこのスタッフの方にお会いして、心底感激したのですが、その話はまた今度。
で、何が言いたいかというと、ある意味、住職塾は”マネジメントに関する、何か最新の、イノヴェイティブな理論とか、やり方”を教えてくれるのではありません。もちろん、そういう側面も多分にあります。
ただ、それって畢竟、「いかにして考え(=教え、=安心)や気持ちを、上手に、深く相手に伝えていくか」ということに集約されるかもしれません。だからこそ、どうしたら伝えられるかを考えるためのフレームワークだったと思う。(もちろん、それだけじゃないですけどね)
これは、既にウチのお寺の護持会活動や、酉の市にも活かされていると実感しております。
4.覚悟・・・最後になります。
これが一番、書きづらいです。上手く表現できるかどうか。
詳しくは、<後編>とも大きくリンクするので、そこで述べたいと思います。
ごく簡単に言えば「おまえは坊さんとして生きていく覚悟があるのか?」ということです。
その覚悟を何度も確かめられ、問われたような講義でした。そうする中で、確かとは言い難いけれど、何ものかを掴んだ、そんなニュアンスです。
・・・とりあえず、前編はここまでにします。
2013年03月22日
え~?!!これってホントに●●料理なの?
明日でお彼岸も終わりですね。
西光寺では、彼岸入りの日、17日に本堂にて春彼岸の法要をいたしました。
当日は日曜日で、とても天気が良く、暖かでしたので、大変多くの方にお参り頂き、有り難かったです。
反面、本堂に入りきらず、廊下でお立ち頂きました方もいらっしゃいました。申し訳なかったです。
さて、お彼岸というのは・・・去年も書いたかもしれませんが、元々は苦しみ多き迷いの世界=此岸(この世界)から、安楽なる世界、悟りの世界(彼岸)へわたる、ということです。般若心経の正式名称は「まかはんにゃ”はらみた”しんぎょう」といいますが、このカッコの”はらみた”の語源がパーラミター、つまり”到彼岸”(彼岸にいたる)ということなのです。
そういえば、お彼岸中にお墓参りに来られた方が、「まぁ、どのお墓もきれいにお花が替えられているわね~」と仰っていました。それだけ、みなさんお参りに来て下さったということ。誠に有り難いことです。
いきなり、お彼岸とは全然関係ない話になります。
私、泰明は料理が趣味なのですが、前々からやってみたかったことがあります。
それは、「フレンチやイタリアンのエッセンスを採り入れた、おしゃれな精進料理ができないか?」ということです。
「いや、なんでフレンチなの?」とか突っ込まないで下さい。長くなるので(笑)そのうち書くかもしれませんが。
精進料理というのは、もともと修行僧が精進し、修行をつつがなく行い、仏道を成就するために定められた料理で、中国で完成された様式とされています。
簡単に言えば、ヴィーガン、つまり、お肉、お魚、卵、牛乳など乳製品を使いません。(これだってかなりすごいことです)
それに加えて、五葷(ごくん)と呼ばれる野菜も使いません。これは実はいろいろに定義されますが、一般的には「にんにく」「たまねぎ」「にら」「らっきょう」「あさつき」などを指します。
(ちなみに、インドで生まれたブッダ=お釈迦様のころは、お肉も魚も食べていたようです)
なんで精進料理が生まれたのか、これまた興味深いのですが、私もまだ勉強不足で、あまりお話はできません・・・ごめんなさい。
ただ、インドから仏教が中国に入り、陰陽五行説の影響を受けたこと(=中国的聖性)。そもそも托鉢して回るという習慣が中国に根付いておらず、いきおい、自分たちで調理をしなければならなかったこと。お寺の所在する位置が、山奥に入っていったこと、などが指摘されます。
私が修行させてもらっていた大本山永平寺でもこれに準じた料理で、朝はおかゆとごま塩、たくあん。昼は一汁一菜。夜は一汁二菜といった感じ。出汁は椎茸と昆布。野菜の煮物などがおかずです。ごま豆腐が有名ですが、実は、あれは修行僧用ではなく、お客様用のお料理だったりします。
話を戻して。
なんと言っても、こんなモダン精進料理(?)、レシピがないので(笑)、よく買っている『料理通信』のバックナンバーをぱらぱら見たり、かつて行ったpassage53の料理を思い出したり、行ってみたいお店No1の大阪"la cime"高田シェフのブログを覗いたり。(高田シェフの盛りつけ、ホントに芸術的です)結構考えました。
で、今回はとりあえず、二つ作ってみました。

<カリフラワーとクルミのロースト、カレー風味(パプリカマヨネーズ)>
ゆでたカリフラワーとクルミ、イタリアンパセリをカレー粉、塩で和えたもの。「え?カレー粉って精進??」いわゆるルウは動物油脂やタマネギなどが入っていますが、カレー粉って要するにターメリックとかを調合しただけなので、実は五葷や動物性のものは入っていないんですね。
「え?マヨネーズって卵使ってんじゃん」そうなんですが、これは豆乳をピーナッツオイルで乳化させ、そこへフレンチマスタード、白ワインヴィネガーと塩で味を調整し、パプリカパウダーを入れて色を作りました。
このマヨネーズ、本当に美味しい!本物そっくりのテクスチャーです。お皿の赤いのがパプリカパウダー。

<ジャガイモのピューレ、枝豆のセルクル仕立て バジルソースとラディッシュ>
こっちはFacebookで先行アップしました(笑)
ジャガイモを豆乳でのばして、ドライタイムとキャトルエピス(南仏料理で使われる4種=キャトルのスパイスを調合したもの)を振って香り付け。
バジルソースはいわゆる”ジェノベーゼ”みたいですが、ニンニクとチーズを使わず、カシューナッツとオリーブオイルだけで作っています。
セルクル(丸い型)でソースとジャガイモを。ラディッシュで同じく”円”を意識してみました。
もしリクエストが有れば、また作ってみたいと思います。
・
・・
・・・え?味はどうかって?
是非、お作りになってお試し下さい★
西光寺では、彼岸入りの日、17日に本堂にて春彼岸の法要をいたしました。
当日は日曜日で、とても天気が良く、暖かでしたので、大変多くの方にお参り頂き、有り難かったです。
反面、本堂に入りきらず、廊下でお立ち頂きました方もいらっしゃいました。申し訳なかったです。
さて、お彼岸というのは・・・去年も書いたかもしれませんが、元々は苦しみ多き迷いの世界=此岸(この世界)から、安楽なる世界、悟りの世界(彼岸)へわたる、ということです。般若心経の正式名称は「まかはんにゃ”はらみた”しんぎょう」といいますが、このカッコの”はらみた”の語源がパーラミター、つまり”到彼岸”(彼岸にいたる)ということなのです。
そういえば、お彼岸中にお墓参りに来られた方が、「まぁ、どのお墓もきれいにお花が替えられているわね~」と仰っていました。それだけ、みなさんお参りに来て下さったということ。誠に有り難いことです。
いきなり、お彼岸とは全然関係ない話になります。
私、泰明は料理が趣味なのですが、前々からやってみたかったことがあります。
それは、「フレンチやイタリアンのエッセンスを採り入れた、おしゃれな精進料理ができないか?」ということです。
「いや、なんでフレンチなの?」とか突っ込まないで下さい。長くなるので(笑)そのうち書くかもしれませんが。
精進料理というのは、もともと修行僧が精進し、修行をつつがなく行い、仏道を成就するために定められた料理で、中国で完成された様式とされています。
簡単に言えば、ヴィーガン、つまり、お肉、お魚、卵、牛乳など乳製品を使いません。(これだってかなりすごいことです)
それに加えて、五葷(ごくん)と呼ばれる野菜も使いません。これは実はいろいろに定義されますが、一般的には「にんにく」「たまねぎ」「にら」「らっきょう」「あさつき」などを指します。
(ちなみに、インドで生まれたブッダ=お釈迦様のころは、お肉も魚も食べていたようです)
なんで精進料理が生まれたのか、これまた興味深いのですが、私もまだ勉強不足で、あまりお話はできません・・・ごめんなさい。
ただ、インドから仏教が中国に入り、陰陽五行説の影響を受けたこと(=中国的聖性)。そもそも托鉢して回るという習慣が中国に根付いておらず、いきおい、自分たちで調理をしなければならなかったこと。お寺の所在する位置が、山奥に入っていったこと、などが指摘されます。
私が修行させてもらっていた大本山永平寺でもこれに準じた料理で、朝はおかゆとごま塩、たくあん。昼は一汁一菜。夜は一汁二菜といった感じ。出汁は椎茸と昆布。野菜の煮物などがおかずです。ごま豆腐が有名ですが、実は、あれは修行僧用ではなく、お客様用のお料理だったりします。
話を戻して。
なんと言っても、こんなモダン精進料理(?)、レシピがないので(笑)、よく買っている『料理通信』のバックナンバーをぱらぱら見たり、かつて行ったpassage53の料理を思い出したり、行ってみたいお店No1の大阪"la cime"高田シェフのブログを覗いたり。(高田シェフの盛りつけ、ホントに芸術的です)結構考えました。
で、今回はとりあえず、二つ作ってみました。

<カリフラワーとクルミのロースト、カレー風味(パプリカマヨネーズ)>
ゆでたカリフラワーとクルミ、イタリアンパセリをカレー粉、塩で和えたもの。「え?カレー粉って精進??」いわゆるルウは動物油脂やタマネギなどが入っていますが、カレー粉って要するにターメリックとかを調合しただけなので、実は五葷や動物性のものは入っていないんですね。
「え?マヨネーズって卵使ってんじゃん」そうなんですが、これは豆乳をピーナッツオイルで乳化させ、そこへフレンチマスタード、白ワインヴィネガーと塩で味を調整し、パプリカパウダーを入れて色を作りました。
このマヨネーズ、本当に美味しい!本物そっくりのテクスチャーです。お皿の赤いのがパプリカパウダー。

<ジャガイモのピューレ、枝豆のセルクル仕立て バジルソースとラディッシュ>
こっちはFacebookで先行アップしました(笑)
ジャガイモを豆乳でのばして、ドライタイムとキャトルエピス(南仏料理で使われる4種=キャトルのスパイスを調合したもの)を振って香り付け。
バジルソースはいわゆる”ジェノベーゼ”みたいですが、ニンニクとチーズを使わず、カシューナッツとオリーブオイルだけで作っています。
セルクル(丸い型)でソースとジャガイモを。ラディッシュで同じく”円”を意識してみました。
もしリクエストが有れば、また作ってみたいと思います。
・
・・
・・・え?味はどうかって?
是非、お作りになってお試し下さい★
2013年03月15日
その「祈り」に意味はあるのか?
先日、3.11慰霊行脚についてアップしました。
恥ずかしながら、というか蛇足ながら、いくつかの思うことを書いていきたいと思います。

(宮戸島の風景。あまりにも綺麗ですが、後ろを振り向くと、数軒の礎石を残して、堤防、家屋、みな流されております)
+++
行く前のこと。
まず、やはり端的に今回のことを”ブログに書くことが誇示すること”となりはしないか?という疑念がありました。
言ってみれば、これは今回のことに限らないんですけどね。
ただの増上慢、つまり”俺ってこんなに良いことをしたんだぜ!!”的な気持ちが表れてはこないだろうか?、もしくはブログに表記する=誇示しているのではないか、という自問です。もっと言えば、善意を売り物にしている、ということ。
これは、”ないつもり”で向かった電車の中でも、知らず知らずにその頭がもたげてくる。そんな気持ちで行っていないのに、ふとした瞬間に浮かんでしまう。まったく、名利の心は恐ろしいものです。(これ本音)
ただ、くどくなりますが、もう少し丁寧に吟味すると・・・
つまり、”書くことでよく思われたい”あるいは逆に”書くことで「坊主のくせに自慢してやがる」と言われるのを嫌がる”というのは、まったく反対のことを言っているようだけれども、実は「我が身かわいさ」故なのです。この我が身かわいさ、に気付いてしまった・・・克服できているとは口が裂けても言えませんが、少なくとも「気をつけていないと現れてくるのが、この”名利の心、我が身かわいさ”なんだな」とは感じました。
それに、『正法眼蔵随聞記』にも”世俗の法と仏教の法は違うものである。いたずらに、世法を仏法に当てはめるべきではない”というようなことも書かれていたと記憶しております。だから、仏法に生きる僧侶は、仏法に適う生き方を絶えず模索し、実践していかなければならないのでしょうね。
+++
それから、「祈り」に対して、根本的な疑問がありました。
すなわち「祈りって必要か?」ということ。「祈って何になる?」と言い換えてもいいかもしれません。
・・・ずいぶん不信心な発言に聞こえますよね。「坊主のくせに、よくそんなこと言うな」と不快に思われたらすみません。これもしかし、偽らざる本心だったりします。
「祈るってなんだろう」と結構真剣に考えたりしておりました。仏教的に、例えば「祈祷」という言葉があるので、その意味を禅学大辞典とか、織田得能仏教辞典で調べたりとか。・・・結局、よく分かりませんでした。
ただ、一つだけ言えるのは、今までの人生の中で自分は”本当に祈らなければならなかったこと”がほぼ皆無だったかもしれません。
まぁ、これは良いとか悪いとかは言えないのが難しいのですが・・・。
+++
「自分のやっていることは無駄なんじゃないか?」やはり行脚の前にも、考えます。
さて、当日は本当に寒く、前日が10度を優に超えていたのが嘘のようでした。雪は舞い散り、昨夜の一降りだけで10cmは積もっています。
そんな中、出かけた行脚。これは所謂行脚姿をして、手には鈴をもち、お経を唱えながら被災地を歩くもの。
被災した松島のお寺の檀家さんが先導してくださり、ところどころ特に多く亡くなられた場所に於いては、立ち止まり特別なお経を読みます。
瓦礫の山だったところは今は草が生え、何も知らなければ、もしかしたらただの空き地に見えたかもしれません。松林は壊滅的なダメージを受けたとは言え、何本も今なおその姿をたたえていますし、澄み渡った空には悠然と鳥が飛んでいる。口をつくお経が、まるで虚空に吸い込まれて、ただ静寂が残っているだけ、という圧倒的な空虚感すらしてきます。
とにかく、寒かった。また、電車も止まっていたくらい風が強かった。正直、手がかじかんで鈴を落としそうにもなりました。
その刹那、「意味があるとかないとか、それが戯論だったんじゃないか」と思えてきました。それって全部自分が基準。自分が意味があるとおもえば、だれに言われようとあるわけだし。ないものもない。それにしがみついている”自分”。
これは誤解の無いように言いますが「自分が良いと思えば、それでいい」というような幼稚な発想ではありません。
求めてくれる方がいて、提供できる"安心”があるならば、そしてそれが僧侶ができることであれば、やらない理由は一毫もありません。難癖をつけることは、実はそれもある種の我が身の優位性、または”やること、もしくはやらないことに言い訳を考えているだけ”を人に知られんとするからに他ならないのかもしれません。
かつて全国曹洞宗青年会の前会長が、さる講習会で、私共青年僧侶にこのように言われたことが、強く印象に残っています。
「みなさんの周りのお寺さん、とくにご年配の僧侶でも、”ああいうボランティアに従事することが坊さんの本来の活動だとは思わない。もっと他にやることがあるだろ?”と言われる方がいると思います。しかし、私は敢えて言います。それは”全くの戯論”である、と。」
(余談ですが、このあたりのことを含めて『正法眼蔵』「諸悪莫作」という巻が、最近、非常に強い力を持って私にせまってくる様な気がします。”気がします”と逃げているのは、あまりにも難しくて、よく分からないからです。でも、分からなくても「何かがある」ことはよく分かります。また参究してみたいと思います)
+++
法要の中で、啓白文(けいびゃくもん)という文章を読み上げます。
簡単に言えば、これは「法要の趣意書」であり、これを仏の前にて奉読するわけですが、今回、これを読まれたのが、この被災寺院(住職さんの命も建物も全てを失われた)の住職さんの弟さんでありました。
原文は覚えていませんが、途中「どんなに辛いことがあったこの場所だとしても、生き残った人はこの土地を離れないでくれ、生きてくれ。」という意味の言葉が出てきました。
実際、法要に参列された方はもちろん、このお寺のお檀家さんであり、亡き住職のお身内の方であった訳ですが、私が感じたのは”前を向いて生きている”ということでした。(ただし、これは全部がそうだとか、そういう簡単な話ではありません)
言うまでも無く、私が想像できないほどの辛苦を受けてこられたと思います。きっと、この方々も必死に祈り、涙を流され、悲しみにうちひしがれてここまでこられたんだろうと思います。その方々が淡々と、しかししっかりと生きておられる。そのお姿に衝撃に近い感激を受けました。
+++
法要後、遅い昼食をいただきに行きました。
まぁせっかくですから(笑)、名物の牛タンを。当然、僧衣を着たまま
ええ、皆さんご存知の「利久」です★
美味しくいただいて後、会計をしたとき、まだ20代後半とおぼしき若い男の店員さんが、たぶん接客で決められたフレーズであろう「ありがとうございました。またお越し下さい」と言われた後、私の姿をちらっと見られて言いました。
「ご苦労様でした。ありがとうございました。」
私は、この一言に、あの未曾有の震災直後に世界から絶賛された東北の美徳、美しい生き様、即ち自分をよく調え、他人を慮る気持ちが結実されていると感じました。そして私たち僧侶の生き方が、ほんの僅かでも、彼の地の方に安らぎを感じてもらえることができるなら、まだまだやれることはあるだろうと確信したのです。
+++
長文をお読み下さり、本当にありがとうございました。
今回のまとめです。
「祈るだけでは、何もはじまらない。
しかし、祈りからしか、何もはじまらない。」
恥ずかしながら、というか蛇足ながら、いくつかの思うことを書いていきたいと思います。

(宮戸島の風景。あまりにも綺麗ですが、後ろを振り向くと、数軒の礎石を残して、堤防、家屋、みな流されております)
+++
行く前のこと。
まず、やはり端的に今回のことを”ブログに書くことが誇示すること”となりはしないか?という疑念がありました。
言ってみれば、これは今回のことに限らないんですけどね。
「おほよそ菩提心の行願には、菩提心の発不発、行道不行道を世人にしられんことをおもはざるべし、しられざらんといとなむべし。いはんやみずから口称せんや。」『正法眼蔵』「谿声山色」巻
ただの増上慢、つまり”俺ってこんなに良いことをしたんだぜ!!”的な気持ちが表れてはこないだろうか?、もしくはブログに表記する=誇示しているのではないか、という自問です。もっと言えば、善意を売り物にしている、ということ。
これは、”ないつもり”で向かった電車の中でも、知らず知らずにその頭がもたげてくる。そんな気持ちで行っていないのに、ふとした瞬間に浮かんでしまう。まったく、名利の心は恐ろしいものです。(これ本音)
ただ、くどくなりますが、もう少し丁寧に吟味すると・・・
つまり、”書くことでよく思われたい”あるいは逆に”書くことで「坊主のくせに自慢してやがる」と言われるのを嫌がる”というのは、まったく反対のことを言っているようだけれども、実は「我が身かわいさ」故なのです。この我が身かわいさ、に気付いてしまった・・・克服できているとは口が裂けても言えませんが、少なくとも「気をつけていないと現れてくるのが、この”名利の心、我が身かわいさ”なんだな」とは感じました。
それに、『正法眼蔵随聞記』にも”世俗の法と仏教の法は違うものである。いたずらに、世法を仏法に当てはめるべきではない”というようなことも書かれていたと記憶しております。だから、仏法に生きる僧侶は、仏法に適う生き方を絶えず模索し、実践していかなければならないのでしょうね。
+++
それから、「祈り」に対して、根本的な疑問がありました。
すなわち「祈りって必要か?」ということ。「祈って何になる?」と言い換えてもいいかもしれません。
・・・ずいぶん不信心な発言に聞こえますよね。「坊主のくせに、よくそんなこと言うな」と不快に思われたらすみません。これもしかし、偽らざる本心だったりします。
「祈るってなんだろう」と結構真剣に考えたりしておりました。仏教的に、例えば「祈祷」という言葉があるので、その意味を禅学大辞典とか、織田得能仏教辞典で調べたりとか。・・・結局、よく分かりませんでした。
ただ、一つだけ言えるのは、今までの人生の中で自分は”本当に祈らなければならなかったこと”がほぼ皆無だったかもしれません。
まぁ、これは良いとか悪いとかは言えないのが難しいのですが・・・。
+++
「自分のやっていることは無駄なんじゃないか?」やはり行脚の前にも、考えます。
さて、当日は本当に寒く、前日が10度を優に超えていたのが嘘のようでした。雪は舞い散り、昨夜の一降りだけで10cmは積もっています。
そんな中、出かけた行脚。これは所謂行脚姿をして、手には鈴をもち、お経を唱えながら被災地を歩くもの。
被災した松島のお寺の檀家さんが先導してくださり、ところどころ特に多く亡くなられた場所に於いては、立ち止まり特別なお経を読みます。
瓦礫の山だったところは今は草が生え、何も知らなければ、もしかしたらただの空き地に見えたかもしれません。松林は壊滅的なダメージを受けたとは言え、何本も今なおその姿をたたえていますし、澄み渡った空には悠然と鳥が飛んでいる。口をつくお経が、まるで虚空に吸い込まれて、ただ静寂が残っているだけ、という圧倒的な空虚感すらしてきます。
とにかく、寒かった。また、電車も止まっていたくらい風が強かった。正直、手がかじかんで鈴を落としそうにもなりました。
その刹那、「意味があるとかないとか、それが戯論だったんじゃないか」と思えてきました。それって全部自分が基準。自分が意味があるとおもえば、だれに言われようとあるわけだし。ないものもない。それにしがみついている”自分”。
これは誤解の無いように言いますが「自分が良いと思えば、それでいい」というような幼稚な発想ではありません。
求めてくれる方がいて、提供できる"安心”があるならば、そしてそれが僧侶ができることであれば、やらない理由は一毫もありません。難癖をつけることは、実はそれもある種の我が身の優位性、または”やること、もしくはやらないことに言い訳を考えているだけ”を人に知られんとするからに他ならないのかもしれません。
かつて全国曹洞宗青年会の前会長が、さる講習会で、私共青年僧侶にこのように言われたことが、強く印象に残っています。
「みなさんの周りのお寺さん、とくにご年配の僧侶でも、”ああいうボランティアに従事することが坊さんの本来の活動だとは思わない。もっと他にやることがあるだろ?”と言われる方がいると思います。しかし、私は敢えて言います。それは”全くの戯論”である、と。」
(余談ですが、このあたりのことを含めて『正法眼蔵』「諸悪莫作」という巻が、最近、非常に強い力を持って私にせまってくる様な気がします。”気がします”と逃げているのは、あまりにも難しくて、よく分からないからです。でも、分からなくても「何かがある」ことはよく分かります。また参究してみたいと思います)
+++
法要の中で、啓白文(けいびゃくもん)という文章を読み上げます。
簡単に言えば、これは「法要の趣意書」であり、これを仏の前にて奉読するわけですが、今回、これを読まれたのが、この被災寺院(住職さんの命も建物も全てを失われた)の住職さんの弟さんでありました。
原文は覚えていませんが、途中「どんなに辛いことがあったこの場所だとしても、生き残った人はこの土地を離れないでくれ、生きてくれ。」という意味の言葉が出てきました。
実際、法要に参列された方はもちろん、このお寺のお檀家さんであり、亡き住職のお身内の方であった訳ですが、私が感じたのは”前を向いて生きている”ということでした。(ただし、これは全部がそうだとか、そういう簡単な話ではありません)
言うまでも無く、私が想像できないほどの辛苦を受けてこられたと思います。きっと、この方々も必死に祈り、涙を流され、悲しみにうちひしがれてここまでこられたんだろうと思います。その方々が淡々と、しかししっかりと生きておられる。そのお姿に衝撃に近い感激を受けました。
+++
法要後、遅い昼食をいただきに行きました。
まぁせっかくですから(笑)、名物の牛タンを。当然、僧衣を着たまま

ええ、皆さんご存知の「利久」です★
美味しくいただいて後、会計をしたとき、まだ20代後半とおぼしき若い男の店員さんが、たぶん接客で決められたフレーズであろう「ありがとうございました。またお越し下さい」と言われた後、私の姿をちらっと見られて言いました。
「ご苦労様でした。ありがとうございました。」
私は、この一言に、あの未曾有の震災直後に世界から絶賛された東北の美徳、美しい生き様、即ち自分をよく調え、他人を慮る気持ちが結実されていると感じました。そして私たち僧侶の生き方が、ほんの僅かでも、彼の地の方に安らぎを感じてもらえることができるなら、まだまだやれることはあるだろうと確信したのです。
+++
長文をお読み下さり、本当にありがとうございました。
今回のまとめです。
「祈るだけでは、何もはじまらない。
しかし、祈りからしか、何もはじまらない。」