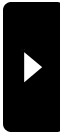2013年05月09日
そうかい、そうかい、総会。
またブログの更新をサボってしまいました・・・。何かと慌ただしくて、すっかりご無沙汰です。読んで下さっている方(特に檀家さま)には申し訳なく思っています。(ホントです)
さて、ここ2週間は、何らかの総会やら会議やらが多くありました。
坊さんって、お経読んでるだけのイメージがあるかと思いますが、意外にお経を読んでる時間は長くありません(笑)
一ヶ寺の住職ともなれば、宗教法人法では代表役員ですし(従ってそれに準じた業務があります)、それ以外に、教区会(宗派によって定義が異なりますが、曹洞宗では「同宗近隣寺院の会」)、法類会(そのお寺の歴史的繋がりのある寺院の会)、市町村の仏教会(たいていは伝統仏教教団で構成される)とか、宗教者連絡会(通常は仏教、神道やキリスト教など)など、程度の差こそあれ、結構いろんな組織に所属しているんですね。
先日は、ここ西光寺にて、東三河曹洞宗青年会の総会がありました。(下の写真参照)
もう何度も書いているので、ご存知の方も多いかと思いますが、曹洞宗青年会は、原則40歳以下の僧侶で構成され、この東三河一円に住する若手僧侶60名弱で組織されます。
2年任期で役員交代があり、ちょうど一年前に泰明もお役を頂戴しました。
活動としては、東日本大震災などのボランティア活動や坐禅会、僧侶対象の研修会などを行っています。
今年は5月26日(もうすぐですね)に、大きな記念大会があります。愛知岐阜三重静岡4県にまたがる10の青年会が一堂に集い、檀家さんや僧侶向けの式典を行います。
担当は輪番制(順繰り)で、今回の担当は、私たちの東三河曹洞宗青年会です。そして・・・この式典の司会を、私不肖泰明めがつとめることになっています。(内心、どきどきです)
この大会のチケットもありますので、また告知しますね。

その翌日は、25年度、第一回目の護持会役員会でした。
護持会(ごじかい)というのは、各お寺の檀家さんで構成される会のことです。会長は檀家さんの中から選出され、名前の通り”護持=お寺を守り、たもつ”ことを目的としています。それだけでなく、大本山への旅行や、各種のイベントなども護持会の協力のもと、行っています。
西光寺の護持会は、十数年間、有名無実化しておりました。2年前に、新会長を選出し、役員さんも大幅に増員しました。
中々泰明が至らないものですから、役員さん始め、檀家さんにもご迷惑をお掛けしております。人間で言ったら2歳児ですから(笑)
しかし、ゆっくりとですが、確実に活動が歩んでいるという手応えはあります。ひとえに役員さんのお蔭です。無償でご奉仕いただいている役員さんには、感謝の言葉もありません。
「もう2年か」と思う一方「まだ2年」という想いもあります。
お寺のため、檀家さんの為に、少しでも良い活動にしていきたいと思っています。
GWの中日は、酉の市関係のことで、さる方にお会いしてきました。詳しいことはもう少し決まってからじゃないと、皆さんにもご報告できないのですが(のどまで出かかっているけど・・・笑)、ともあれ、「お寺」という枠組みを超えた、社会的にも意義のある活動をしよう、という流れです。
実は、4月の一ヶ月は、ほとんどこのために傾注していたと言っても過言ではない日々でした。ブログ放置もこれが原因だったかもしれません。でも、とりあえずは一山越えた感があります。
さてまた昨日は、泰明が住職をさせていただいている豊川市のお寺(満目院)関係の会議でした。いつも思うのは、西光寺と比べて「やっぱり土地柄ってあるなぁ」ということと、「どこにでもすごい(立派な)坊さんはいるなぁ」ということです。
会議以上に、懇親会でのお話に深く感銘を受ける泰明でした。
今日は今日で、これから青年会の会議です。さっきの記念大会についての会議。
何しろ、とても大きなホールですし、記念講演には、『ほんまでっかTV』でおなじみの武田邦彦教授もお招きしているので、司会の責任は重大です(笑)
長々すみません。
最後に、護持会役員会が終わった後、会長さんから頂いた言葉を書いておきます。
「あなたが『お寺は葬式や法事だけの場所じゃない。生きている人、縁ある人に、より充実した人生を送って欲しい』と思っていろいろ活動したい気持ちはよく分かるよ。
ちょっとずつだよ、泰明さん。コツコツと継続していくことさ」
本当に有り難いです。西光寺は檀家さんに恵まれているなぁ、としみじみ思います。 合掌
さて、ここ2週間は、何らかの総会やら会議やらが多くありました。
坊さんって、お経読んでるだけのイメージがあるかと思いますが、意外にお経を読んでる時間は長くありません(笑)
一ヶ寺の住職ともなれば、宗教法人法では代表役員ですし(従ってそれに準じた業務があります)、それ以外に、教区会(宗派によって定義が異なりますが、曹洞宗では「同宗近隣寺院の会」)、法類会(そのお寺の歴史的繋がりのある寺院の会)、市町村の仏教会(たいていは伝統仏教教団で構成される)とか、宗教者連絡会(通常は仏教、神道やキリスト教など)など、程度の差こそあれ、結構いろんな組織に所属しているんですね。
先日は、ここ西光寺にて、東三河曹洞宗青年会の総会がありました。(下の写真参照)
もう何度も書いているので、ご存知の方も多いかと思いますが、曹洞宗青年会は、原則40歳以下の僧侶で構成され、この東三河一円に住する若手僧侶60名弱で組織されます。
2年任期で役員交代があり、ちょうど一年前に泰明もお役を頂戴しました。
活動としては、東日本大震災などのボランティア活動や坐禅会、僧侶対象の研修会などを行っています。
今年は5月26日(もうすぐですね)に、大きな記念大会があります。愛知岐阜三重静岡4県にまたがる10の青年会が一堂に集い、檀家さんや僧侶向けの式典を行います。
担当は輪番制(順繰り)で、今回の担当は、私たちの東三河曹洞宗青年会です。そして・・・この式典の司会を、私不肖泰明めがつとめることになっています。(内心、どきどきです)
この大会のチケットもありますので、また告知しますね。

その翌日は、25年度、第一回目の護持会役員会でした。
護持会(ごじかい)というのは、各お寺の檀家さんで構成される会のことです。会長は檀家さんの中から選出され、名前の通り”護持=お寺を守り、たもつ”ことを目的としています。それだけでなく、大本山への旅行や、各種のイベントなども護持会の協力のもと、行っています。
西光寺の護持会は、十数年間、有名無実化しておりました。2年前に、新会長を選出し、役員さんも大幅に増員しました。
中々泰明が至らないものですから、役員さん始め、檀家さんにもご迷惑をお掛けしております。人間で言ったら2歳児ですから(笑)
しかし、ゆっくりとですが、確実に活動が歩んでいるという手応えはあります。ひとえに役員さんのお蔭です。無償でご奉仕いただいている役員さんには、感謝の言葉もありません。
「もう2年か」と思う一方「まだ2年」という想いもあります。
お寺のため、檀家さんの為に、少しでも良い活動にしていきたいと思っています。
GWの中日は、酉の市関係のことで、さる方にお会いしてきました。詳しいことはもう少し決まってからじゃないと、皆さんにもご報告できないのですが(のどまで出かかっているけど・・・笑)、ともあれ、「お寺」という枠組みを超えた、社会的にも意義のある活動をしよう、という流れです。
実は、4月の一ヶ月は、ほとんどこのために傾注していたと言っても過言ではない日々でした。ブログ放置もこれが原因だったかもしれません。でも、とりあえずは一山越えた感があります。
さてまた昨日は、泰明が住職をさせていただいている豊川市のお寺(満目院)関係の会議でした。いつも思うのは、西光寺と比べて「やっぱり土地柄ってあるなぁ」ということと、「どこにでもすごい(立派な)坊さんはいるなぁ」ということです。
会議以上に、懇親会でのお話に深く感銘を受ける泰明でした。
今日は今日で、これから青年会の会議です。さっきの記念大会についての会議。
何しろ、とても大きなホールですし、記念講演には、『ほんまでっかTV』でおなじみの武田邦彦教授もお招きしているので、司会の責任は重大です(笑)
長々すみません。
最後に、護持会役員会が終わった後、会長さんから頂いた言葉を書いておきます。
「あなたが『お寺は葬式や法事だけの場所じゃない。生きている人、縁ある人に、より充実した人生を送って欲しい』と思っていろいろ活動したい気持ちはよく分かるよ。
ちょっとずつだよ、泰明さん。コツコツと継続していくことさ」
本当に有り難いです。西光寺は檀家さんに恵まれているなぁ、としみじみ思います。 合掌
2013年04月04日
【スピンオフ】住職塾セミナー@東別院での話

住職塾に関する記事を連載しておりますが、ここでスピンオフ記事として、名古屋の東別院にて行われた、住職塾のイントロダクション的講座、『住職塾セミナー』について書きたいと思います。(実はオマケ的に書いていたのですが、結構濃い目の内容になってしまいました・・・笑)
このセミナーは、住職塾に興味のある方を対象とした2時間程度のプレセミナーで、このときは30人ほどの方が来ていました。
本当にたまたまなんですが、私がブログを拝見していた、同じ豊橋市のお寺さんも来られていて、そこで初めてお目にかかれたのでした。もちろん、宗派も違いますし、初対面です。でもこういうご縁が、住職塾らしい(笑)
さて、前回の記事に「来期から講座を担当される素晴らしいあるスタッフの方」について、心底感激したと書きました。
この方は、日本の大手企業のコンサルティングを手がけられ、さらに、誰もが知っている有名IT企業にも籍を置かれていた、超がいっぱいつく(笑)優秀な方です。しかも私と同じ年(?!!)
曰く、
「日本の現状を見てきて、
1.お金が原動力になる時代は終わり(智恵や意欲など無形の価値こそ力)
2.商品やサービスはすぐに陳腐化する
3.「人づくり」に関する社会的機能の衰退
という事を感じた。
自分が、ある仏教系大学のコンサルティングをしていたときに、仏教の可能性に気がついた。仏教がダメになるなら、日本がダメになる。」(超要約してます)
懇親会でも少しお話をさせていただく機会があったのですが、とにかく前職の実情が想像を絶するほど過酷。「よく生きてこられたなぁ」と心配になってしまうほど。でも、このように、日本のある意味トップの方が、仏教の可能性に気がついて下さり、そして賭けてくれている。これって私にとっては、すごく心強いです。つまり、坊さんが「人生お金じゃないですよ。スキルや知識じゃないですよ」と声をからしても「いやいや、社会人経験のない奴に言われたくないわ」みたいに一蹴されてしまうんですよね(涙)
と、いうか、それ以上に、「僧侶・在家」という枠組みの新たなフェーズ(いや、実際のところは新しくもないんだそうですが・・・)、新しい関係性、つまり、”僧侶を養うことで功徳を積み、安心を得る、という本来の役割をもう少し拡大解釈した「僧侶=お寺のよきパートナー、アドバイザー、コンサルタント」”という一歩進んだ関係を提示しつつあるのかも、と内心ではとても期待しております。(詳しく書くと長くなるので、今日は割愛します)
閑話休題。
セミナーの質疑応答の際、”お寺の音楽イベント”についての質問がありました。
それを聞いていた時に、ちょっと思いだしたことがあって。
何というか、「あぁ、やっぱりね」みたいな。実は一年前の光明寺でのプレセミナーでも、内容は違うけれど、音楽イベントに関する質問がでていました。
面白いことに、『未来の住職塾』をやっているうちに、こうした○○イベント的な話って、受講生同士あんまりしなくなるんですよね。何というか、そこの部分にはあまり関心がなくなるというか。
自分でも恥ずかしいことなので、ちょっと表現がうまく出来ないんですが、「お寺のイベント」に対する思いって、受講前は「何かイベントしないと、お寺が衰退してしまう」とか「人が集まらないと」みたいな、要は”変な危機感を募らせた”もので、間違った救いをイベントに求めてしまってました。
言うなれば、イベントは”救世主的機能を持つ、何だか分からないけど強力なアイテム”として見てしまっている。さらに言うなら、イベントをしたことで”今までとは違う”とか”一人でも多く来てくれたら安心”といった、これまた変な満足感がある(苦笑)イベントに使われている、というような。
でも、受講していくうちに、イベントに対する考え方そのものが変化してきて、例えばもしイベントをするのなら(そもそもイベントにウェイトを置いていないので)、仏教的な意味合いや機能、誰に届けたくて、どんな成果があるか、ということに関心が向いてくる。”イベントをまさに仏教の方便として使う”、ようはイベントは、数ある1つの選択肢に過ぎなくなってくる感覚。
これって考えてみれば、至極当たり前で何の不思議もないんですが、やっぱり変な危機感があると、前述のようにおかしな思考に陥ってしまうんですよね(自分のことなので、尚更恥ずかしいですが・・・)と、まぁそういう訳で、イベント救世主論(?)はだれもしなくなる。
で、偶然、拝見していた真言宗のお寺さんが、素晴らしい記事を書かれていました。
http://www.hasedera.net/blog/2013/03/post_319.html
特にココ↓(引用させていただきます)
住職というのは、その縁起に伝えられる開山開基の人々の宗教的なテーマを、より意識的に、自覚的に、選択的に継承し、そのテーマをリフレインし、その動機づけを我が動機として本願を地域社会や時代に向けて具体化し、また個人においてはその本願を生き(ようとす)るのが、責務というか定めなのではないだろうか。
でも、寺づくり、開かれた寺院という言葉が独り歩きして、受けの良い、イベント性のある行事や、あるいは社会参加する仏教(エンゲイジド・ブッディズム)でありたいと急ぐあまりに、本尊の本願とはかけ離れた活動に熱中してしまうとしたら、空疎なことになってしまうと思う。
・・・もう、まったくその通りとしか言いようがない。
敢えて言えば、別に本尊様に限らず、宗旨、開山、開祖と置き換えてもよいのかも、と私は思います。(これすら当たり前ですが・・・)とにかく回り道をして、時間をくって、でも本当に心からこの意見に賛同できるようになったのは、逆に住職塾のお蔭かもしれません。
そもそも”(うちの)お寺じゃなくても一向に差し支えないイベント”なら、はじめからやる必要などないのです。彼岸寺風にいえば「そこに仏教はあるのか?」ということです。
ちょっと矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、"だから今まで通りで良いのだ"とか"新しいことをすべきではない"ということを言いたいのではありません。
その”新しいこと”はもしかしたら仏教的にとても意義在ることで、それが今後何十年続くスタンダードになるようなこともあるでしょう。ただ、私個人にはそのようなエポックメイキングなことを創り出すのは到底無理ですし、そんなことが簡単に生まれるならば、私とは比較にならないほど聡明な僧侶が五万といる訳ですから、とうの昔に誰かが生み出してくれているはずですし…。
お寺、と一口に言っても、機能的なものは一つではありません。一般の方からすれば基本的には「お墓があって法事や葬式をしてもらう場所」だろうと思います。付け加えるならば「観光で行く所」とか。
ただ、私たち僧侶にとっては、それだけではないはずです。聞法の道場だったり、ご祈祷寺だったり、叢林という機能もあるでしょう。
そう考えていくと、そもそも"お寺って何?"という視点からはじめなければならないと私は思っていました。
また、仮にイベントをした場合、「仏教を伝えたい」という気持ちがありますよね。ではその”伝えるべき仏教”は自分にあるか?体現しているのだろうか?ただ教科書を丸暗記したような話をしていないだろうか・・・。
また”何をもって「広まる」ことを意味するのか”とか。
さらに言えば、”仏教を広める”ことがどの範囲、射程で言っているのか?とか。広めることの意義は??
勿論、「梵天勧請」の話もあるし、宗教法人法(第一章1条2「・・・教義を広め、儀式行事を行い・・・」)というのもあるし・・・。でも道元禅師には師匠の如浄禅師から言われた「一箇半箇を接得せよ」って言葉もあったり。
そんな折、出会った文があります。
「はじめて発心するときは、他人のために法をもとめず、名利をなげすてきたる。名利をもとむるにあらず、ただひとすぢに得道をこころざす。かつて国王大臣の恭敬供養をまつこと、期せざるものなり(中略)
しかあるを、おろかなる人は、たとひ道心ありといへども、はやく本志をわすれて、あやまりて人天の供養をまちて、仏法の功徳いたれりとよろこぶ。国王大臣の帰依しきりなれば、わがみちの現成とおもへり。これは学道の一魔なり。
あはれむこころわするべからずといふも、よろこぶことなかるべし。」
『正法眼蔵』「谿声山色」巻
本当に、住職塾は考えさせられます(笑)
(蛇足)上記の部分、ラフな現代語訳です。
「(僧侶が)はじめて”出家しよう”との思いを起こすときは、他人のためにすることではなく、まして自分の名誉のためでもない。名誉や名声など求めず、ただひたすらに仏道の成就をこころざす。国王や大臣といった権力者の帰依を期待することなど、まったく思わないものだ。(中略)
しかし、愚かな人は、たとえ出家の心があっても、早々にその志を忘れて、誤って世間の人が尊敬してくれるのをまって、それが仏教の功徳が現れた、とよろこぶ。権力者が帰依してくれたことが、そのまま自分の仏道の達成だと勘違いしてしまう。これは間違っている。権力者をふくめ、世間の人を哀れむ心を忘れてはいけないが、しかし、自分に付き従うことを喜ぶべきではないのである」
2013年03月15日
その「祈り」に意味はあるのか?
先日、3.11慰霊行脚についてアップしました。
恥ずかしながら、というか蛇足ながら、いくつかの思うことを書いていきたいと思います。

(宮戸島の風景。あまりにも綺麗ですが、後ろを振り向くと、数軒の礎石を残して、堤防、家屋、みな流されております)
+++
行く前のこと。
まず、やはり端的に今回のことを”ブログに書くことが誇示すること”となりはしないか?という疑念がありました。
言ってみれば、これは今回のことに限らないんですけどね。
ただの増上慢、つまり”俺ってこんなに良いことをしたんだぜ!!”的な気持ちが表れてはこないだろうか?、もしくはブログに表記する=誇示しているのではないか、という自問です。もっと言えば、善意を売り物にしている、ということ。
これは、”ないつもり”で向かった電車の中でも、知らず知らずにその頭がもたげてくる。そんな気持ちで行っていないのに、ふとした瞬間に浮かんでしまう。まったく、名利の心は恐ろしいものです。(これ本音)
ただ、くどくなりますが、もう少し丁寧に吟味すると・・・
つまり、”書くことでよく思われたい”あるいは逆に”書くことで「坊主のくせに自慢してやがる」と言われるのを嫌がる”というのは、まったく反対のことを言っているようだけれども、実は「我が身かわいさ」故なのです。この我が身かわいさ、に気付いてしまった・・・克服できているとは口が裂けても言えませんが、少なくとも「気をつけていないと現れてくるのが、この”名利の心、我が身かわいさ”なんだな」とは感じました。
それに、『正法眼蔵随聞記』にも”世俗の法と仏教の法は違うものである。いたずらに、世法を仏法に当てはめるべきではない”というようなことも書かれていたと記憶しております。だから、仏法に生きる僧侶は、仏法に適う生き方を絶えず模索し、実践していかなければならないのでしょうね。
+++
それから、「祈り」に対して、根本的な疑問がありました。
すなわち「祈りって必要か?」ということ。「祈って何になる?」と言い換えてもいいかもしれません。
・・・ずいぶん不信心な発言に聞こえますよね。「坊主のくせに、よくそんなこと言うな」と不快に思われたらすみません。これもしかし、偽らざる本心だったりします。
「祈るってなんだろう」と結構真剣に考えたりしておりました。仏教的に、例えば「祈祷」という言葉があるので、その意味を禅学大辞典とか、織田得能仏教辞典で調べたりとか。・・・結局、よく分かりませんでした。
ただ、一つだけ言えるのは、今までの人生の中で自分は”本当に祈らなければならなかったこと”がほぼ皆無だったかもしれません。
まぁ、これは良いとか悪いとかは言えないのが難しいのですが・・・。
+++
「自分のやっていることは無駄なんじゃないか?」やはり行脚の前にも、考えます。
さて、当日は本当に寒く、前日が10度を優に超えていたのが嘘のようでした。雪は舞い散り、昨夜の一降りだけで10cmは積もっています。
そんな中、出かけた行脚。これは所謂行脚姿をして、手には鈴をもち、お経を唱えながら被災地を歩くもの。
被災した松島のお寺の檀家さんが先導してくださり、ところどころ特に多く亡くなられた場所に於いては、立ち止まり特別なお経を読みます。
瓦礫の山だったところは今は草が生え、何も知らなければ、もしかしたらただの空き地に見えたかもしれません。松林は壊滅的なダメージを受けたとは言え、何本も今なおその姿をたたえていますし、澄み渡った空には悠然と鳥が飛んでいる。口をつくお経が、まるで虚空に吸い込まれて、ただ静寂が残っているだけ、という圧倒的な空虚感すらしてきます。
とにかく、寒かった。また、電車も止まっていたくらい風が強かった。正直、手がかじかんで鈴を落としそうにもなりました。
その刹那、「意味があるとかないとか、それが戯論だったんじゃないか」と思えてきました。それって全部自分が基準。自分が意味があるとおもえば、だれに言われようとあるわけだし。ないものもない。それにしがみついている”自分”。
これは誤解の無いように言いますが「自分が良いと思えば、それでいい」というような幼稚な発想ではありません。
求めてくれる方がいて、提供できる"安心”があるならば、そしてそれが僧侶ができることであれば、やらない理由は一毫もありません。難癖をつけることは、実はそれもある種の我が身の優位性、または”やること、もしくはやらないことに言い訳を考えているだけ”を人に知られんとするからに他ならないのかもしれません。
かつて全国曹洞宗青年会の前会長が、さる講習会で、私共青年僧侶にこのように言われたことが、強く印象に残っています。
「みなさんの周りのお寺さん、とくにご年配の僧侶でも、”ああいうボランティアに従事することが坊さんの本来の活動だとは思わない。もっと他にやることがあるだろ?”と言われる方がいると思います。しかし、私は敢えて言います。それは”全くの戯論”である、と。」
(余談ですが、このあたりのことを含めて『正法眼蔵』「諸悪莫作」という巻が、最近、非常に強い力を持って私にせまってくる様な気がします。”気がします”と逃げているのは、あまりにも難しくて、よく分からないからです。でも、分からなくても「何かがある」ことはよく分かります。また参究してみたいと思います)
+++
法要の中で、啓白文(けいびゃくもん)という文章を読み上げます。
簡単に言えば、これは「法要の趣意書」であり、これを仏の前にて奉読するわけですが、今回、これを読まれたのが、この被災寺院(住職さんの命も建物も全てを失われた)の住職さんの弟さんでありました。
原文は覚えていませんが、途中「どんなに辛いことがあったこの場所だとしても、生き残った人はこの土地を離れないでくれ、生きてくれ。」という意味の言葉が出てきました。
実際、法要に参列された方はもちろん、このお寺のお檀家さんであり、亡き住職のお身内の方であった訳ですが、私が感じたのは”前を向いて生きている”ということでした。(ただし、これは全部がそうだとか、そういう簡単な話ではありません)
言うまでも無く、私が想像できないほどの辛苦を受けてこられたと思います。きっと、この方々も必死に祈り、涙を流され、悲しみにうちひしがれてここまでこられたんだろうと思います。その方々が淡々と、しかししっかりと生きておられる。そのお姿に衝撃に近い感激を受けました。
+++
法要後、遅い昼食をいただきに行きました。
まぁせっかくですから(笑)、名物の牛タンを。当然、僧衣を着たまま
ええ、皆さんご存知の「利久」です★
美味しくいただいて後、会計をしたとき、まだ20代後半とおぼしき若い男の店員さんが、たぶん接客で決められたフレーズであろう「ありがとうございました。またお越し下さい」と言われた後、私の姿をちらっと見られて言いました。
「ご苦労様でした。ありがとうございました。」
私は、この一言に、あの未曾有の震災直後に世界から絶賛された東北の美徳、美しい生き様、即ち自分をよく調え、他人を慮る気持ちが結実されていると感じました。そして私たち僧侶の生き方が、ほんの僅かでも、彼の地の方に安らぎを感じてもらえることができるなら、まだまだやれることはあるだろうと確信したのです。
+++
長文をお読み下さり、本当にありがとうございました。
今回のまとめです。
「祈るだけでは、何もはじまらない。
しかし、祈りからしか、何もはじまらない。」
恥ずかしながら、というか蛇足ながら、いくつかの思うことを書いていきたいと思います。

(宮戸島の風景。あまりにも綺麗ですが、後ろを振り向くと、数軒の礎石を残して、堤防、家屋、みな流されております)
+++
行く前のこと。
まず、やはり端的に今回のことを”ブログに書くことが誇示すること”となりはしないか?という疑念がありました。
言ってみれば、これは今回のことに限らないんですけどね。
「おほよそ菩提心の行願には、菩提心の発不発、行道不行道を世人にしられんことをおもはざるべし、しられざらんといとなむべし。いはんやみずから口称せんや。」『正法眼蔵』「谿声山色」巻
ただの増上慢、つまり”俺ってこんなに良いことをしたんだぜ!!”的な気持ちが表れてはこないだろうか?、もしくはブログに表記する=誇示しているのではないか、という自問です。もっと言えば、善意を売り物にしている、ということ。
これは、”ないつもり”で向かった電車の中でも、知らず知らずにその頭がもたげてくる。そんな気持ちで行っていないのに、ふとした瞬間に浮かんでしまう。まったく、名利の心は恐ろしいものです。(これ本音)
ただ、くどくなりますが、もう少し丁寧に吟味すると・・・
つまり、”書くことでよく思われたい”あるいは逆に”書くことで「坊主のくせに自慢してやがる」と言われるのを嫌がる”というのは、まったく反対のことを言っているようだけれども、実は「我が身かわいさ」故なのです。この我が身かわいさ、に気付いてしまった・・・克服できているとは口が裂けても言えませんが、少なくとも「気をつけていないと現れてくるのが、この”名利の心、我が身かわいさ”なんだな」とは感じました。
それに、『正法眼蔵随聞記』にも”世俗の法と仏教の法は違うものである。いたずらに、世法を仏法に当てはめるべきではない”というようなことも書かれていたと記憶しております。だから、仏法に生きる僧侶は、仏法に適う生き方を絶えず模索し、実践していかなければならないのでしょうね。
+++
それから、「祈り」に対して、根本的な疑問がありました。
すなわち「祈りって必要か?」ということ。「祈って何になる?」と言い換えてもいいかもしれません。
・・・ずいぶん不信心な発言に聞こえますよね。「坊主のくせに、よくそんなこと言うな」と不快に思われたらすみません。これもしかし、偽らざる本心だったりします。
「祈るってなんだろう」と結構真剣に考えたりしておりました。仏教的に、例えば「祈祷」という言葉があるので、その意味を禅学大辞典とか、織田得能仏教辞典で調べたりとか。・・・結局、よく分かりませんでした。
ただ、一つだけ言えるのは、今までの人生の中で自分は”本当に祈らなければならなかったこと”がほぼ皆無だったかもしれません。
まぁ、これは良いとか悪いとかは言えないのが難しいのですが・・・。
+++
「自分のやっていることは無駄なんじゃないか?」やはり行脚の前にも、考えます。
さて、当日は本当に寒く、前日が10度を優に超えていたのが嘘のようでした。雪は舞い散り、昨夜の一降りだけで10cmは積もっています。
そんな中、出かけた行脚。これは所謂行脚姿をして、手には鈴をもち、お経を唱えながら被災地を歩くもの。
被災した松島のお寺の檀家さんが先導してくださり、ところどころ特に多く亡くなられた場所に於いては、立ち止まり特別なお経を読みます。
瓦礫の山だったところは今は草が生え、何も知らなければ、もしかしたらただの空き地に見えたかもしれません。松林は壊滅的なダメージを受けたとは言え、何本も今なおその姿をたたえていますし、澄み渡った空には悠然と鳥が飛んでいる。口をつくお経が、まるで虚空に吸い込まれて、ただ静寂が残っているだけ、という圧倒的な空虚感すらしてきます。
とにかく、寒かった。また、電車も止まっていたくらい風が強かった。正直、手がかじかんで鈴を落としそうにもなりました。
その刹那、「意味があるとかないとか、それが戯論だったんじゃないか」と思えてきました。それって全部自分が基準。自分が意味があるとおもえば、だれに言われようとあるわけだし。ないものもない。それにしがみついている”自分”。
これは誤解の無いように言いますが「自分が良いと思えば、それでいい」というような幼稚な発想ではありません。
求めてくれる方がいて、提供できる"安心”があるならば、そしてそれが僧侶ができることであれば、やらない理由は一毫もありません。難癖をつけることは、実はそれもある種の我が身の優位性、または”やること、もしくはやらないことに言い訳を考えているだけ”を人に知られんとするからに他ならないのかもしれません。
かつて全国曹洞宗青年会の前会長が、さる講習会で、私共青年僧侶にこのように言われたことが、強く印象に残っています。
「みなさんの周りのお寺さん、とくにご年配の僧侶でも、”ああいうボランティアに従事することが坊さんの本来の活動だとは思わない。もっと他にやることがあるだろ?”と言われる方がいると思います。しかし、私は敢えて言います。それは”全くの戯論”である、と。」
(余談ですが、このあたりのことを含めて『正法眼蔵』「諸悪莫作」という巻が、最近、非常に強い力を持って私にせまってくる様な気がします。”気がします”と逃げているのは、あまりにも難しくて、よく分からないからです。でも、分からなくても「何かがある」ことはよく分かります。また参究してみたいと思います)
+++
法要の中で、啓白文(けいびゃくもん)という文章を読み上げます。
簡単に言えば、これは「法要の趣意書」であり、これを仏の前にて奉読するわけですが、今回、これを読まれたのが、この被災寺院(住職さんの命も建物も全てを失われた)の住職さんの弟さんでありました。
原文は覚えていませんが、途中「どんなに辛いことがあったこの場所だとしても、生き残った人はこの土地を離れないでくれ、生きてくれ。」という意味の言葉が出てきました。
実際、法要に参列された方はもちろん、このお寺のお檀家さんであり、亡き住職のお身内の方であった訳ですが、私が感じたのは”前を向いて生きている”ということでした。(ただし、これは全部がそうだとか、そういう簡単な話ではありません)
言うまでも無く、私が想像できないほどの辛苦を受けてこられたと思います。きっと、この方々も必死に祈り、涙を流され、悲しみにうちひしがれてここまでこられたんだろうと思います。その方々が淡々と、しかししっかりと生きておられる。そのお姿に衝撃に近い感激を受けました。
+++
法要後、遅い昼食をいただきに行きました。
まぁせっかくですから(笑)、名物の牛タンを。当然、僧衣を着たまま

ええ、皆さんご存知の「利久」です★
美味しくいただいて後、会計をしたとき、まだ20代後半とおぼしき若い男の店員さんが、たぶん接客で決められたフレーズであろう「ありがとうございました。またお越し下さい」と言われた後、私の姿をちらっと見られて言いました。
「ご苦労様でした。ありがとうございました。」
私は、この一言に、あの未曾有の震災直後に世界から絶賛された東北の美徳、美しい生き様、即ち自分をよく調え、他人を慮る気持ちが結実されていると感じました。そして私たち僧侶の生き方が、ほんの僅かでも、彼の地の方に安らぎを感じてもらえることができるなら、まだまだやれることはあるだろうと確信したのです。
+++
長文をお読み下さり、本当にありがとうございました。
今回のまとめです。
「祈るだけでは、何もはじまらない。
しかし、祈りからしか、何もはじまらない。」
2013年03月10日
これから東北(松島)入りします
いまから仙台経由で松島まで行ってきます。
明日の3.11 三回忌慰霊の行脚と法要に参加する為です。
これは、私が幹事を務めさせて頂いている声明会(=お経読み方練習会)と複数の声明会がジョイントして集結し、おつとめするというもの。
文字通り、行脚(=網代傘に手甲、脚絆という出で立ちで歩く)姿で、沿岸部を歩きながらお経を唱えます。
その後は、津波でご住職のお命が奪われた東松島のお寺にて慰霊法要です。
詳細は後日。
明日の3.11 三回忌慰霊の行脚と法要に参加する為です。
これは、私が幹事を務めさせて頂いている声明会(=お経読み方練習会)と複数の声明会がジョイントして集結し、おつとめするというもの。
文字通り、行脚(=網代傘に手甲、脚絆という出で立ちで歩く)姿で、沿岸部を歩きながらお経を唱えます。
その後は、津波でご住職のお命が奪われた東松島のお寺にて慰霊法要です。
詳細は後日。
2013年02月09日
笑う門には福来たる -落語と大般若祈祷会-
あらら、また時間が空いてしまいました。
先日を振り返って。
2月4日、この日は立春。西光寺では、毎年この日に「大般若祈祷会(だいはんにゃきとうえ)」を行います。
これは、檀家さま皆さまの一年の無事、無病息災などをお祈りするというもの。
特に、600巻(巻、と書いてありますが、実際は巻物ではなく、蛇腹折り)の大般若経典をパラパラとめくり(=転読、てんどく、と言います)その功徳をもって、無事を祈るというものです。
この日はちょっと天候が悪く、そして寒かったのでお参りの方は平年より若干少ないかな、といった感じでした。お参り頂いた方にはお足元のお悪い中をお出かけ頂き、感謝しております。
さて、今年は初めて法要後に”落語寄席”をしました。
この前日に、昨年NHKで放送された「落語deブッダ」の録画を再見していたのですが、改めて気付いたことに、古典落語”書き割り盗人”が仏教の謂う”空”の思想を現しているのだとか。
「さすが釈先生!」と思いつつ、今回の法要にびったりじゃん!と、にんまり。
大般若経典(=空の思想を説く)と落語会とのマッチングとタイミングの良さに内心ほくほくしながら、翌日の法話ネタにしたのでした(笑)

で、この日は豊橋天狗連より鶴橋減滅渡(つるはしへるめっと)さんをお迎えしての高座。
「・・・あれ、この話どこかで聞いたことがある!」と思ったら果たして「崇徳院」という古典でした。(泰明は勉強不足でタイトルまでは分かりませんでした)さすがにセミプロの呼び声高い減滅渡さん、素晴らしかったです。
古典のおもしろさって、素人の私にはよく分かりませんが、多分「同じ話でも噺家によって切り口が違う」ところにあるのではないでしょうか?
たとえは違うかもしれませんが、クラシックに於けるコンダクターみたいな(違うか・・・)
或いは、名曲のカバーとかも。
メロディ(ストーリー)は知っていても、その方の個性やカラーがしっかり反映される所に、職人芸たる良さがにじみ出るのではないでしょうか。
あ、そうそう、泰明個人的には桂枝雀さんが好きなんですが、ネット情報に依ると「枝雀さんが好きな人は、たいてい心が病んでいる」そうな。そういえば私のギターの先生も「見ていて重くなる」って仰ってたっけ。
とほほ・・・。
先日を振り返って。
2月4日、この日は立春。西光寺では、毎年この日に「大般若祈祷会(だいはんにゃきとうえ)」を行います。
これは、檀家さま皆さまの一年の無事、無病息災などをお祈りするというもの。
特に、600巻(巻、と書いてありますが、実際は巻物ではなく、蛇腹折り)の大般若経典をパラパラとめくり(=転読、てんどく、と言います)その功徳をもって、無事を祈るというものです。
この日はちょっと天候が悪く、そして寒かったのでお参りの方は平年より若干少ないかな、といった感じでした。お参り頂いた方にはお足元のお悪い中をお出かけ頂き、感謝しております。
さて、今年は初めて法要後に”落語寄席”をしました。
この前日に、昨年NHKで放送された「落語deブッダ」の録画を再見していたのですが、改めて気付いたことに、古典落語”書き割り盗人”が仏教の謂う”空”の思想を現しているのだとか。
「さすが釈先生!」と思いつつ、今回の法要にびったりじゃん!と、にんまり。
大般若経典(=空の思想を説く)と落語会とのマッチングとタイミングの良さに内心ほくほくしながら、翌日の法話ネタにしたのでした(笑)

で、この日は豊橋天狗連より鶴橋減滅渡(つるはしへるめっと)さんをお迎えしての高座。
「・・・あれ、この話どこかで聞いたことがある!」と思ったら果たして「崇徳院」という古典でした。(泰明は勉強不足でタイトルまでは分かりませんでした)さすがにセミプロの呼び声高い減滅渡さん、素晴らしかったです。
古典のおもしろさって、素人の私にはよく分かりませんが、多分「同じ話でも噺家によって切り口が違う」ところにあるのではないでしょうか?
たとえは違うかもしれませんが、クラシックに於けるコンダクターみたいな(違うか・・・)
或いは、名曲のカバーとかも。
メロディ(ストーリー)は知っていても、その方の個性やカラーがしっかり反映される所に、職人芸たる良さがにじみ出るのではないでしょうか。
あ、そうそう、泰明個人的には桂枝雀さんが好きなんですが、ネット情報に依ると「枝雀さんが好きな人は、たいてい心が病んでいる」そうな。そういえば私のギターの先生も「見ていて重くなる」って仰ってたっけ。
とほほ・・・。
2012年12月13日
今週土日に”写経”しませんか?
今週15日(土)夜と16日(日)昼の2回、西光寺で写経会をします。お檀家さんじゃなくても、初めての方でも、筆に慣れていない方でも大丈夫です!!泰明が一からご案内します。まだ残席在りますので、大募集です!
***
年末だけど、忘年会シーズンだけど・・・一緒に般若心経を書きませんか?

慌ただしく生きる現代人にこそ、静謐の時間を味わって欲しい。
普段の生活では忘れがちな”心を落ち着けて自分と向き合う”体験を、”写経”を通して、感じて下さい。
土曜の夜と日曜の昼の2回開催します。(どちらでもOKです)
(*飲みに行くのもいいけれど、土曜の夜こそあえて!)
(夜の部)12月15日(土)19時~21時
(昼の部)12月16日(日)14時~16時
*場所:西光寺(豊橋市大手町120)
*会費:300円
*内容:写経の仕方、般若心経の解説の後に写経をします。
筆ペンかペンを用意しますので、お好きな方をお使い下さい。
正座が出来なくても大丈夫です。
お申し込みは saikouji@citrus.ocn.ne.jp もしくはこのブログの「オーナーへメッセージ」機能をご利用下さい。お名前、ご住所、電話番号を明記して下さい。みなさんのご参加、お待ちしております。
***
年末だけど、忘年会シーズンだけど・・・一緒に般若心経を書きませんか?

慌ただしく生きる現代人にこそ、静謐の時間を味わって欲しい。
普段の生活では忘れがちな”心を落ち着けて自分と向き合う”体験を、”写経”を通して、感じて下さい。
土曜の夜と日曜の昼の2回開催します。(どちらでもOKです)
(*飲みに行くのもいいけれど、土曜の夜こそあえて!)
(夜の部)12月15日(土)19時~21時
(昼の部)12月16日(日)14時~16時
*場所:西光寺(豊橋市大手町120)
*会費:300円
*内容:写経の仕方、般若心経の解説の後に写経をします。
筆ペンかペンを用意しますので、お好きな方をお使い下さい。
正座が出来なくても大丈夫です。
お申し込みは saikouji@citrus.ocn.ne.jp もしくはこのブログの「オーナーへメッセージ」機能をご利用下さい。お名前、ご住所、電話番号を明記して下さい。みなさんのご参加、お待ちしております。