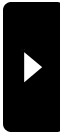2013年03月08日
正法眼蔵の真筆拝覧と眼蔵会
アクセス数が上がりそうもないタイトルだよなぁ、と思いつつ、久方ぶりのブログです。・・・最近、ちょっと気がつくと平気で半月もブログを放置してしまってます。反省です。
さて、先日、私の所属する東三河曹洞宗青年会(東三河の曹洞宗青年僧侶=40歳以下、60名ほどで構成される組織)主催の『正法眼蔵』講義が行われました。
正法眼蔵とは、”しょうぼうげんぞう”と読み、曹洞宗の宗祖、道元禅師が書かれた書物です。よく「日本最初の哲学書」なんて言われていたりもします。また、タイトルは”仏教の正しき教えを見ききし集めた”くらいの意味(だったような・・・)です。
いろんな編集形式がありますが、一口にいって95巻からなる書物で、一巻一巻にタイトルが附され、その教えが記されております。
そして、我が街、豊橋のお寺に、実は道元禅師の御真筆、要するに写本ではない、本物の正法眼蔵が蔵されております。
今回、特別にその正法眼蔵「山水経」(さんすいきょう)を拝見させていただき、引き続き、この「山水経」についての講義が行われました。これに併せて、私の属する会だけではなく、県内の他のエリアの青年会、岐阜、三重、静岡などの隣県の会にもお声掛けし、50余名が集まりました。

ちなみに、この正法眼蔵山水経は重要文化財です。私も、数年前に豊橋市美術館で1度拝見したのみ。当然、ガラス越しですし、1ページ分(冊子のようになっているため)しか見られなかった。
かつて私が師事していた書家の先生は「とにかく本物を何度も見ること。そして絶対にガラス越しではだめだよ」と仰っていました。
まさにこの日、間近で正法眼蔵を拝見することができ、法悦(ほうえつ・・・仏教の教えに触れる喜び)とはこういうことなのか、と本当に感激しました。
曹洞宗で江戸時代最大の学僧と呼ばれた面山瑞方禅師も、真筆をご覧になられたとき
「方に今、真蹟を拝読し、告誡の始末に感激す。」と書かれています。
うまく言えないのですが、やはり書というのは人柄がでるような気がします。もちろん時代によって字勢とか運筆とか違うわけですが、道元禅師の書はとにかくキレイ。綺麗といっても我々が想像する「きちんとした楷書」という意味では無く(そもそも、宋時代のスタイルなので)、線がとても繊細で、一見壊れそうな雰囲気。しかし、繊細と言っても、逆に迷いのない、まるで研ぎ澄まされた小刀のような字。たぶんお人柄がにじみ出ているのでしょう。
その日は、拝覧の後にそのまま講義をいただきました。講師は私の尊敬する先輩であり、曹洞宗の研究機関におつとめの方。何度も書いていますが、”平成の面山様”と私が常にお慕いしている方です。
特に今回は、山水経の中でも最も勘所となる冒頭部分「而今の山水は、古仏の道現成なり」を特に綿密にご講義いただきました。
・・・上手く訳せる自信がないのですが、一応、現代語訳すると・・・
”今この瞬間に、我々が目の当たりにしている山や水は、それ自体がすでに仏の世界を表した言葉で在り道理である”くらいでしょうか。
はい、何のことが全然わかりませんよね。いいんです。私も理解できてるわけではないので・・・(汗)
でも、佐々木中曰く「なんだか意味が分からない、納得できず気持ち悪い」と感じることこそ本当の文であり、本当の読書である、ということらしいので、これからも研鑽していきたいと思います。
講師をお勤めいただきました先輩、並びに会場主さま、各方面でご加担いただきました会員諸師にこの場をお借りして御礼申し上げます。素晴らしい眼蔵会でした。ありがとうございました。
さて、先日、私の所属する東三河曹洞宗青年会(東三河の曹洞宗青年僧侶=40歳以下、60名ほどで構成される組織)主催の『正法眼蔵』講義が行われました。
正法眼蔵とは、”しょうぼうげんぞう”と読み、曹洞宗の宗祖、道元禅師が書かれた書物です。よく「日本最初の哲学書」なんて言われていたりもします。また、タイトルは”仏教の正しき教えを見ききし集めた”くらいの意味(だったような・・・)です。
いろんな編集形式がありますが、一口にいって95巻からなる書物で、一巻一巻にタイトルが附され、その教えが記されております。
そして、我が街、豊橋のお寺に、実は道元禅師の御真筆、要するに写本ではない、本物の正法眼蔵が蔵されております。
今回、特別にその正法眼蔵「山水経」(さんすいきょう)を拝見させていただき、引き続き、この「山水経」についての講義が行われました。これに併せて、私の属する会だけではなく、県内の他のエリアの青年会、岐阜、三重、静岡などの隣県の会にもお声掛けし、50余名が集まりました。

ちなみに、この正法眼蔵山水経は重要文化財です。私も、数年前に豊橋市美術館で1度拝見したのみ。当然、ガラス越しですし、1ページ分(冊子のようになっているため)しか見られなかった。
かつて私が師事していた書家の先生は「とにかく本物を何度も見ること。そして絶対にガラス越しではだめだよ」と仰っていました。
まさにこの日、間近で正法眼蔵を拝見することができ、法悦(ほうえつ・・・仏教の教えに触れる喜び)とはこういうことなのか、と本当に感激しました。
曹洞宗で江戸時代最大の学僧と呼ばれた面山瑞方禅師も、真筆をご覧になられたとき
「方に今、真蹟を拝読し、告誡の始末に感激す。」と書かれています。
うまく言えないのですが、やはり書というのは人柄がでるような気がします。もちろん時代によって字勢とか運筆とか違うわけですが、道元禅師の書はとにかくキレイ。綺麗といっても我々が想像する「きちんとした楷書」という意味では無く(そもそも、宋時代のスタイルなので)、線がとても繊細で、一見壊れそうな雰囲気。しかし、繊細と言っても、逆に迷いのない、まるで研ぎ澄まされた小刀のような字。たぶんお人柄がにじみ出ているのでしょう。
その日は、拝覧の後にそのまま講義をいただきました。講師は私の尊敬する先輩であり、曹洞宗の研究機関におつとめの方。何度も書いていますが、”平成の面山様”と私が常にお慕いしている方です。
特に今回は、山水経の中でも最も勘所となる冒頭部分「而今の山水は、古仏の道現成なり」を特に綿密にご講義いただきました。
・・・上手く訳せる自信がないのですが、一応、現代語訳すると・・・
”今この瞬間に、我々が目の当たりにしている山や水は、それ自体がすでに仏の世界を表した言葉で在り道理である”くらいでしょうか。
はい、何のことが全然わかりませんよね。いいんです。私も理解できてるわけではないので・・・(汗)
でも、佐々木中曰く「なんだか意味が分からない、納得できず気持ち悪い」と感じることこそ本当の文であり、本当の読書である、ということらしいので、これからも研鑽していきたいと思います。
講師をお勤めいただきました先輩、並びに会場主さま、各方面でご加担いただきました会員諸師にこの場をお借りして御礼申し上げます。素晴らしい眼蔵会でした。ありがとうございました。
2012年01月26日
【感謝!】ブログ一周年★+道元禅師のお誕生日
今日は私にとって特別な日。
それは、曹洞宗を開かれた、道元禅師(1200~1253)のお誕生日。
そして、私事、拙ブログの開設記念日でもあります。あれから1年が経ちました。曲がりなりにも、今日までやってこられたのは、檀家さんはじめ、多くの方々のご支援のお陰です。ありがとうございます。

今日はこの2つのテーマで少し。
まず、仏教者としての記事。
道元禅師とはどういう方か?ということを僅かに書いておきます。
道元禅師は、正治2年(1200年)、久我通具公(こがみちとも・村上源氏の流れ)を父として誕生。
母は藤原家の関係の方とされています。(しかし、未だに判然としていない)
ま、ごく簡単に言えば、家柄も正しい名門のセレブという感じでしょうか。
京都にお生まれ (ちなみに亡くなられるのも京都。永平寺じゃないんですねぇ)なのですが、この場所も確定されていません。ただ、一応関係のあった場所というのがありまして、現在は「誕生寺」というお寺が建てられています。
それから、重要なのは、母が道元禅師8歳の時に亡くなられたこと。このことが禅師の幼子心に痛烈な“無常観”を植え付け、これが機縁となって出家したと伝えられています。
今日はここまでにしておきます。来年はもう少し書いてみたいと思います。
次はブログについて。
まず、ホントにブログをやっていて良かった!と心から思えます。改めて皆さんに御礼申し上げます。いろんな変化が起きた一年でした。
この記事を書くにあたり、自分が一番はじめに書いた記事「はじめに」を読み返していました。さすがに何度も推敲を重ねただけあって、自分なりにはよく書けている・・・じゃなくて・・・(笑)
よく思えば、“芯がぶれていない”、悪く書けば“進歩がない”ということを感じました。一年経った後も、「はじめに」に書いた気持ちは全くもって相変わらずだし、むしろ強くなっているくらいです。2年目も“ぶれずに”書いていきたいと思います。
そして、おもしろいことに、“目指すべき3つのブログ”はこれまた全く気持ちに変わりがない。
奇しくも「彼岸寺」のメンバーには先日実際にお会いし、お話することもできました。
金子牧師さんとは遂に昨年末、一緒にライブをする仲に(笑)それ以上に、宗教者として、親しくお話を(というか、泰明が一方的に悩み相談をしてもらってる・・・汗)させてもらっています。
それから今年は、是非tenjin先輩の講義を拝聴したいと思います。やはり仏教を学ぶことは、心臓が鼓動するが如く、毎日毎日休まず続けなければ、と思うこのごろです。
さて、と言っても、ブログを始めてから何も変わらなかった訳ではありません。
一番大きな変化は、“理論より実践”と申しましょうか、頭で考えていたこと、それが実行し、実際の形になってきつつある。
ブログを始めた当初は、割とブログの中だけの表現・発信・発言をして満足していたのが、徐々にそれだけにとどまらず、実際のお寺や、豊橋という地域や、「どすごいブロガー」同士・檀家さまといった人とのつながりという、極めて実生活上に影響をしてきたこと、これは大きな変化です。
実際、文章を書き続けることで、自分の考えをまとめることが出来たり、それを人に伝えることも(苦手ではあるけれど)昔ほどは苦でもなくなりました。何かを伝えたい、と思うこともあり、同時に”伝えること”とはどういうことか、という事も考えるようになりました。確かに小さな変化かもしれませんが、自分の中では大きな前進です。
2年目は、“承”の年として、ブログを今まで通りのスタンス(説明文のような感じで、専門用語を極力使わず、分かりやすいように)を守って、お寺の生活を綴っていきたい、と思っております。(それが出来たとき、次のステージに進めるのかも、と考えています。)
次のステージというのは・・・具体的には、早急に西光寺のホームページを作らなきゃ、と。ホームページを作ることで、西光寺のオフィシャルな情報や、基本的な仏事(葬儀とか、法要とか、仏壇のお参りのしかたとか、西光寺の年間行事とか)についてのご案内ができる。こうすることでブログとは別にしておきたい。
そうすると、今まで未分化だったブログの記事が、少し役割分担ができ、基本情報はホームページで、そして泰明のやや個人的・内面的な文章はブログで、と考えています。(ま、まだ当分はできませんが・・・)
ということで、こんなブログですが、2年目もどうぞ宜しくお願い致します。
2012年01月24日
物事への欲や興味がありません
久々「悩みのるつぼ」。
朝日新聞土曜版beの紙面からピックアップして、なにがしかを書き連ねるコーナーです。(毎週、一応目は通していたのですが、このところ特に採り上げたいと思う内容がなくって・・・)
私が興味を引くのは、“なぜ質問者は「物事に対する欲や興味がうすく」なってしまったのか?”という点です。
この点が分かると、とても面白い。面白いと言っては失礼ですが、何故興味があるのかといえば・・・
「この人、坊さんになったらいいのに」
と思うからです。
先日の記事にもチラッと書きましたが、最近、道元禅師の著された『学道用心集(がくどうようじんしゅう)』を拝読しています。
この書は、道元禅師が弟子の懐奘禅師に説かれた、学道の基本となる心得を書き付けたものです。
そのはじめに、
「誠に夫れ無常を観ずる時、吾我の心生ぜず、名利の念起こらず、時光の太(はなは)だ速やかなることを恐怖(くふ)す。」とあります。
要するに、
「誠にもって、“無常”というものをよく観察したとき、吾我(自我だとか他者という区別の心、エゴ)も生まれないし、名利を愛する気持ちなども起こらず、ただ時間の過ぎ去っていく早さをおそれるものだ」というような意味になろうかと思います。(尤も、岸沢惟安老師の提唱によれば、もっとずっと深い理解がされていますが・・・難しい)
この質問者さんが何故“名誉欲”がうすいのかは分かりません。でも、少なくとも名利を求める気持ちは大きくないはず。そう言う意味では、結構お坊さんに向いているのかな、と人ごとながら思ってしまいました。
それに、こうした人を受け入れることができるのも、またお寺なのかな、とじみじみ思う朝でした。
朝日新聞土曜版beの紙面からピックアップして、なにがしかを書き連ねるコーナーです。(毎週、一応目は通していたのですが、このところ特に採り上げたいと思う内容がなくって・・・)
*質問者(男性・24歳)
昔から周りの人間と比べて、物事に対する欲や興味がうすく、あらゆる職業に興味がわきません。
出世して偉くなって収入を増やしたいとか、会社の業績を挙げようなどとは全く思いませんでした。同じ会社の人たちと、そのような価値観の違いが重なり、先日、ついに退職を決意しました。
私は物心ついたときから将来の夢が特にありませんでした。一日三食食べられればいいと書いた記憶が残っています。
どんな肩書きもほしいとは思わないし、日本経済のために身を削ってといった思いもありません。
ただ、毎日を平和に穏やかに過ごすことができたら・・・。
しかし、現代の社会はそのような人間をなかなか受け入れてはくれません。むしろ排除していく傾向にあるのではないでしょうか。
今の世を生きて行くには、欲や夢が必要だということなのでしょうか。それらを抱くにはどうすればよいでしょうか。
*回答者(経済学者 金子勝氏)
あたなは、欲がなく、職業に関して将来の夢もないと悩んでいます。しかし、欲や夢がないことが悪いことなのでしょうか。
今は「1日3食」食べられない不安を抱えた人たちがたくさんいます。同世代の人が非正社員になり、無年金の独居老人もおり、母子家庭と子どもの貧困も増えています。
あなたが書くように「現代社会はそのような人間」を「排除」する傾向にあります。それが問題なのです。
そういう人たちのために役立つ仕事を選んでみてはいかがでしょうか。
あなたには、欲も夢もない代わりに、「アラユルコトヲ ジブンノカンジョウニ入レズニ」という立派な個性が天から与えられています。きっと「よだかの星」のように燃え続けることができるはずです。
(*質問・回答ともに泰明による取意抜粋)
私が興味を引くのは、“なぜ質問者は「物事に対する欲や興味がうすく」なってしまったのか?”という点です。
この点が分かると、とても面白い。面白いと言っては失礼ですが、何故興味があるのかといえば・・・
「この人、坊さんになったらいいのに」
と思うからです。
先日の記事にもチラッと書きましたが、最近、道元禅師の著された『学道用心集(がくどうようじんしゅう)』を拝読しています。
この書は、道元禅師が弟子の懐奘禅師に説かれた、学道の基本となる心得を書き付けたものです。
そのはじめに、
「誠に夫れ無常を観ずる時、吾我の心生ぜず、名利の念起こらず、時光の太(はなは)だ速やかなることを恐怖(くふ)す。」とあります。
要するに、
「誠にもって、“無常”というものをよく観察したとき、吾我(自我だとか他者という区別の心、エゴ)も生まれないし、名利を愛する気持ちなども起こらず、ただ時間の過ぎ去っていく早さをおそれるものだ」というような意味になろうかと思います。(尤も、岸沢惟安老師の提唱によれば、もっとずっと深い理解がされていますが・・・難しい)
この質問者さんが何故“名誉欲”がうすいのかは分かりません。でも、少なくとも名利を求める気持ちは大きくないはず。そう言う意味では、結構お坊さんに向いているのかな、と人ごとながら思ってしまいました。
それに、こうした人を受け入れることができるのも、またお寺なのかな、とじみじみ思う朝でした。
2011年12月01日
座れ坐れ据われ
早いもので、今日から師走に入りました。
そして、今日から“臘八摂心”。
・・・まったく読めないですよね、この単語。
“ろうはつせっしん”と読みます。
臘(臘月=12月)八(=8日)を意味しており、これはブッダが悟りを開かれた日、とされています。
12月8日を成道会(じょうどうえ)といい、仏教徒の中では非常に重要な3つの日・・・おさらいですが、生まれた日(4月8日)と亡くなられた日(2月15日)・・・の一つです。
そして、ブッダは菩提樹の木の下で一週間の坐禅をし、ついに8日の朝、明けの明星を見て悟られた、とされています。
その故事に因んでするのが、この臘八摂心なのです。“摂心”は簡単に言うなら“集中坐禅期間”とでも言いましょうか。我々僧侶は、この故事を追体験し、自らの修行の糧とするべく坐ります。
思い起こせば永平寺の修行時代は、この摂心がとても辛く感じました(笑)
だって、朝3時に起きてから、夜9時に寝るまで、ほとんどずっと坐禅。食事も坐禅を組んだまま。それを一週間ですよ!!!
恥ずかしながら、一年目の時は、もう少しで摂心が終わるという寸前に、たぶん今から考えるとエコノミー症候群になったようで、強烈な吐き気を催してしまい、あえなく終了直前でダウンという悲惨な思い出も・・・。
西光寺に戻ってきてからはさすがに一日中坐ることはできませんので、普通と同じように坐っていますが・・・それでも、こうしたことを単なる思い出とか、故事だけのものにしてはいけないとは思っています。
話が戻っちゃうけど、永平寺での摂心はとても寒く(当たり前か)この頃は雪がちらつきます。体の芯まで冷え切るこの寒い朝、一日の一番はじめの坐禅後に“しょうが湯”が振る舞われます。
これは砂糖とショウガを湯で溶かして葛でとろみをつけたもので、冷え切った体に染み渡り、あんなおいしいものはないんじゃないか、と言うくらいおいしく、また有り難いものでした。
西光寺では除夜の鐘の時に、私が作った手作り“しょうが湯”をお出ししていますよ。是非お越し下さい。
・・・なんかいつも食べ物の話ばっかりなような・・・。
そして、今日から“臘八摂心”。
・・・まったく読めないですよね、この単語。
“ろうはつせっしん”と読みます。
臘(臘月=12月)八(=8日)を意味しており、これはブッダが悟りを開かれた日、とされています。
12月8日を成道会(じょうどうえ)といい、仏教徒の中では非常に重要な3つの日・・・おさらいですが、生まれた日(4月8日)と亡くなられた日(2月15日)・・・の一つです。
そして、ブッダは菩提樹の木の下で一週間の坐禅をし、ついに8日の朝、明けの明星を見て悟られた、とされています。
その故事に因んでするのが、この臘八摂心なのです。“摂心”は簡単に言うなら“集中坐禅期間”とでも言いましょうか。我々僧侶は、この故事を追体験し、自らの修行の糧とするべく坐ります。
思い起こせば永平寺の修行時代は、この摂心がとても辛く感じました(笑)
だって、朝3時に起きてから、夜9時に寝るまで、ほとんどずっと坐禅。食事も坐禅を組んだまま。それを一週間ですよ!!!
恥ずかしながら、一年目の時は、もう少しで摂心が終わるという寸前に、たぶん今から考えるとエコノミー症候群になったようで、強烈な吐き気を催してしまい、あえなく終了直前でダウンという悲惨な思い出も・・・。
西光寺に戻ってきてからはさすがに一日中坐ることはできませんので、普通と同じように坐っていますが・・・それでも、こうしたことを単なる思い出とか、故事だけのものにしてはいけないとは思っています。
話が戻っちゃうけど、永平寺での摂心はとても寒く(当たり前か)この頃は雪がちらつきます。体の芯まで冷え切るこの寒い朝、一日の一番はじめの坐禅後に“しょうが湯”が振る舞われます。
これは砂糖とショウガを湯で溶かして葛でとろみをつけたもので、冷え切った体に染み渡り、あんなおいしいものはないんじゃないか、と言うくらいおいしく、また有り難いものでした。
西光寺では除夜の鐘の時に、私が作った手作り“しょうが湯”をお出ししていますよ。是非お越し下さい。
・・・なんかいつも食べ物の話ばっかりなような・・・。
2011年09月29日
今日は何の日・・・?
道元禅師のお誕生日(1月26日)を俟って始めたこのブログですが、はや8ヶ月が経ちました。皆さま方のお蔭で細々と続けてこられました。ありがとうございます。
で、今日は何の日かと申しますと・・・
曹洞宗を将来した道元禅師と、曹洞宗の基礎を築かれた瑩山禅師(けいざんぜんじ)の亡くなられた日、御命日なのです。
御命日にあたり、何か気の利いたことを書ければいいのですが、学のない泰明はそうともいかず・・・なので、ごくごく基本的なことを書きます。お檀家様や皆さまも是非「へぇ~」と納得していただければと思います。
さて、西光寺のお檀家様の中にも、「西光寺って禅宗だよね」とか「総持寺なんて聞いたことない」と言われる方も多々みえます。
西光寺は曹洞宗に属していますが、この曹洞宗と言うのは、大きなくくりで言えば“禅宗”の中のひとつ。
禅宗は達摩(だるま)大師を祖として、インドから中国に伝えた仏教の教えを言います。日本では、曹洞宗のほかに臨済宗、黄檗宗(おうばくしゅう)があります。
で、その曹洞宗を開かれたのは道元禅師(1200~1253)です。ここまでは皆さんオッケーですか??
そして、禅師の開かれたお寺はご存知、福井県の永平寺、曹洞宗の大本山です。
実は、曹洞宗にはもう一つ大本山があります。
横浜市鶴見区にある総持寺(そうじじ)というのがそれで、石原裕次郎さんのお墓があり、派手な(失礼!)お年忌をすることでテレビに結構出ていますね。
泰明も修行こそしていませんが、総持寺には何度も行ったことがありますし、一度は舘ひろしさんと廊下ですれ違ったこともあります★
この総持寺を開かれた方こそ、瑩山禅師(1264~1325…異説あり)なのです。禅師は、道元禅師から数えると4代目の法孫(弟子)になります。もともとは能登にあった総持寺ですが、明治期に現在の横浜市に移し、今年でちょうど100年。ですので、今年は100周年の記念事業が行われています。
さて、曹洞宗では、“一仏両祖”(いちぶつりょうそ)として、一仏=お釈迦様と、両祖=道元禅師・瑩山禅師を敬い崇めています。いわば、両祖というのは父母のように一対をなし、優しく、そして時に厳しく我々遠孫を見守ってくださる、ということです。
御征忌(ごしょうき…この御命日をこのように呼びます)にちなみ、書かせていただきました。来年はもう少しかっこいいことを書けるように勉強してきます(笑)
で、今日は何の日かと申しますと・・・
曹洞宗を将来した道元禅師と、曹洞宗の基礎を築かれた瑩山禅師(けいざんぜんじ)の亡くなられた日、御命日なのです。
御命日にあたり、何か気の利いたことを書ければいいのですが、学のない泰明はそうともいかず・・・なので、ごくごく基本的なことを書きます。お檀家様や皆さまも是非「へぇ~」と納得していただければと思います。
さて、西光寺のお檀家様の中にも、「西光寺って禅宗だよね」とか「総持寺なんて聞いたことない」と言われる方も多々みえます。
西光寺は曹洞宗に属していますが、この曹洞宗と言うのは、大きなくくりで言えば“禅宗”の中のひとつ。
禅宗は達摩(だるま)大師を祖として、インドから中国に伝えた仏教の教えを言います。日本では、曹洞宗のほかに臨済宗、黄檗宗(おうばくしゅう)があります。
で、その曹洞宗を開かれたのは道元禅師(1200~1253)です。ここまでは皆さんオッケーですか??
そして、禅師の開かれたお寺はご存知、福井県の永平寺、曹洞宗の大本山です。
実は、曹洞宗にはもう一つ大本山があります。
横浜市鶴見区にある総持寺(そうじじ)というのがそれで、石原裕次郎さんのお墓があり、派手な(失礼!)お年忌をすることでテレビに結構出ていますね。
泰明も修行こそしていませんが、総持寺には何度も行ったことがありますし、一度は舘ひろしさんと廊下ですれ違ったこともあります★
この総持寺を開かれた方こそ、瑩山禅師(1264~1325…異説あり)なのです。禅師は、道元禅師から数えると4代目の法孫(弟子)になります。もともとは能登にあった総持寺ですが、明治期に現在の横浜市に移し、今年でちょうど100年。ですので、今年は100周年の記念事業が行われています。
さて、曹洞宗では、“一仏両祖”(いちぶつりょうそ)として、一仏=お釈迦様と、両祖=道元禅師・瑩山禅師を敬い崇めています。いわば、両祖というのは父母のように一対をなし、優しく、そして時に厳しく我々遠孫を見守ってくださる、ということです。
御征忌(ごしょうき…この御命日をこのように呼びます)にちなみ、書かせていただきました。来年はもう少しかっこいいことを書けるように勉強してきます(笑)
2011年08月08日
ヒンヤリした~~~~~い!
暑くて何にも考える気になりませんね。パソコンの文章を読むだけでも辛い。
さて、今日は何にも思い浮かばないので、小ネタ。
私は、自分のHNとして”泰明@西光寺”とか、”泰明”と名前で書いてます。これ、理由があるんです。
実は、私が修行した大本山永平寺(福井県)では、修行僧は基本的に姓では呼ばず、ファーストネームというか名前(僧名)で呼ばれます。その名残というか癖なんですね。もし永平寺に行かれたら、修行僧の名札を見てください。みんなファーストネームだけ書かれています。
私も本名が泰明ですが、戸籍は「やすあき」と訓読み、僧名は音読みにして「たいめい」と読みます。
この”僧名=本名の音読み”というパターンが割と一般的です。(もちろん、一般家庭から出家された方は違います。例えば「一郎」なんて僧名らしくないので、大抵は僧名か号を師匠から付与されます)
そうですね、例えば・・・”昌道”というお名前があったとすると、普通は「まさみち」と読みますが、僧名にすると「しょうどう」となります。
そんなわけで、”泰明”と書いていますが、自分的には「たいめい」と読んでもらっているつもりなのです。
何でこんなことを書いているかというと、最近ブロガーさんやブログを読んでくださっている方にお会いすると、一様に「やすあきさん」と呼ばれることが多いので・・・。まぁどっちでもいいんですけどね(笑)
そうそう、面白いことが2つ。
永平寺では、同じ読みの方がいらっしゃると、後から入った人は変えさせられます。
さっきの例なら先に「昌道」さんが修行していたら、後から入った「正道」さんは、同じ「しょうどう」という読みなので、変更しなくてはなりません。だいたいは、自分の号(雅号みたいなもの)を使います。私の場合は、「観山(かんざん)」という号を師匠からもらっています。
後は・・・同じ曹洞宗の大本山でも横浜の総持寺は、名字で呼び合うらしいです。何でかな??
疑問ついでに、何で永平寺は名前で呼ぶんでしょうか?
”出家したら釈氏と称せよ”っていう言葉の名残り?宗侶でご存知の方、教えてください。
さて、今日は何にも思い浮かばないので、小ネタ。
私は、自分のHNとして”泰明@西光寺”とか、”泰明”と名前で書いてます。これ、理由があるんです。
実は、私が修行した大本山永平寺(福井県)では、修行僧は基本的に姓では呼ばず、ファーストネームというか名前(僧名)で呼ばれます。その名残というか癖なんですね。もし永平寺に行かれたら、修行僧の名札を見てください。みんなファーストネームだけ書かれています。
私も本名が泰明ですが、戸籍は「やすあき」と訓読み、僧名は音読みにして「たいめい」と読みます。
この”僧名=本名の音読み”というパターンが割と一般的です。(もちろん、一般家庭から出家された方は違います。例えば「一郎」なんて僧名らしくないので、大抵は僧名か号を師匠から付与されます)
そうですね、例えば・・・”昌道”というお名前があったとすると、普通は「まさみち」と読みますが、僧名にすると「しょうどう」となります。
そんなわけで、”泰明”と書いていますが、自分的には「たいめい」と読んでもらっているつもりなのです。
何でこんなことを書いているかというと、最近ブロガーさんやブログを読んでくださっている方にお会いすると、一様に「やすあきさん」と呼ばれることが多いので・・・。まぁどっちでもいいんですけどね(笑)
そうそう、面白いことが2つ。
永平寺では、同じ読みの方がいらっしゃると、後から入った人は変えさせられます。
さっきの例なら先に「昌道」さんが修行していたら、後から入った「正道」さんは、同じ「しょうどう」という読みなので、変更しなくてはなりません。だいたいは、自分の号(雅号みたいなもの)を使います。私の場合は、「観山(かんざん)」という号を師匠からもらっています。
後は・・・同じ曹洞宗の大本山でも横浜の総持寺は、名字で呼び合うらしいです。何でかな??
疑問ついでに、何で永平寺は名前で呼ぶんでしょうか?
”出家したら釈氏と称せよ”っていう言葉の名残り?宗侶でご存知の方、教えてください。