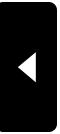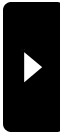2013年03月12日
3.11慰霊行脚の旅
大震災から2年がたちました。
3月10,11日と、東松島市へ行ってきました。慰霊法要、ならびに沿岸被災地の行脚に参加するためです。
今回の慰霊法要は、声明練習会(=節やメロディー付きのお経を勉強する会)を中心に全国から40数名の僧侶、虚無僧が集まり、行われました。
当日は大変寒く、雪が降り積もり、さらに舞い散る、という中での行脚、法要でした。

・・・何かを伝えたい、書かないと、と思うのですが、うまく言葉を紡げません。
また機会を見つけて書きます。菲才の身ゆえ、お許し下さい。
なんか丸投げ(投げやり??)な感じで大変申し訳ないのですが、同じく神奈川から参加されたkameno老師のブログが写真、説明共に完璧だと思いますので、よろしければご覧下さい。泰明も何ショットか写っています。
http://teishoin.net/blog/004869.html
http://teishoin.net/blog/004870.html
kamenoさん、ありがとうございます!この場をお借りして御礼申し上げます。
3月10,11日と、東松島市へ行ってきました。慰霊法要、ならびに沿岸被災地の行脚に参加するためです。
今回の慰霊法要は、声明練習会(=節やメロディー付きのお経を勉強する会)を中心に全国から40数名の僧侶、虚無僧が集まり、行われました。
当日は大変寒く、雪が降り積もり、さらに舞い散る、という中での行脚、法要でした。

・・・何かを伝えたい、書かないと、と思うのですが、うまく言葉を紡げません。
また機会を見つけて書きます。菲才の身ゆえ、お許し下さい。
なんか丸投げ(投げやり??)な感じで大変申し訳ないのですが、同じく神奈川から参加されたkameno老師のブログが写真、説明共に完璧だと思いますので、よろしければご覧下さい。泰明も何ショットか写っています。
http://teishoin.net/blog/004869.html
http://teishoin.net/blog/004870.html
kamenoさん、ありがとうございます!この場をお借りして御礼申し上げます。
2013年02月15日
今日は3つの記念日のひとつ
今日、2月15日は仏教徒にとって非常に重要な3つの日のひとつ、「涅槃会」(ねはんえ)です。
涅槃とは、本来、煩悩を消し去った後の安楽なる状態を言うのですが、これが転じてお釈迦様のご命日とされています。もう少し言えば、ブッダは“死”というものを以て、安楽なることを示されたということで、「涅槃」という言葉が使われています。

(↑これは西光寺所蔵の涅槃図 元図は中国敦煌の莫高窟という仏教遺跡にあるそうです・・・ちなみに莫高窟は、”ばっこうくつ”と読み、世界遺産です)
さて、昨年同様に、今日はせっかくなので、『佛垂般涅槃略説教誡経』を採り上げてみたいと思います。長いタイトルですが、ずばりこれはお釈迦様が亡くなる前に、最後に遺した言葉・教えのお経とされています。
つまりご遺言です。
ちなみに読み方は「ぶっすいはつねはんりゃくせつきょうかいきょう」もしくは「ぶっしはつねはんりゃくせつきょうかいきょう」、略して“遺経”(ゆいきょう)とか、“遺教経”とか言われています。まぁ文字通り「最後に遺されたお経」ということですね。(以下、「遺経」と書きます)
泰明は個人的にこの「遺経」が非常に気に入っています。西光寺ではお通夜にこのお経をおつとめするので、年に何十回も読むから、ということもありますが、「死の直前」という臨場感あふれる描写と、教えが割と平易で、身に染みる感じがするからです。
それからいくつも”汝等比丘”(なんだちびく、と読む)ではじまるパラグラフがありますが、これは「あなたたち修行者よ」と遺された弟子達に教えを語りかけるシーンで、それが余計にこのお経の現実感と雰囲気を出しています。
実際はとても長いお経なので、この中から一部分だけを書きます。せっかくなので、道元禅師も最後に書かれたという8種の教え八大人覚(はちだいにんがく)です。
簡単に訳しますと
「あなたがた修行者たちよ、覚えておきなさい。欲深い人はさらなる利益を求めるために苦悩もまた多いもの。欲をコントロールできる人はいたずらに”もっともっと”と求めることがないので、煩わす心の苦しみがないのです。だから今すぐにでもこれを身につけなさい。(中略)欲をコントロールできる人は、様々な欲望(主に食・性・睡眠・金・名誉)に自分を振り回されることがないのです。」
むか~し、ボーイスカウトのキャンプに行ったときの話です。
心配性な泰明は”あれも要るかもしれん、これもあったら快適だろう”と大きなリュックサックに荷物がパンパン。当然、寝袋から着替え、食料など一切合切を入れるのです。
小学生の時に10kgを超える荷物を背負って歩くのはかなりしんどい。やっとの思いでキャンプ場についても、荷物が多いと「これをなくさないように。あれはここにおいて・・・あれ?どこやったっけ」という始末。
キャンプに入る前に、荷物点検があるのですが、怖いリーダーたち(笑)が、余計なものを持ち込んでいないかどうか、全ての装備をチェックします。その時に、たくさん出てきた荷物を”早く仕舞わないと”と思っていた折り、リーダーが言いました。
「かつて小さなリュックと寝袋だけで来た先輩がいるんだよ。本当に必要なモノだけを見定めて、あとは木の枝や葉、ロープなどで工夫して快適なキャンプをする。これが大事なんだ」と。
心配性な泰明はその時は「無理。これ以上は荷物を削れない」と思っていたのですが、何度も何度もキャンプに行くと、本当に必要なモノ、またそのモノで工夫して使えるモノの”勘所”が分かってきます。
お釈迦様の言う、「少欲」とは「無欲」とイコールではないはずです。むしろ、無欲になろうとするそれもある種の欲望なのですから。
人生をキャンプ生活だとすると(笑)、このボーイスカウトで身にしみたことと、この少欲は大変似通った教えなのかもしれません。
涅槃とは、本来、煩悩を消し去った後の安楽なる状態を言うのですが、これが転じてお釈迦様のご命日とされています。もう少し言えば、ブッダは“死”というものを以て、安楽なることを示されたということで、「涅槃」という言葉が使われています。

(↑これは西光寺所蔵の涅槃図 元図は中国敦煌の莫高窟という仏教遺跡にあるそうです・・・ちなみに莫高窟は、”ばっこうくつ”と読み、世界遺産です)
さて、昨年同様に、今日はせっかくなので、『佛垂般涅槃略説教誡経』を採り上げてみたいと思います。長いタイトルですが、ずばりこれはお釈迦様が亡くなる前に、最後に遺した言葉・教えのお経とされています。
つまりご遺言です。
ちなみに読み方は「ぶっすいはつねはんりゃくせつきょうかいきょう」もしくは「ぶっしはつねはんりゃくせつきょうかいきょう」、略して“遺経”(ゆいきょう)とか、“遺教経”とか言われています。まぁ文字通り「最後に遺されたお経」ということですね。(以下、「遺経」と書きます)
泰明は個人的にこの「遺経」が非常に気に入っています。西光寺ではお通夜にこのお経をおつとめするので、年に何十回も読むから、ということもありますが、「死の直前」という臨場感あふれる描写と、教えが割と平易で、身に染みる感じがするからです。
それからいくつも”汝等比丘”(なんだちびく、と読む)ではじまるパラグラフがありますが、これは「あなたたち修行者よ」と遺された弟子達に教えを語りかけるシーンで、それが余計にこのお経の現実感と雰囲気を出しています。
実際はとても長いお経なので、この中から一部分だけを書きます。せっかくなので、道元禅師も最後に書かれたという8種の教え八大人覚(はちだいにんがく)です。
汝等比丘当に知るべし、多欲の人は利を求むること多きが故に苦悩もまた多し 少欲の人は無求無欲なれば則ちこの患無し、直爾に少欲すら尚お応に修習すべし。(中略)亦復諸根の為に牽かれず
簡単に訳しますと
「あなたがた修行者たちよ、覚えておきなさい。欲深い人はさらなる利益を求めるために苦悩もまた多いもの。欲をコントロールできる人はいたずらに”もっともっと”と求めることがないので、煩わす心の苦しみがないのです。だから今すぐにでもこれを身につけなさい。(中略)欲をコントロールできる人は、様々な欲望(主に食・性・睡眠・金・名誉)に自分を振り回されることがないのです。」
むか~し、ボーイスカウトのキャンプに行ったときの話です。
心配性な泰明は”あれも要るかもしれん、これもあったら快適だろう”と大きなリュックサックに荷物がパンパン。当然、寝袋から着替え、食料など一切合切を入れるのです。
小学生の時に10kgを超える荷物を背負って歩くのはかなりしんどい。やっとの思いでキャンプ場についても、荷物が多いと「これをなくさないように。あれはここにおいて・・・あれ?どこやったっけ」という始末。
キャンプに入る前に、荷物点検があるのですが、怖いリーダーたち(笑)が、余計なものを持ち込んでいないかどうか、全ての装備をチェックします。その時に、たくさん出てきた荷物を”早く仕舞わないと”と思っていた折り、リーダーが言いました。
「かつて小さなリュックと寝袋だけで来た先輩がいるんだよ。本当に必要なモノだけを見定めて、あとは木の枝や葉、ロープなどで工夫して快適なキャンプをする。これが大事なんだ」と。
心配性な泰明はその時は「無理。これ以上は荷物を削れない」と思っていたのですが、何度も何度もキャンプに行くと、本当に必要なモノ、またそのモノで工夫して使えるモノの”勘所”が分かってきます。
お釈迦様の言う、「少欲」とは「無欲」とイコールではないはずです。むしろ、無欲になろうとするそれもある種の欲望なのですから。
人生をキャンプ生活だとすると(笑)、このボーイスカウトで身にしみたことと、この少欲は大変似通った教えなのかもしれません。
2012年05月17日
結婚記念日とお年忌の意外な共通点?
結婚記念日はお年忌?
のっけから縁起でもないタイトルです。
結婚記念日に夫婦のどちらかが亡くなった、とかそういう悲しい話ではありません。
”結婚は人生の墓場?だからお年忌???”そんなブラックジョークをかましている訳でも、もちろんありません。
今日は私たちの結婚記念日。3周年になりました。
毎年、結婚披露宴をしたホテルのレストランで、年に一度の贅沢を、ということでお食事に行きます。高い、(物理的にも金額的にも)レストランでは緊張します。(地震とか支払いとか・・・笑)

味はどうかって?そりゃ”蜜の味”ですがな(冷笑)

さて、くだらない親父ギャグはおいといて、美味しいお料理を堪能した訳ですが、その時に、ふと思ったこと、思い出したことを一つ。
今思い返すと、結婚式の前後は、ものすごいストレスだった。
いや、誤解を招く表現だが、決して”結婚したこと”がストレスだったのではありません。だって、現におかげさまで割と幸せに生きていますので・・・。
ではなく、結婚式も仏前だったので、自分でいろいろ式次第とかを作り、披露宴も会場のキャパいっぱい。有り難い事にライブ演奏や出し物も多数あったし(その調整も)、会場セッティングの関係で、席次表も自作を余儀なくされたので、それも全力投球。
加えて、新婚旅行(さる理由からパックツアーではなく、全行程2人旅だった・・・しかもフランス語は話せないのに行き先はフランス)の準備とか、披露宴とは別に親しい友人達を招いての1.5次会もやった。
と言うわけで、過剰表現ではなく、ホントに一時期、円形に脱毛化が進んで、まるで江戸時代の月代(さかやき)みたいに。
え?もとより頭はつるつるだから関係ないじゃん、ですって?まぁ確かに・・・。でも、ホントに薄くなるんですね。びっくりです。
と言うわけで、式の前後自体は大変だったのですが、おかげさまで子宝にも恵まれ、毎日それなりにやっております。
で、ここで思ったのが、”おかげさま”ということ。
披露宴や式に多数の方がご臨席下さったのも、やはりご縁があってのこと。その後の結婚生活もまぁまぁ円満無事(?!)にやれているのも、ご縁のある皆さんのおかげ。
例えばですよ。子どもが生まれる。そうすると泣き声が気になるじゃないですか、近隣の方に迷惑掛けるんじゃないかって。もしそれが例えば東京みたいな人口密集地帯で、なおかつ隣人の顔も名前もしらない、挨拶もしたことないでは、それだけのことだけど、不安材料になりません?
それだけ、人間が生きるって事は、無数の、それこそ”見える縁”も”見えない縁”もあり、その中で生きているってことなんでしょうね。

(今日の写真は全部そのレストランのお料理で、撮影は私)
そういう意味では、実はお年忌もそうだったりします。
一周忌と三回忌って別名があるんですが、それは”小祥忌”と”大祥忌”と言います。
”祥”(めでたいこと、さいわい)という文字が何故、本来は死者を供養する儀式に付いているのか?それは諸説あるそうですが、”中国では服喪の最後が大祥忌”であり、”大過なく遺族が過ごせ、そして故人が平安の世界に住んでいる証し”としてめでたい祭り(吉祭)としてこの大祥忌を行うのだそうです。
ここで肝心なのは、やはり”死者”も”生者”も共に安寧であることを祈っていることではないでしょうか。
もし死者儀礼が、単に死者へのみ、だとしたら、我々生者はその儀礼を行う必要があるのでしょうか。そして死者のみ、という断定はできるのでしょうか?
(これは間違ってはいけませんが、”だから必要ない”ということではありません。それから”死者へ捧げる”ことができるのは、ある意味宗教者のつとめかもしれません。)
”死”を見つめることで、実は”生”をより生き生きとして、充実感を伴ったものに、そして明日への糧となる、というのが、年回忌という節目ではないか。
その点では、結婚記念日という節目で”結婚生活”あるいは”結婚するということ”を見つめ、より良き生活にするということと、実は同じ事を”死”の観点から捉え直しているのが年回忌などの儀礼だと私は思います。
・・・せっかくの結婚記念日なのにね。こんな事、書かなくてもいいのに。もっとハッピーな話題はないの?・・・と一人で突っ込みを入れつつ(汗)、最後にずいぶん前に読んだbe(朝日新聞土曜版)のインタビュー記事の言葉を書き付けておきます。
のっけから縁起でもないタイトルです。
結婚記念日に夫婦のどちらかが亡くなった、とかそういう悲しい話ではありません。
”結婚は人生の墓場?だからお年忌???”そんなブラックジョークをかましている訳でも、もちろんありません。
今日は私たちの結婚記念日。3周年になりました。
毎年、結婚披露宴をしたホテルのレストランで、年に一度の贅沢を、ということでお食事に行きます。高い、(物理的にも金額的にも)レストランでは緊張します。(地震とか支払いとか・・・笑)

味はどうかって?そりゃ”蜜の味”ですがな(冷笑)

さて、くだらない親父ギャグはおいといて、美味しいお料理を堪能した訳ですが、その時に、ふと思ったこと、思い出したことを一つ。
今思い返すと、結婚式の前後は、ものすごいストレスだった。
いや、誤解を招く表現だが、決して”結婚したこと”がストレスだったのではありません。だって、現におかげさまで割と幸せに生きていますので・・・。
ではなく、結婚式も仏前だったので、自分でいろいろ式次第とかを作り、披露宴も会場のキャパいっぱい。有り難い事にライブ演奏や出し物も多数あったし(その調整も)、会場セッティングの関係で、席次表も自作を余儀なくされたので、それも全力投球。
加えて、新婚旅行(さる理由からパックツアーではなく、全行程2人旅だった・・・しかもフランス語は話せないのに行き先はフランス)の準備とか、披露宴とは別に親しい友人達を招いての1.5次会もやった。
と言うわけで、過剰表現ではなく、ホントに一時期、円形に脱毛化が進んで、まるで江戸時代の月代(さかやき)みたいに。
え?もとより頭はつるつるだから関係ないじゃん、ですって?まぁ確かに・・・。でも、ホントに薄くなるんですね。びっくりです。
と言うわけで、式の前後自体は大変だったのですが、おかげさまで子宝にも恵まれ、毎日それなりにやっております。
で、ここで思ったのが、”おかげさま”ということ。
披露宴や式に多数の方がご臨席下さったのも、やはりご縁があってのこと。その後の結婚生活もまぁまぁ円満無事(?!)にやれているのも、ご縁のある皆さんのおかげ。
例えばですよ。子どもが生まれる。そうすると泣き声が気になるじゃないですか、近隣の方に迷惑掛けるんじゃないかって。もしそれが例えば東京みたいな人口密集地帯で、なおかつ隣人の顔も名前もしらない、挨拶もしたことないでは、それだけのことだけど、不安材料になりません?
それだけ、人間が生きるって事は、無数の、それこそ”見える縁”も”見えない縁”もあり、その中で生きているってことなんでしょうね。

(今日の写真は全部そのレストランのお料理で、撮影は私)
そういう意味では、実はお年忌もそうだったりします。
一周忌と三回忌って別名があるんですが、それは”小祥忌”と”大祥忌”と言います。
”祥”(めでたいこと、さいわい)という文字が何故、本来は死者を供養する儀式に付いているのか?それは諸説あるそうですが、”中国では服喪の最後が大祥忌”であり、”大過なく遺族が過ごせ、そして故人が平安の世界に住んでいる証し”としてめでたい祭り(吉祭)としてこの大祥忌を行うのだそうです。
ここで肝心なのは、やはり”死者”も”生者”も共に安寧であることを祈っていることではないでしょうか。
もし死者儀礼が、単に死者へのみ、だとしたら、我々生者はその儀礼を行う必要があるのでしょうか。そして死者のみ、という断定はできるのでしょうか?
(これは間違ってはいけませんが、”だから必要ない”ということではありません。それから”死者へ捧げる”ことができるのは、ある意味宗教者のつとめかもしれません。)
”死”を見つめることで、実は”生”をより生き生きとして、充実感を伴ったものに、そして明日への糧となる、というのが、年回忌という節目ではないか。
その点では、結婚記念日という節目で”結婚生活”あるいは”結婚するということ”を見つめ、より良き生活にするということと、実は同じ事を”死”の観点から捉え直しているのが年回忌などの儀礼だと私は思います。
・・・せっかくの結婚記念日なのにね。こんな事、書かなくてもいいのに。もっとハッピーな話題はないの?・・・と一人で突っ込みを入れつつ(汗)、最後にずいぶん前に読んだbe(朝日新聞土曜版)のインタビュー記事の言葉を書き付けておきます。
周りを見渡すと、ただ漠然と生きている人が多いと思うようになった。いつか死ぬのだから一生懸命生きよう、という意識が現代には希薄すぎると思います。
吉田太一さん 遺品整理専門会社キーパーズ社長
2012年05月04日
”かかりつけの僧侶”、いりますか?
うちの母、けっこう『通販生活』が好きで、(モノは高いのでたくさん買えないが)定期購読しています。
今号、「これ読んでみりん」と手渡されたページ、好評コラム「舞台裏座談会」シリーズ、題して『新世代僧侶の巻』でした。
葬式や法事だけに囚われない、新しい形の活動をされている現役僧侶4名が集まっての座談会。
一ページ目の見出しには
「普段から、人の生き死にや悩みを相談する、”かかりつけ僧侶”のような関係になれたらと思うんです。」とあります。
ホント、そうだよなぁ、と頷きつつ、ページをめくると・・・おぉ、面白そうな座談会のメンバー。
釈徹宗さんに、三浦明利さん、そして彼岸寺の松本さんに青江さん。
奇しくも、全員浄土真宗。
ご存じない方もいらっしゃるかもしれません。
釈先生は、何冊も本をお書きになられ、たしか内田樹先生とも共著があるはず。拝読したことはないですが、非常にわかりやすい喩えで仏教を解説されると耳にしたことがあります。
そして三浦さんは尼僧さん。しかもシンガーソングライターという顔もお持ちです。
チーム彼岸寺は松本さんに青江さん。青江さん、いい顔で写っています(笑)
座談会の内容、とても分かりやすくて面白いのですが、結構な文章量なので、泰明が”これは”と思った箇所を抜粋します。

以下、『通販生活』(2012夏号)より
++++++++++++
(僧侶の給料について。法人税がかからないのは「宗教活動」のみなので、僧侶個人の給金には所得税がかかる。お賽銭や御布施も、すべて宗教法人に入れなければならない、などの話が出た折に)
松本師「住職には宗教者としての顔以外に、宗教法人の代表という一面もありますからね」
+++
(松本さんから、地域や宗派、都市部や田舎、お寺の規模の大小など、さまざまな軸を持つお寺に対して「現在お寺の運営モデル」を研究している、という話を受け・・・)
釈師「それは面白い。僕はね、『お坊さんこそお寺へ行け』とよく言っているんです。よそのお寺へ行けば、ものすごいヒントがある。特性に合った活動をすればお寺が面白くなるのは間違いないので、その特性をいかに見分けるかは重要なポイントです。」
+++
松本師「お坊さんの仕事って、悩んでいる人に自分の得意分野で寄り添っていくことだと思うんです。」
+++
司会:東日本大震災が起きて以降、被災地で活動される僧侶の方々が注目を集めました。
釈師「各地域の寺院が、様々な活動のコネクターとなりました。宗派に関係なく、さらにはキリスト教やNGOなども受け入れて、お寺がボランティアや避難所の拠点となったのが特徴的ですね。」
+++
(1ページ目の「普段から、人の生き死にや悩みを相談する、”かかりつけ僧侶”のような関係になれたらと思うんです」の発言に続けて)
釈師「お寺は葬式のときだけ利用しようとすると割高になりますが、普段から使っていれば、かなりお安くなるんじゃないでしょうか(笑)」
松本師「よく葬儀での御布施が高いと言われますが、あれは本来、お寺との生涯に渡っての親密なおつきあいを前提としているものでしょう。」
釈師「葬式だけじゃなく、医療や教育など世の中全体が、支払ったお金に見合ったサービスを求める「消費者体質」になっていますからね。」
釈師「お坊さんも、葬式という”点”だけで関わってもなかなか寄り添えない。そうではなく、喜びや悲しみなど、その人の人生に”線”で関わることができれば、お葬式もいいものになるんじゃないですかね。」
++++++++++++
なかなか面白い座談会でした。釈徹宗師のお話は簡潔でよどみない。頷くことばかりでした。
余談ですが、この座談会に参加された各僧侶の紹介写真に、私の後頭部も写っていました(笑)光明寺で行われたセミナー時のものです。
実は今号の『通販生活』はこの座談会も面白かったのですが、もう一つ、興味深い記事を発見しました。またの機会に。
今号、「これ読んでみりん」と手渡されたページ、好評コラム「舞台裏座談会」シリーズ、題して『新世代僧侶の巻』でした。
葬式や法事だけに囚われない、新しい形の活動をされている現役僧侶4名が集まっての座談会。
一ページ目の見出しには
「普段から、人の生き死にや悩みを相談する、”かかりつけ僧侶”のような関係になれたらと思うんです。」とあります。
ホント、そうだよなぁ、と頷きつつ、ページをめくると・・・おぉ、面白そうな座談会のメンバー。
釈徹宗さんに、三浦明利さん、そして彼岸寺の松本さんに青江さん。
奇しくも、全員浄土真宗。
ご存じない方もいらっしゃるかもしれません。
釈先生は、何冊も本をお書きになられ、たしか内田樹先生とも共著があるはず。拝読したことはないですが、非常にわかりやすい喩えで仏教を解説されると耳にしたことがあります。
そして三浦さんは尼僧さん。しかもシンガーソングライターという顔もお持ちです。
チーム彼岸寺は松本さんに青江さん。青江さん、いい顔で写っています(笑)
座談会の内容、とても分かりやすくて面白いのですが、結構な文章量なので、泰明が”これは”と思った箇所を抜粋します。

以下、『通販生活』(2012夏号)より
++++++++++++
(僧侶の給料について。法人税がかからないのは「宗教活動」のみなので、僧侶個人の給金には所得税がかかる。お賽銭や御布施も、すべて宗教法人に入れなければならない、などの話が出た折に)
松本師「住職には宗教者としての顔以外に、宗教法人の代表という一面もありますからね」
+++
(松本さんから、地域や宗派、都市部や田舎、お寺の規模の大小など、さまざまな軸を持つお寺に対して「現在お寺の運営モデル」を研究している、という話を受け・・・)
釈師「それは面白い。僕はね、『お坊さんこそお寺へ行け』とよく言っているんです。よそのお寺へ行けば、ものすごいヒントがある。特性に合った活動をすればお寺が面白くなるのは間違いないので、その特性をいかに見分けるかは重要なポイントです。」
+++
松本師「お坊さんの仕事って、悩んでいる人に自分の得意分野で寄り添っていくことだと思うんです。」
+++
司会:東日本大震災が起きて以降、被災地で活動される僧侶の方々が注目を集めました。
釈師「各地域の寺院が、様々な活動のコネクターとなりました。宗派に関係なく、さらにはキリスト教やNGOなども受け入れて、お寺がボランティアや避難所の拠点となったのが特徴的ですね。」
+++
(1ページ目の「普段から、人の生き死にや悩みを相談する、”かかりつけ僧侶”のような関係になれたらと思うんです」の発言に続けて)
釈師「お寺は葬式のときだけ利用しようとすると割高になりますが、普段から使っていれば、かなりお安くなるんじゃないでしょうか(笑)」
松本師「よく葬儀での御布施が高いと言われますが、あれは本来、お寺との生涯に渡っての親密なおつきあいを前提としているものでしょう。」
釈師「葬式だけじゃなく、医療や教育など世の中全体が、支払ったお金に見合ったサービスを求める「消費者体質」になっていますからね。」
釈師「お坊さんも、葬式という”点”だけで関わってもなかなか寄り添えない。そうではなく、喜びや悲しみなど、その人の人生に”線”で関わることができれば、お葬式もいいものになるんじゃないですかね。」
++++++++++++
なかなか面白い座談会でした。釈徹宗師のお話は簡潔でよどみない。頷くことばかりでした。
余談ですが、この座談会に参加された各僧侶の紹介写真に、私の後頭部も写っていました(笑)光明寺で行われたセミナー時のものです。
実は今号の『通販生活』はこの座談会も面白かったのですが、もう一つ、興味深い記事を発見しました。またの機会に。
タグ :通販生活
2012年05月01日
GW楽しんでいますか??
お久しぶりです。何だかんだで五月に入りました。
GW4日目です。みなさん、連休を満喫していらっしゃるでしょうか?朝日新聞の調査では、連休には「どこにも行かない」が60%程度だったと記憶しています。
出かけるにしろ、自宅でリラックスするにしろ、普段の仕事の疲れやストレスを発散して、有意義な連休になりますよう、お祈りしています。
仏典(パーリ長老偈註)にも「琴の弦は、張ることが急であっても、また緩くても良い音は出ない。緩急よろしきを得て、はじめて良い音を出すものである。」というのがあります。
これは琴のことを言っているのではなく、修行者のありようを指しています。
怠けず、同時に過度の無理な努力もせず、程度を辨えたときにさとりが開ける、という意味であります。悟りを求める修行僧ではなくても、市井に暮らすみなさまもまた同様だと思います。どうぞご自愛下さい。
あ、私ですか?GWなんてないですよ(笑)基本的にお休みがないですから。なんと言っても、これは生き方だし、それは譲れないので。

話が変わって、この5月1日は私にとって、特別な日。それは、今から8年前の今日、大本山永平寺の修行を終えた日でもあり、3年前の今日は晋山式という正式に住職になる式をした日でもあります。
節目に当たり、今の自分と過去の自分を照らし合わせて、未来を見つめる。当たり前のようですが、淡々とこれを実行していこうと思います。
今朝のNHK Eテレでやっていた「にほんごであそぼ」に良いことばが紹介されていました。
「稽古とは 一より習い 十を知り 十よりかへる もとのその一」
千利休の言葉だそうです。まるで十牛図を短歌にしたような世界。まったく、そうありたいものです。
GW4日目です。みなさん、連休を満喫していらっしゃるでしょうか?朝日新聞の調査では、連休には「どこにも行かない」が60%程度だったと記憶しています。
出かけるにしろ、自宅でリラックスするにしろ、普段の仕事の疲れやストレスを発散して、有意義な連休になりますよう、お祈りしています。
仏典(パーリ長老偈註)にも「琴の弦は、張ることが急であっても、また緩くても良い音は出ない。緩急よろしきを得て、はじめて良い音を出すものである。」というのがあります。
これは琴のことを言っているのではなく、修行者のありようを指しています。
怠けず、同時に過度の無理な努力もせず、程度を辨えたときにさとりが開ける、という意味であります。悟りを求める修行僧ではなくても、市井に暮らすみなさまもまた同様だと思います。どうぞご自愛下さい。
あ、私ですか?GWなんてないですよ(笑)基本的にお休みがないですから。なんと言っても、これは生き方だし、それは譲れないので。

話が変わって、この5月1日は私にとって、特別な日。それは、今から8年前の今日、大本山永平寺の修行を終えた日でもあり、3年前の今日は晋山式という正式に住職になる式をした日でもあります。
節目に当たり、今の自分と過去の自分を照らし合わせて、未来を見つめる。当たり前のようですが、淡々とこれを実行していこうと思います。
今朝のNHK Eテレでやっていた「にほんごであそぼ」に良いことばが紹介されていました。
「稽古とは 一より習い 十を知り 十よりかへる もとのその一」
千利休の言葉だそうです。まるで十牛図を短歌にしたような世界。まったく、そうありたいものです。
2012年04月13日
戒名なんて不要だ、と思うすべての方へ
先日のYahoo!ニュースに、『戒名必要ない56%、葬式簡素派9割…読売調査』というのがありました。
採り上げようかな~、と思っていたのですが、「花まつり」とか地元大手町お花見と重なってしまって書くことが出来ませんでした。・・・余談ですが、お釈迦様の誕生日「花まつり」は、ちょっと想像以上にたくさんの方にお参り頂きました。有難うございます。甘茶ティーバッグは午前中に完売!ついでに大手町のお花見も楽しかった。いろんな世代が寄って(酔って、ではない・・・笑)、改めてコミュニティの強さを認識しました・・・。
さて、そうこうしているうちに、私の尊敬する曹洞宗僧侶、tenjin先輩のブログに『反・戒名不要論』という名ログを発見。ここに採り上げる次第です。
何度もこのブログで申し上げていますが、先輩は学生時代の寮の先輩で、私など及びもつかないほど該博で、同時に非常に優れた学僧でいらっしゃいます。密かに“平成の面山さま”と私なんかはお慕いしています。
そんな訳で、先輩のブログは、時事ネタ以外はかなり内容が高度で、正直、私程度の者が拝読しても理解できないところが多々あります。同時に、僧侶として共感を覚えたり、叱咤激励されている気分になったり、誠に得ること多し、なのです。
ですが、正直、仏教や禅の知識のない方が読まれると、何を言っているのか多分本当に分からないと思うんですね(笑)で、このブログは“一般の方(特に西光寺の檀家さん)にお読み頂く”ことを標榜しているので、先輩のブログに私自身が学ばせて貰っても、それをあまり公開することはありませんでした。(あ、でも本当に素晴らしいブログですよ!)
と言うことで、前置きが非常に長くなってしまいましたが、本題に入ります。
まずは、tenjin師のログをご覧下さい。
http://blog.goo.ne.jp/tenjin95/e/a43878f52687519e199e103363d2a400?fm=rss
補足的に結論だけ言うと、曹洞宗の葬儀は“戒名と不可分”なのです。何故ならば、葬儀の中に“授戒”というパートがあるからです。これは戒を戒師(=導師)より故人に授けられ、これを以てはじめて「仏となる=成仏」とするのであり、その証として血脈(けちみゃく)と戒名が授けられるのです。その“成仏の証”として、そして“仏としての名”としてのものが戒名であります。
ですから、生前の生き様や、季節や、お名前の人文字、性格、趣味やその他さまざまな事を考慮して、住職は故人様に戒名を授けます。もちろん、仏教に関係した言葉で。(逆に言えば、だから生前でも授与される)まさに“名付けの親”になるわけです。
この点で、明言しておきますが“自分で戒名をつけた”というのは戒名として定義されません。そんな単純で基本的なことも知らないままマスコミは、某落語家の“自分でつけた戒名”とやらで一頻り騒いだりするわけです。
だから、戒名が不要だ、と言う方は、少なくとも禅宗式の葬儀は“できない”と思って下さい。不可分だからです。禅宗に限らず基本的に浄土系以外の宗派の葬儀も同様に“授戒”という形式があると聞いています。
で、問題は“何故、みなさんは戒名を不要と思うか”であります。そこを考えることが、僧侶にとっても、みなさんにとっても大切な事だと思います。もちろん、僧侶側のこうした「葬儀の説明」が不足している、という批判もあるでしょう。それに葬儀(というか死が)はいつ行われるか分からない。だから“事前に説明を受ける”ことも絶対に可能だ、とは言えません。
ですが、みなさんは例えば私のような僧侶が“葬儀や戒名”について、上記のようにお話したとして、それを真摯に受け止めてくれるでしょうか?もちろん、これをご覧の方々は“Yes”と仰ってくれるかもしれない。しかし、みんながみんなそうでしょうか?
お寺や仏教に対する偏見や先入観にまみれた方々に、いくら我々が声をからして訴えたとしても、所詮は“聞く耳持たない”ものです。現実、そういう方を何十人も私は見てきています。
おっと、いつになく愚痴っぽくなりました(汗)

話を戻して、まぁ一般的に“戒名が不要=戒名料が法外に高い”という考えがあるからでしょうね。ちなみに西光寺では特例を除き“戒名料”という独立した名目の御布施は納めて貰っていません。前述のように“葬儀と不可分”だからです。
とにかく、こうして問題になったこと自体、それがそのまま問題なのではありません。「過ちと知りて改めざる、これを過ちという」と儒教でも言いますよね。折角なので、葬儀の意味について、戒名について、みなさんも少し学ばれては如何でしょうか?
そうすれば、“良いと思うから必要、悪いと思うから不要”という短絡的で自己中心的な問題を超えた先が見えると思います。・・・そんなの個人の自由じゃん、と思う方は、その“個人の自由”ですら他者や環境との関わりの中で、たまたまそう勝手に思い込んでいるだけのものと知った方が良いですよ。つまりは他者との関係とは不可分のもので、独立的で絶対的な自由などというものは、所詮は幻想に過ぎない、というごくごく基本的なセオリーも知らない浅はかな考えだ、ということ。
蛇足。このブログは「一般の方(特に西光寺の檀家さん)」をターゲットとしていますが、その実、かなり同業者がご覧になっているご様子。この問題を機に、我々自身も教化の在り方を考えなくてはいけないかもしれませんね。
採り上げようかな~、と思っていたのですが、「花まつり」とか地元大手町お花見と重なってしまって書くことが出来ませんでした。・・・余談ですが、お釈迦様の誕生日「花まつり」は、ちょっと想像以上にたくさんの方にお参り頂きました。有難うございます。甘茶ティーバッグは午前中に完売!ついでに大手町のお花見も楽しかった。いろんな世代が寄って(酔って、ではない・・・笑)、改めてコミュニティの強さを認識しました・・・。
さて、そうこうしているうちに、私の尊敬する曹洞宗僧侶、tenjin先輩のブログに『反・戒名不要論』という名ログを発見。ここに採り上げる次第です。
何度もこのブログで申し上げていますが、先輩は学生時代の寮の先輩で、私など及びもつかないほど該博で、同時に非常に優れた学僧でいらっしゃいます。密かに“平成の面山さま”と私なんかはお慕いしています。
そんな訳で、先輩のブログは、時事ネタ以外はかなり内容が高度で、正直、私程度の者が拝読しても理解できないところが多々あります。同時に、僧侶として共感を覚えたり、叱咤激励されている気分になったり、誠に得ること多し、なのです。
ですが、正直、仏教や禅の知識のない方が読まれると、何を言っているのか多分本当に分からないと思うんですね(笑)で、このブログは“一般の方(特に西光寺の檀家さん)にお読み頂く”ことを標榜しているので、先輩のブログに私自身が学ばせて貰っても、それをあまり公開することはありませんでした。(あ、でも本当に素晴らしいブログですよ!)
と言うことで、前置きが非常に長くなってしまいましたが、本題に入ります。
まずは、tenjin師のログをご覧下さい。
http://blog.goo.ne.jp/tenjin95/e/a43878f52687519e199e103363d2a400?fm=rss
補足的に結論だけ言うと、曹洞宗の葬儀は“戒名と不可分”なのです。何故ならば、葬儀の中に“授戒”というパートがあるからです。これは戒を戒師(=導師)より故人に授けられ、これを以てはじめて「仏となる=成仏」とするのであり、その証として血脈(けちみゃく)と戒名が授けられるのです。その“成仏の証”として、そして“仏としての名”としてのものが戒名であります。
ですから、生前の生き様や、季節や、お名前の人文字、性格、趣味やその他さまざまな事を考慮して、住職は故人様に戒名を授けます。もちろん、仏教に関係した言葉で。(逆に言えば、だから生前でも授与される)まさに“名付けの親”になるわけです。
この点で、明言しておきますが“自分で戒名をつけた”というのは戒名として定義されません。そんな単純で基本的なことも知らないままマスコミは、某落語家の“自分でつけた戒名”とやらで一頻り騒いだりするわけです。
だから、戒名が不要だ、と言う方は、少なくとも禅宗式の葬儀は“できない”と思って下さい。不可分だからです。禅宗に限らず基本的に浄土系以外の宗派の葬儀も同様に“授戒”という形式があると聞いています。
で、問題は“何故、みなさんは戒名を不要と思うか”であります。そこを考えることが、僧侶にとっても、みなさんにとっても大切な事だと思います。もちろん、僧侶側のこうした「葬儀の説明」が不足している、という批判もあるでしょう。それに葬儀(というか死が)はいつ行われるか分からない。だから“事前に説明を受ける”ことも絶対に可能だ、とは言えません。
ですが、みなさんは例えば私のような僧侶が“葬儀や戒名”について、上記のようにお話したとして、それを真摯に受け止めてくれるでしょうか?もちろん、これをご覧の方々は“Yes”と仰ってくれるかもしれない。しかし、みんながみんなそうでしょうか?
お寺や仏教に対する偏見や先入観にまみれた方々に、いくら我々が声をからして訴えたとしても、所詮は“聞く耳持たない”ものです。現実、そういう方を何十人も私は見てきています。
おっと、いつになく愚痴っぽくなりました(汗)

話を戻して、まぁ一般的に“戒名が不要=戒名料が法外に高い”という考えがあるからでしょうね。ちなみに西光寺では特例を除き“戒名料”という独立した名目の御布施は納めて貰っていません。前述のように“葬儀と不可分”だからです。
とにかく、こうして問題になったこと自体、それがそのまま問題なのではありません。「過ちと知りて改めざる、これを過ちという」と儒教でも言いますよね。折角なので、葬儀の意味について、戒名について、みなさんも少し学ばれては如何でしょうか?
そうすれば、“良いと思うから必要、悪いと思うから不要”という短絡的で自己中心的な問題を超えた先が見えると思います。・・・そんなの個人の自由じゃん、と思う方は、その“個人の自由”ですら他者や環境との関わりの中で、たまたまそう勝手に思い込んでいるだけのものと知った方が良いですよ。つまりは他者との関係とは不可分のもので、独立的で絶対的な自由などというものは、所詮は幻想に過ぎない、というごくごく基本的なセオリーも知らない浅はかな考えだ、ということ。
蛇足。このブログは「一般の方(特に西光寺の檀家さん)」をターゲットとしていますが、その実、かなり同業者がご覧になっているご様子。この問題を機に、我々自身も教化の在り方を考えなくてはいけないかもしれませんね。