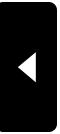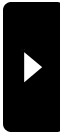2013年03月15日
その「祈り」に意味はあるのか?
先日、3.11慰霊行脚についてアップしました。
恥ずかしながら、というか蛇足ながら、いくつかの思うことを書いていきたいと思います。

(宮戸島の風景。あまりにも綺麗ですが、後ろを振り向くと、数軒の礎石を残して、堤防、家屋、みな流されております)
+++
行く前のこと。
まず、やはり端的に今回のことを”ブログに書くことが誇示すること”となりはしないか?という疑念がありました。
言ってみれば、これは今回のことに限らないんですけどね。
ただの増上慢、つまり”俺ってこんなに良いことをしたんだぜ!!”的な気持ちが表れてはこないだろうか?、もしくはブログに表記する=誇示しているのではないか、という自問です。もっと言えば、善意を売り物にしている、ということ。
これは、”ないつもり”で向かった電車の中でも、知らず知らずにその頭がもたげてくる。そんな気持ちで行っていないのに、ふとした瞬間に浮かんでしまう。まったく、名利の心は恐ろしいものです。(これ本音)
ただ、くどくなりますが、もう少し丁寧に吟味すると・・・
つまり、”書くことでよく思われたい”あるいは逆に”書くことで「坊主のくせに自慢してやがる」と言われるのを嫌がる”というのは、まったく反対のことを言っているようだけれども、実は「我が身かわいさ」故なのです。この我が身かわいさ、に気付いてしまった・・・克服できているとは口が裂けても言えませんが、少なくとも「気をつけていないと現れてくるのが、この”名利の心、我が身かわいさ”なんだな」とは感じました。
それに、『正法眼蔵随聞記』にも”世俗の法と仏教の法は違うものである。いたずらに、世法を仏法に当てはめるべきではない”というようなことも書かれていたと記憶しております。だから、仏法に生きる僧侶は、仏法に適う生き方を絶えず模索し、実践していかなければならないのでしょうね。
+++
それから、「祈り」に対して、根本的な疑問がありました。
すなわち「祈りって必要か?」ということ。「祈って何になる?」と言い換えてもいいかもしれません。
・・・ずいぶん不信心な発言に聞こえますよね。「坊主のくせに、よくそんなこと言うな」と不快に思われたらすみません。これもしかし、偽らざる本心だったりします。
「祈るってなんだろう」と結構真剣に考えたりしておりました。仏教的に、例えば「祈祷」という言葉があるので、その意味を禅学大辞典とか、織田得能仏教辞典で調べたりとか。・・・結局、よく分かりませんでした。
ただ、一つだけ言えるのは、今までの人生の中で自分は”本当に祈らなければならなかったこと”がほぼ皆無だったかもしれません。
まぁ、これは良いとか悪いとかは言えないのが難しいのですが・・・。
+++
「自分のやっていることは無駄なんじゃないか?」やはり行脚の前にも、考えます。
さて、当日は本当に寒く、前日が10度を優に超えていたのが嘘のようでした。雪は舞い散り、昨夜の一降りだけで10cmは積もっています。
そんな中、出かけた行脚。これは所謂行脚姿をして、手には鈴をもち、お経を唱えながら被災地を歩くもの。
被災した松島のお寺の檀家さんが先導してくださり、ところどころ特に多く亡くなられた場所に於いては、立ち止まり特別なお経を読みます。
瓦礫の山だったところは今は草が生え、何も知らなければ、もしかしたらただの空き地に見えたかもしれません。松林は壊滅的なダメージを受けたとは言え、何本も今なおその姿をたたえていますし、澄み渡った空には悠然と鳥が飛んでいる。口をつくお経が、まるで虚空に吸い込まれて、ただ静寂が残っているだけ、という圧倒的な空虚感すらしてきます。
とにかく、寒かった。また、電車も止まっていたくらい風が強かった。正直、手がかじかんで鈴を落としそうにもなりました。
その刹那、「意味があるとかないとか、それが戯論だったんじゃないか」と思えてきました。それって全部自分が基準。自分が意味があるとおもえば、だれに言われようとあるわけだし。ないものもない。それにしがみついている”自分”。
これは誤解の無いように言いますが「自分が良いと思えば、それでいい」というような幼稚な発想ではありません。
求めてくれる方がいて、提供できる"安心”があるならば、そしてそれが僧侶ができることであれば、やらない理由は一毫もありません。難癖をつけることは、実はそれもある種の我が身の優位性、または”やること、もしくはやらないことに言い訳を考えているだけ”を人に知られんとするからに他ならないのかもしれません。
かつて全国曹洞宗青年会の前会長が、さる講習会で、私共青年僧侶にこのように言われたことが、強く印象に残っています。
「みなさんの周りのお寺さん、とくにご年配の僧侶でも、”ああいうボランティアに従事することが坊さんの本来の活動だとは思わない。もっと他にやることがあるだろ?”と言われる方がいると思います。しかし、私は敢えて言います。それは”全くの戯論”である、と。」
(余談ですが、このあたりのことを含めて『正法眼蔵』「諸悪莫作」という巻が、最近、非常に強い力を持って私にせまってくる様な気がします。”気がします”と逃げているのは、あまりにも難しくて、よく分からないからです。でも、分からなくても「何かがある」ことはよく分かります。また参究してみたいと思います)
+++
法要の中で、啓白文(けいびゃくもん)という文章を読み上げます。
簡単に言えば、これは「法要の趣意書」であり、これを仏の前にて奉読するわけですが、今回、これを読まれたのが、この被災寺院(住職さんの命も建物も全てを失われた)の住職さんの弟さんでありました。
原文は覚えていませんが、途中「どんなに辛いことがあったこの場所だとしても、生き残った人はこの土地を離れないでくれ、生きてくれ。」という意味の言葉が出てきました。
実際、法要に参列された方はもちろん、このお寺のお檀家さんであり、亡き住職のお身内の方であった訳ですが、私が感じたのは”前を向いて生きている”ということでした。(ただし、これは全部がそうだとか、そういう簡単な話ではありません)
言うまでも無く、私が想像できないほどの辛苦を受けてこられたと思います。きっと、この方々も必死に祈り、涙を流され、悲しみにうちひしがれてここまでこられたんだろうと思います。その方々が淡々と、しかししっかりと生きておられる。そのお姿に衝撃に近い感激を受けました。
+++
法要後、遅い昼食をいただきに行きました。
まぁせっかくですから(笑)、名物の牛タンを。当然、僧衣を着たまま
ええ、皆さんご存知の「利久」です★
美味しくいただいて後、会計をしたとき、まだ20代後半とおぼしき若い男の店員さんが、たぶん接客で決められたフレーズであろう「ありがとうございました。またお越し下さい」と言われた後、私の姿をちらっと見られて言いました。
「ご苦労様でした。ありがとうございました。」
私は、この一言に、あの未曾有の震災直後に世界から絶賛された東北の美徳、美しい生き様、即ち自分をよく調え、他人を慮る気持ちが結実されていると感じました。そして私たち僧侶の生き方が、ほんの僅かでも、彼の地の方に安らぎを感じてもらえることができるなら、まだまだやれることはあるだろうと確信したのです。
+++
長文をお読み下さり、本当にありがとうございました。
今回のまとめです。
「祈るだけでは、何もはじまらない。
しかし、祈りからしか、何もはじまらない。」
恥ずかしながら、というか蛇足ながら、いくつかの思うことを書いていきたいと思います。

(宮戸島の風景。あまりにも綺麗ですが、後ろを振り向くと、数軒の礎石を残して、堤防、家屋、みな流されております)
+++
行く前のこと。
まず、やはり端的に今回のことを”ブログに書くことが誇示すること”となりはしないか?という疑念がありました。
言ってみれば、これは今回のことに限らないんですけどね。
「おほよそ菩提心の行願には、菩提心の発不発、行道不行道を世人にしられんことをおもはざるべし、しられざらんといとなむべし。いはんやみずから口称せんや。」『正法眼蔵』「谿声山色」巻
ただの増上慢、つまり”俺ってこんなに良いことをしたんだぜ!!”的な気持ちが表れてはこないだろうか?、もしくはブログに表記する=誇示しているのではないか、という自問です。もっと言えば、善意を売り物にしている、ということ。
これは、”ないつもり”で向かった電車の中でも、知らず知らずにその頭がもたげてくる。そんな気持ちで行っていないのに、ふとした瞬間に浮かんでしまう。まったく、名利の心は恐ろしいものです。(これ本音)
ただ、くどくなりますが、もう少し丁寧に吟味すると・・・
つまり、”書くことでよく思われたい”あるいは逆に”書くことで「坊主のくせに自慢してやがる」と言われるのを嫌がる”というのは、まったく反対のことを言っているようだけれども、実は「我が身かわいさ」故なのです。この我が身かわいさ、に気付いてしまった・・・克服できているとは口が裂けても言えませんが、少なくとも「気をつけていないと現れてくるのが、この”名利の心、我が身かわいさ”なんだな」とは感じました。
それに、『正法眼蔵随聞記』にも”世俗の法と仏教の法は違うものである。いたずらに、世法を仏法に当てはめるべきではない”というようなことも書かれていたと記憶しております。だから、仏法に生きる僧侶は、仏法に適う生き方を絶えず模索し、実践していかなければならないのでしょうね。
+++
それから、「祈り」に対して、根本的な疑問がありました。
すなわち「祈りって必要か?」ということ。「祈って何になる?」と言い換えてもいいかもしれません。
・・・ずいぶん不信心な発言に聞こえますよね。「坊主のくせに、よくそんなこと言うな」と不快に思われたらすみません。これもしかし、偽らざる本心だったりします。
「祈るってなんだろう」と結構真剣に考えたりしておりました。仏教的に、例えば「祈祷」という言葉があるので、その意味を禅学大辞典とか、織田得能仏教辞典で調べたりとか。・・・結局、よく分かりませんでした。
ただ、一つだけ言えるのは、今までの人生の中で自分は”本当に祈らなければならなかったこと”がほぼ皆無だったかもしれません。
まぁ、これは良いとか悪いとかは言えないのが難しいのですが・・・。
+++
「自分のやっていることは無駄なんじゃないか?」やはり行脚の前にも、考えます。
さて、当日は本当に寒く、前日が10度を優に超えていたのが嘘のようでした。雪は舞い散り、昨夜の一降りだけで10cmは積もっています。
そんな中、出かけた行脚。これは所謂行脚姿をして、手には鈴をもち、お経を唱えながら被災地を歩くもの。
被災した松島のお寺の檀家さんが先導してくださり、ところどころ特に多く亡くなられた場所に於いては、立ち止まり特別なお経を読みます。
瓦礫の山だったところは今は草が生え、何も知らなければ、もしかしたらただの空き地に見えたかもしれません。松林は壊滅的なダメージを受けたとは言え、何本も今なおその姿をたたえていますし、澄み渡った空には悠然と鳥が飛んでいる。口をつくお経が、まるで虚空に吸い込まれて、ただ静寂が残っているだけ、という圧倒的な空虚感すらしてきます。
とにかく、寒かった。また、電車も止まっていたくらい風が強かった。正直、手がかじかんで鈴を落としそうにもなりました。
その刹那、「意味があるとかないとか、それが戯論だったんじゃないか」と思えてきました。それって全部自分が基準。自分が意味があるとおもえば、だれに言われようとあるわけだし。ないものもない。それにしがみついている”自分”。
これは誤解の無いように言いますが「自分が良いと思えば、それでいい」というような幼稚な発想ではありません。
求めてくれる方がいて、提供できる"安心”があるならば、そしてそれが僧侶ができることであれば、やらない理由は一毫もありません。難癖をつけることは、実はそれもある種の我が身の優位性、または”やること、もしくはやらないことに言い訳を考えているだけ”を人に知られんとするからに他ならないのかもしれません。
かつて全国曹洞宗青年会の前会長が、さる講習会で、私共青年僧侶にこのように言われたことが、強く印象に残っています。
「みなさんの周りのお寺さん、とくにご年配の僧侶でも、”ああいうボランティアに従事することが坊さんの本来の活動だとは思わない。もっと他にやることがあるだろ?”と言われる方がいると思います。しかし、私は敢えて言います。それは”全くの戯論”である、と。」
(余談ですが、このあたりのことを含めて『正法眼蔵』「諸悪莫作」という巻が、最近、非常に強い力を持って私にせまってくる様な気がします。”気がします”と逃げているのは、あまりにも難しくて、よく分からないからです。でも、分からなくても「何かがある」ことはよく分かります。また参究してみたいと思います)
+++
法要の中で、啓白文(けいびゃくもん)という文章を読み上げます。
簡単に言えば、これは「法要の趣意書」であり、これを仏の前にて奉読するわけですが、今回、これを読まれたのが、この被災寺院(住職さんの命も建物も全てを失われた)の住職さんの弟さんでありました。
原文は覚えていませんが、途中「どんなに辛いことがあったこの場所だとしても、生き残った人はこの土地を離れないでくれ、生きてくれ。」という意味の言葉が出てきました。
実際、法要に参列された方はもちろん、このお寺のお檀家さんであり、亡き住職のお身内の方であった訳ですが、私が感じたのは”前を向いて生きている”ということでした。(ただし、これは全部がそうだとか、そういう簡単な話ではありません)
言うまでも無く、私が想像できないほどの辛苦を受けてこられたと思います。きっと、この方々も必死に祈り、涙を流され、悲しみにうちひしがれてここまでこられたんだろうと思います。その方々が淡々と、しかししっかりと生きておられる。そのお姿に衝撃に近い感激を受けました。
+++
法要後、遅い昼食をいただきに行きました。
まぁせっかくですから(笑)、名物の牛タンを。当然、僧衣を着たまま

ええ、皆さんご存知の「利久」です★
美味しくいただいて後、会計をしたとき、まだ20代後半とおぼしき若い男の店員さんが、たぶん接客で決められたフレーズであろう「ありがとうございました。またお越し下さい」と言われた後、私の姿をちらっと見られて言いました。
「ご苦労様でした。ありがとうございました。」
私は、この一言に、あの未曾有の震災直後に世界から絶賛された東北の美徳、美しい生き様、即ち自分をよく調え、他人を慮る気持ちが結実されていると感じました。そして私たち僧侶の生き方が、ほんの僅かでも、彼の地の方に安らぎを感じてもらえることができるなら、まだまだやれることはあるだろうと確信したのです。
+++
長文をお読み下さり、本当にありがとうございました。
今回のまとめです。
「祈るだけでは、何もはじまらない。
しかし、祈りからしか、何もはじまらない。」
2013年03月12日
3.11慰霊行脚の旅
大震災から2年がたちました。
3月10,11日と、東松島市へ行ってきました。慰霊法要、ならびに沿岸被災地の行脚に参加するためです。
今回の慰霊法要は、声明練習会(=節やメロディー付きのお経を勉強する会)を中心に全国から40数名の僧侶、虚無僧が集まり、行われました。
当日は大変寒く、雪が降り積もり、さらに舞い散る、という中での行脚、法要でした。

・・・何かを伝えたい、書かないと、と思うのですが、うまく言葉を紡げません。
また機会を見つけて書きます。菲才の身ゆえ、お許し下さい。
なんか丸投げ(投げやり??)な感じで大変申し訳ないのですが、同じく神奈川から参加されたkameno老師のブログが写真、説明共に完璧だと思いますので、よろしければご覧下さい。泰明も何ショットか写っています。
http://teishoin.net/blog/004869.html
http://teishoin.net/blog/004870.html
kamenoさん、ありがとうございます!この場をお借りして御礼申し上げます。
3月10,11日と、東松島市へ行ってきました。慰霊法要、ならびに沿岸被災地の行脚に参加するためです。
今回の慰霊法要は、声明練習会(=節やメロディー付きのお経を勉強する会)を中心に全国から40数名の僧侶、虚無僧が集まり、行われました。
当日は大変寒く、雪が降り積もり、さらに舞い散る、という中での行脚、法要でした。

・・・何かを伝えたい、書かないと、と思うのですが、うまく言葉を紡げません。
また機会を見つけて書きます。菲才の身ゆえ、お許し下さい。
なんか丸投げ(投げやり??)な感じで大変申し訳ないのですが、同じく神奈川から参加されたkameno老師のブログが写真、説明共に完璧だと思いますので、よろしければご覧下さい。泰明も何ショットか写っています。
http://teishoin.net/blog/004869.html
http://teishoin.net/blog/004870.html
kamenoさん、ありがとうございます!この場をお借りして御礼申し上げます。
2013年03月10日
これから東北(松島)入りします
いまから仙台経由で松島まで行ってきます。
明日の3.11 三回忌慰霊の行脚と法要に参加する為です。
これは、私が幹事を務めさせて頂いている声明会(=お経読み方練習会)と複数の声明会がジョイントして集結し、おつとめするというもの。
文字通り、行脚(=網代傘に手甲、脚絆という出で立ちで歩く)姿で、沿岸部を歩きながらお経を唱えます。
その後は、津波でご住職のお命が奪われた東松島のお寺にて慰霊法要です。
詳細は後日。
明日の3.11 三回忌慰霊の行脚と法要に参加する為です。
これは、私が幹事を務めさせて頂いている声明会(=お経読み方練習会)と複数の声明会がジョイントして集結し、おつとめするというもの。
文字通り、行脚(=網代傘に手甲、脚絆という出で立ちで歩く)姿で、沿岸部を歩きながらお経を唱えます。
その後は、津波でご住職のお命が奪われた東松島のお寺にて慰霊法要です。
詳細は後日。
2012年09月25日
『未来の住職塾』VS「現職研修会」2
前回のつづき
後編:僧侶は果たして”人びとのこころ”と向き合っているのか
前回からのつづきで、現職研修会、統一テーマの「人びとのこころに向き合うために」についてである。
この講義はロールプレイを行った。具体的には”相談者がお寺に来て、その相談を住職が聞く”という設定で、僧侶がそれぞれ”相談者””受け手(住職)””観察者(会話に入らずにやりとりを見守る)”の3役に分かれて演じる(=ロールプレイ)、というもの。
その”相談者の設定=シナリオ”を見て、私は驚愕した。
以上が設定である。
私が驚いたのは2点。
1つ目は、シナリオの荒さ(よく言えば自由度が高い)である。
このシナリオ、よ~く見ると、相談者の男性については、たったの2点しか書かれていない。
すなわち、20歳の大学生であること、それから、父親に声を掛けなかったことを後悔しているという2点である。
これではまず相談者の役をやる方が困る。情報量が少なすぎる。話すことがない。どんな風に感じて、何を本当に悩んでいるのか、父親とは疎遠だったのか、どこに住んでいてどんな会社に勤めていたのか、心を通わせたくても人物像が全く浮かび上がってこない。
同時に、受け手=話を聞く住職役も大変である。相談する方も自分の気持ちや置かれた状況が分かっていないのに、答えるなんて土台無理な話。
これでは「人びとのこころと向き合うために」以前の問題で、その”こころ”すら設定できていない。当然向き合えない。
「向き合うために」と言うなら、人びとのこころを正しく理解しようとするのが最優先ではないか。
ここで私が思い出したのは「未来の住職塾」で行った”ペルソナ作り”というもの。
ここでいうペルソナ(ゲームじゃないよ・・・古!)とは、企業が商品を開発する際に、統計のデータを使った平均的な数値を元にするのではなく、仮想の人物を仕立て(と言っても、実在に限りなく近い=実在しててもおかしくない)、その人物が”購入するであろう”製品を作り出す、その”仮想の人物像”のことである。
これをお寺に置き換え、あるセグメントにお寺との縁を持ってもらうイベントや製品やプロジェクト(企業でいうなら商品)を考える、というグループワークをした。つまり、ペルソナを作り(=衆生を想定し)、商品(=仏縁)を作るのである。
ちなみに、その時の我がチームは(Wさん、Mくんありがとう!)かなり気合いが入っており(笑)、作り上げたペルソナは、およそ以下の通り。
いや、実際我がチームは数ヶ月前まで大学生という方がいたので、ありえる設定に近づけたのだが、とにかく細かい。こんな細かくしなければならない理由は、それほど人の気持ちは推し量りがたいものだから。(であればこそ、より深い理解をしようとするのは慈悲心ではないか。)もちろん、この人物が仮にいたとして、実際に話す機会があったとしても、である。
だからこそ、この人物ならどう考え、どう悩み、どう喜ぶか、見えない相手に心を配るのである。

・・・話がだいぶ脱線したが、戻して驚愕の理由2点目。
2つ目は、そもそも相談内容の前に、この設定が”相談にくる存在なのか”、ということ。
私はどうしてもそれが気になり、グループディスカッションの時、同じグループの7人の僧侶に聞いてみた。「あなたのお寺で、20歳の大学生が相談に来たことがありますか?自死された方の遺族と接したことがありますか?」と。
前者でイエスと答えたのは0人、後者は1人だった。
正直に告白すると、これを聞いたとき、かなりの虚脱感に襲われた。
僧侶は悩める方の”受け皿”???それは本当にそうなのか?それって僧侶が勝手にそう思っているだけじゃないの??
図らずも、これが現実だ、と突きつけられた気がした。
結局、我々には、人びとがお寺へ相談にお越し下さるのかどうか、という根本的な視点が抜け落ち”困ったら普通はお寺に相談来るでしょ”という何か僧侶の増上慢的な考えが見え隠れする。
かつて曹洞宗総合研究センターが発刊した『僧侶』だったと思うが、そこに「信頼できる人は?」という一般人へのアンケート結果があったと記憶している(間違っていたらご指摘を)
そこでは、”僧侶は信頼できる”と答えた人のパーセンテージは一桁だった。しかも”占い師”に僅かに負けていた(もしくは勝っていたかも・・・しかしながら同じ一桁だった気がする)
同グループの僧侶にたずねたという先の数字が図らずも表しているように、相談されたことがない、接したことがないのなら、シンパシーを感じられなくて当然かもしれない。
だったら、まず考えるべきは、”相談される信頼関係”を檀家さまと構築するのが先決ではないのか。或いは檀家のみならず”相談するに足る人物”になることが。(もし『未来の住職塾』なら、間違いなく真っ先にここを考えるだろう)
もちろん、これは言うほど簡単ではないことは明白だ。、”相談に乗る”ことより”相談される関係になる”方が、遙かに多くの手順を必要とし、遙かに多く自分自身の生き方、在り方が問われる。
(前述と矛盾するし、本論から逸れるので詳述はしませんが、”頼られる僧侶”に結果としてなるのは良いと思う。でもそれを目指すのも、また間違いです)
実際、この時のグループディスカッションでも、50代とおぼしき先輩僧侶が「現職研修では、講師の先生が偉いこと言うけど、それを実践できるかどうか(がとても難しく、不安だ) 第一、ウチのお寺がある村も田舎だが”神も仏もあるものか!”とくってかかってくる檀家もおるし。そういう人に接するだけでも大変だ」と漏らしておられた。
私も日々現実の檀務(=業務)でイヤと言うほど理解しているし、実際落ち込んだり、打ちひしがれている。「ああ言えば良かった」、「あれは言うべきではなかった」などの反省は毎日である。
特に、今は護持会活動を中心として、お寺からの案内や、イベント、そして組織の構築に非力ながら力を入れているので、余計に強く思うことが多い。
(最近、私と同世代のイケメン檀家さんに”泰明さんは、ホントに高いコミュニケーション能力をお持ちですよね”と感心されたが、内心はこんなもんです・・・とほほ)
それはテクニックとか、理論などといった次元ではないからだ。
でも、である。1ミリでも相手が心を開いてくださる可能性があるのならば、その努力を怠ってはいけないような気がする。
それは決して距離という”結果”の問題などではなく、どこまでも歩み寄ろうとして続ける行為そのものなのだから。そしてその行為こそが、いわゆる慈悲の心がおこす利他行(りたぎょう)であり、仏教を単なる理論や思想ではなく、仏道という実践たらしめているものではなかろうか。
後編:僧侶は果たして”人びとのこころ”と向き合っているのか
前回からのつづきで、現職研修会、統一テーマの「人びとのこころに向き合うために」についてである。
この講義はロールプレイを行った。具体的には”相談者がお寺に来て、その相談を住職が聞く”という設定で、僧侶がそれぞれ”相談者””受け手(住職)””観察者(会話に入らずにやりとりを見守る)”の3役に分かれて演じる(=ロールプレイ)、というもの。
その”相談者の設定=シナリオ”を見て、私は驚愕した。
●シナリオ1
・男性:20歳(大学生)
・父親(52歳)を5年前に亡くした。
・父親は殆ど休みなく働いていた。
・出勤途中に自死してしまった。
・明らかに過労状態であった。
・当日の朝は、特に疲れた顔をしていたが、特に声もかけなかったこともあり、後悔している。
以上が設定である。
私が驚いたのは2点。
1つ目は、シナリオの荒さ(よく言えば自由度が高い)である。
このシナリオ、よ~く見ると、相談者の男性については、たったの2点しか書かれていない。
すなわち、20歳の大学生であること、それから、父親に声を掛けなかったことを後悔しているという2点である。
これではまず相談者の役をやる方が困る。情報量が少なすぎる。話すことがない。どんな風に感じて、何を本当に悩んでいるのか、父親とは疎遠だったのか、どこに住んでいてどんな会社に勤めていたのか、心を通わせたくても人物像が全く浮かび上がってこない。
同時に、受け手=話を聞く住職役も大変である。相談する方も自分の気持ちや置かれた状況が分かっていないのに、答えるなんて土台無理な話。
これでは「人びとのこころと向き合うために」以前の問題で、その”こころ”すら設定できていない。当然向き合えない。
「向き合うために」と言うなら、人びとのこころを正しく理解しようとするのが最優先ではないか。
ここで私が思い出したのは「未来の住職塾」で行った”ペルソナ作り”というもの。
ここでいうペルソナ(ゲームじゃないよ・・・古!)とは、企業が商品を開発する際に、統計のデータを使った平均的な数値を元にするのではなく、仮想の人物を仕立て(と言っても、実在に限りなく近い=実在しててもおかしくない)、その人物が”購入するであろう”製品を作り出す、その”仮想の人物像”のことである。
これをお寺に置き換え、あるセグメントにお寺との縁を持ってもらうイベントや製品やプロジェクト(企業でいうなら商品)を考える、というグループワークをした。つまり、ペルソナを作り(=衆生を想定し)、商品(=仏縁)を作るのである。
ちなみに、その時の我がチームは(Wさん、Mくんありがとう!)かなり気合いが入っており(笑)、作り上げたペルソナは、およそ以下の通り。
<ペルソナ>
・都内の有名私立大学工学部に在籍(エリート意識あり)する男性大学生
・両親は会社を経営。自宅は目黒。三階建ての持ち家で、家の車はポルシェ(金銭的に裕福)
・交際している彼女は、私立他大学で、テニスサークル(実態は遊びサークルだけど)で知り合う
・プログラミング能力に長け、研究室では他のゼミ生に一目置かれる存在
・主にSNSで友人たちと連絡をとり、BBQが好き
・しかし色白で背はすらっと高く、ブランドも好きなおしゃれさん
・尊敬する先輩から新興宗教に勧誘され、一応は入信しているようだが、根はさめている+友人たちに勧めたりもしない(宗教を信じるなんて、心が弱いのね的な上から目線を持っている)
・口癖は”夢はないんだよね”というニヒルな面も。だが、心底は”夢をみたい”と思っている
・バイトは塾講師+コンビニ
・・・以下略
いや、実際我がチームは数ヶ月前まで大学生という方がいたので、ありえる設定に近づけたのだが、とにかく細かい。こんな細かくしなければならない理由は、それほど人の気持ちは推し量りがたいものだから。(であればこそ、より深い理解をしようとするのは慈悲心ではないか。)もちろん、この人物が仮にいたとして、実際に話す機会があったとしても、である。
だからこそ、この人物ならどう考え、どう悩み、どう喜ぶか、見えない相手に心を配るのである。

・・・話がだいぶ脱線したが、戻して驚愕の理由2点目。
2つ目は、そもそも相談内容の前に、この設定が”相談にくる存在なのか”、ということ。
私はどうしてもそれが気になり、グループディスカッションの時、同じグループの7人の僧侶に聞いてみた。「あなたのお寺で、20歳の大学生が相談に来たことがありますか?自死された方の遺族と接したことがありますか?」と。
前者でイエスと答えたのは0人、後者は1人だった。
正直に告白すると、これを聞いたとき、かなりの虚脱感に襲われた。
僧侶は悩める方の”受け皿”???それは本当にそうなのか?それって僧侶が勝手にそう思っているだけじゃないの??
図らずも、これが現実だ、と突きつけられた気がした。
結局、我々には、人びとがお寺へ相談にお越し下さるのかどうか、という根本的な視点が抜け落ち”困ったら普通はお寺に相談来るでしょ”という何か僧侶の増上慢的な考えが見え隠れする。
かつて曹洞宗総合研究センターが発刊した『僧侶』だったと思うが、そこに「信頼できる人は?」という一般人へのアンケート結果があったと記憶している(間違っていたらご指摘を)
そこでは、”僧侶は信頼できる”と答えた人のパーセンテージは一桁だった。しかも”占い師”に僅かに負けていた(もしくは勝っていたかも・・・しかしながら同じ一桁だった気がする)
同グループの僧侶にたずねたという先の数字が図らずも表しているように、相談されたことがない、接したことがないのなら、シンパシーを感じられなくて当然かもしれない。
だったら、まず考えるべきは、”相談される信頼関係”を檀家さまと構築するのが先決ではないのか。或いは檀家のみならず”相談するに足る人物”になることが。(もし『未来の住職塾』なら、間違いなく真っ先にここを考えるだろう)
もちろん、これは言うほど簡単ではないことは明白だ。、”相談に乗る”ことより”相談される関係になる”方が、遙かに多くの手順を必要とし、遙かに多く自分自身の生き方、在り方が問われる。
(前述と矛盾するし、本論から逸れるので詳述はしませんが、”頼られる僧侶”に結果としてなるのは良いと思う。でもそれを目指すのも、また間違いです)
実際、この時のグループディスカッションでも、50代とおぼしき先輩僧侶が「現職研修では、講師の先生が偉いこと言うけど、それを実践できるかどうか(がとても難しく、不安だ) 第一、ウチのお寺がある村も田舎だが”神も仏もあるものか!”とくってかかってくる檀家もおるし。そういう人に接するだけでも大変だ」と漏らしておられた。
私も日々現実の檀務(=業務)でイヤと言うほど理解しているし、実際落ち込んだり、打ちひしがれている。「ああ言えば良かった」、「あれは言うべきではなかった」などの反省は毎日である。
特に、今は護持会活動を中心として、お寺からの案内や、イベント、そして組織の構築に非力ながら力を入れているので、余計に強く思うことが多い。
(最近、私と同世代のイケメン檀家さんに”泰明さんは、ホントに高いコミュニケーション能力をお持ちですよね”と感心されたが、内心はこんなもんです・・・とほほ)
それはテクニックとか、理論などといった次元ではないからだ。
でも、である。1ミリでも相手が心を開いてくださる可能性があるのならば、その努力を怠ってはいけないような気がする。
それは決して距離という”結果”の問題などではなく、どこまでも歩み寄ろうとして続ける行為そのものなのだから。そしてその行為こそが、いわゆる慈悲の心がおこす利他行(りたぎょう)であり、仏教を単なる理論や思想ではなく、仏道という実践たらしめているものではなかろうか。
2012年09月24日
『未来の住職塾』VS「現職研修会」1
前編:アウトライン
いきなり刺激的なタイトルだが、別に優劣をつける意図が有るわけではないのでご了承を・・・。
とりあえずは、両講座の概略から。
「未来の住職塾」は、既に高名なインターネットヴァーチャル超宗派寺院 彼岸寺の松本師が主催する”お寺の未来を考えるセミナー”である。現在全国5会場、各会場15名程度の、宗派も年齢もバラバラの僧侶が参加している。
このセミナーが耳目を集めるのは、東大卒にしてMBAホルダーの現役僧侶、松本師が、ドラッカーなどのいわゆる”マネジメント”理論を駆使し、それを中心に据えた異色のセミナーだからである。
しかし、表面的なプロフィールやマスコミでの採り上げられ方、或いは”外から見ているイメージ”に反して、内実、何もエキセントリックなことをしている訳ではない。
畢竟、こうした理論を自分のお寺にどう当てはめて、いかにしてより良い関係を檀家さまと築きあげ、良いお寺にしていくか、更には僧侶としてどういう歩みを進めるべきか、を具に考えることがメインテーマである。(むしろ私なぞは、講義が終わると”僧侶としての道心”が常に問いつめられている様な気がして、いつも反省しきり)
「現職研修会」とは、曹洞宗の55歳以下の僧侶が対象で、1年に必ず一度受講義務のある原則2日間の講座のことである。
基本的には宗務所単位(説明が面倒なので、ほぼ都道府県別、と思ってください)で企画・開催され、愛知県は4コマの授業で構成される。
曹洞宗の僧侶においては、もっとも基本的で、かつ重要な講義といって差し支えない。
ちなみに愛知県下は、数百人の対象僧侶が集まり、二日間の講義を受ける。
さて、図らずもその両講座を立て続けに受講して気づいたことがある。
始めに断っておくが、以下は現職研修会に対する曹洞宗宗務庁への批判ではない。そのように取られる懸念があるから先に書いておく。
また、現職研修会は4つのジャンル(4科目、と言った方が分かり易い)に分けられており、今から申し述べることは、今年の「統一テーマ」すなわち、曹洞宗が全国一律で決めるジャンルについてでしかない。つまりは、現職研修会の内容全てではなく一部を採り上げるのみである。

さて、長々と前置きを記したが、本題に移る。
今年の曹洞宗の現職研修会、統一テーマとして決められたのは「人びとのこころに向き合うために」というものである。
このテーマの主眼には、現代のストレス社会が生み出す、家族や会社或いは学校の人間関係の不和、またストレスによる身体的、精神的疾患や肥大化する苦悩に対し、我々僧侶が”受け皿”として、どう向き合っていったら良いのか、ということにある。
精神的な”受け皿”として期待されているとはいえ、しかしながら、実際は、悩める方にどのように対応すればよいのか、僧侶自身も少なからず迷いがあり、不安がある。
それに対し、”いかにして人びとの苦悩に向き合い寄り添うことが出来るか”の基本的なスキルと意識の向上を目的としたのが、今回のテーマである。
さて、実はこのテーマ2年連続で開かれ、昨年度の実習は「手紙で相談を受けた場合」であったようだ。(残念ながら、昨年は受講できなかった)
そして、本年は「面接相談のロールプレイ」が行われた。
ロールプレイとは、要するに”相談者がお寺に来て、その相談を住職が聞く”という設定で、僧侶がそれぞれ”相談者役””受け手役(=住職)””観察者(会話に入らずにやりとりを見守る)”の3役に分かれて演じる(=ロールプレイ)、というもの。
最初に、概論的な講義があった。例えば、相談者に対して”自死念慮を持っていると推察される方には敢えてその気持ちを問い、言葉にさせることで、思いとどまらせる可能性が増える”、とか”安易に仏教の教義を持ち出さない”とか、”分析的、解釈的な理解で結論を出さない”などと言ったこと。
1チームはおよそ8名で、実際のロールプレイを2回行った。
相談事は、あらかじめ紙が配られ、そこには相談者の年齢や置かれた状況・悩みなどのシナリオが書かれている。
相談者の役はこれを読み、その身になったつもりで”受け手(住職)”に相談をする。
一回のロールプレイが終わったら、”相談者””受け手””観察者”の順で感想を述べ合う。そして改善点などをディスカッションするという流れ。
文字にすると、非常に具体的で実践的なセミナーに思える。だが、ここには大きな落とし穴があったように感じられた。
まず始めに、グループ分けと役割(ロール)決め。
他の会場ならいざ知らず、愛知県の会場は人数も多い。当然、周りは全く知らない僧侶ばかり、ということも多々ある。にも関わらず、あまりにもグループ分けと役割決めが拙速、お互い目配せするだけで進まない。
こうしたとき、例えば「9月生まれの方は相談者をやってください。いなければ10月生まれ」とか「年齢の一番下の方が受け手をやってください」など講師からの指示があれば割に早い。おかげで、今回のロールプレイは当初、きわめてギクシャクした関係からスタートした。
ま、このグループ分けや役割決めは実はたいした問題ではない。こんなことは、他の組織だって起こりうることだし、人生の様々な点で起こりうる。
が、私は次の”相談者の設定=シナリオ”を見て驚愕した。
*後半へつづく
いきなり刺激的なタイトルだが、別に優劣をつける意図が有るわけではないのでご了承を・・・。
とりあえずは、両講座の概略から。
「未来の住職塾」は、既に高名なインターネットヴァーチャル超宗派寺院 彼岸寺の松本師が主催する”お寺の未来を考えるセミナー”である。現在全国5会場、各会場15名程度の、宗派も年齢もバラバラの僧侶が参加している。
このセミナーが耳目を集めるのは、東大卒にしてMBAホルダーの現役僧侶、松本師が、ドラッカーなどのいわゆる”マネジメント”理論を駆使し、それを中心に据えた異色のセミナーだからである。
しかし、表面的なプロフィールやマスコミでの採り上げられ方、或いは”外から見ているイメージ”に反して、内実、何もエキセントリックなことをしている訳ではない。
畢竟、こうした理論を自分のお寺にどう当てはめて、いかにしてより良い関係を檀家さまと築きあげ、良いお寺にしていくか、更には僧侶としてどういう歩みを進めるべきか、を具に考えることがメインテーマである。(むしろ私なぞは、講義が終わると”僧侶としての道心”が常に問いつめられている様な気がして、いつも反省しきり)
「現職研修会」とは、曹洞宗の55歳以下の僧侶が対象で、1年に必ず一度受講義務のある原則2日間の講座のことである。
基本的には宗務所単位(説明が面倒なので、ほぼ都道府県別、と思ってください)で企画・開催され、愛知県は4コマの授業で構成される。
曹洞宗の僧侶においては、もっとも基本的で、かつ重要な講義といって差し支えない。
ちなみに愛知県下は、数百人の対象僧侶が集まり、二日間の講義を受ける。
さて、図らずもその両講座を立て続けに受講して気づいたことがある。
始めに断っておくが、以下は現職研修会に対する曹洞宗宗務庁への批判ではない。そのように取られる懸念があるから先に書いておく。
また、現職研修会は4つのジャンル(4科目、と言った方が分かり易い)に分けられており、今から申し述べることは、今年の「統一テーマ」すなわち、曹洞宗が全国一律で決めるジャンルについてでしかない。つまりは、現職研修会の内容全てではなく一部を採り上げるのみである。

さて、長々と前置きを記したが、本題に移る。
今年の曹洞宗の現職研修会、統一テーマとして決められたのは「人びとのこころに向き合うために」というものである。
このテーマの主眼には、現代のストレス社会が生み出す、家族や会社或いは学校の人間関係の不和、またストレスによる身体的、精神的疾患や肥大化する苦悩に対し、我々僧侶が”受け皿”として、どう向き合っていったら良いのか、ということにある。
精神的な”受け皿”として期待されているとはいえ、しかしながら、実際は、悩める方にどのように対応すればよいのか、僧侶自身も少なからず迷いがあり、不安がある。
それに対し、”いかにして人びとの苦悩に向き合い寄り添うことが出来るか”の基本的なスキルと意識の向上を目的としたのが、今回のテーマである。
さて、実はこのテーマ2年連続で開かれ、昨年度の実習は「手紙で相談を受けた場合」であったようだ。(残念ながら、昨年は受講できなかった)
そして、本年は「面接相談のロールプレイ」が行われた。
ロールプレイとは、要するに”相談者がお寺に来て、その相談を住職が聞く”という設定で、僧侶がそれぞれ”相談者役””受け手役(=住職)””観察者(会話に入らずにやりとりを見守る)”の3役に分かれて演じる(=ロールプレイ)、というもの。
最初に、概論的な講義があった。例えば、相談者に対して”自死念慮を持っていると推察される方には敢えてその気持ちを問い、言葉にさせることで、思いとどまらせる可能性が増える”、とか”安易に仏教の教義を持ち出さない”とか、”分析的、解釈的な理解で結論を出さない”などと言ったこと。
1チームはおよそ8名で、実際のロールプレイを2回行った。
相談事は、あらかじめ紙が配られ、そこには相談者の年齢や置かれた状況・悩みなどのシナリオが書かれている。
相談者の役はこれを読み、その身になったつもりで”受け手(住職)”に相談をする。
一回のロールプレイが終わったら、”相談者””受け手””観察者”の順で感想を述べ合う。そして改善点などをディスカッションするという流れ。
文字にすると、非常に具体的で実践的なセミナーに思える。だが、ここには大きな落とし穴があったように感じられた。
まず始めに、グループ分けと役割(ロール)決め。
他の会場ならいざ知らず、愛知県の会場は人数も多い。当然、周りは全く知らない僧侶ばかり、ということも多々ある。にも関わらず、あまりにもグループ分けと役割決めが拙速、お互い目配せするだけで進まない。
こうしたとき、例えば「9月生まれの方は相談者をやってください。いなければ10月生まれ」とか「年齢の一番下の方が受け手をやってください」など講師からの指示があれば割に早い。おかげで、今回のロールプレイは当初、きわめてギクシャクした関係からスタートした。
ま、このグループ分けや役割決めは実はたいした問題ではない。こんなことは、他の組織だって起こりうることだし、人生の様々な点で起こりうる。
が、私は次の”相談者の設定=シナリオ”を見て驚愕した。
*後半へつづく
タグ :未来の住職塾ファン・デル・ローエ
2012年09月13日
神仏和合-神職さんと僧侶が語らう日-
いやぁ、先手を取られました(笑)
まずは、「彼岸寺」(ヴァーチャル超宗派寺院)のこの記事をご覧下さい。
(以下、文・写真は彼岸寺のサイトより抄出)
2012年8月22日、東京・神田明神にて「神仏和合― 今、知りたい神道 仏教のこと」を開催しました。当日は、神職12名、僧侶18名が参加し、笑い声の絶えない和やかな雰囲気で、活発な情報交換が行われました。
*神道と仏教が積み上げてきた歴史を"知る"
まずはじめに、主催者友光より「子供が生まれたらお宮参り、七五三で神社へ行って写真撮って、お盆に実家帰ってお墓参りがあって、地元のお祭りの太鼓の練習して友達作って、神輿担いで親父の背中を追い抜いて、新年は初詣行って、親が亡くなったら葬式に坊さん呼んでお経上げてもらう。そうやって地域とのつながりや親との付き合い、先祖とのつながりを作ってきたのが今の日本人と信仰、心の姿だと思います。お互いが長い間積み上げてきた歴史を知ることで、今後の個々の活動に活かせる視点やアイディアを持ち帰って下さい」という旨の挨拶の後、手水をとり、神田明神本殿にて正式参拝を行いました。
お祓いと共に雅楽の演奏と巫女舞を奉納していただき、神社での参拝作法として玉串奉奠(たまぐしほうてん)の作法を教えていただきました。
参拝の後は、神田明神の権宮司である清水さんによる「神社概説セミナー」です。近代における神道、神社本庁の成り立ちや、神社と寺院の数の比較、神職と僧侶の数の比較などが示され、全国のコンビニの総数が四万店ある一方、八万社を持つ神道と七万七千の寺院を持つ仏教で協力関係を作れれば、それは日本にとって大きな力になるという前向きなご意見をいただきました。

*お坊さんが神職さんに聞きたいことは?
グループディスカッション(テーマを決めて班毎に意見をまとめるというものではなく班に分かれて僧侶から神職の方への自由な質問タイム)では、40分という短い時間でしたが、各版(ママ)からふだんは聞けないような突っ込んだ質問が行われていました。
・神道では亡くなられた方の魂がどこへ行くのか?
・廃寺になるお寺がありますが、廃神社はありますか?
・女性の宮司さんは居ますか?
・グリーフケアなどに神道はどういう関わり方をされていますか?
・全ての神社に共通する教義はありますか?
・悩みを持った参拝者の方に対してどういった話し、働きかけをしていますか?
共通する気づきとしては、お互いが勝手な思い込みでお互いを定義付けしていただけで、実際に顔をあわせて話をしてみると遠いようで近く、また多くの違いがありました。
仏教が経典や開祖をルーツとし「言葉や教義」によって人々と接していくのに対して、神道は「お祭りや自然の営みの中で感覚的」に癒しや人とのつながりを発生させているという点に違いの根源があるように感じました。
その後の懇親会でも話し足りない神職と僧侶が賑やかに話し合っていました。
今後継続開催していく中で、今までの日本にはなかった新しい神道と仏教のアクションを生み出していけそうな、多くの可能性が見えた第一回「神仏和合」でした。
次回は寺院で神職からの質問に答えます。仏教では宗派による見解の違いなどありますが、あえて最大公約数的な意見に終始せず、「うちの宗派ではこう言っている」「その上で私はこのように解釈し、檀家さんにはこう伝えています」といったように個人個人がいかに教義を受け止め、実践しているのかを神職の皆さんにお見せ出来れば、多少遠回りであっても、より深い理解と気づきが得れるのではと期待しています。
(以上、彼岸寺サイトより)
実は、極秘裏に(←ブログに書く時点で”極秘”ではないですが・・・)、この”神仏和合”とほぼ全く同じ企画を進めていた泰明。年末から来年初頭に開催できるかなぁ、と踏んでいたのですが。
見たとき「あぁ、先を越されちゃった」と思いました(笑)
ま、冗談はさておいて、こうした宗教間の対話が面白いと感じるのは、”自分の信仰で、自分はこう考える。こう生きるようになった”という、その宗教者固有の話と、社会一般から見て、文化的に或いは風習としてその宗教が実社会に与える影響を知る、という2つの面です。
特に、本文の最後にあった、”「うちの宗派ではこう言っている」「その上で私はこのように解釈し、檀家さんにはこう伝えています」といったように個人個人がいかに教義を受け止め、実践しているのかを”相手に伝えるって、簡単そうで、実は非常に難しいことだったりします。
だからこそ、内面的・個人的な話と、外面的・客観的な話がとても興味深いんですね。
逆に決してやってはいけないことは、”教義の議論”ですね。
信仰なんて、つきつめれば個人の問題でしかないわけで、それを他者に押しつけたり、他人をやりこめて優越感に浸るなんて言語道断。しかし、こんな基本的なことが、意外に分かっていない人が多い。
だから先日の「キリスト教にまなぶ」という研修会も、他の僧侶に”そんな研修会をする意味があるのか?”みたいなことを言われたりしました(涙)
ともあれ、こうした企画を通して、また一歩勉強をさせていただければ、と切に思っている泰明です。
まずは、「彼岸寺」(ヴァーチャル超宗派寺院)のこの記事をご覧下さい。
(以下、文・写真は彼岸寺のサイトより抄出)
2012年8月22日、東京・神田明神にて「神仏和合― 今、知りたい神道 仏教のこと」を開催しました。当日は、神職12名、僧侶18名が参加し、笑い声の絶えない和やかな雰囲気で、活発な情報交換が行われました。
*神道と仏教が積み上げてきた歴史を"知る"
まずはじめに、主催者友光より「子供が生まれたらお宮参り、七五三で神社へ行って写真撮って、お盆に実家帰ってお墓参りがあって、地元のお祭りの太鼓の練習して友達作って、神輿担いで親父の背中を追い抜いて、新年は初詣行って、親が亡くなったら葬式に坊さん呼んでお経上げてもらう。そうやって地域とのつながりや親との付き合い、先祖とのつながりを作ってきたのが今の日本人と信仰、心の姿だと思います。お互いが長い間積み上げてきた歴史を知ることで、今後の個々の活動に活かせる視点やアイディアを持ち帰って下さい」という旨の挨拶の後、手水をとり、神田明神本殿にて正式参拝を行いました。
お祓いと共に雅楽の演奏と巫女舞を奉納していただき、神社での参拝作法として玉串奉奠(たまぐしほうてん)の作法を教えていただきました。
参拝の後は、神田明神の権宮司である清水さんによる「神社概説セミナー」です。近代における神道、神社本庁の成り立ちや、神社と寺院の数の比較、神職と僧侶の数の比較などが示され、全国のコンビニの総数が四万店ある一方、八万社を持つ神道と七万七千の寺院を持つ仏教で協力関係を作れれば、それは日本にとって大きな力になるという前向きなご意見をいただきました。

*お坊さんが神職さんに聞きたいことは?
グループディスカッション(テーマを決めて班毎に意見をまとめるというものではなく班に分かれて僧侶から神職の方への自由な質問タイム)では、40分という短い時間でしたが、各版(ママ)からふだんは聞けないような突っ込んだ質問が行われていました。
・神道では亡くなられた方の魂がどこへ行くのか?
・廃寺になるお寺がありますが、廃神社はありますか?
・女性の宮司さんは居ますか?
・グリーフケアなどに神道はどういう関わり方をされていますか?
・全ての神社に共通する教義はありますか?
・悩みを持った参拝者の方に対してどういった話し、働きかけをしていますか?
共通する気づきとしては、お互いが勝手な思い込みでお互いを定義付けしていただけで、実際に顔をあわせて話をしてみると遠いようで近く、また多くの違いがありました。
仏教が経典や開祖をルーツとし「言葉や教義」によって人々と接していくのに対して、神道は「お祭りや自然の営みの中で感覚的」に癒しや人とのつながりを発生させているという点に違いの根源があるように感じました。
その後の懇親会でも話し足りない神職と僧侶が賑やかに話し合っていました。
今後継続開催していく中で、今までの日本にはなかった新しい神道と仏教のアクションを生み出していけそうな、多くの可能性が見えた第一回「神仏和合」でした。
次回は寺院で神職からの質問に答えます。仏教では宗派による見解の違いなどありますが、あえて最大公約数的な意見に終始せず、「うちの宗派ではこう言っている」「その上で私はこのように解釈し、檀家さんにはこう伝えています」といったように個人個人がいかに教義を受け止め、実践しているのかを神職の皆さんにお見せ出来れば、多少遠回りであっても、より深い理解と気づきが得れるのではと期待しています。
(以上、彼岸寺サイトより)
実は、極秘裏に(←ブログに書く時点で”極秘”ではないですが・・・)、この”神仏和合”とほぼ全く同じ企画を進めていた泰明。年末から来年初頭に開催できるかなぁ、と踏んでいたのですが。
見たとき「あぁ、先を越されちゃった」と思いました(笑)
ま、冗談はさておいて、こうした宗教間の対話が面白いと感じるのは、”自分の信仰で、自分はこう考える。こう生きるようになった”という、その宗教者固有の話と、社会一般から見て、文化的に或いは風習としてその宗教が実社会に与える影響を知る、という2つの面です。
特に、本文の最後にあった、”「うちの宗派ではこう言っている」「その上で私はこのように解釈し、檀家さんにはこう伝えています」といったように個人個人がいかに教義を受け止め、実践しているのかを”相手に伝えるって、簡単そうで、実は非常に難しいことだったりします。
だからこそ、内面的・個人的な話と、外面的・客観的な話がとても興味深いんですね。
逆に決してやってはいけないことは、”教義の議論”ですね。
信仰なんて、つきつめれば個人の問題でしかないわけで、それを他者に押しつけたり、他人をやりこめて優越感に浸るなんて言語道断。しかし、こんな基本的なことが、意外に分かっていない人が多い。
だから先日の「キリスト教にまなぶ」という研修会も、他の僧侶に”そんな研修会をする意味があるのか?”みたいなことを言われたりしました(涙)
ともあれ、こうした企画を通して、また一歩勉強をさせていただければ、と切に思っている泰明です。