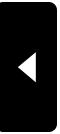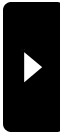2012年09月11日
今時の手元供養、ペンダントとか
もう、けっこう前の話になるんですが、現代仏壇やメモリアルペンダントのデザイナーをされている、どすごいブロガー、エプロンデザイナーさんが西光寺に来て下さり、お話をさせていただく機会を得ました。(この記事、書いておいたのにアップし忘れてた・・・ごめんなさい)
この数日前に、ご本人から”手元供養や、仏壇についての僧侶としての意見を伺いたい”、と丁寧なメールを頂戴し、今回の運びとなりました。地方ブログならでは。感謝です。
お会いしたこの日は、実は坐禅会の翌日で、なぜか昨夜のテンションそのままに、多岐にわたる会話ができました。(いや、正確にはこっちが話し散らした、という感じ・・・)
私自身も、手元供養やメモリアルペンダントの実態をお伺いすることができ、誠に得がたい、貴重な時間をいただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。
さて、手元供養とかメモリアルペンダントってどんなものかご存じでしょうか?
私は恥ずかしながら、よく知りませんでした。お骨の一部をペンダントに入れる、といったくらいの知識。
手元供養に至っては、まったくの無知。
今回のお話で、分骨(いわゆる、本山などに納骨する小さなお骨壺)をきれいにディスプレイして、文字通り手元で供養するのが手元供養だと知りました。
そのデザインを見せて頂き、また具体的に長男家系ではない方や、結婚された娘さん(つまり、直接的に自分の血縁の仏壇を置けない方)が手元供養をされている事実を知りました。彼ら彼女らの置かれた状況などを知り、いたく感心したのでした。勉強になります。
ただ、1つ気になったのが、ペンダントであれ、手元供養であれ、基本的に位牌や本尊と言った、いわば”敬うべき対象”がないことです。
「自分の家族が亡くなったんだから、別にお骨を祀るだけで何が悪い?!」と感じられるかもしれません。まぁ、その気持ちもわかります。悪くはないのかもしれない。
ですが、それって、結局のところ、”悲しいから、いつも手元に置いておきたい”という、言葉は悪いですが”ペット”即ち”愛玩の対象”になってはしませんか?
あまねく世界宗教が、本来”葬式の教え”ではないのにも関わらず、葬儀を、儀礼を執り行っているその背後には、”愛する人が死ぬというやりきれなさ”を何とか精算するためのものじゃないでしょうか。大部分の日本仏教が”没後作僧”という形式を採用したり、神への礼拝を通し”神のもとへ”というキリスト教の儀礼であったり(違っていたらごめんなさい)。
いずれにせよ、こうした儀礼には、宗教者が本来持っているだろう”慈しみの心”の発露であるし、同時に故人が”異化”(仏教の場合なら「ほとけ」という存在に転化)することで、ようやく少し安心できるのかな、と思います。
結局、言い方は悪いですが、宗教・信仰なき供養って(そもそも供養という単語自体が仏教語だが)、”もう使えないのに愛着のある鞄”を持っていることと変わらないのでは・・・と危惧しています。
ま、ともあれ、このとき”も”、とにかく私が一方的に話してしまって、後でけっこう反省したのですが(←こればっかり)、中でも印象的だったご質問をいただきました。それは・・・
「お坊さんとして、何をしているときが、一番楽しいですか?」というもの。
これ、結構難しいですよ!
一瞬戸惑いました。
楽しいこと・・・あんまりないような気がします(笑)
このときは、
「今の様に、仏教の話を、気軽に会話するようにできることです。
葬儀や法事の場ではなく、形式的な食事の席でもなく、大上段からの話でもなく、キャッチボールをするように、自然に仏教の話ができること、できる機会が、自分にとっての喜びです。」
とお答えしました。
もちろん、それはただ自分が話をした満足感という卑小なものではなく、相手の方が納得したり、新しいことに気づいて下さったり、新たな視座や知識を提供できれば、という条件付きですけど。
ともあれ、貴重な時間でした。
この数日前に、ご本人から”手元供養や、仏壇についての僧侶としての意見を伺いたい”、と丁寧なメールを頂戴し、今回の運びとなりました。地方ブログならでは。感謝です。
お会いしたこの日は、実は坐禅会の翌日で、なぜか昨夜のテンションそのままに、多岐にわたる会話ができました。(いや、正確にはこっちが話し散らした、という感じ・・・)
私自身も、手元供養やメモリアルペンダントの実態をお伺いすることができ、誠に得がたい、貴重な時間をいただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。
さて、手元供養とかメモリアルペンダントってどんなものかご存じでしょうか?
私は恥ずかしながら、よく知りませんでした。お骨の一部をペンダントに入れる、といったくらいの知識。
手元供養に至っては、まったくの無知。
今回のお話で、分骨(いわゆる、本山などに納骨する小さなお骨壺)をきれいにディスプレイして、文字通り手元で供養するのが手元供養だと知りました。
そのデザインを見せて頂き、また具体的に長男家系ではない方や、結婚された娘さん(つまり、直接的に自分の血縁の仏壇を置けない方)が手元供養をされている事実を知りました。彼ら彼女らの置かれた状況などを知り、いたく感心したのでした。勉強になります。
ただ、1つ気になったのが、ペンダントであれ、手元供養であれ、基本的に位牌や本尊と言った、いわば”敬うべき対象”がないことです。
「自分の家族が亡くなったんだから、別にお骨を祀るだけで何が悪い?!」と感じられるかもしれません。まぁ、その気持ちもわかります。悪くはないのかもしれない。
ですが、それって、結局のところ、”悲しいから、いつも手元に置いておきたい”という、言葉は悪いですが”ペット”即ち”愛玩の対象”になってはしませんか?
あまねく世界宗教が、本来”葬式の教え”ではないのにも関わらず、葬儀を、儀礼を執り行っているその背後には、”愛する人が死ぬというやりきれなさ”を何とか精算するためのものじゃないでしょうか。大部分の日本仏教が”没後作僧”という形式を採用したり、神への礼拝を通し”神のもとへ”というキリスト教の儀礼であったり(違っていたらごめんなさい)。
いずれにせよ、こうした儀礼には、宗教者が本来持っているだろう”慈しみの心”の発露であるし、同時に故人が”異化”(仏教の場合なら「ほとけ」という存在に転化)することで、ようやく少し安心できるのかな、と思います。
結局、言い方は悪いですが、宗教・信仰なき供養って(そもそも供養という単語自体が仏教語だが)、”もう使えないのに愛着のある鞄”を持っていることと変わらないのでは・・・と危惧しています。
ま、ともあれ、このとき”も”、とにかく私が一方的に話してしまって、後でけっこう反省したのですが(←こればっかり)、中でも印象的だったご質問をいただきました。それは・・・
「お坊さんとして、何をしているときが、一番楽しいですか?」というもの。
これ、結構難しいですよ!
一瞬戸惑いました。
楽しいこと・・・あんまりないような気がします(笑)
このときは、
「今の様に、仏教の話を、気軽に会話するようにできることです。
葬儀や法事の場ではなく、形式的な食事の席でもなく、大上段からの話でもなく、キャッチボールをするように、自然に仏教の話ができること、できる機会が、自分にとっての喜びです。」
とお答えしました。
もちろん、それはただ自分が話をした満足感という卑小なものではなく、相手の方が納得したり、新しいことに気づいて下さったり、新たな視座や知識を提供できれば、という条件付きですけど。
ともあれ、貴重な時間でした。
2012年07月28日
今時の若者(プチ坐禅会報告 -後半-)
暑いですね。
坐禅会の記事の続きを書こうと思ったら、すでに10日以上も放置してしまいました。なんか、いろいろあったこの頃です。
さて、もう忘れかけていますが、次回への備忘の意味も込めてメモ。
<次回へのリクエスト>
参加者の方々に懇親会中に今回の坐禅会について、伺いました。その時にいただいたご意見を書いてみます。
*坐禅時間
=今回は25分。どうやら大方の皆様にとってはちょうど良い長さだったみたいです。
・・・私も何度か坐禅をレクチャーさせてもらって、結果的に25分くらいはちょうどいいと感じていたので。
*坐禅中
=警策(バシッ!とたたくこと)の受け方を教えてほしい。
・・・やっぱり、みなさんのイメージの中では、坐禅と言ったらこれがつきものみたい。まぁ間違ってはいないんだろうけど。
=自分の姿勢がどれくらい曲がっているのか、こっそりデジカメで写してほしい。
・・・これは面白いですね。普通の坐禅会でこれをやっている人は皆無でしょう。
坐っている方からすると、何度も同じことばかり言われるのが不思議らしい。つまり、自分では”姿勢が曲がっている”と指摘されて、直すんだけど、また数分後に同じことを言われる。それが不思議みたい。ほんとに曲がってるの?さっき直したじゃん、というように。
そうでしょうね。これって案外自分の人生みたいで(笑)人から言われると直すんだけど、自分では”もうこれで直った!”と思っている。しかし、知らず知らずのうちに、またそのクセが現れてきてしまうんですね。これ、坐禅の姿勢も同じ。
*開催時期
=極寒にやりたい。
・・・これは何となくわかります。寒けりゃいいってもんでもないけど、たぶん寒い方が自分的に”修行している”と思いやすいんでしょうね。
*その他
=仏教概論みたいなことをしてほしい。
・・・これも面白いですね。坐禅会に来ている方だから、多少なりとも仏教を学びたい、という意識があるから、という意見を頂戴しました。なるほどね。でも大切なことだと思います。
=泰明の一日が知りたい
・・・そのためにこのブログがあるんですが(笑)もっと詳しく、タイムスケジュールも含めて、というリクエストがありました。

とまぁ、大まかにはこんな感じでした。みなさま、忌憚のないご意見をありがとうございました。
ただ、私の予想ではもっともっと”坐禅の効能”つまり、坐禅をしたらどうなるのか?何かいいことがあるのか?というような質問がたくさん出るかと思っていたのですが、存外なかったです。
個人的な反省点としては、とにかくしゃべりすぎたかな、と。もう少しコール&レスポンス的なトークにしたかったのですが、欲をかいて坐禅以外にも仏教全般や宗教についても話したので、たぶん、聞いている方はジャンルが多すぎて、散漫な印象を受けられたのでは、と反省。
どうしても、多角的な話をしたかったというのもあります。一様な話だと、みなさんがこの先、仏教や宗教に触れた時に、ゆがんだ理解になってしまうかも、という危惧があったり。ま、余計なお世話なんですけどね・・・。
坐禅会の記事の続きを書こうと思ったら、すでに10日以上も放置してしまいました。なんか、いろいろあったこの頃です。
さて、もう忘れかけていますが、次回への備忘の意味も込めてメモ。
<次回へのリクエスト>
参加者の方々に懇親会中に今回の坐禅会について、伺いました。その時にいただいたご意見を書いてみます。
*坐禅時間
=今回は25分。どうやら大方の皆様にとってはちょうど良い長さだったみたいです。
・・・私も何度か坐禅をレクチャーさせてもらって、結果的に25分くらいはちょうどいいと感じていたので。
*坐禅中
=警策(バシッ!とたたくこと)の受け方を教えてほしい。
・・・やっぱり、みなさんのイメージの中では、坐禅と言ったらこれがつきものみたい。まぁ間違ってはいないんだろうけど。
=自分の姿勢がどれくらい曲がっているのか、こっそりデジカメで写してほしい。
・・・これは面白いですね。普通の坐禅会でこれをやっている人は皆無でしょう。
坐っている方からすると、何度も同じことばかり言われるのが不思議らしい。つまり、自分では”姿勢が曲がっている”と指摘されて、直すんだけど、また数分後に同じことを言われる。それが不思議みたい。ほんとに曲がってるの?さっき直したじゃん、というように。
そうでしょうね。これって案外自分の人生みたいで(笑)人から言われると直すんだけど、自分では”もうこれで直った!”と思っている。しかし、知らず知らずのうちに、またそのクセが現れてきてしまうんですね。これ、坐禅の姿勢も同じ。
*開催時期
=極寒にやりたい。
・・・これは何となくわかります。寒けりゃいいってもんでもないけど、たぶん寒い方が自分的に”修行している”と思いやすいんでしょうね。
*その他
=仏教概論みたいなことをしてほしい。
・・・これも面白いですね。坐禅会に来ている方だから、多少なりとも仏教を学びたい、という意識があるから、という意見を頂戴しました。なるほどね。でも大切なことだと思います。
=泰明の一日が知りたい
・・・そのためにこのブログがあるんですが(笑)もっと詳しく、タイムスケジュールも含めて、というリクエストがありました。

とまぁ、大まかにはこんな感じでした。みなさま、忌憚のないご意見をありがとうございました。
ただ、私の予想ではもっともっと”坐禅の効能”つまり、坐禅をしたらどうなるのか?何かいいことがあるのか?というような質問がたくさん出るかと思っていたのですが、存外なかったです。
個人的な反省点としては、とにかくしゃべりすぎたかな、と。もう少しコール&レスポンス的なトークにしたかったのですが、欲をかいて坐禅以外にも仏教全般や宗教についても話したので、たぶん、聞いている方はジャンルが多すぎて、散漫な印象を受けられたのでは、と反省。
どうしても、多角的な話をしたかったというのもあります。一様な話だと、みなさんがこの先、仏教や宗教に触れた時に、ゆがんだ理解になってしまうかも、という危惧があったり。ま、余計なお世話なんですけどね・・・。
2012年07月19日
「坐禅ってすっごく新鮮ですね!」(プチ坐禅会報告)
7月16日、海の日の話。
夕刻、16時より、西光寺にてプチ坐禅会をしました。
まぁ、基本的に多くの禅宗寺院で坐禅会はしていると思います。定期的にであれ、スポット的にであれ。
西光寺でも、かつて(私が10代の頃まで)毎月8,18,28日の夜、坐禅会が開かれていました。
で、今回の坐禅会。今までのとは少し違う視点を盛り込んでみました。
1.開催日時
・・・前にfacebookで”GW最後の日って、なんかテンション下がるよね。そんなときに、坐禅でもしませんか?”と書いたところ、意外や意外、同世代の方の反応が良かったので、連休最終日に。
所謂サラリーマンに来て欲しかったので。しかも時間は早めスタート早め終わり(←結果的に”早め終わり”は出来なかった・・・汗)
2.レクチャー
・・・多分、一般的な坐禅会って、坐禅の仕方とか警策(きょうさく、と読みます。バシーン!ってたたくやつ)の受け方とか、基本作法とかいろいろ教わると思います。で、すぐに坐禅。
でも今回は、同世代をターゲットにしているので、敢えて細かい作法とか経典には触れませんでした。
逆に概論というか、禅の歴史は勿論だけど、”スティーブ・ジョブズとzen”とか、アメリカやフランスに与えた文化的側面としての禅、プラグマティックな禅、みたいな多面的な話をしました。最後に坐禅指導をしました。
3.懇親会
・・・これは下の4.とも関連があるけれど、兎に角、坐禅のみではなく、坐禅を体験して貰うことで、仏教に興味をもってほしいなぁ、と思うのです。
別に檀家を増やそうとか、曹洞宗の教義を押しつけるとかではなくて、ただ折角仏教という”すごい面白いコンテンツ”があるのに、それを知らない手はないんじゃないかと、私自身が思っているからです。
で、そうしたトークをする場所がどうしても必要だった。葬儀や法事の後席でもなく(基本親族がいるから+やはり故人を偲ぶ時間だと思うので)、さりとて、お寺の本堂で何十人も、というものでもなく(会話にならない)、あくまで、きちんと対話ができる距離感と人数で。
4.人数・年齢制限
・・・ということで、7人限定。私としては、結果これがジャストサイズ。とても良かった(お蔭で、しゃべりすぎた)
年齢制限はしていないんだけど、同世代をメインに据えているのは、同時代性(つまり、会話が”通じる”)を大切にしたいし、この世代って、多分ほとんど仏教や宗教に関して考えたこともないし、必要もないと思っているだろうから。
もちろん、これ以上の世代の方でも関心無い方は多いだろうし、逆もあるだろうし。

結局、仏教とりわけ禅なんかは、自己を究明し、自己(エゴ・我執)を放下することが肝だと思うんだけど、変に仏教の知識(しかも偏った)や、”人生の師”みたいに思われている世代って、こっちがどんなに話しても結局は聞いていないんだよね。聞いてたとしても、自分の経験・知識のなかで”置き換え可能な&理解可能な”情報に変質して分かったことにしちゃう。「俺知ってるよ」「おまえの言いたいことは分かるよ」的な。だから本当のところは届かない。そういうのを目の当たりにすると・・・(以下略)。
それなら、まるっと何にも知らない方に、仏教のいろんな面に触れて欲しかった。
興味ない点もあるだろうけど、何事も一面的な理解・一方的な決めつけなんて、大したことがない。というか、そういうのを捨てなよ、というのが仏教だったり、禅だったりするんだと思います。
また次の機会に。
2012年07月15日
伝えたいことがあるんだ。
*今日は幾分しのぎやすいですね。三連休のかたは楽しんでいらっしゃるでしょうか?さて、明日はいよいよ泰明主催の坐禅会です。昨夜から、レジュメを超!真剣に作ってます。*
ここんところ、檀家さまにお送りするお盆の案内状制作にかかりきりだ。
自分の文才の無さが恨めしい。
今までは、というか、ホントにここ数年前まで、西光寺が檀家さまにお送りする手紙は、春秋のお彼岸や、お盆の法要案内だけだった。寺報もない。もちろん、それをどうこういう気は毛頭無いし、それだって大変だ。かつては、手書きで何百という宛名を書いていたわけだし、文面もガリ版刷り(←って分かる?)
それが(僕が小さい時分に)パソコンを導入し、宛名はラベル印刷に。ドット印刷だったからキーカタカタ、という甲高い声が、いつも寺務所からしたもんだった。
それでも、封入物は手で折り、のり付けも勿論自分たちでしていた。今から考えると、途方もない作業だったが、それしかないのだから仕方がない。
繰り返すが、本当に、ここ数年までそんな感じ。で、今は”宛名や文面データを印刷会社に送信>封入までの全ての作業をしてくれる”というオートメーション化(?)に頼り切り。
その時に、はじめて、気がついた。(慣習、疑うことを知らないというのは恐ろしい)
他にも情報を載せよう、と。
今更のエクスキューズではないが、今まで皆無だった訳ではない。新聞の切り抜きや、お寺や住職に関する情報を法要の案内と共に入れていた。でも、本当に”伝えたいこと”はあったのか?我が身から出る言葉を紡いできたのだろうか?仏教の教えを、伝えたい!と切に思ったことはあったのだろうか?
・・・愕然とした。そうだ、ほとんどない。
そんなわけで、最近、護持会の活動や、お寺に関するあれこれ(豆知識など)を載せている。が、しかし、ここでも問題が。
伝えたい、知って欲しいとは思うのだが、前述の通り文才が無い。加えて、分かりやすいだけでいいのだろうか、と言う疑問も首をもたげる。わかりやすすぎると、かえって何も残らない。記憶にも。それ以上に、意味するところが曖昧で粗雑になり、ひいては誤謬を生む温床となる。しかし、専門用語をちりばめた、上から目線の物言いはしたくない。
そんなおり、先週、「布教師講習会」という会があった。実は私も布教師というお役を拝命したので、その研修会だ。
その時は、人権学習と、「典令(=ようするに法要の司会・解説のことですね)について」であった。
人権学習はさておき、典令について、大きなヒントをいただいた。
それは「復唱的解説」というもの。
簡単にいえばこんなかんじ。
「・・・導師さま、ご住職様が上殿されます。本堂にお上がりになられます。
導師さんが焼香された後、三拝いたします。五体投地のお拝を3度されます・・・」
ここで、「導師」「上殿」「三拝」というタームが出てくる。しかし、すぐに言葉を継いで、平易な解説をしている。なるほど~これなら、専門用語も残しつつ、さりとて専門用語を解さない方への配慮もできる。
では何故、専門用語を”残さないといけない”のか?だって、それは仏教のエレメントだからですよ。分かりやすければ何でもいいなんて、そんな人を馬鹿にしたことができますか。
話を明日の坐禅会にうつす。
前ログでアナウンスしたとおり、明日夕刻から坐禅会をします。
今回は明確に7人限定であること、できれば20~40代の方へ(そして所謂”宗教のしの字も知らないし、別にそんなのなくたって生きていけるよ”という、ごく一般的な方)参加して欲しい旨を明記した。果たせるかな、今回ご参加頂く方は、おおむねそのようだ。
坐禅会のレジュメは、世代も考慮し、多面的な説明、文化的な面にも触れた。
当たり前だが、坐禅とは?禅とは?というあたりから、世界的に広がりを見せる、Zen的な世界、文化面にも少し触れる。
専門外なので、さわりだけだが・・・特に、ビートニク(ビートジェネレーション)やその後のヒッピームーブメント、patagoniaのイヴォン・シュイナードや、最近では超有名なスティーブ・ジョブズの事などを記してみた。
果たしてどうなるでしょうか?
お楽しみに★
ここんところ、檀家さまにお送りするお盆の案内状制作にかかりきりだ。
自分の文才の無さが恨めしい。
今までは、というか、ホントにここ数年前まで、西光寺が檀家さまにお送りする手紙は、春秋のお彼岸や、お盆の法要案内だけだった。寺報もない。もちろん、それをどうこういう気は毛頭無いし、それだって大変だ。かつては、手書きで何百という宛名を書いていたわけだし、文面もガリ版刷り(←って分かる?)
それが(僕が小さい時分に)パソコンを導入し、宛名はラベル印刷に。ドット印刷だったからキーカタカタ、という甲高い声が、いつも寺務所からしたもんだった。
それでも、封入物は手で折り、のり付けも勿論自分たちでしていた。今から考えると、途方もない作業だったが、それしかないのだから仕方がない。
繰り返すが、本当に、ここ数年までそんな感じ。で、今は”宛名や文面データを印刷会社に送信>封入までの全ての作業をしてくれる”というオートメーション化(?)に頼り切り。
その時に、はじめて、気がついた。(慣習、疑うことを知らないというのは恐ろしい)
他にも情報を載せよう、と。
今更のエクスキューズではないが、今まで皆無だった訳ではない。新聞の切り抜きや、お寺や住職に関する情報を法要の案内と共に入れていた。でも、本当に”伝えたいこと”はあったのか?我が身から出る言葉を紡いできたのだろうか?仏教の教えを、伝えたい!と切に思ったことはあったのだろうか?
・・・愕然とした。そうだ、ほとんどない。
そんなわけで、最近、護持会の活動や、お寺に関するあれこれ(豆知識など)を載せている。が、しかし、ここでも問題が。
伝えたい、知って欲しいとは思うのだが、前述の通り文才が無い。加えて、分かりやすいだけでいいのだろうか、と言う疑問も首をもたげる。わかりやすすぎると、かえって何も残らない。記憶にも。それ以上に、意味するところが曖昧で粗雑になり、ひいては誤謬を生む温床となる。しかし、専門用語をちりばめた、上から目線の物言いはしたくない。
そんなおり、先週、「布教師講習会」という会があった。実は私も布教師というお役を拝命したので、その研修会だ。
その時は、人権学習と、「典令(=ようするに法要の司会・解説のことですね)について」であった。
人権学習はさておき、典令について、大きなヒントをいただいた。
それは「復唱的解説」というもの。
簡単にいえばこんなかんじ。
「・・・導師さま、ご住職様が上殿されます。本堂にお上がりになられます。
導師さんが焼香された後、三拝いたします。五体投地のお拝を3度されます・・・」
ここで、「導師」「上殿」「三拝」というタームが出てくる。しかし、すぐに言葉を継いで、平易な解説をしている。なるほど~これなら、専門用語も残しつつ、さりとて専門用語を解さない方への配慮もできる。
では何故、専門用語を”残さないといけない”のか?だって、それは仏教のエレメントだからですよ。分かりやすければ何でもいいなんて、そんな人を馬鹿にしたことができますか。
話を明日の坐禅会にうつす。
前ログでアナウンスしたとおり、明日夕刻から坐禅会をします。
今回は明確に7人限定であること、できれば20~40代の方へ(そして所謂”宗教のしの字も知らないし、別にそんなのなくたって生きていけるよ”という、ごく一般的な方)参加して欲しい旨を明記した。果たせるかな、今回ご参加頂く方は、おおむねそのようだ。
坐禅会のレジュメは、世代も考慮し、多面的な説明、文化的な面にも触れた。
当たり前だが、坐禅とは?禅とは?というあたりから、世界的に広がりを見せる、Zen的な世界、文化面にも少し触れる。
専門外なので、さわりだけだが・・・特に、ビートニク(ビートジェネレーション)やその後のヒッピームーブメント、patagoniaのイヴォン・シュイナードや、最近では超有名なスティーブ・ジョブズの事などを記してみた。
果たしてどうなるでしょうか?
お楽しみに★
2012年07月11日
若い坊さんが教会になだれ込む??
昨日、私の所属する東三河曹洞宗青年会主催の研修会が、日本基督教団豊橋教会で行われました。
そうです、私のような曹洞宗の若手僧侶(U40)が、他宗教を学ぶ目的で、教会をお借りし、牧師さんよりお話を頂戴したのです。
集まった青年僧侶21名。みな正装をして教会の席に着いた姿は、異様ともとれるし(笑)、美しい光景ともとれました。

結論から言えば、ものすごく充実した、有意義な研修会になりました。
先のログでも触れましたが、「他の宗教や宗派をまなぶことは、振り返って我が身の有り様、自身の信仰を自省し、より深く学ぶ機縁になる」と書きました。
また、そこでは触れませんでしたが、もっとも重要なのは、宗教の壁とか、宗派間の議論のあるなしではなく、畢竟「相手に対して敬意を抱き、学ばせて頂くという謙虚な態度」、これに尽きるかと思います。
これなくしては、どんな研修も意味のないものになりますし、教える側、学ぶ側双方にとって不幸なものになります。(というか、それがないから、やれ”壁”だの”論争”などになる。正義を振りかざして相手に迫るとき、そこに既に正義はないのです)
そうした点においては、価値のある研修になりました。
さて、当日はパワーポイントまで準備されている熱の入れよう。金子牧師さんにはただ感謝です。
事前の入念なる打ち合わせの賜か(←自意識過剰か?!笑)、短い時間ながらも非常に多面的なお話をいただきました。特に、宗教者として、というか宗教者だからこそお互いに理解できる深いお話もいただきました。
・日本基督教団について(プロテスタント、ということ。プロテスタントのなりたち)
・儀礼の意味や形(礼拝のプロット)
・牧師になるには(教団の養成システム・神学校でのカリキュラムや教育内容について)
・組織の形(教区や教派の在り方など)
・葬儀の意味や牧師としての役目(葬儀のスタイルや、進行にについて)
・現代に生きるキリスト者としてのメッセージ
・賛美歌「Amazing Grace -くすしきみ恵み-」体験

さらっと項目だけ書きましたが、これを1時間に凝縮してお話をいただきました。これだけでも、充分に興味深い内容です。
私個人としては、やはり、キリスト者としての生き方、特に「お見舞い」や「看取り」という生き方に強く感銘をうけました。
かつて、親しい檀家さんの最後に際し、ある僧侶が法衣を纏ってお見舞いに行ったそうです。すると、同じ病室の方から「もう来ないでくれ」と言われたとか。やはり僧侶=葬式という禁忌のイメージから一般の方が脱することができない象徴的なエピソードです。
それから、神学校のカリキュラムが興味深い。曹洞宗の教化研修所(という機関があるんです)のカリキュラムに相似していて、これも参考になりました。
また、少し驚いたのは、「日本の教会はカウンセリング=傾聴=人の話を聞く、という点で遅れている」というお話。先日も曹洞宗青年会で「傾聴について」の研修会があったばかりで、どちらかというとカウンセリングに関しては神父さんや牧師さん、キリスト教の宗教者が数段先を行っているイメージがありました。(たぶん、懺悔とか告白?のイメージなのかな・・・基本カトリックらしいですが)
牧師さんの口からその発言を伺うと、単純に驚きを隠せません。
最後の質疑応答も、想像以上に白熱し(というか、今までの研修会でこんなにも質疑がでたことはない)、時間も延長。そのまま熱気がさめやらぬ中、懇親会という「場外延長戦(笑)」に突入したのでした。
懇親会では、金子牧師ご夫妻のお人柄か、各テーブルで引っ張りだこ。時間も大幅に延長したのですが、まだまだお伺いしたいこと、対話したいことが山のようにある、という印象を受けました。
ともあれ、金子牧師ご夫妻と、教会を快く使わせてくださった教会関係者の皆様方には、この場をお借りして御礼申し上げます。
泰明 合掌
***おまけエピソード***
私だけちょっと早めに教会にお邪魔したのですが、先に近所の違う教派の牧師さんがお見えになっていました。なんでも金子牧師さんにお話があるとのことで、ふらりと。もちろん、この研修会のことはご存知ありません。
で、談たまたま研修会の話になり(プロジェクターとか準備してあるけど、今から何かあるの?)、私を紹介して頂いたのですが・・・
実はその牧師さんは、私の中学の同級生のお父様でした。これにはお互いびっくり!!
同級生の彼は教会の子だって当然知ってたし、その教会の場所まで知っていたのですが、まさかこのタイミングでお父様であるT牧師にお目にかかれるとは。まさに仏縁であります(笑)
とてもフランクな明るいT牧師。最後には「息子にメールで送るから」と言われ、私とツーショット写真を撮られました。
しかも、結局、そのまま研修会にもご臨席いただきました。誠に得難い貴重な時間を過ごすことができました。感謝の言葉もありません。
2012年07月09日
キリスト者との対話ーライブ報告
昨日は宮下町にある日本酒の美味しい居酒屋(というにはオシャレすぎますが・・・笑)「天に月、地に山」さんでライブ出演。
豊橋教会の金子牧師さんと共演を果たせました。牧師さんはじめ、店主の津谷さん、お越しくださった皆様にはただただ感謝です。
曲は、
1. Alberta - Eric Clapton ver.
2. Crazy Love -Van Morrison
3. Entertainer AKA 'Sting'
ー泰明のソロ
4. 中華料理 ー山崎まさよし
5. San Francisco Bay Blues - Eric Clapton ver.
でごさいました。牧師さんの選曲です。非常に渋いです。泰明も大好きな曲ばかりでした。反省点としては、話が長いこと、始まる前に飲み過ぎたことでしょうか(笑)

あ、あと失念していたユニット名はBJ Brothers でした。B=Buddha, J=Jesusであります。
ともあれ、楽しく演奏をさせていただきました。
閑話休題。
明日は、曹洞宗青年会の研修会で、日本基督教団豊橋教会にお邪魔して、お話を頂戴します。そう、また金子牧師さんです(笑)牧師さんと私、ほとんど毎日のように会っています。世間でいうところの恋人状態です( ´ ▽ ` )ノ
真面目な話、他の宗教を学ぶことは自らの信仰を考えること。そして、自らの信仰をより深く理解しようとするための気付きになりえます。
同時に、自らの信仰を深めることは、自身の信仰を絶対の正義として他者へ振りかざすことではなく、他者もまた自分と同じように彼等自身の信仰に対する態度を理解し、寛容することであります。
その意味で、他宗派や他宗教への学びは謙虚にしていきたいと私は感じています。
あと今ひとつ大切なことは、今、この日本の中において、等しく"宗教者"であり、その意味では立場や問題点は共有されるべきだろうということです。
その意味で、私たちが社会へコミットする、或いは敢えてコミットしない、何れにせよ、宗教団体が認知されている以上、それらの態度は今の日本の社会に対して必ずエフェクトがあります。
では、そのエフェクトをどう考えるか、更にどのようにアチーブしていくべきなのか、此処が時代を同じくして生きる宗教者に課せられた命題であろうと思います。
それを考えるとき、そこには教義や教学理解の闘争、論争、まして信仰心の濃淡など入る余地はありません。
であればこそ、対話をして、それを続けていくべきであろう、というのが本研修会のテーマであります。
・・・ま、何だかんだ言って、研修会の後の懇親会が楽しみなだけなんですけどね。なんちゃって(笑)
豊橋教会の金子牧師さんと共演を果たせました。牧師さんはじめ、店主の津谷さん、お越しくださった皆様にはただただ感謝です。
曲は、
1. Alberta - Eric Clapton ver.
2. Crazy Love -Van Morrison
3. Entertainer AKA 'Sting'
ー泰明のソロ
4. 中華料理 ー山崎まさよし
5. San Francisco Bay Blues - Eric Clapton ver.
でごさいました。牧師さんの選曲です。非常に渋いです。泰明も大好きな曲ばかりでした。反省点としては、話が長いこと、始まる前に飲み過ぎたことでしょうか(笑)

あ、あと失念していたユニット名はBJ Brothers でした。B=Buddha, J=Jesusであります。
ともあれ、楽しく演奏をさせていただきました。
閑話休題。
明日は、曹洞宗青年会の研修会で、日本基督教団豊橋教会にお邪魔して、お話を頂戴します。そう、また金子牧師さんです(笑)牧師さんと私、ほとんど毎日のように会っています。世間でいうところの恋人状態です( ´ ▽ ` )ノ
真面目な話、他の宗教を学ぶことは自らの信仰を考えること。そして、自らの信仰をより深く理解しようとするための気付きになりえます。
同時に、自らの信仰を深めることは、自身の信仰を絶対の正義として他者へ振りかざすことではなく、他者もまた自分と同じように彼等自身の信仰に対する態度を理解し、寛容することであります。
その意味で、他宗派や他宗教への学びは謙虚にしていきたいと私は感じています。
あと今ひとつ大切なことは、今、この日本の中において、等しく"宗教者"であり、その意味では立場や問題点は共有されるべきだろうということです。
その意味で、私たちが社会へコミットする、或いは敢えてコミットしない、何れにせよ、宗教団体が認知されている以上、それらの態度は今の日本の社会に対して必ずエフェクトがあります。
では、そのエフェクトをどう考えるか、更にどのようにアチーブしていくべきなのか、此処が時代を同じくして生きる宗教者に課せられた命題であろうと思います。
それを考えるとき、そこには教義や教学理解の闘争、論争、まして信仰心の濃淡など入る余地はありません。
であればこそ、対話をして、それを続けていくべきであろう、というのが本研修会のテーマであります。
・・・ま、何だかんだ言って、研修会の後の懇親会が楽しみなだけなんですけどね。なんちゃって(笑)