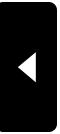2011年03月04日
仏教Q&A お寺を変わりたい!
<ご質問>
家は●●寺にお世話になっているようなんだけど、ちょっと信頼できない和尚様なんです。約束守らなかったり、お堂にほこりが積もってたり、花がドライフラワーになってたり…。出来たら自分の代から(考えたくないけど親が亡くなったら)■■寺に変えたいのだけど、そういうのって大丈夫なのでしょうか?
<回答>
菩提寺(お墓があったり、葬儀や年忌をお願いしているお寺)を変えたい、ということなのですが、はっきり言って”可能”です。
ただし、先方のお寺さんにきちんとご意向(離檀=檀家をやめること)をお伝えしてください。その際に、離檀料がかかるお寺もあるし(西光寺はありません、念のため)、境内に墓地があるなら、ほとんどのお寺は「墓地も引っ越ししてください」と言われると思います。(例外はありますし、豊橋で言うなら向山や飯村、梅田川霊園といった市営墓地にあるならその限りではありません)
すると、当然金銭的にも(お墓の撤去料は墓石屋さんに支払います)勿論の事、もしかしたら人的関係において(離檀を巡って住職と揉めるとか)も負担が質問者さんに降りかかってくると思うのです。そうであれば、互いに嫌な思いをしてまで、そして多額の費用をかけてまで先祖の眠る場所をあちこち引っ越していいのかなぁと思わないでもないのです。
まずは、機会があったら、今のお寺に通ってみて住職から話を聞いてみたり、苦言を呈してみたりしてはいかがですか?確かに、これは厳しい選択かもしれません。今まであまり付き合いがないのならなおさらですよね。それは承知しています。
ただ、こうやって檀家さんが働きかけないと(いや、働きかけなかったから)住職が堕落していったのかもしれません。逆に言えば、きちんとした檀家さんをお持ちのお寺は、決して堕落もしないし、経済的にも安定して、(そして結構大事ですが)評判も地に落ちるということはないと思います。それくらい、檀家さんというのは大切な存在です。鏡みたいなもんですから。
ちょっと質問者さんに酷なことを言っているかもしれません。私もそれは承知しています。
でも、人間ってだれでもそうですが、一人というのは弱いものです。ほとんどのお寺は、住職は一人で切り盛りをしています。修行していたって出家していたって、やっぱり1人は心細いもんです。1人だとできることも限られてくるし、社会的にもついていけなくなるし・・・だから、簡単にダメになってしまう恐れがある。(でも、1人でお住まいでも、素晴らしい住職はたくさんいますけどね)
その住職をかばうつもりは毛頭ないのですが、お檀家さんにはお寺を変える力がある、ということは知っておいてほしいと思います。
それでも、ど~~~~~~してもそのお寺が嫌だったら・・・またその時は私に相談してください。一緒に考えていきましょう。
家は●●寺にお世話になっているようなんだけど、ちょっと信頼できない和尚様なんです。約束守らなかったり、お堂にほこりが積もってたり、花がドライフラワーになってたり…。出来たら自分の代から(考えたくないけど親が亡くなったら)■■寺に変えたいのだけど、そういうのって大丈夫なのでしょうか?
<回答>
菩提寺(お墓があったり、葬儀や年忌をお願いしているお寺)を変えたい、ということなのですが、はっきり言って”可能”です。
ただし、先方のお寺さんにきちんとご意向(離檀=檀家をやめること)をお伝えしてください。その際に、離檀料がかかるお寺もあるし(西光寺はありません、念のため)、境内に墓地があるなら、ほとんどのお寺は「墓地も引っ越ししてください」と言われると思います。(例外はありますし、豊橋で言うなら向山や飯村、梅田川霊園といった市営墓地にあるならその限りではありません)
すると、当然金銭的にも(お墓の撤去料は墓石屋さんに支払います)勿論の事、もしかしたら人的関係において(離檀を巡って住職と揉めるとか)も負担が質問者さんに降りかかってくると思うのです。そうであれば、互いに嫌な思いをしてまで、そして多額の費用をかけてまで先祖の眠る場所をあちこち引っ越していいのかなぁと思わないでもないのです。
まずは、機会があったら、今のお寺に通ってみて住職から話を聞いてみたり、苦言を呈してみたりしてはいかがですか?確かに、これは厳しい選択かもしれません。今まであまり付き合いがないのならなおさらですよね。それは承知しています。
ただ、こうやって檀家さんが働きかけないと(いや、働きかけなかったから)住職が堕落していったのかもしれません。逆に言えば、きちんとした檀家さんをお持ちのお寺は、決して堕落もしないし、経済的にも安定して、(そして結構大事ですが)評判も地に落ちるということはないと思います。それくらい、檀家さんというのは大切な存在です。鏡みたいなもんですから。
ちょっと質問者さんに酷なことを言っているかもしれません。私もそれは承知しています。
でも、人間ってだれでもそうですが、一人というのは弱いものです。ほとんどのお寺は、住職は一人で切り盛りをしています。修行していたって出家していたって、やっぱり1人は心細いもんです。1人だとできることも限られてくるし、社会的にもついていけなくなるし・・・だから、簡単にダメになってしまう恐れがある。(でも、1人でお住まいでも、素晴らしい住職はたくさんいますけどね)
その住職をかばうつもりは毛頭ないのですが、お檀家さんにはお寺を変える力がある、ということは知っておいてほしいと思います。
それでも、ど~~~~~~してもそのお寺が嫌だったら・・・またその時は私に相談してください。一緒に考えていきましょう。
2011年03月03日
仏教Q&A 地鎮祭
<ご質問>
住宅の新築では、当たり前のように地鎮祭を行うのだけど、それってほぼ100%神主さんが来る神式のなんだけど、やっぱり仏式のもあるんですよね?
それとか、地鎮祭だけじゃなくて、上棟式や竣工式、建築関係の神式と仏式の違いみたいなものってあるのですか?
例えば、神式の地鎮祭って、神様に降りてきてもらって、これから建築工事するから守ってね的な話をして、みんなでお参りして、帰っていただいて、最後にお神酒でお開き(なおらい)をやるんだけど、地鎮祭一つとっても全然違いそう。どうなんでしょうか?
<回答>
いやぁ、これもいい質問ですね。質問者さんは建築関係のお仕事をされているそうで、それでこのような事を疑問に思われそうです。
まず、仏式の地鎮祭に関しては、存在します。実際に見たこともあります。(でもお寺ですが・・・笑)
ただし、上棟式はないと思います。(後日補:曹洞宗でも上棟式はあります。雲栄山さん、ご指摘いただきありがとうございました。)竣工式は「落慶式(らっけいしき)」という形で法要をするのが一般的です。
仏式の地鎮祭って、完全に神式を見倣って始められたと私は思ってましたが、どうもそうでもないらしいです。(その説明は後にします。)
さて、その仏式ですが、基本的には質問者さんの(つまり神式)流れと酷似しています。(たぶん、仏教が真似したんだろうと思いますが・・・)
最初に、土地を清める儀式をして、そして災いをなくし、工事を無事に円成できるようにとお経をよみ、参列者に焼香してもらって終わりです。
「鎮守」(ちんじゅ)という概念はみなさんご存知ですか?要するに土地を守る神様なんですが、こうした神様にお経を読むこともあるんですよ。(鎮守諷経、ちんじゅふぎん、と言います)
それ(鎮守)は仏教とか神道とかあまり意識する前の、更に古い日本人が持つ認識だと思います。というのも、最初に「神道のやり方を仏教がまねたと思っていたけど、違うみたい」と書きましたが、典拠になりそうな本を持ってました。(ラッキー
 )
)『神道祭祀 -神をまつることの意味-』(真弓常忠・朱鷺書房)がそれで、この中に「地鎮祭の記録」という項があります。(P307~311まで適宜参照)
これによると・・・
*『日本書紀』に拠れば持統天皇のころ、新しい都を作る際に地鎮祭が行われた。(神式)
*その後、藤原京や平城京の地鎮祭もおこなわれた。
*しかしそれより前、孝徳天皇(白雉二年)の頃には難波宮造営の際に”僧尼二千百余を請し”仏式で地鎮祭が行われた。
*地霊の鎮祭は宮殿の造営ではじまったわけではなく、既に弥生時代の祭祀がそうであった。
*この大地はもとより地上の万物、すべて神の坐す処として崇めたのが日本の信仰である。それ故、その地に建造物を設ける場合は必ずその神におことわりをして、工事の無事竣工を祈り、建物の長久堅固に守護されることを祈ったのである。神道という言葉の生ずるよりはるか以前からの日本の習俗であった。
ということで、非常に古い意識があって始められたんですね。でも圧倒的に神式が多いのは、多分、神仏習合で宗教間の摩擦が少なく、住み分けが上手くいっていたからなんだと思います。日本の宗教は面白いですね。
ご質問、ありがとうございました。
タグ :豊橋
2011年03月02日
仏教Q&A タマシイって何?
「お仏壇とか、お位牌って魂抜きは、いる? いらない?
そもそも魂って何?あるの?
魂ってどこにいるの?お墓?お位牌??」
(お仏壇のクリーニング屋さんより)
<回答>
さて、今回も非常に難しいご質問をいただきました。
(回答が遅くなってしまって本当にすみません)
ご質問を抜粋して掲載させていただきましたが、全文の中には”「(お精抜きやお精入れは)同じ宗派でもお寺さんによって違うから、するしないはお客様にお寺さんに聞いてもらって」と(仏壇クリーニングの)師匠から言われました”とあります。
まず始めに、”魂抜き”とか”お精入れ”って何?ということをご説明します。
これは、要するに新しくお位牌とかお仏壇とかお仏像とか、お墓とかを建立した時、最初にする供養のことで、簡単に言えば「ご先祖の霊をここに来ていただく」とか「新しくタマシイを入れる」「仏像の目を入れる」とか言ったニュアンスがあります。(逆に古いものを壊したり、破棄したりする前には逆に”抜く”という供養が必要になります)
ややこしいのは、いろいろと言い方があって、「お精入れ(おしょういれ)」、「魂入れ(たましいいれ)」「開眼(かいげん)供養」「聖化(せいか)」などと言ったりします。
お仏像は特に「開眼供養」と言ったりしますが、これは歴史にお詳しい方ならご存知かと思いますが、東大寺の大仏さんも、大勢の僧侶を招聘してこの開眼供養をしていますよね。
そして、さらに難しくしているのが、「霊」とか「魂」と言った概念です。
ここからは慎重に言を進めなければいけないと思うのですが、元来、仏教にはこうした概念は極めて希薄です。ない、とも言い切れないのが難しいところなんですが、基本的にはありません。
じゃあなんで魂入れなんてやるの?ってことですが、これは先日も書いた「これからの葬儀の・・・」にあるように、位牌とかお墓、或いは魂というものは儒教文化がベースだからです。(しかし、それ以前インドにも霊という概念はありました。だから説明するのが難しいのです)
それで、何でお寺によって、”する””しない”が違うのか、みなさんも本当に疑問に思われると思います。私も非常に不思議なんですが、やはりこれは民俗信仰とか、神道とか、風習とかそうした土着のものが入交った状態が、現在まで続く「仏教文化」ですので、その土地その場所での、民衆の要望に応える形で供養をしてきた、という背景があるんだと思います。(そうでなければ、こんな風に仏教が発展することもなかったんじゃないかと思います)
だからお寺ごとに違うのです。
それに加えて、曹洞宗というのは教義としての縛りが比較的緩いのか、(逆に言えば、だからこそここまで発展してきた)地方によって独自の文化を形成していることが非常に多く、私自身も地方のお寺へお手伝いに行くと、聞いたことのない名前の供養があったりします。
なんだか”逃げ”、みたいに聞こえますか?
そう思われても仕方のない部分は確かにあります。でも、くれぐれも言いますが、本来的な仏教にはそうした概念は極めて少ないです。なぜならば、仏教は悟りを得るもの、自己とは何かを探求しつづけるその姿勢が所謂、仏教であるからです。
で、答えになっていないようですが、参考までに「お精入れ、抜き」の有無を書きます。西光寺では・・・
*お位牌・・・する
*お仏像(仏壇の本尊)・・・する
*お墓・・・する
*お塔婆・・・しない
*お仏壇・・・しない
です。これはいいとか悪いとか、そもそも教義に契合できるものではないので、西光寺の形式がそうなっている、としかお答えできません。もちろん、お寺によっては、上記の5種類すべて「する」ところも当然あるでしょうし、バラバラのところもあるでしょう。
こうした”みなさんにとって切実な”問題を、学者や僧侶は軽んじてきた歴史があるのかどうなのか、(というよりは、民衆の要請に応えるのが第一だったからか)民俗的な仏教については、教義や仏教史の研究に比べ、驚くほど記述(=研究)が少ないのが実情です。
ちなみに、曹洞宗には『曹洞宗行持軌範』という法要や所作、特別な行事に関してのマニュアルみたいなものがあるんですが、ここには「お精入れ」とか「魂いれ」という表現はなく、「開眼供養」という名称で記載されています。しかし、”抜く方法”(魂抜き・お精抜き)に関しては記述がなく、私も非常に困っていたのですが、近年ではそうした学問の泰斗であられる僧侶の本が出ていますので、私はそれを参考にしています。(その本にも書いてありましたが、こうしたことは天台宗などの影響を受けつつ、今まで受け継いできたので、どう考えても教義として曹洞宗に合致しない点もあります)
それでですね。みなさんも知りたいであろう、「霊」とか「魂」についてですが・・・
私、個人的には「ある」と感じたことはあまりないです。ただし、霊を「幽霊」みたいに捉えてしまうとこまるのですが、もう少しやわらかく、幅を持たせたニュアンスで先祖の「霊」や「魂」を見ています。(もちろん、はっきり「ある」という僧侶もいますし、そうした方からすると、私の意見は「まったくけしからんし、信仰がない」訳で、叱責されるのも覚悟の上です。)
結局、霊とか魂とか「ある、ない」の二分法で侃々諤々の議論をするのは無益のような気もします。
実証的に、科学的に説明できないから「いない」と言い張る人(これが大部分でしょうね)もいれば、パワースポット大好きな方は「なにかある」と思われるでしょうし、実際に「見える」と断言する方もいる。それは人それぞれでいいと思うんです。
ただ、私個人的な見解を申し上げれば「ある」ならあったなりに、「ない」ならないなりに、丁寧にお仏壇なり仏像なりお墓に接してほしいのです。「ない」と思う人は、ないことを理由にそれらを邪険に扱いますか?そこが問題なのです。あってもなくても、お墓やお位牌を大切に敬う、そして思うだけではなく、実際に拝んだり、丁寧に扱ったりする、それが一番肝要なのです。
(*そういう意味では、私個人的にはお墓や仏像などには「お精入れ」という表現より、「聖化」(ただの石や木の像を、お墓や仏像として”聖なるものに転換する”)という方がしっくりきます)
曹洞宗の回向文(まぁ祝詞みたいなものとお考えください。また機会があれば詳しく説明します)には「仏身は法界に充満し、普く一切群生の前に現ず。縁に従い感に赴いて遍からずということなし。」というフレーズがあります。
ちょっと意訳すると「仏さんというのは、この世界に満ち満ちている(空気のような)もので、すべての人たちの前に現れている。(みなさんが)手を合わせるとき、或いは供養の心を持つときに、あらわれないということはない」みたいな感じです。
魂が位牌にいるのかお墓にいるのか、お寺にいるのか・・・その答えが上記の文章だと思ってください。
くどいようですが、有無の二元論ではないと思うのです。とにかく大切に思う、敬う、拝む、そうした感情~行為の連なりが、もっとも重要な宗教心だと私は考えています。
そもそも魂って何?あるの?
魂ってどこにいるの?お墓?お位牌??」
(お仏壇のクリーニング屋さんより)
<回答>
さて、今回も非常に難しいご質問をいただきました。
(回答が遅くなってしまって本当にすみません)
ご質問を抜粋して掲載させていただきましたが、全文の中には”「(お精抜きやお精入れは)同じ宗派でもお寺さんによって違うから、するしないはお客様にお寺さんに聞いてもらって」と(仏壇クリーニングの)師匠から言われました”とあります。
まず始めに、”魂抜き”とか”お精入れ”って何?ということをご説明します。
これは、要するに新しくお位牌とかお仏壇とかお仏像とか、お墓とかを建立した時、最初にする供養のことで、簡単に言えば「ご先祖の霊をここに来ていただく」とか「新しくタマシイを入れる」「仏像の目を入れる」とか言ったニュアンスがあります。(逆に古いものを壊したり、破棄したりする前には逆に”抜く”という供養が必要になります)
ややこしいのは、いろいろと言い方があって、「お精入れ(おしょういれ)」、「魂入れ(たましいいれ)」「開眼(かいげん)供養」「聖化(せいか)」などと言ったりします。
お仏像は特に「開眼供養」と言ったりしますが、これは歴史にお詳しい方ならご存知かと思いますが、東大寺の大仏さんも、大勢の僧侶を招聘してこの開眼供養をしていますよね。
そして、さらに難しくしているのが、「霊」とか「魂」と言った概念です。
ここからは慎重に言を進めなければいけないと思うのですが、元来、仏教にはこうした概念は極めて希薄です。ない、とも言い切れないのが難しいところなんですが、基本的にはありません。
じゃあなんで魂入れなんてやるの?ってことですが、これは先日も書いた「これからの葬儀の・・・」にあるように、位牌とかお墓、或いは魂というものは儒教文化がベースだからです。(しかし、それ以前インドにも霊という概念はありました。だから説明するのが難しいのです)
それで、何でお寺によって、”する””しない”が違うのか、みなさんも本当に疑問に思われると思います。私も非常に不思議なんですが、やはりこれは民俗信仰とか、神道とか、風習とかそうした土着のものが入交った状態が、現在まで続く「仏教文化」ですので、その土地その場所での、民衆の要望に応える形で供養をしてきた、という背景があるんだと思います。(そうでなければ、こんな風に仏教が発展することもなかったんじゃないかと思います)
だからお寺ごとに違うのです。
それに加えて、曹洞宗というのは教義としての縛りが比較的緩いのか、(逆に言えば、だからこそここまで発展してきた)地方によって独自の文化を形成していることが非常に多く、私自身も地方のお寺へお手伝いに行くと、聞いたことのない名前の供養があったりします。
なんだか”逃げ”、みたいに聞こえますか?
そう思われても仕方のない部分は確かにあります。でも、くれぐれも言いますが、本来的な仏教にはそうした概念は極めて少ないです。なぜならば、仏教は悟りを得るもの、自己とは何かを探求しつづけるその姿勢が所謂、仏教であるからです。
で、答えになっていないようですが、参考までに「お精入れ、抜き」の有無を書きます。西光寺では・・・
*お位牌・・・する
*お仏像(仏壇の本尊)・・・する
*お墓・・・する
*お塔婆・・・しない
*お仏壇・・・しない
です。これはいいとか悪いとか、そもそも教義に契合できるものではないので、西光寺の形式がそうなっている、としかお答えできません。もちろん、お寺によっては、上記の5種類すべて「する」ところも当然あるでしょうし、バラバラのところもあるでしょう。
こうした”みなさんにとって切実な”問題を、学者や僧侶は軽んじてきた歴史があるのかどうなのか、(というよりは、民衆の要請に応えるのが第一だったからか)民俗的な仏教については、教義や仏教史の研究に比べ、驚くほど記述(=研究)が少ないのが実情です。
ちなみに、曹洞宗には『曹洞宗行持軌範』という法要や所作、特別な行事に関してのマニュアルみたいなものがあるんですが、ここには「お精入れ」とか「魂いれ」という表現はなく、「開眼供養」という名称で記載されています。しかし、”抜く方法”(魂抜き・お精抜き)に関しては記述がなく、私も非常に困っていたのですが、近年ではそうした学問の泰斗であられる僧侶の本が出ていますので、私はそれを参考にしています。(その本にも書いてありましたが、こうしたことは天台宗などの影響を受けつつ、今まで受け継いできたので、どう考えても教義として曹洞宗に合致しない点もあります)
それでですね。みなさんも知りたいであろう、「霊」とか「魂」についてですが・・・
私、個人的には「ある」と感じたことはあまりないです。ただし、霊を「幽霊」みたいに捉えてしまうとこまるのですが、もう少しやわらかく、幅を持たせたニュアンスで先祖の「霊」や「魂」を見ています。(もちろん、はっきり「ある」という僧侶もいますし、そうした方からすると、私の意見は「まったくけしからんし、信仰がない」訳で、叱責されるのも覚悟の上です。)
結局、霊とか魂とか「ある、ない」の二分法で侃々諤々の議論をするのは無益のような気もします。
実証的に、科学的に説明できないから「いない」と言い張る人(これが大部分でしょうね)もいれば、パワースポット大好きな方は「なにかある」と思われるでしょうし、実際に「見える」と断言する方もいる。それは人それぞれでいいと思うんです。
ただ、私個人的な見解を申し上げれば「ある」ならあったなりに、「ない」ならないなりに、丁寧にお仏壇なり仏像なりお墓に接してほしいのです。「ない」と思う人は、ないことを理由にそれらを邪険に扱いますか?そこが問題なのです。あってもなくても、お墓やお位牌を大切に敬う、そして思うだけではなく、実際に拝んだり、丁寧に扱ったりする、それが一番肝要なのです。
(*そういう意味では、私個人的にはお墓や仏像などには「お精入れ」という表現より、「聖化」(ただの石や木の像を、お墓や仏像として”聖なるものに転換する”)という方がしっくりきます)
曹洞宗の回向文(まぁ祝詞みたいなものとお考えください。また機会があれば詳しく説明します)には「仏身は法界に充満し、普く一切群生の前に現ず。縁に従い感に赴いて遍からずということなし。」というフレーズがあります。
ちょっと意訳すると「仏さんというのは、この世界に満ち満ちている(空気のような)もので、すべての人たちの前に現れている。(みなさんが)手を合わせるとき、或いは供養の心を持つときに、あらわれないということはない」みたいな感じです。
魂が位牌にいるのかお墓にいるのか、お寺にいるのか・・・その答えが上記の文章だと思ってください。
くどいようですが、有無の二元論ではないと思うのです。とにかく大切に思う、敬う、拝む、そうした感情~行為の連なりが、もっとも重要な宗教心だと私は考えています。
2011年03月02日
仏教Q&A お経とは・・・
みなさまからのご質問に不肖泰明がお答えしていく大人気(ホントか??!)のコーナーです。今日は3つのご質問にお答えします。
<質問>
*お経について*
お祝いのお経と葬儀のお経って違うのですか?またお祝いのお経は嬉しそうに読むのですか?
<答え>
お祝いのお経と葬儀や法事のお経は、同じものもあれば、違うものもあると思います。
というのも、葬儀であれ、法事であれ、お祝いであれ、そこで”お経を読む”というのは、基本的な考え方として「お経を読んだ功徳(善い行い)を、他のもの(=仏様とかご先祖さまとか、お施主さま=クライアント)に振り向ける」ということがベースだからです。これを”回向”(えこう)といいます。
ですから、お経が終わると、引き続き、僧侶が何か祝詞みたいなものを読んでいるんですが、これが”回向文”(えこうもん)といい、お経の功徳を何に対してどのように振り向けるか、という事が書かれています。
西光寺では、法事の際に、(差支えなければ、ですが)参列者の方々にも一緒に読んでいただきます。これは一緒に読むことによって、それぞれの功徳(善い行い)を、ご先祖に向ける、という意味があるからです。
ちなみにお祝いの時も嬉しそうには読みません(笑)
<質問>
*その他*
駅前でボロボロのお寺様の格好をして店先でお金もらうまでお経を唱えているおじさんがいます。
本物のお寺様なのでしょうか?
<答え>
これは超難問です・・・。ホントに托鉢(たくはつ)をされている可能性もあるし、そうでない可能性もあるし。
ただ、もし曹洞宗なら、布施されたとき「ざいほうにせ、くどくむりょう・・・」という短い句をお唱えします。私がむかし駅前で見た僧侶もどきは、布施されたとき「ありがとうございます」と言っていたので、「これは絶対偽物だ!」と思ったことを覚えています。
布施は、イコール自分の収入ではないので、「ありがとう」ではおかしいのです。布施をした人が、布施をしたことで功徳を積む、という基本ルールがあるからです。イメージとしては、”寄付”と言った方が分かりやすいかもしれません。(ただ、厳密には全然違う意味なんですけどね。これも詳しく書くと、とんでもない文量に・・・ )
)
それから、托鉢って、普通は一か所に立ってやるもんじゃなくて、歩いて家々を回るものだと思うんですよね。だから駅前で募金活動みたいにやっている方は・・・どうなんですかね?・・・そういえば、昔一度だけ私が法衣(=要するに僧侶の恰好)姿で、そうした方の前を通ったら背中を向けられたことがありましたよ(笑)
<質問>
*お経について*
お経はどうして漢字ばかりで意味がよく解らないものが多いのでしょうか?聖書は意味がわかるように書かれていますよね。意味が解れば有難い内容や、勉強になることが多いのだと思いますが。
<答え>
質問者様のおしゃる通りです
お経が漢字ばっかりなのは、インド生まれの仏典が中国で漢訳されて、それが日本に入ってきたからです。もう一ついうなら、日本人の知識階級が”漢字を読めた”からです。正確に言えば、「訓読というシステムを発明した」から和語にする必要がなかった、とも言えます。
写経や読経が行われ始めたのは、平安期だと聞いたことがあります。その当時から、お経を読んだり書いたりするとご利益があると考えられていたのです。
それから、”あんまり意味が解らんことを、何となくありがたく思ってしまう”という意識が私たちの中にあるみたいです。
数年前に、こんなことがありました。
東海地区の僧侶とお寺の総代さんが集まって大きな集会(500人規模・檀家さんがほとんど)をしたときのことです。この集会は、講演を聞いたり、お経を読んだりして総代さんの檀信徒としての意識を高め、同時に僧侶もあるべき曹洞宗の姿を考え、実行していくという目的があります。
曹洞宗の行政を執行しているトップの僧侶も来て、集会の最後に、質問・要望コーナーが設けられていました。
一人の若手僧侶(たぶん40代前半)が、行政トップの僧侶に対して「お経の意味が分からない、という声がたくさん檀家さんから上がっています。だれでも読んで理解できるようなお経を、曹洞宗として作ってほしいです」との要望を出しました。
私もそれを聞いていて、「そうだよな~」と思った刹那、70代とおぼしき総代さん(男性)がすかさず手を挙げてこう言い放ちました。「わからんから、ありがたいんじゃないか。」
まぁ現代の感覚からすれば、若手僧侶に分があるような気もしますが、さりとて、総代さんが言われたのも本音でしょう。
どちらがいいとか悪いとかではなく、まずは「お経の解釈ができる僧侶になる」のが先決で、その後、「檀家さんにお経の意味を説明できる僧侶になる」のが大事なのではないでしょうか。が、口で言えるほど容易ではないんですがね・・・私もかなりかなり反省しています・・・。すみません。
<質問>
*お経について*
お祝いのお経と葬儀のお経って違うのですか?またお祝いのお経は嬉しそうに読むのですか?
<答え>
お祝いのお経と葬儀や法事のお経は、同じものもあれば、違うものもあると思います。
というのも、葬儀であれ、法事であれ、お祝いであれ、そこで”お経を読む”というのは、基本的な考え方として「お経を読んだ功徳(善い行い)を、他のもの(=仏様とかご先祖さまとか、お施主さま=クライアント)に振り向ける」ということがベースだからです。これを”回向”(えこう)といいます。
ですから、お経が終わると、引き続き、僧侶が何か祝詞みたいなものを読んでいるんですが、これが”回向文”(えこうもん)といい、お経の功徳を何に対してどのように振り向けるか、という事が書かれています。
西光寺では、法事の際に、(差支えなければ、ですが)参列者の方々にも一緒に読んでいただきます。これは一緒に読むことによって、それぞれの功徳(善い行い)を、ご先祖に向ける、という意味があるからです。
ちなみにお祝いの時も嬉しそうには読みません(笑)
<質問>
*その他*
駅前でボロボロのお寺様の格好をして店先でお金もらうまでお経を唱えているおじさんがいます。
本物のお寺様なのでしょうか?
<答え>
これは超難問です・・・。ホントに托鉢(たくはつ)をされている可能性もあるし、そうでない可能性もあるし。
ただ、もし曹洞宗なら、布施されたとき「ざいほうにせ、くどくむりょう・・・」という短い句をお唱えします。私がむかし駅前で見た僧侶もどきは、布施されたとき「ありがとうございます」と言っていたので、「これは絶対偽物だ!」と思ったことを覚えています。
布施は、イコール自分の収入ではないので、「ありがとう」ではおかしいのです。布施をした人が、布施をしたことで功徳を積む、という基本ルールがあるからです。イメージとしては、”寄付”と言った方が分かりやすいかもしれません。(ただ、厳密には全然違う意味なんですけどね。これも詳しく書くと、とんでもない文量に・・・
 )
)それから、托鉢って、普通は一か所に立ってやるもんじゃなくて、歩いて家々を回るものだと思うんですよね。だから駅前で募金活動みたいにやっている方は・・・どうなんですかね?・・・そういえば、昔一度だけ私が法衣(=要するに僧侶の恰好)姿で、そうした方の前を通ったら背中を向けられたことがありましたよ(笑)
<質問>
*お経について*
お経はどうして漢字ばかりで意味がよく解らないものが多いのでしょうか?聖書は意味がわかるように書かれていますよね。意味が解れば有難い内容や、勉強になることが多いのだと思いますが。
<答え>
質問者様のおしゃる通りです

お経が漢字ばっかりなのは、インド生まれの仏典が中国で漢訳されて、それが日本に入ってきたからです。もう一ついうなら、日本人の知識階級が”漢字を読めた”からです。正確に言えば、「訓読というシステムを発明した」から和語にする必要がなかった、とも言えます。
写経や読経が行われ始めたのは、平安期だと聞いたことがあります。その当時から、お経を読んだり書いたりするとご利益があると考えられていたのです。
それから、”あんまり意味が解らんことを、何となくありがたく思ってしまう”という意識が私たちの中にあるみたいです。
数年前に、こんなことがありました。
東海地区の僧侶とお寺の総代さんが集まって大きな集会(500人規模・檀家さんがほとんど)をしたときのことです。この集会は、講演を聞いたり、お経を読んだりして総代さんの檀信徒としての意識を高め、同時に僧侶もあるべき曹洞宗の姿を考え、実行していくという目的があります。
曹洞宗の行政を執行しているトップの僧侶も来て、集会の最後に、質問・要望コーナーが設けられていました。
一人の若手僧侶(たぶん40代前半)が、行政トップの僧侶に対して「お経の意味が分からない、という声がたくさん檀家さんから上がっています。だれでも読んで理解できるようなお経を、曹洞宗として作ってほしいです」との要望を出しました。
私もそれを聞いていて、「そうだよな~」と思った刹那、70代とおぼしき総代さん(男性)がすかさず手を挙げてこう言い放ちました。「わからんから、ありがたいんじゃないか。」
まぁ現代の感覚からすれば、若手僧侶に分があるような気もしますが、さりとて、総代さんが言われたのも本音でしょう。
どちらがいいとか悪いとかではなく、まずは「お経の解釈ができる僧侶になる」のが先決で、その後、「檀家さんにお経の意味を説明できる僧侶になる」のが大事なのではないでしょうか。が、口で言えるほど容易ではないんですがね・・・私もかなりかなり反省しています・・・。すみません。
2011年02月24日
仏教Q&A お寺について
みなさまからのご質問に不肖泰明がお答えしていくコーナーです。今日は3つのご質問にお答えします。
<質問>
*修行について*
インドやチベットのお坊さんを時々テレビでみると、「むっちゃ日々修行してる!!」と感じるのですがどうも日本のお坊さんにはそんな雰囲気がないです。 実際はどうなんですか?
<答え>
これは・・・答えに窮しますね(笑)というのも、インドやチベットのお坊さんがどんな生活をしているのか、私は見聞きしたわけではないからです。だから比較のしようがないんですよね・・・。
日本の僧侶が修行していないように見える、とのことですが、これは結構複雑な問題です。
というのは、意図的にであれ、無意識的にであれ、テレビが放送する映像は”編集”というマジックによって、いか様にでもコントロールできるからです。つまり、みなさんが”日本の坊主は堕落していて、他国の僧侶は立派だ”と思われたとき、どうしてそんな風に思われるのか、その原因を疑ってみる必要があると思うのです。(もっとも、私も「堕落側」だよなぁ・・・反省 )
)
閑話休題。
加えて比較の仕様がないのは、日本のお寺とチベットや他国のお寺だと、存在意義(他国では一定期間のみ出家を体験するシステム)も、経営システム(日本のお寺は大抵、寺壇制度をベースに住職とごく少数の家族で経営されている)も、修業期間もお寺の在り方(宗教法人法とか所謂、国法)も、およそすべて違うと思うからです。
それに、日本のお寺、と一口に言っても、私がいる西光寺のような、お檀家さまの布施収入を基盤とした普通のお寺から、観光寺(文化財を多く擁し、観光収入が基盤)、土地がふんだんにあるお寺(檀家さんが数件でも、土地からの収入が莫大なお寺)、祈祷寺(ご祈祷での収入が基盤)、或いは修行道場(永平寺とか)では、在り方がまるで違います。
そうしたことから、”一般の方から求められる事が異なっている”ために、一様に論じることができないのです。極端に言えば、修行が厳しいということは、逆に言ったら”一般の方と接点をなくしてもいい”という態度に陥ることもあるでしょうし、うがった見方をすれば「(厳しい)修行を見世物にする」ことに他ならないのです。
ちなみに・・・私もいた永平寺の修行生活はNHKで何度も放送されているのでご存じと思いますが、それをご覧になると、簡単に「インドやチベットの方が厳しい」とは言えなくなると思いますよ(笑)
それから、これも補足ですが、たぶんインドには本来の仏教の修行僧はほぼいないはずです。
ほぼ、と言ったのは、正確にカウントできないことと、歴史的に見て1200年初頭にイスラムの攻撃を受けて、インド最後の仏教僧院が破壊され、仏教がインドにおいては潰えたからです。ただ、僧院が破壊されたからといって、信者すべてが殺されたわけではなさそうですので、その後はよく分かりません。(後代の中国僧がインドに行ったとき、まだ寺院らしきものがあったとかなかったとか)
インド(というか仏教聖地)にあるお寺のほとんどが日本などの他国から援助を受けて設立された寺院ばかりと聞きます。ただ、日本人でも一人インドで仏教を復興させようとご尽力されている方がいらっしゃるという話も聞いたことがあります。(確か佐々木氏、だったか、桜井氏だったか・・・うろ覚えですみません)
ちょっと手元に資料がないので、正確な記述ができませんでしたが、僧侶の方でお気づきになった点がありましたら、どうぞご指摘ください。
ついでに・・・これは完全に余談ですが、私は過去スリランカに2度行ったことがあります。キャンディという古都(日本で言うなら京都、ちなみに世界遺産)に「仏歯寺」という、そのものズバリ、ブッダの歯を祀るお寺があります。
その中にお参りに行ったとき、歯を祀る黄金の厨子の両脇にいたスリランカの僧侶が、私の顔を見るなり第一声、「Donation!」と手をだしてきました。言うまでもなく、これは「寄付」という意味で、せっかくお参りして心がきれいになるかと思いきや、この僧侶のおかげでゲンナリなってしまいました(笑)
参考までに申しますと、この歯を祀る厨子の前に、厳重にはめ込まれた防弾ガラスがあります。ご存知かとは思いますが、タミル人との内戦などもあり、こうした仏教遺跡が次々と破壊されてきた経緯があるのです。この防弾ガラスを寄付された方こそ、時の曹洞宗大本山永平寺住職 丹羽廉芳禅師であります。何でも厚さ10cm以上あるんだそうで、故禅師様のおかげで、安心してお参りできました。ありがたいことです。
<質問>
*お寺の名前*
よくお寺の名前の前に○○山と書いてあるのですがあの山って実在するの? また何の意味があるんですか?海じゃだめなの?
<答え>
これは非常にいい質問です。
答えは、”本来は実在した山”です。もともとは中国で、山中に建てられたお寺を、○○山××寺というように呼んだことに由来します。ですから、中国などでは、まず山の名前があって、そこに建てたから、その名前使ったようです。
しかし、後代には平地に建てても、その伝統に倣って●●山と山号(さんごう)を付けました。
(ですから、実際に山がなくても付けるし、またあったとしても改称したりしています。永平寺なんかも改称しています)
中国禅宗系の思想を汲んだお寺が、中国のその風習を真似したので、日本の禅宗系ではほとんどのお寺に「●●山」とついています。でも、逆に山号がないお寺もあります。飛鳥奈良の頃に建立されたお寺がそうです。この時代はまだ日本に”禅宗”という概念がなかったと思われます。
ちなみに、西光寺の山号は「日東山」(にっとうざん)です。
<質問>
*お寺の名前*
○○院ってお寺と○○寺ってお寺の名前についてです。 どっちがエライとかあるんですか?
<答え>
どちらがエライとかはないと思います。
辞書的な意味だと、”寺”は「一般には蘭若・精舎などの建造物の総称」、”院”は「垣で囲んだ屋舎。広義には区画を有する建物の意で、官庁や学者の居所をいう」(共に『禅学大辞典』)とあります。
歴史的に言えば、”寺”より”院”の方が新しく使われた言葉のようです。
ただ、『寺院』の項に「寺と院と分けていえば、寺は本寺、院は本寺に付属する坊・塔頭・寺内などをいう」とありますので、本来的には”寺”が本社だとしたら”院”は子会社(?)なのかもしれませんが、現在ではどちらがエライというような区別はできないと思います。
まぁ簡単に言えば、”いつの時代も必ず親会社の方が、子会社より売り上げが大きい”、とは言い切れませんよね。子会社の業績が目覚ましく、それが故に親会社が存続できる、みたいなことは往々にしてあるわけでして。それと同じです。まして、仏教の歴史は会社とはくらべものにならないほどの長さを持っているので、当然お寺ごとの栄枯盛衰はあったと思います。(西光寺も創建時代からすると、異常に住職の数が少ない=住職がいなくて廃寺同然の時代があったはずです)
だから現在ではどちらがエライってことはないのです。
素晴らしいご質問をありがとうございました。 合掌
<質問>
*修行について*
インドやチベットのお坊さんを時々テレビでみると、「むっちゃ日々修行してる!!」と感じるのですがどうも日本のお坊さんにはそんな雰囲気がないです。 実際はどうなんですか?
<答え>
これは・・・答えに窮しますね(笑)というのも、インドやチベットのお坊さんがどんな生活をしているのか、私は見聞きしたわけではないからです。だから比較のしようがないんですよね・・・。
日本の僧侶が修行していないように見える、とのことですが、これは結構複雑な問題です。
というのは、意図的にであれ、無意識的にであれ、テレビが放送する映像は”編集”というマジックによって、いか様にでもコントロールできるからです。つまり、みなさんが”日本の坊主は堕落していて、他国の僧侶は立派だ”と思われたとき、どうしてそんな風に思われるのか、その原因を疑ってみる必要があると思うのです。(もっとも、私も「堕落側」だよなぁ・・・反省
 )
)閑話休題。
加えて比較の仕様がないのは、日本のお寺とチベットや他国のお寺だと、存在意義(他国では一定期間のみ出家を体験するシステム)も、経営システム(日本のお寺は大抵、寺壇制度をベースに住職とごく少数の家族で経営されている)も、修業期間もお寺の在り方(宗教法人法とか所謂、国法)も、およそすべて違うと思うからです。
それに、日本のお寺、と一口に言っても、私がいる西光寺のような、お檀家さまの布施収入を基盤とした普通のお寺から、観光寺(文化財を多く擁し、観光収入が基盤)、土地がふんだんにあるお寺(檀家さんが数件でも、土地からの収入が莫大なお寺)、祈祷寺(ご祈祷での収入が基盤)、或いは修行道場(永平寺とか)では、在り方がまるで違います。
そうしたことから、”一般の方から求められる事が異なっている”ために、一様に論じることができないのです。極端に言えば、修行が厳しいということは、逆に言ったら”一般の方と接点をなくしてもいい”という態度に陥ることもあるでしょうし、うがった見方をすれば「(厳しい)修行を見世物にする」ことに他ならないのです。
ちなみに・・・私もいた永平寺の修行生活はNHKで何度も放送されているのでご存じと思いますが、それをご覧になると、簡単に「インドやチベットの方が厳しい」とは言えなくなると思いますよ(笑)
それから、これも補足ですが、たぶんインドには本来の仏教の修行僧はほぼいないはずです。
ほぼ、と言ったのは、正確にカウントできないことと、歴史的に見て1200年初頭にイスラムの攻撃を受けて、インド最後の仏教僧院が破壊され、仏教がインドにおいては潰えたからです。ただ、僧院が破壊されたからといって、信者すべてが殺されたわけではなさそうですので、その後はよく分かりません。(後代の中国僧がインドに行ったとき、まだ寺院らしきものがあったとかなかったとか)
インド(というか仏教聖地)にあるお寺のほとんどが日本などの他国から援助を受けて設立された寺院ばかりと聞きます。ただ、日本人でも一人インドで仏教を復興させようとご尽力されている方がいらっしゃるという話も聞いたことがあります。(確か佐々木氏、だったか、桜井氏だったか・・・うろ覚えですみません)
ちょっと手元に資料がないので、正確な記述ができませんでしたが、僧侶の方でお気づきになった点がありましたら、どうぞご指摘ください。
ついでに・・・これは完全に余談ですが、私は過去スリランカに2度行ったことがあります。キャンディという古都(日本で言うなら京都、ちなみに世界遺産)に「仏歯寺」という、そのものズバリ、ブッダの歯を祀るお寺があります。
その中にお参りに行ったとき、歯を祀る黄金の厨子の両脇にいたスリランカの僧侶が、私の顔を見るなり第一声、「Donation!」と手をだしてきました。言うまでもなく、これは「寄付」という意味で、せっかくお参りして心がきれいになるかと思いきや、この僧侶のおかげでゲンナリなってしまいました(笑)
参考までに申しますと、この歯を祀る厨子の前に、厳重にはめ込まれた防弾ガラスがあります。ご存知かとは思いますが、タミル人との内戦などもあり、こうした仏教遺跡が次々と破壊されてきた経緯があるのです。この防弾ガラスを寄付された方こそ、時の曹洞宗大本山永平寺住職 丹羽廉芳禅師であります。何でも厚さ10cm以上あるんだそうで、故禅師様のおかげで、安心してお参りできました。ありがたいことです。
<質問>
*お寺の名前*
よくお寺の名前の前に○○山と書いてあるのですがあの山って実在するの? また何の意味があるんですか?海じゃだめなの?
<答え>
これは非常にいい質問です。
答えは、”本来は実在した山”です。もともとは中国で、山中に建てられたお寺を、○○山××寺というように呼んだことに由来します。ですから、中国などでは、まず山の名前があって、そこに建てたから、その名前使ったようです。
しかし、後代には平地に建てても、その伝統に倣って●●山と山号(さんごう)を付けました。
(ですから、実際に山がなくても付けるし、またあったとしても改称したりしています。永平寺なんかも改称しています)
中国禅宗系の思想を汲んだお寺が、中国のその風習を真似したので、日本の禅宗系ではほとんどのお寺に「●●山」とついています。でも、逆に山号がないお寺もあります。飛鳥奈良の頃に建立されたお寺がそうです。この時代はまだ日本に”禅宗”という概念がなかったと思われます。
ちなみに、西光寺の山号は「日東山」(にっとうざん)です。
<質問>
*お寺の名前*
○○院ってお寺と○○寺ってお寺の名前についてです。 どっちがエライとかあるんですか?
<答え>
どちらがエライとかはないと思います。
辞書的な意味だと、”寺”は「一般には蘭若・精舎などの建造物の総称」、”院”は「垣で囲んだ屋舎。広義には区画を有する建物の意で、官庁や学者の居所をいう」(共に『禅学大辞典』)とあります。
歴史的に言えば、”寺”より”院”の方が新しく使われた言葉のようです。
ただ、『寺院』の項に「寺と院と分けていえば、寺は本寺、院は本寺に付属する坊・塔頭・寺内などをいう」とありますので、本来的には”寺”が本社だとしたら”院”は子会社(?)なのかもしれませんが、現在ではどちらがエライというような区別はできないと思います。
まぁ簡単に言えば、”いつの時代も必ず親会社の方が、子会社より売り上げが大きい”、とは言い切れませんよね。子会社の業績が目覚ましく、それが故に親会社が存続できる、みたいなことは往々にしてあるわけでして。それと同じです。まして、仏教の歴史は会社とはくらべものにならないほどの長さを持っているので、当然お寺ごとの栄枯盛衰はあったと思います。(西光寺も創建時代からすると、異常に住職の数が少ない=住職がいなくて廃寺同然の時代があったはずです)
だから現在ではどちらがエライってことはないのです。
素晴らしいご質問をありがとうございました。 合掌
2011年02月22日
仏教Q&A:戒名について
****************************
遅くなってしまいました。皆様方よりいただきましたご質問を、ちょっとづつですがお答えしていきたいと思っています。お答えできるまで、お時間をいただいてしまいますが、何分にも学びが浅いもので・・・どうかご寛容のほど、よろしくお願いいたします。
****************************
<質問>
戒名について、自分で好きな漢字やカタカナ、ローマ字で生前に戒名をつくっておいて受戒をしていただいてら戒名になりますか?
例)モテモテ院サケサケ最強大居士
<回答>
面白いご質問ですね~!
まず、最初に結論を申し上げます。
自分で作った戒名は「戒名」には(定義として)なりません。自分で作ったら、まぁ「あだ名」といったところでしょうか。
それから、カタカナとかローマ字は・・・どうなんでしょうか?これは超難問です。
資格のある僧侶が、きちんとした法式をもって授戒したら、それは戒名なので、(そんなことはまずないですが)カタカナで戒名をつけたら、それは戒名として成り立つのではないでしょうか。(見たことないけど・・・)
ただし、自分の好きな漢字や自分の名前の一文字を入れてほしい、と住職にリクエストのは大いに結構だとおもいます。(西光寺でも、「この一文字を入れてほしい」と言われることがよくあります)
以下は解説です。
そもそも戒名とは何か?ということから始めましょう。(今回はいつになく長くなる気がする・・・)
戒名というと、皆さん”お葬式でもらえる故人の名前”ということはご存じだと思います。
それプラス、”いくつかランクがある”とか”一文字いくらで、長いのは高い”みたいなことをイメージされるんじゃないかと思います。
じゃあなんで「名前」とか「別名」とか「異名」とか言わずに「戒名」なのかと言いますと、それは曹洞宗では葬儀で『授戒(じゅかい)』をするからです。(ちなみに宗派によっては「戒名」とは言わず「法名」と言ったりします)
では、『授戒』とは何か?という流れになりますよね。
授戒というのは、「戒を授けること」であり、導師(住職)から戒法を故人様にお授けすることです。これを、葬儀の冒頭にやっています。(地域によっては、手順が異なりますので、あくまで西光寺の一例としてお考えください)
また、『戒』とは何か?ということなのですが、これは非常に難しく、一面的に答えることは私にはできません。ただ、この場合、戒とは「仏に帰依すること。そして心身の悪を防ぎ、善い行いをするための掟」くらいにご理解ください。私は葬儀の中では”故人様が仏との縁を結び、仏の世界に入る準備をします”というような説明をしています。
ということで、授戒とは、仏との縁を結ぶことです。なぜ授戒をするかというと、それは葬儀の時に、故人様を安らかな世界に導くためにいたします。ごく簡単に言うなら「仏の弟子入り」をするのです。だから「成仏」(=仏に成る)と言ったり、故人のことを「ほとけさん」と言ったりします。(ただ、この表現は必ずしも曹洞宗や仏教の教義と契合しているわけではなく、多分に民俗信仰の要素を取り入れて使われる言葉です)
そして導師から戒を授けられて(=すなわち仏との縁を結び、故人を仏の弟子にして差し上げて)、最後には安らかな世界にお送りするというのが、曹洞宗の一般的な葬儀の流れです。
(*ここら辺の事を、もっと詳しく「これからの『葬儀』の話をしよう」で採り上げたいと思っていますので、またアップしましたらご覧ください。たぶん説明し始めると、”ど長くなる”ので、今日は質問の意図と離れるため、やめます。それから今回のこの説明は、教義的な面からの説明ではなく、あくまで一般的な見方=民俗的な観点に寄っています)
その時、導師から戒を授けられた証が、”戒名”であり、今一つは”お血脈(おけちみゃく)”なのです。戒名は言うなれば、故人様が成仏し、安らかな世界で生きる新しい名前で、お血脈とは、ブッダから累々と続く「教えの家系図」が記されています。家系図の最後に住職の名前、そして故人様のお名前が記されている、というわけです。(血脈は紙でできており、通常10cm四方・厚さ5mm位の大きさに折りたたんであります)
ちなみに、曹洞宗で言うなら、「●●××居士」というのが(男性なら)一般的ですが、正確にはこの中で戒名というのは「××」の部分でしかありません。
細かく見ていくと、道号(●●)+戒名(××)+位階(居士)を組み合わせたもので、位階の部分は男性か女性か、或いは幼児か乳幼児か、といったように分かれています。このブログを始めた最初の方に、お寺に対する本音(前半)をいう記事を書きましたが、ここでも少し触れているので、よろしければご覧ください。
もう少しだけお付き合いください。
この道号(●●)と戒名(××)にはそれぞれ相応しい語句があります。簡単に言えば禅語だとか風景、スケール感のある言葉・仏教語などがそれにあたるとされています。
ついでに、これはある住職さんからお聞きしたことですが、「戒名には、平仄も関係があって、平、もしくは仄がすべて同じにならないようにして付けなさい」と言われたことがあります。
「平仄(ひょうそく)」って何???って感じですよね。
中国語に四声というのがあるのはご存じだと思います。(いわゆるマ→、マ↑、マ↓、マ^、みたいなやつです)この発音を大きく二種類に分けたものが平仄です。「平」は平声、「仄」は上声・去声・入声というグループに分けられます。たぶん、漢詩を作られる方は常識だと思います。結局、音のリズムを単調にさせないために、平仄があるんじゃないでしょうか。こんなことも戒名をつける上では重要なんですね。
今回は、いつもにも増して長くなってしまいました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
遅くなってしまいました。皆様方よりいただきましたご質問を、ちょっとづつですがお答えしていきたいと思っています。お答えできるまで、お時間をいただいてしまいますが、何分にも学びが浅いもので・・・どうかご寛容のほど、よろしくお願いいたします。
****************************
<質問>
戒名について、自分で好きな漢字やカタカナ、ローマ字で生前に戒名をつくっておいて受戒をしていただいてら戒名になりますか?
例)モテモテ院サケサケ最強大居士
<回答>
面白いご質問ですね~!
まず、最初に結論を申し上げます。
自分で作った戒名は「戒名」には(定義として)なりません。自分で作ったら、まぁ「あだ名」といったところでしょうか。
それから、カタカナとかローマ字は・・・どうなんでしょうか?これは超難問です。
資格のある僧侶が、きちんとした法式をもって授戒したら、それは戒名なので、(そんなことはまずないですが)カタカナで戒名をつけたら、それは戒名として成り立つのではないでしょうか。(見たことないけど・・・)
ただし、自分の好きな漢字や自分の名前の一文字を入れてほしい、と住職にリクエストのは大いに結構だとおもいます。(西光寺でも、「この一文字を入れてほしい」と言われることがよくあります)
以下は解説です。
そもそも戒名とは何か?ということから始めましょう。(今回はいつになく長くなる気がする・・・)
戒名というと、皆さん”お葬式でもらえる故人の名前”ということはご存じだと思います。
それプラス、”いくつかランクがある”とか”一文字いくらで、長いのは高い”みたいなことをイメージされるんじゃないかと思います。
じゃあなんで「名前」とか「別名」とか「異名」とか言わずに「戒名」なのかと言いますと、それは曹洞宗では葬儀で『授戒(じゅかい)』をするからです。(ちなみに宗派によっては「戒名」とは言わず「法名」と言ったりします)
では、『授戒』とは何か?という流れになりますよね。
授戒というのは、「戒を授けること」であり、導師(住職)から戒法を故人様にお授けすることです。これを、葬儀の冒頭にやっています。(地域によっては、手順が異なりますので、あくまで西光寺の一例としてお考えください)
また、『戒』とは何か?ということなのですが、これは非常に難しく、一面的に答えることは私にはできません。ただ、この場合、戒とは「仏に帰依すること。そして心身の悪を防ぎ、善い行いをするための掟」くらいにご理解ください。私は葬儀の中では”故人様が仏との縁を結び、仏の世界に入る準備をします”というような説明をしています。
ということで、授戒とは、仏との縁を結ぶことです。なぜ授戒をするかというと、それは葬儀の時に、故人様を安らかな世界に導くためにいたします。ごく簡単に言うなら「仏の弟子入り」をするのです。だから「成仏」(=仏に成る)と言ったり、故人のことを「ほとけさん」と言ったりします。(ただ、この表現は必ずしも曹洞宗や仏教の教義と契合しているわけではなく、多分に民俗信仰の要素を取り入れて使われる言葉です)
そして導師から戒を授けられて(=すなわち仏との縁を結び、故人を仏の弟子にして差し上げて)、最後には安らかな世界にお送りするというのが、曹洞宗の一般的な葬儀の流れです。
(*ここら辺の事を、もっと詳しく「これからの『葬儀』の話をしよう」で採り上げたいと思っていますので、またアップしましたらご覧ください。たぶん説明し始めると、”ど長くなる”ので、今日は質問の意図と離れるため、やめます。それから今回のこの説明は、教義的な面からの説明ではなく、あくまで一般的な見方=民俗的な観点に寄っています)
その時、導師から戒を授けられた証が、”戒名”であり、今一つは”お血脈(おけちみゃく)”なのです。戒名は言うなれば、故人様が成仏し、安らかな世界で生きる新しい名前で、お血脈とは、ブッダから累々と続く「教えの家系図」が記されています。家系図の最後に住職の名前、そして故人様のお名前が記されている、というわけです。(血脈は紙でできており、通常10cm四方・厚さ5mm位の大きさに折りたたんであります)
ちなみに、曹洞宗で言うなら、「●●××居士」というのが(男性なら)一般的ですが、正確にはこの中で戒名というのは「××」の部分でしかありません。
細かく見ていくと、道号(●●)+戒名(××)+位階(居士)を組み合わせたもので、位階の部分は男性か女性か、或いは幼児か乳幼児か、といったように分かれています。このブログを始めた最初の方に、お寺に対する本音(前半)をいう記事を書きましたが、ここでも少し触れているので、よろしければご覧ください。
もう少しだけお付き合いください。
この道号(●●)と戒名(××)にはそれぞれ相応しい語句があります。簡単に言えば禅語だとか風景、スケール感のある言葉・仏教語などがそれにあたるとされています。
ついでに、これはある住職さんからお聞きしたことですが、「戒名には、平仄も関係があって、平、もしくは仄がすべて同じにならないようにして付けなさい」と言われたことがあります。
「平仄(ひょうそく)」って何???って感じですよね。
中国語に四声というのがあるのはご存じだと思います。(いわゆるマ→、マ↑、マ↓、マ^、みたいなやつです)この発音を大きく二種類に分けたものが平仄です。「平」は平声、「仄」は上声・去声・入声というグループに分けられます。たぶん、漢詩を作られる方は常識だと思います。結局、音のリズムを単調にさせないために、平仄があるんじゃないでしょうか。こんなことも戒名をつける上では重要なんですね。
今回は、いつもにも増して長くなってしまいました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。