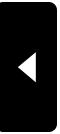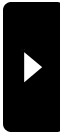2012年06月05日
『未来の住職塾』から見えるもの
何だか、前回の記事は大風呂敷というか、テーマが茫洋としすぎていたきらいがありました。
要約すれば、「未来の住職塾は、おもしろい。が、しかし、セミナーがあたかも“お寺離れの救世主”であるかのごとく、盲目的に持ち上げてしまう自身の心を見つめ直すべき」ということでありました。
これは、たぶん同じ僧侶じゃないと共感できない、というか僧侶でも個々人でその感覚が違うので、何ともいえませんが、極論からすると、「お寺をどうしたいのか?自分はどう生きたいのか?」と言うことを突きつけられていると私は感じました。
というか、それを感じないようでは、また考えないようでは、正直、これだけの耳目を集める、そして実際にクオリティの高いセミナーであっても(いや、であるからこそ)、それ自体を自ら吟味し、咀嚼しないと、何の役にも立たず、意味もないのではないかと思えます。(だから、このセミナーに“新しい!すばらしい!”と猪突猛進し、グループワークで積極的な発言をすることが“正しい”みたいな空気はちょっと苦手 )
)
つまり、本当に大切なことは、たぶん『未来の住職塾』を受講してお寺を経営すること(だけ)ではなく、『未来の住職塾』から得たものを通して見すえる、僧侶としてのあり方、これを生きることなのだと考えます。
それが結果的に、還俗(僧侶をやめる)という選択肢もあるだろうし、経営第一主義に走ってとにかくお寺を存続させることだけを考えることもあるだろうし(←泰明には無理)、例えば自らのお寺をたたんで、師家(しけ。修行道場などで僧侶に教えを説き、導くことのできる、学問も修行も積んだ僧侶)となって生きることもありえるだろうし、はたまた宗派の行政のトップに上り詰めることもあるだろうし、後は、布教師とか海外に出たり、御詠歌、和讃のエキスパートになって人に教えるでもいいし、とにかく道は一つではないし、何かの道を強制(或いは誘導)させることでもないと思うんですよね。
そしておそらくは、あのスターチーム(と私が勝手に呼んでいる彼岸寺の運営メンバー)も同じようなことを考えていらっしゃると、いささか強引に思っていたりするわけです。
話題はそれるようですが・・・手前の話で恐縮です。先月より東京で行われている『正法眼蔵』の講義に行き始めました。行き始めました、と言うより一回しか行っていないのでエラソーに言えないのですが(汗)、これからも参学するつもりです。
これをご覧の皆様は、とうにご存じかと思いますが、曹洞宗を開かれた道元禅師が手ずから書かれた書物が『正法眼蔵』です。このタイトルは、正法=仏の正しい教え、眼蔵=その眼目、神髄を集めた書、というような意味がありまして、75巻とか、95巻ある書物の総称です。(日本初の哲学書、なんて形容されたりして、実際、哲学者が広く影響を受け、また研究の対象としていると聞いています)
前々から、この講義に参加したい、とは思っていたのですがなかなか踏ん切りがつかなかった。でも、不思議なことに、今年から『未来の住職塾』に行くことになって、ますますこの『正法眼蔵』の講義で参学したい、と思えるようになりました。
言ってみれば、かたやドラッカーやコトラーの理論を用い、MBAホルダーが教える新感覚のお寺マネジメント。かたや、曹洞宗学のホープと期待される(そして泰明が“平成の面山さま”とお慕いする)これまた若手僧侶による、曹洞宗の神髄『正法眼蔵』講義、まるで正反対のことをやっているように思えるかもしれません。が、なぜだか、2つながら相矛盾することなくすんなり腑に落ちるのです。
端から見れば、「2つの先端」を行ってバランスを取ろうとしているのかもしれない。別々のベクトルの、どちらかに偏らないように・・・と、普通ならそう考えそうなものですが、なぜだか、自分の中では”偏る”という考えもあまりなくって、両の先端を”突き進みたい”、のです。
テーマや内容だけパッと見ると、非常に前者は打算的なセミナーに感じるかもしれません。檀家を増やしたり、寺院経営を安定させたり、派手なイベントをうって参拝者を集めたり、というような。
でも、現段階で、私にはそれを目的にして受講しているつもりは微塵もありません。たぶん、主催者の皆さんもそうでしょう。
結局、お寺を考え、自らのあり方を徹底的に考えるとき、そこにはただ、ひとりの僧侶としての自分しかいなくて、それは僧侶であるが故に、たぶん”仏教とは”ということしか考えられないのだと今は思います。
では、後者はどうなのか。「正法眼蔵を学ぶことが、そのまま現代を生きる我々の生き方を示し、衆生の苦しみを救うことになるのか、もっと他にやることはあるのではないか?」こう自問した日々もありました。宗学に関してかなり懐疑的だった時期も長くありました。が、結局、ここに戻ってきました。(この課程については上手く書けないので略)
だからこそ、そこには矛盾もなく、”両の先端を突き進みたい”、という自然な気持ちに繋がっているのかもしれません。
もう少し話を続けますが、では何故私が『未来の住職塾』に参加しているか、ということについて。
・・・正直、まぁ縁があった、ということでしょうか・・・(爆)
そもそも、彼岸寺はかなり前から読んでいましたし、私の永平寺での同期が執筆していることもあり、ごく自然に触れていました。しかし、しかしです。未来の住職塾に先駆けて行われたプレセミナー(1月@東京 光明寺)の募集要項は、すっかり見落としていました(涙)
その後、朝日新聞土曜版のフロントランナー(1面インタビュー記事)に出られていた池口龍法師(浄土宗)のメルマガを拝読していたら、たまたまそのプレセミナーのことが書かれていて、そこで知った、という次第。(ちょいと脱線しますが、最近の池口師のメルマガにも「お寺に人を集めるのは良いが、結局その後、仏教の教えを説けるか?」というようなことが問題提起されていました。まさにその通りです。だから信仰に裏打ちされた教学は必須で、自らの言葉で人に説くこと、説けなくても伝えようとすることが重要だと思うのです)
回りくどい説明はさておき、さっきから考えていたんですが、たぶん、主に3つの理由が参加動機です。
1.お寺の内部組織をマネージする方法を知りたい。
(・・・特にHRM。なぜならば、拙寺では現在までそうした組織が活動していなかったから)
2.他宗派とのコミュニケーションとその可能性(・・・知り合いを作ると言うより、他宗派のお寺のおかれ方や包括宗教法人との関係を知りたい。それから、他宗派の僧侶の生の声=それぞれの教義とか宗学に関する疑問とか、僧侶としての考えを伺いたい。あとは例えば、合同で法要やプロジェクトを進める場合の“最大公約数”とか、修行や声明・法式に関する互換性とか)
3.講師や運営スタッフの魅力(別にここでヨイショする気は毛頭ないのですが・・・笑・・・実際お会いしたりお話をさせていただいて、人間的に非常に魅力的だったということは断言しておきます。)
・・・まだ1回目なので、結論づけてはいけませんが、特に2.の動機、「他宗派の教義に関して、その教義を信奉する僧侶の生の声を聞きたい」という点では、松本師と親鸞聖人の悟りについての見解を話せたことが非常に印象的でした。
まさに、こうしたことはただ知識や歴史としての仏教を学ぶだけでは見えないから、その教えで生きている僧侶の話ってとても興味深いんですよね。逆に、懇親会で受講生の方といろんなお話をさせてもらったのですが、松本師とのその一瞬しか、そうした会話がなかったのが、残念と言えば残念かな。ま、一回目だし。それに、だからこそ自らも学ばないと、と思えるんですけどね。
さんざん長くなりましたが、最後に現在、興味を持っていること。
これはtenjin先輩のご指摘で、私も「はっ!」と思い出したのですが、彼岸寺に限らず、“寺離れが進み、「新しい仏教」が生まれる”(実際は、“かのように見える”、と続くべき)この時代の状況って、明治期にそっくりなんだそうです。
私も何かの本で、明治期(それも確か初期)の仏教運動についての記事を読んだのですが、(大谷光瑞←字合ってますか?・・・の探検隊あたりからだったかなぁ・・・)かなり前に読んだこともあり、それがどの本なのか記憶がない。
でもうろ覚えだけど、“宗派を超えた動き”、“一般人に訴えかける分かりやすさ”“宗学を振りかざしてはいない=考古学とか文献学という西洋思想に基づいた云々”という点があったように思います。(ホントにうろ覚えです)
その運動が、どのように興り、どのような終焉を迎えたのか。これが非常に興味ある点です。今年のテーマ。
最後にくどいですが、これは『未来の住職塾』や今起こっている新しい仏教ムーブメントへの批判ではありません。(というか、批判したいなら、そもそもお金を払って参加しない・・・笑)
あくまで、仏道のまなびは“古教照心”なのであります。
(まだ1回目なので、いや、なのに、か・・・こんな駄文長文をお読み頂き、ただただ感謝です。ありがとうございました。)
要約すれば、「未来の住職塾は、おもしろい。が、しかし、セミナーがあたかも“お寺離れの救世主”であるかのごとく、盲目的に持ち上げてしまう自身の心を見つめ直すべき」ということでありました。
これは、たぶん同じ僧侶じゃないと共感できない、というか僧侶でも個々人でその感覚が違うので、何ともいえませんが、極論からすると、「お寺をどうしたいのか?自分はどう生きたいのか?」と言うことを突きつけられていると私は感じました。
というか、それを感じないようでは、また考えないようでは、正直、これだけの耳目を集める、そして実際にクオリティの高いセミナーであっても(いや、であるからこそ)、それ自体を自ら吟味し、咀嚼しないと、何の役にも立たず、意味もないのではないかと思えます。(だから、このセミナーに“新しい!すばらしい!”と猪突猛進し、グループワークで積極的な発言をすることが“正しい”みたいな空気はちょっと苦手
 )
)つまり、本当に大切なことは、たぶん『未来の住職塾』を受講してお寺を経営すること(だけ)ではなく、『未来の住職塾』から得たものを通して見すえる、僧侶としてのあり方、これを生きることなのだと考えます。
それが結果的に、還俗(僧侶をやめる)という選択肢もあるだろうし、経営第一主義に走ってとにかくお寺を存続させることだけを考えることもあるだろうし(←泰明には無理)、例えば自らのお寺をたたんで、師家(しけ。修行道場などで僧侶に教えを説き、導くことのできる、学問も修行も積んだ僧侶)となって生きることもありえるだろうし、はたまた宗派の行政のトップに上り詰めることもあるだろうし、後は、布教師とか海外に出たり、御詠歌、和讃のエキスパートになって人に教えるでもいいし、とにかく道は一つではないし、何かの道を強制(或いは誘導)させることでもないと思うんですよね。
そしておそらくは、あのスターチーム(と私が勝手に呼んでいる彼岸寺の運営メンバー)も同じようなことを考えていらっしゃると、いささか強引に思っていたりするわけです。
話題はそれるようですが・・・手前の話で恐縮です。先月より東京で行われている『正法眼蔵』の講義に行き始めました。行き始めました、と言うより一回しか行っていないのでエラソーに言えないのですが(汗)、これからも参学するつもりです。
これをご覧の皆様は、とうにご存じかと思いますが、曹洞宗を開かれた道元禅師が手ずから書かれた書物が『正法眼蔵』です。このタイトルは、正法=仏の正しい教え、眼蔵=その眼目、神髄を集めた書、というような意味がありまして、75巻とか、95巻ある書物の総称です。(日本初の哲学書、なんて形容されたりして、実際、哲学者が広く影響を受け、また研究の対象としていると聞いています)
前々から、この講義に参加したい、とは思っていたのですがなかなか踏ん切りがつかなかった。でも、不思議なことに、今年から『未来の住職塾』に行くことになって、ますますこの『正法眼蔵』の講義で参学したい、と思えるようになりました。
言ってみれば、かたやドラッカーやコトラーの理論を用い、MBAホルダーが教える新感覚のお寺マネジメント。かたや、曹洞宗学のホープと期待される(そして泰明が“平成の面山さま”とお慕いする)これまた若手僧侶による、曹洞宗の神髄『正法眼蔵』講義、まるで正反対のことをやっているように思えるかもしれません。が、なぜだか、2つながら相矛盾することなくすんなり腑に落ちるのです。
端から見れば、「2つの先端」を行ってバランスを取ろうとしているのかもしれない。別々のベクトルの、どちらかに偏らないように・・・と、普通ならそう考えそうなものですが、なぜだか、自分の中では”偏る”という考えもあまりなくって、両の先端を”突き進みたい”、のです。
テーマや内容だけパッと見ると、非常に前者は打算的なセミナーに感じるかもしれません。檀家を増やしたり、寺院経営を安定させたり、派手なイベントをうって参拝者を集めたり、というような。
でも、現段階で、私にはそれを目的にして受講しているつもりは微塵もありません。たぶん、主催者の皆さんもそうでしょう。
結局、お寺を考え、自らのあり方を徹底的に考えるとき、そこにはただ、ひとりの僧侶としての自分しかいなくて、それは僧侶であるが故に、たぶん”仏教とは”ということしか考えられないのだと今は思います。
では、後者はどうなのか。「正法眼蔵を学ぶことが、そのまま現代を生きる我々の生き方を示し、衆生の苦しみを救うことになるのか、もっと他にやることはあるのではないか?」こう自問した日々もありました。宗学に関してかなり懐疑的だった時期も長くありました。が、結局、ここに戻ってきました。(この課程については上手く書けないので略)
だからこそ、そこには矛盾もなく、”両の先端を突き進みたい”、という自然な気持ちに繋がっているのかもしれません。
もう少し話を続けますが、では何故私が『未来の住職塾』に参加しているか、ということについて。
・・・正直、まぁ縁があった、ということでしょうか・・・(爆)
そもそも、彼岸寺はかなり前から読んでいましたし、私の永平寺での同期が執筆していることもあり、ごく自然に触れていました。しかし、しかしです。未来の住職塾に先駆けて行われたプレセミナー(1月@東京 光明寺)の募集要項は、すっかり見落としていました(涙)
その後、朝日新聞土曜版のフロントランナー(1面インタビュー記事)に出られていた池口龍法師(浄土宗)のメルマガを拝読していたら、たまたまそのプレセミナーのことが書かれていて、そこで知った、という次第。(ちょいと脱線しますが、最近の池口師のメルマガにも「お寺に人を集めるのは良いが、結局その後、仏教の教えを説けるか?」というようなことが問題提起されていました。まさにその通りです。だから信仰に裏打ちされた教学は必須で、自らの言葉で人に説くこと、説けなくても伝えようとすることが重要だと思うのです)
回りくどい説明はさておき、さっきから考えていたんですが、たぶん、主に3つの理由が参加動機です。
1.お寺の内部組織をマネージする方法を知りたい。
(・・・特にHRM。なぜならば、拙寺では現在までそうした組織が活動していなかったから)
2.他宗派とのコミュニケーションとその可能性(・・・知り合いを作ると言うより、他宗派のお寺のおかれ方や包括宗教法人との関係を知りたい。それから、他宗派の僧侶の生の声=それぞれの教義とか宗学に関する疑問とか、僧侶としての考えを伺いたい。あとは例えば、合同で法要やプロジェクトを進める場合の“最大公約数”とか、修行や声明・法式に関する互換性とか)
3.講師や運営スタッフの魅力(別にここでヨイショする気は毛頭ないのですが・・・笑・・・実際お会いしたりお話をさせていただいて、人間的に非常に魅力的だったということは断言しておきます。)
・・・まだ1回目なので、結論づけてはいけませんが、特に2.の動機、「他宗派の教義に関して、その教義を信奉する僧侶の生の声を聞きたい」という点では、松本師と親鸞聖人の悟りについての見解を話せたことが非常に印象的でした。
まさに、こうしたことはただ知識や歴史としての仏教を学ぶだけでは見えないから、その教えで生きている僧侶の話ってとても興味深いんですよね。逆に、懇親会で受講生の方といろんなお話をさせてもらったのですが、松本師とのその一瞬しか、そうした会話がなかったのが、残念と言えば残念かな。ま、一回目だし。それに、だからこそ自らも学ばないと、と思えるんですけどね。
さんざん長くなりましたが、最後に現在、興味を持っていること。
これはtenjin先輩のご指摘で、私も「はっ!」と思い出したのですが、彼岸寺に限らず、“寺離れが進み、「新しい仏教」が生まれる”(実際は、“かのように見える”、と続くべき)この時代の状況って、明治期にそっくりなんだそうです。
私も何かの本で、明治期(それも確か初期)の仏教運動についての記事を読んだのですが、(大谷光瑞←字合ってますか?・・・の探検隊あたりからだったかなぁ・・・)かなり前に読んだこともあり、それがどの本なのか記憶がない。
でもうろ覚えだけど、“宗派を超えた動き”、“一般人に訴えかける分かりやすさ”“宗学を振りかざしてはいない=考古学とか文献学という西洋思想に基づいた云々”という点があったように思います。(ホントにうろ覚えです)
その運動が、どのように興り、どのような終焉を迎えたのか。これが非常に興味ある点です。今年のテーマ。
最後にくどいですが、これは『未来の住職塾』や今起こっている新しい仏教ムーブメントへの批判ではありません。(というか、批判したいなら、そもそもお金を払って参加しない・・・笑)
あくまで、仏道のまなびは“古教照心”なのであります。
(まだ1回目なので、いや、なのに、か・・・こんな駄文長文をお読み頂き、ただただ感謝です。ありがとうございました。)
2012年06月04日
『未来の住職塾』に思うこと
急に湿度があがり、いよいよ入梅といった感がありますね。
iPhone4sを買おうか買うまいか、真剣に悩む泰明です・・・。(他に悩みがないのか)
さて、怒濤の5月後半も過ぎ、何となく一息ついています。今日は久しぶりにいくつかの書物(道元禅師撰『典座教訓』、AsahiGlobe、岸沢惟安老師『典座教訓講話』などなど)を読んだりしています。岸沢老師の典座教訓、素晴らしく綿密で(いや、もともと綿密ですが)、老婆心の至りと言ったご講話。正直、『学道用心集』の提唱ですら飲み込めないことが多々あり、『正法眼蔵』に至っては、なおさらに、ですが、この『典座教訓』に関しては、レイアウトも良いのか、大変親切な提唱であります。
えーと、いきなり話は変わりますが、『未来の住職塾』について、少し思うことを述べてみたいと思います。
『未来の住職塾』って何?という方は→まずコチラ
先月下旬に第1回目(全6回)が開催されました。受講してすぐにこのセミナーについて感想やら思うことを書かなかったのは、書かなかったと言うより、うまく気持ちの整理がつかず“書けなかった”というのが本心。
結論的に言えば、“このセミナーと「新しい仏教」に対する過度の期待への自己抑制心”が始まる前からあったのです。たぶん、それと実際のセミナーの内容、それから受講生の方々との会話の中で生まれる気持ちとが混在していた。
どういう意味かと申しますと・・・。
例えば、現在、“僧職系男子”という言葉がはやったり『美坊主図鑑』という本が売れていたりします。それは悪いことだとは思えません。
その裏側には、“今までの僧侶像からの脱皮、或いは破壊”という明確なイメージがあります。葬式や法事をするだけの僧侶、外車を乗り回したりする僧侶、難しい教義の話をして周りを困惑させる僧侶、夜な夜な遊び歩く僧侶。みなさんの中には、多かれ少なかれ、こうしたイメージ(というか偏見)がおありかと思います。(ついでに、“悪い僧侶像”というのは、果たして本当なのか、本当だとして、それは全ての僧侶に適応される事象なのか、という一般人に対する批判もわいてきます。)
逆にそのイメージを打破するために、音楽のイベントをやったり、寺コン(お寺で合コン)をやってみたり、要するに“抹香臭くない、ポップなイベント”が取り沙汰されています。
これも別に悪いことだとは思えません。
が、しかし、まず第一に“それらはお寺でやる必要があるのか”もっと言えば、“そこに仏教はあるのか?”ということが疑問です。
更に踏み込めば、先のセミナーでも「お寺にたくさんの人が来てくれるようにしたい」と参加者は口々に言います。どうしたら、多くの人がお寺に寄ってくれるようになるか、と真剣に考え、議論します。
けれど、来てくれるくれない以前に、そもそも“たくさんの人が来てくれる”こととはどういうことなのか、もう少し言えば仏教的に善なのかどうなのか、集めることが100%良いことなのか、それから来てくれた方にどのようなアプローチをするのか、つまり檀家にしたいのか、ただ来てくれれば良いのか、仏教の教えを聞いて欲しいのか、イベントの輪を広げて欲しいのか、明確なヴィジョンはありません。
(もちろん、それは各お寺それぞれの事情がありましょうから、一様な答えは存在しないでしょう。)
私が、始まる前から思っていた疑念というのは、それです。明確に申し上げますが、それは、このセミナーに対しての疑念ではなく、自らの信仰心、宗教者の端くれとしての在り方=どう僧侶として生きていきたいか、に対する自問であります。
少なくとも、私に限って言えば、もし例えばイベントでお寺に人が集まる、しかも有り難い事に同世代が多く来た、しかも仏教に関心があるようでいくつかの質問をされた・・・その時に、きちんと仏教の、というか曹洞宗の教えを説けるかどうか、甚だ疑問です。
教えを説くというのは、教科書をオウム返しの様のように話すことではありません。暗記をして、それを諳んじることではない。
資料(お経や祖録=代々の高僧が綴った教えの書)に基づき、自身の信仰心と修行に裏打ちされた話ができるかどうか、本当に疑問です。
結局、通仏教的な、要するに“公約数の最大化”を狙ったような、単純な話にはなりはしないか。もしそれで仏教が事足りるのなら、どうして祖師方(道元禅師だけ、或いは曹洞宗だけ、という狭義の祖師ではなく、広く日本や中国やインドの祖師)は、あれだけの辛苦、労苦を厭わず、ただ仏教の為に生きることができたのか、への答えになりません。
その意味で(最初に申し上げておきますが、他者とか他宗派の批判ではありません)、このセミナーの参加者の中には“このセミナーは非情に斬新だ。新しい仏教の在り方がある。これさえ受講すれば、自ずと人が集まってきて、お寺は安泰だ、”と盲信するかのような過度の期待感が漂っていることが否めませんでした。
まぁそれも別に悪いことだとは思えませんが、お寺を安泰に、つまり安定的な経営をするためだけが僧侶の役目なのか、このセミナーの主眼なのかと、私は思えるのです。そこを疑わない限り、せっかくの充実したセミナーが、単なる“食っていく寺の経営方法”に堕してしまうのではないかと。
かなり批判的に書いていますが、この批判の矛先はセミナーの内容に関してではありません。セミナーの内容自体は、とても充実しています。
しつこいようですが、あくまで、参加する私自身の心を批判的に言っているのです。
そうこうしているうちに、講師の松本師が彼岸寺にこんな記事をアップされていました。
(全文は→コチラ)
***
***
書かずもがな、だけれど、松本師はもうお気づきなんだと思います。
変革、と言う言葉を単純に外的なもの、組織や構造的なもの、と取る以上に、“僧侶の宗教心”という所まで範囲を広げても良いのだろうと思います。だから単なる組織や構造の話ではなく、自らの宗教心が変わっていく、という点も内包して良かろうと思うのです。
その意味で、狭義の“変革=新しい仏教(しかも、我々は”新しい“と定義できるほど、仏教の勉強をしていない)”だけに捕らわれると、文字通り“飛び立つ翼をもがれる”のではないかと危惧します。
・・・これだけ書きちらかしたので、「それじゃあ、『未来の住職塾』なんて受講するなよ!」、と怒られそうですが、そこはそんなに単純な話ではありません。また今度。乱文ご容赦下さい。
iPhone4sを買おうか買うまいか、真剣に悩む泰明です・・・。(他に悩みがないのか)
さて、怒濤の5月後半も過ぎ、何となく一息ついています。今日は久しぶりにいくつかの書物(道元禅師撰『典座教訓』、AsahiGlobe、岸沢惟安老師『典座教訓講話』などなど)を読んだりしています。岸沢老師の典座教訓、素晴らしく綿密で(いや、もともと綿密ですが)、老婆心の至りと言ったご講話。正直、『学道用心集』の提唱ですら飲み込めないことが多々あり、『正法眼蔵』に至っては、なおさらに、ですが、この『典座教訓』に関しては、レイアウトも良いのか、大変親切な提唱であります。
えーと、いきなり話は変わりますが、『未来の住職塾』について、少し思うことを述べてみたいと思います。
『未来の住職塾』って何?という方は→まずコチラ
先月下旬に第1回目(全6回)が開催されました。受講してすぐにこのセミナーについて感想やら思うことを書かなかったのは、書かなかったと言うより、うまく気持ちの整理がつかず“書けなかった”というのが本心。
結論的に言えば、“このセミナーと「新しい仏教」に対する過度の期待への自己抑制心”が始まる前からあったのです。たぶん、それと実際のセミナーの内容、それから受講生の方々との会話の中で生まれる気持ちとが混在していた。
どういう意味かと申しますと・・・。
例えば、現在、“僧職系男子”という言葉がはやったり『美坊主図鑑』という本が売れていたりします。それは悪いことだとは思えません。
その裏側には、“今までの僧侶像からの脱皮、或いは破壊”という明確なイメージがあります。葬式や法事をするだけの僧侶、外車を乗り回したりする僧侶、難しい教義の話をして周りを困惑させる僧侶、夜な夜な遊び歩く僧侶。みなさんの中には、多かれ少なかれ、こうしたイメージ(というか偏見)がおありかと思います。(ついでに、“悪い僧侶像”というのは、果たして本当なのか、本当だとして、それは全ての僧侶に適応される事象なのか、という一般人に対する批判もわいてきます。)
逆にそのイメージを打破するために、音楽のイベントをやったり、寺コン(お寺で合コン)をやってみたり、要するに“抹香臭くない、ポップなイベント”が取り沙汰されています。
これも別に悪いことだとは思えません。
が、しかし、まず第一に“それらはお寺でやる必要があるのか”もっと言えば、“そこに仏教はあるのか?”ということが疑問です。
更に踏み込めば、先のセミナーでも「お寺にたくさんの人が来てくれるようにしたい」と参加者は口々に言います。どうしたら、多くの人がお寺に寄ってくれるようになるか、と真剣に考え、議論します。
けれど、来てくれるくれない以前に、そもそも“たくさんの人が来てくれる”こととはどういうことなのか、もう少し言えば仏教的に善なのかどうなのか、集めることが100%良いことなのか、それから来てくれた方にどのようなアプローチをするのか、つまり檀家にしたいのか、ただ来てくれれば良いのか、仏教の教えを聞いて欲しいのか、イベントの輪を広げて欲しいのか、明確なヴィジョンはありません。
(もちろん、それは各お寺それぞれの事情がありましょうから、一様な答えは存在しないでしょう。)
私が、始まる前から思っていた疑念というのは、それです。明確に申し上げますが、それは、このセミナーに対しての疑念ではなく、自らの信仰心、宗教者の端くれとしての在り方=どう僧侶として生きていきたいか、に対する自問であります。
少なくとも、私に限って言えば、もし例えばイベントでお寺に人が集まる、しかも有り難い事に同世代が多く来た、しかも仏教に関心があるようでいくつかの質問をされた・・・その時に、きちんと仏教の、というか曹洞宗の教えを説けるかどうか、甚だ疑問です。
教えを説くというのは、教科書をオウム返しの様のように話すことではありません。暗記をして、それを諳んじることではない。
資料(お経や祖録=代々の高僧が綴った教えの書)に基づき、自身の信仰心と修行に裏打ちされた話ができるかどうか、本当に疑問です。
結局、通仏教的な、要するに“公約数の最大化”を狙ったような、単純な話にはなりはしないか。もしそれで仏教が事足りるのなら、どうして祖師方(道元禅師だけ、或いは曹洞宗だけ、という狭義の祖師ではなく、広く日本や中国やインドの祖師)は、あれだけの辛苦、労苦を厭わず、ただ仏教の為に生きることができたのか、への答えになりません。
その意味で(最初に申し上げておきますが、他者とか他宗派の批判ではありません)、このセミナーの参加者の中には“このセミナーは非情に斬新だ。新しい仏教の在り方がある。これさえ受講すれば、自ずと人が集まってきて、お寺は安泰だ、”と盲信するかのような過度の期待感が漂っていることが否めませんでした。
まぁそれも別に悪いことだとは思えませんが、お寺を安泰に、つまり安定的な経営をするためだけが僧侶の役目なのか、このセミナーの主眼なのかと、私は思えるのです。そこを疑わない限り、せっかくの充実したセミナーが、単なる“食っていく寺の経営方法”に堕してしまうのではないかと。
かなり批判的に書いていますが、この批判の矛先はセミナーの内容に関してではありません。セミナーの内容自体は、とても充実しています。
しつこいようですが、あくまで、参加する私自身の心を批判的に言っているのです。
そうこうしているうちに、講師の松本師が彼岸寺にこんな記事をアップされていました。
(全文は→コチラ)
***
MBAというのはもちろん役に立つ部分もたくさんあるのだけど、上手に距離をとって付き合わないと、社会変革の旅に飛び立つ翼をもがれるというか、体制側に取り込まれやすくなることがあると思います。
つまりビジネススクールというのは、悪く見れば、変革を志向する人を集めて、変革の方法を教えるふりをしながら、既存の枠組みにはめこんで飼いならし、小さな変革の兵士へと育てつつ、大きな変革への牙を抜いてしまう、そういう側面が少なからずあるように感じました。
***
書かずもがな、だけれど、松本師はもうお気づきなんだと思います。
変革、と言う言葉を単純に外的なもの、組織や構造的なもの、と取る以上に、“僧侶の宗教心”という所まで範囲を広げても良いのだろうと思います。だから単なる組織や構造の話ではなく、自らの宗教心が変わっていく、という点も内包して良かろうと思うのです。
その意味で、狭義の“変革=新しい仏教(しかも、我々は”新しい“と定義できるほど、仏教の勉強をしていない)”だけに捕らわれると、文字通り“飛び立つ翼をもがれる”のではないかと危惧します。
・・・これだけ書きちらかしたので、「それじゃあ、『未来の住職塾』なんて受講するなよ!」、と怒られそうですが、そこはそんなに単純な話ではありません。また今度。乱文ご容赦下さい。
2012年06月01日
東奔西僧(?)
はい、前回に引き続きバタバタ日記です。
京都で行われた第一回目の『未来の住職塾』に参加してきました。
そもそもこの『未来の住職塾』とは何なのか、と申しますと・・・
超宗派のインターネット寺院「彼岸寺」を運営する松本紹圭師(浄土真宗・・・ちなみに泰明と同学年)と青江覚峰師(浄土真宗)2人のMBAホルダーが講師となり、経営学の観点・手法から“これからの100年を生きるお寺づくり”を目指してお寺の在り方を学ぶセミナー。各会場15名と少人数制を貫き、グループワークなども多用する、新しい形の住職塾です。
あ、言い忘れましたが、NHKの「おはよう日本」で放映されました。
会場入りしたらテレビクルーがいたので「やっぱりな~」と思ったのですが(プレセミナーもフジテレビが来ていたので)、今回はNHK!!!しかも全国版。
しかも泰明はバッチリ映っていたそうです。自己紹介をした時のシーンらしい。
放映された朝、檀家さんからすぐに電話がかかってきました。“映っていたそうです”と書いたのは、そうです、見そびれました・・・(涙)&いつ放送されたか知らなかった。
ちょっと、自分の中で消化しきれないほど、いろんなことを考えさせられたセミナーでした。良くも悪くも、ね。
ただ、講師の松本さんやスタッフの松島さん松下さんには純粋に深く感謝しています。もちろん、ご縁を頂いた同じ班やクラスの方にも、です。
また落ち着いたら振り返りつつ書いてみようと思います。ただ、一点だけ。
同じ曹洞宗内の同じくらいの僧侶と話していても「おかれている立場や、お寺の在り方って千差万別だわ・・・」と実感するのですが、他宗派の方とお話していて「千差万別どころか、“万差億別”じゃん」と痛感しました。年齢や性別、宗派もバラバラ。檀家さんや門徒さん、要するに外から見ているお寺以上に、中から見えるお寺の在り方・意識も、全然違う。興味深いセミナーでした。
えっと翌日、今度は名古屋へ。
これはプライベートなので、まぁあんまり詳しくは書きませんが、ライブを見に行ってきました。私が音楽を聴くきっかけとなった、思い入れもあり、また超がつくほど有名なバンドです。・・・最高でした。完全燃焼でした。
後は・・・
丸1日、「曹洞宗青年会漬け」って日がありました。
朝9時に、同じ青年会の役員さんと打ち合わせ。その日の夕方から第一回目の役員会があったので、その為に打ち合わせ。
何事も最初が肝心!でありますので、議題や議事の進行などをかなり真剣にチェック。あっという間に1時間が経ち、そそくさと移動。10時から隣のお寺で別の打ち合わせ=準備会。青年会主催の参禅会が6月23日に行われるのでその会議へ。午前中いっぱい、かかり切りでした。
昼からは、青年会の役員として、日頃から大変お世話になっている2つのお寺へ就任のご挨拶回り。豊橋と豊川のさる大きなお寺のご住職さまにご挨拶に参りました。こういうときは、曹洞宗の僧侶として最も正式な衣を着ることになっています。ま、礼服みたいなもんですかねぇ。
挨拶が終わって、夕方から会議。
第1回目と言うことで、どうしても議題の量も多いので、集中力が必要な会議でした。終わったてみたら2時間弱も経ってた・・・。議論も出来たし、方向性も明確に打ち出せたと思うので、まぁ良かったですね。
そうそう、最後に大事なことを。
当青年会では、継続して被災地のボランティアへ行っています。今期は、「月1でボランティアへ!」と責任者の僧侶が熱く語っておられました。ほそぼそとでも続けていくという意思に心を打たれました。
ウチのお檀家さんで、熱心に被災地へのボランティア活動を行っておられる、フクイのカレーでおなじみ、福井さんも、震災一年を迎えて「これからが本番。第二ラウンドのはじまりです」と仰っていました。
誠に、その通りだと思います。どうしても人間は忘れやすい。また、継続ということが尊いのは分かっているけど、出来ない。継続は地味なので、賞賛もされにくい。テレビにもでない、雑誌で採り上げられない。
だからこそ、継続はやはり尊いのです。賞賛を期待しない、されることを誇りに思わない、そう考えて物事を起こすことは本当に大変なことです。“仏道は名聞利養にかかわるべからず”、とは道元禅師のお示しです。
さて、その福井さんからメールを頂戴しました。先週末、塩竃市や山元町を回り、翌日は仙台市若林区でボランティア活動をされたそうです。
以下のサイトで紹介されています。どうぞご覧下さい。
http://ameblo.jp/stanbox7/entry-11263478011.html
http://ringo-radio.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-e1e5.html
http://ameblo.jp/garnet-miyagi/entry-11261401854.html
暑くなってきたら、カレーが食べたいな~~~
京都で行われた第一回目の『未来の住職塾』に参加してきました。
そもそもこの『未来の住職塾』とは何なのか、と申しますと・・・
超宗派のインターネット寺院「彼岸寺」を運営する松本紹圭師(浄土真宗・・・ちなみに泰明と同学年)と青江覚峰師(浄土真宗)2人のMBAホルダーが講師となり、経営学の観点・手法から“これからの100年を生きるお寺づくり”を目指してお寺の在り方を学ぶセミナー。各会場15名と少人数制を貫き、グループワークなども多用する、新しい形の住職塾です。
あ、言い忘れましたが、NHKの「おはよう日本」で放映されました。
会場入りしたらテレビクルーがいたので「やっぱりな~」と思ったのですが(プレセミナーもフジテレビが来ていたので)、今回はNHK!!!しかも全国版。
しかも泰明はバッチリ映っていたそうです。自己紹介をした時のシーンらしい。
放映された朝、檀家さんからすぐに電話がかかってきました。“映っていたそうです”と書いたのは、そうです、見そびれました・・・(涙)&いつ放送されたか知らなかった。
ちょっと、自分の中で消化しきれないほど、いろんなことを考えさせられたセミナーでした。良くも悪くも、ね。
ただ、講師の松本さんやスタッフの松島さん松下さんには純粋に深く感謝しています。もちろん、ご縁を頂いた同じ班やクラスの方にも、です。
また落ち着いたら振り返りつつ書いてみようと思います。ただ、一点だけ。
同じ曹洞宗内の同じくらいの僧侶と話していても「おかれている立場や、お寺の在り方って千差万別だわ・・・」と実感するのですが、他宗派の方とお話していて「千差万別どころか、“万差億別”じゃん」と痛感しました。年齢や性別、宗派もバラバラ。檀家さんや門徒さん、要するに外から見ているお寺以上に、中から見えるお寺の在り方・意識も、全然違う。興味深いセミナーでした。
えっと翌日、今度は名古屋へ。
これはプライベートなので、まぁあんまり詳しくは書きませんが、ライブを見に行ってきました。私が音楽を聴くきっかけとなった、思い入れもあり、また超がつくほど有名なバンドです。・・・最高でした。完全燃焼でした。
後は・・・
丸1日、「曹洞宗青年会漬け」って日がありました。
朝9時に、同じ青年会の役員さんと打ち合わせ。その日の夕方から第一回目の役員会があったので、その為に打ち合わせ。
何事も最初が肝心!でありますので、議題や議事の進行などをかなり真剣にチェック。あっという間に1時間が経ち、そそくさと移動。10時から隣のお寺で別の打ち合わせ=準備会。青年会主催の参禅会が6月23日に行われるのでその会議へ。午前中いっぱい、かかり切りでした。
昼からは、青年会の役員として、日頃から大変お世話になっている2つのお寺へ就任のご挨拶回り。豊橋と豊川のさる大きなお寺のご住職さまにご挨拶に参りました。こういうときは、曹洞宗の僧侶として最も正式な衣を着ることになっています。ま、礼服みたいなもんですかねぇ。
挨拶が終わって、夕方から会議。
第1回目と言うことで、どうしても議題の量も多いので、集中力が必要な会議でした。終わったてみたら2時間弱も経ってた・・・。議論も出来たし、方向性も明確に打ち出せたと思うので、まぁ良かったですね。
そうそう、最後に大事なことを。
当青年会では、継続して被災地のボランティアへ行っています。今期は、「月1でボランティアへ!」と責任者の僧侶が熱く語っておられました。ほそぼそとでも続けていくという意思に心を打たれました。
ウチのお檀家さんで、熱心に被災地へのボランティア活動を行っておられる、フクイのカレーでおなじみ、福井さんも、震災一年を迎えて「これからが本番。第二ラウンドのはじまりです」と仰っていました。
誠に、その通りだと思います。どうしても人間は忘れやすい。また、継続ということが尊いのは分かっているけど、出来ない。継続は地味なので、賞賛もされにくい。テレビにもでない、雑誌で採り上げられない。
だからこそ、継続はやはり尊いのです。賞賛を期待しない、されることを誇りに思わない、そう考えて物事を起こすことは本当に大変なことです。“仏道は名聞利養にかかわるべからず”、とは道元禅師のお示しです。
さて、その福井さんからメールを頂戴しました。先週末、塩竃市や山元町を回り、翌日は仙台市若林区でボランティア活動をされたそうです。
以下のサイトで紹介されています。どうぞご覧下さい。
http://ameblo.jp/stanbox7/entry-11263478011.html
http://ringo-radio.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-e1e5.html
http://ameblo.jp/garnet-miyagi/entry-11261401854.html
暑くなってきたら、カレーが食べたいな~~~

2012年04月22日
風が吹けば、チャリが倒れる・・・。
すごい風雨ですね。気温もぐっと下がったし。みなさん、どうぞご自愛下さい。
さて、先週は・・・
私の所属する東三河曹洞宗青年会の総会がありました。場所は昨年同様、西光寺。何度も書いていますが、この青年会という組織は、名の通り東三河(どすごいエリア)の曹洞宗青年僧(18~40歳)、約60名が所属する組織です。
今年度より、2年間、私も微力ながら役員を拝命しました。もとより浅学の身ですが、こういう時には”ちょうど役目をいただいた”と思い、役員の間は出来ることを出来るだけしていこうと思います。2年間、メンバーが良いので、ホントに楽しみ。有意義な活動をしていきたいと思います。
これまでの2年間(前任期)の役員諸師も非常に優秀で、実行力のあるチームだったと思うし、実際、最後の総会でも、会則を改正したり、ボランティア組織を立ち上げたりと、目に見える成果をいくつか残されました。だから余計にこの「良い流れ」を止めちゃいかんなぁ、と思っております。
さて、総会に続いての懇親会では、日頃はあまり話せない僧侶同士、貴重な意見が交換できました。あまり書けるような内容ではないのですが(くだらない、というより、解説が面倒な事象を扱うことが多いから)、一つだけ。
やはり、ブログであれ、ボランティアであれ、僧侶としての自覚を持って、アクションを起こすことの重要性を再確認しました。同時に、”坊さんに期待されること”というのが、非常に強い先入観として一般の方にはあるんだなぁ、と痛感。
具体的に書くと、誰と何を話したかバレるので(笑)書きませんが・・・。とにかく、我々は普通の人以上に”見られている”し、その見られ方というのも、かなり固定的。
だから、社会的なよい活動をしようとしても「坊さんはお寺におってくれればいいだで」と上の世代には言われ、そのニーズに振り回されていると「坊さんってただ葬式とか法事をやるだけのひとでしょ」と下の世代から言われる。
ま、政治でも一緒ですね。”国民の声”なんて言うけど、所詮は”個人的な欲望”と同義な訳で。だから民主主義は衆愚政治なんて言われます。

閑話休題。
来週はいよいよ西光寺で”太極拳講座”が行われます。
これは西光寺の護持会が主催となって行う、護持会企画の実質的なキックオフイベントに位置づけられます。
定員は55名で、春彼岸の折(1ヶ月前)に参加受付を始めたところ、なんと!満席です!!!All ticket are sold out!(注:参加は無料です・・・笑)
ずっと前に「予想が正しければ、多分満席になる」とブログ上に書きましたが、果たしてその通りになりました。
先日は、この講師をお勤め頂く檀家様と打ち合わせ。
拙ブログもご高覧頂いているそうで、大変恐縮です。しかも、先日はこのブログをプリントアウトしてお持ち下さり、しばしその話に花が咲きました。誠に尊敬できる、面白い方で、話が尽きません。その話題も縦横無尽で・・・。あれ、太極拳講座の打ち合わせってちゃんとやったっけ、みたいな(笑)
そしてそして来週は曹洞宗の大本山 永平寺に一泊で行ってきます。特別な法要に参列するためです。前回は去年の11月に行ったのかな。なんだかんだで、年1~2回は必ず永平寺に拝登しています。ありがたや、ありがたや。
そんな訳で、今週もがんばっていきましょう!!
さて、先週は・・・
私の所属する東三河曹洞宗青年会の総会がありました。場所は昨年同様、西光寺。何度も書いていますが、この青年会という組織は、名の通り東三河(どすごいエリア)の曹洞宗青年僧(18~40歳)、約60名が所属する組織です。
今年度より、2年間、私も微力ながら役員を拝命しました。もとより浅学の身ですが、こういう時には”ちょうど役目をいただいた”と思い、役員の間は出来ることを出来るだけしていこうと思います。2年間、メンバーが良いので、ホントに楽しみ。有意義な活動をしていきたいと思います。
これまでの2年間(前任期)の役員諸師も非常に優秀で、実行力のあるチームだったと思うし、実際、最後の総会でも、会則を改正したり、ボランティア組織を立ち上げたりと、目に見える成果をいくつか残されました。だから余計にこの「良い流れ」を止めちゃいかんなぁ、と思っております。
さて、総会に続いての懇親会では、日頃はあまり話せない僧侶同士、貴重な意見が交換できました。あまり書けるような内容ではないのですが(くだらない、というより、解説が面倒な事象を扱うことが多いから)、一つだけ。
やはり、ブログであれ、ボランティアであれ、僧侶としての自覚を持って、アクションを起こすことの重要性を再確認しました。同時に、”坊さんに期待されること”というのが、非常に強い先入観として一般の方にはあるんだなぁ、と痛感。
具体的に書くと、誰と何を話したかバレるので(笑)書きませんが・・・。とにかく、我々は普通の人以上に”見られている”し、その見られ方というのも、かなり固定的。
だから、社会的なよい活動をしようとしても「坊さんはお寺におってくれればいいだで」と上の世代には言われ、そのニーズに振り回されていると「坊さんってただ葬式とか法事をやるだけのひとでしょ」と下の世代から言われる。
ま、政治でも一緒ですね。”国民の声”なんて言うけど、所詮は”個人的な欲望”と同義な訳で。だから民主主義は衆愚政治なんて言われます。

閑話休題。
来週はいよいよ西光寺で”太極拳講座”が行われます。
これは西光寺の護持会が主催となって行う、護持会企画の実質的なキックオフイベントに位置づけられます。
定員は55名で、春彼岸の折(1ヶ月前)に参加受付を始めたところ、なんと!満席です!!!All ticket are sold out!(注:参加は無料です・・・笑)
ずっと前に「予想が正しければ、多分満席になる」とブログ上に書きましたが、果たしてその通りになりました。
先日は、この講師をお勤め頂く檀家様と打ち合わせ。
拙ブログもご高覧頂いているそうで、大変恐縮です。しかも、先日はこのブログをプリントアウトしてお持ち下さり、しばしその話に花が咲きました。誠に尊敬できる、面白い方で、話が尽きません。その話題も縦横無尽で・・・。あれ、太極拳講座の打ち合わせってちゃんとやったっけ、みたいな(笑)
そしてそして来週は曹洞宗の大本山 永平寺に一泊で行ってきます。特別な法要に参列するためです。前回は去年の11月に行ったのかな。なんだかんだで、年1~2回は必ず永平寺に拝登しています。ありがたや、ありがたや。
そんな訳で、今週もがんばっていきましょう!!
2012年04月03日
続・絵本『地獄』のすごい話
前回、絵本『地獄』が密かに売れている、という記事を書きました。
その絵本にまつわるテレビ番組を見ていて、コメンテーターのあまりのお粗末具合に落胆。あまり悪口めいた事は書きたくないのですが、批判として。
その特集を見たコメンテーターは「トラウマになるかもしれないので、その子どもが受け入れられるかどうかを見極めて読み聞かせなければなりませんね。」と曰った。
何を仰ってるのか?論点はそこじゃないでしょ?仮にトラウマになるとして、それを誰が判断するのですか?親?医者?先生??責任の所在なんて、不明でしょ?
それから、前回の記事にも書いたとおり、この本を読むことで、“悪を止める”という現実に生きている我々の態度に影響する、ということが中心であり、それをあたかもホラー映画の如くに論じている点は、考えが浅はかすぎて、むしろ哀れなくらい。しかもその視聴者は真に受け取るんでしょう「テレビに出ている人が言ってたから」として。
愚かにも程がある。
また、別のコメンテーターは「アメリカでは宗教上の理由で発刊できない。八百万の神ということもアメリカ人は理解できない」だそうで。
だから何なのでしょうか?アメリカ人の考える“宗教”と日本の“宗教”とは全く同じではありません。
これはキリスト教と仏教、或いは神道という意味ではありません。そもそも“宗教”という概念自体がキリスト教を範とし、規定されている言葉だからです。
であればこそ、別にアメリカ人に理解される宗教を我々は打ち出す必要は全くない。余計なお世話だ、というか、この方は何が言いたいんでしょうか?何かにつけ、何事かを一言付け加える事が、現代のインテリジェンスだと勘違いされている、と確か佐々木中も批判的に書いていましたね。何かしゃべっておかないと存在がアピールできないからでしょうか?
一番の欠落は、どなたも“現実世界に生きる我々(というか子ども)にとってのこの絵本の価値”を仰らなかったこと。所詮は「絵本」の話しで、「地獄なんてあるわけない」から「子どものレベル」ということなんでしょう。
私が常々思うのは、別に地獄があっても、なくてもどっちだっていいんです。例えば、一神教や創造主の問題も、“合理主義・科学的に考えたら、神はいない”と思うのでしょう。でも、本当に重要なのは、そんなことではないと思うのです。
いると信じれば、そのように“よく生きる”、いないと思えば、そのように“よく生きる”だけの話しです。そして、その”よく”の意味・行為を担保してくれるのが宗教だったり、道徳だったりする訳です。地獄はいわば、よく生きるための補助線、と言えるかもしれません。
それをすぐに科学的・合理的という短絡的な思考停止状態で生きているから、ようやく今になって社会が、人間が壊れちゃう、というのが私の本心です。
テレビって恐ろしい、とつくづく感じました。短絡的思考停止人間を量産する機械だ、あれは。
・・・とはいうものの、別にマスコミの人間を非難しているわけではありません。私の親友はアナウンサーだし、人格的にも非常に立派な友人です。私自身も“自分はくだらない人間だ”と自認しながら、ドラマを見ています・・・「イサン」大好きだし・・・あ、ビバヒルが終わっちゃう(笑)
ただ、怖いのは民主政治と一緒で“主権者=視聴者の欲望に振り回される”という点です。だから、マスコミが悪いという場合、一番の問題は、あのようなレベルの低いゴシップネタを求める我々のビヘイビアーにあるのです。

それから、最後に蛇足です。
そもそも、地獄とは何なのか?ということについて。
これは、インドの輪廻(というか多分“転生”)に関わることで、輪廻というのは平たく言えば、「生まれ変わり死に変わる」ことであります。
そして、仏教では死んだ後に、6つの世界が想定され、そこへ生まれ変わるとされます。
天人・修羅・人間・餓鬼・地獄・畜生という6つがそれで、六道とか六趣と呼ばれます。前半3つが、善道、よい世界、後半が悪道、即ち悪い世界であります。
(私もよく分からないのですが、この世界観って、仏教が創始したんですかね?そもそも輪廻という思想は汎インド的で、土着のものと聞いておりますが、六道については、疑問です。ご存じの方は教えてください。)
その絵本にまつわるテレビ番組を見ていて、コメンテーターのあまりのお粗末具合に落胆。あまり悪口めいた事は書きたくないのですが、批判として。
その特集を見たコメンテーターは「トラウマになるかもしれないので、その子どもが受け入れられるかどうかを見極めて読み聞かせなければなりませんね。」と曰った。
何を仰ってるのか?論点はそこじゃないでしょ?仮にトラウマになるとして、それを誰が判断するのですか?親?医者?先生??責任の所在なんて、不明でしょ?
それから、前回の記事にも書いたとおり、この本を読むことで、“悪を止める”という現実に生きている我々の態度に影響する、ということが中心であり、それをあたかもホラー映画の如くに論じている点は、考えが浅はかすぎて、むしろ哀れなくらい。しかもその視聴者は真に受け取るんでしょう「テレビに出ている人が言ってたから」として。
愚かにも程がある。
また、別のコメンテーターは「アメリカでは宗教上の理由で発刊できない。八百万の神ということもアメリカ人は理解できない」だそうで。
だから何なのでしょうか?アメリカ人の考える“宗教”と日本の“宗教”とは全く同じではありません。
これはキリスト教と仏教、或いは神道という意味ではありません。そもそも“宗教”という概念自体がキリスト教を範とし、規定されている言葉だからです。
であればこそ、別にアメリカ人に理解される宗教を我々は打ち出す必要は全くない。余計なお世話だ、というか、この方は何が言いたいんでしょうか?何かにつけ、何事かを一言付け加える事が、現代のインテリジェンスだと勘違いされている、と確か佐々木中も批判的に書いていましたね。何かしゃべっておかないと存在がアピールできないからでしょうか?
一番の欠落は、どなたも“現実世界に生きる我々(というか子ども)にとってのこの絵本の価値”を仰らなかったこと。所詮は「絵本」の話しで、「地獄なんてあるわけない」から「子どものレベル」ということなんでしょう。
私が常々思うのは、別に地獄があっても、なくてもどっちだっていいんです。例えば、一神教や創造主の問題も、“合理主義・科学的に考えたら、神はいない”と思うのでしょう。でも、本当に重要なのは、そんなことではないと思うのです。
いると信じれば、そのように“よく生きる”、いないと思えば、そのように“よく生きる”だけの話しです。そして、その”よく”の意味・行為を担保してくれるのが宗教だったり、道徳だったりする訳です。地獄はいわば、よく生きるための補助線、と言えるかもしれません。
それをすぐに科学的・合理的という短絡的な思考停止状態で生きているから、ようやく今になって社会が、人間が壊れちゃう、というのが私の本心です。
テレビって恐ろしい、とつくづく感じました。短絡的思考停止人間を量産する機械だ、あれは。
・・・とはいうものの、別にマスコミの人間を非難しているわけではありません。私の親友はアナウンサーだし、人格的にも非常に立派な友人です。私自身も“自分はくだらない人間だ”と自認しながら、ドラマを見ています・・・「イサン」大好きだし・・・あ、ビバヒルが終わっちゃう(笑)
ただ、怖いのは民主政治と一緒で“主権者=視聴者の欲望に振り回される”という点です。だから、マスコミが悪いという場合、一番の問題は、あのようなレベルの低いゴシップネタを求める我々のビヘイビアーにあるのです。

それから、最後に蛇足です。
そもそも、地獄とは何なのか?ということについて。
これは、インドの輪廻(というか多分“転生”)に関わることで、輪廻というのは平たく言えば、「生まれ変わり死に変わる」ことであります。
そして、仏教では死んだ後に、6つの世界が想定され、そこへ生まれ変わるとされます。
天人・修羅・人間・餓鬼・地獄・畜生という6つがそれで、六道とか六趣と呼ばれます。前半3つが、善道、よい世界、後半が悪道、即ち悪い世界であります。
(私もよく分からないのですが、この世界観って、仏教が創始したんですかね?そもそも輪廻という思想は汎インド的で、土着のものと聞いておりますが、六道については、疑問です。ご存じの方は教えてください。)
2012年04月01日
絵本『地獄』のすごすぎる話
『地獄』、と題された絵本が密かな人気を集めているようです。
数週間前に、ネットのニュースで見て以来、度々メディアでも採り上げられ、昨日は朝のワイドショー(死語か?)でも放送されていました。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120305-00000305-jisin-ent

昨日のテレビでは、幼稚園くらいの子どもがこの『地獄』を読み聞かされて、泣き出すシーンも。
もう少し大きな(小学生?)になると・・・
「ノンフィクションって書いてない?書いてないなら(作り話だから)大丈夫。」と不安そうな表情で必死に絵本の表紙を見る始末(笑)。
ノンフィクションって書いてあったら無条件で信じるんでしょうか?その一見、合理的で賢そうな考えですが、それこそ疑うべき、恐ろしい教育だと思いませんか?
さておき、私がこの本で非常に興味を覚えたのは、実は「しつけに良い」からではありません。
結論から言えば、結局、絶対的・普遍的に善を助長し、悪を抑止する真理、力などどこにもないからこそ(ニーチェを引き合いに出すまでもなく)、その善悪の判断基準はどこにあるのか?という疑問です。
これまた最初に答えを言えば、それは結局、道徳や宗教や地域風習、大きく言えば帰属する社会に対する“信仰”が、個々人をして、その標準ならしめるものであります。であれば、この『地獄』が教育やしつけ、もっと言えば、人格形成に多大な影響を与え、それなしでは結局、どんな法律や実証主義や科学や、合理主義をもってしても自身の“善悪の標準”にはできないのです。
考えてもみてください。もし全時代・全人間共通の普遍+不変的、絶対的真理があるとしたら、そんなものとっくに見つかっています。でも見つからない。さっきも書いたけど、ないからです。
だからこそ、宗教や哲学や道徳や風習に対する信仰、別の言葉に代えれば、それを“身につけること”が、“よく生きる”ための手段であるはず、というのが私の考えです。
ですが、現代人がすべからく持っている合理主義・科学万能・自由をはき違えた自己への“盲信”(あえて盲信と書きます)とそれへの過度の信奉、そしてそれを許してきた社会が崩れつつあります。
これは当たり前です。もう一度書きますが、当たり前です!
なぜならば、合理主義や科学万能は、それ自体、“よく生きる”こととは何も関係なく、そしてみなさんが自明として置く合理主義や科学万能だって、それを信じている限り、所詮は“信仰=盲信”に過ぎません。であればこそ、崩れるのは当然です。(急いで付け加えますが、別に科学者や研究者個人を指しているわけではありません。あくまで、それらの結果を“無条件で信じている”我々の態度を批判するのです。ついでに、私は科学や合理主義を批判しているのではありません。それだけが絶対的真理だと思い込んでいる、我々を、です。)
今、それが崩れつつあり、そうしてようやくその大切さが理解され始めている。
その意味で、この本が売れているという背後には、今まで「取るに足らない物」と打ち棄てられてきた、道徳や宗教や地域風習、帰属する社会に対する“信仰”への、再帰、再評価があるからではないでしょうか。もっとも、テレビでは全くそのことに触れてませんが・・・。
数週間前に、ネットのニュースで見て以来、度々メディアでも採り上げられ、昨日は朝のワイドショー(死語か?)でも放送されていました。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120305-00000305-jisin-ent
わが子が”よい子”に豹変する絵本『地獄』のすごすぎる中身
(女性自身 3月5日(月)17時3分配信)
大人でさえはらわたをえぐられるような凄惨シーン満載の『絵本 地獄』(風濤社刊)が、いま大ブームになっている。東村アキコさんが6歳になる一人息子の子育てライフを描いたマンガ『ママはテンパリスト』(集英社刊)第4巻に、この絵本を読み聞かせる場面が登場。一気に注目を集めることとなった。
ページをめくると血の色を象徴する赤が鮮烈に使われた、色調豊かな地獄ワールドが広がる。「針地獄」「火あぶり地獄」に「かまゆで地獄」。圧巻「なます地獄」の図では、生きたままある人はお尻から杭で串刺しにされ、ある人は包丁で胴体を輪切りにされ、それを煮たり焼いたりしながら喜々として食べる鬼たちの姿が……。
「効果はてきめん。その日から息子がよい子に豹変しました。悪いことをしたら地獄に落とされると口で言うより、ビジュアルでイメージを植え付けたほうが効果的なんでしょう。それからは『えんま様はどこからでも見ている』と感じたのか、親の前だけではなく私がいないところでも『悪いことはできない』と思ってるみたいです」と東村さん。

昨日のテレビでは、幼稚園くらいの子どもがこの『地獄』を読み聞かされて、泣き出すシーンも。
もう少し大きな(小学生?)になると・・・
「ノンフィクションって書いてない?書いてないなら(作り話だから)大丈夫。」と不安そうな表情で必死に絵本の表紙を見る始末(笑)。
ノンフィクションって書いてあったら無条件で信じるんでしょうか?その一見、合理的で賢そうな考えですが、それこそ疑うべき、恐ろしい教育だと思いませんか?
さておき、私がこの本で非常に興味を覚えたのは、実は「しつけに良い」からではありません。
結論から言えば、結局、絶対的・普遍的に善を助長し、悪を抑止する真理、力などどこにもないからこそ(ニーチェを引き合いに出すまでもなく)、その善悪の判断基準はどこにあるのか?という疑問です。
これまた最初に答えを言えば、それは結局、道徳や宗教や地域風習、大きく言えば帰属する社会に対する“信仰”が、個々人をして、その標準ならしめるものであります。であれば、この『地獄』が教育やしつけ、もっと言えば、人格形成に多大な影響を与え、それなしでは結局、どんな法律や実証主義や科学や、合理主義をもってしても自身の“善悪の標準”にはできないのです。
考えてもみてください。もし全時代・全人間共通の普遍+不変的、絶対的真理があるとしたら、そんなものとっくに見つかっています。でも見つからない。さっきも書いたけど、ないからです。
だからこそ、宗教や哲学や道徳や風習に対する信仰、別の言葉に代えれば、それを“身につけること”が、“よく生きる”ための手段であるはず、というのが私の考えです。
ですが、現代人がすべからく持っている合理主義・科学万能・自由をはき違えた自己への“盲信”(あえて盲信と書きます)とそれへの過度の信奉、そしてそれを許してきた社会が崩れつつあります。
これは当たり前です。もう一度書きますが、当たり前です!
なぜならば、合理主義や科学万能は、それ自体、“よく生きる”こととは何も関係なく、そしてみなさんが自明として置く合理主義や科学万能だって、それを信じている限り、所詮は“信仰=盲信”に過ぎません。であればこそ、崩れるのは当然です。(急いで付け加えますが、別に科学者や研究者個人を指しているわけではありません。あくまで、それらの結果を“無条件で信じている”我々の態度を批判するのです。ついでに、私は科学や合理主義を批判しているのではありません。それだけが絶対的真理だと思い込んでいる、我々を、です。)
今、それが崩れつつあり、そうしてようやくその大切さが理解され始めている。
その意味で、この本が売れているという背後には、今まで「取るに足らない物」と打ち棄てられてきた、道徳や宗教や地域風習、帰属する社会に対する“信仰”への、再帰、再評価があるからではないでしょうか。もっとも、テレビでは全くそのことに触れてませんが・・・。