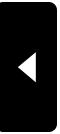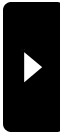2011年07月29日
『道元禅師伝』を拝読して
『道元禅師伝』(菅原研州著・曹洞宗宗務庁刊)を読んだ。
第一に、強く感じ、弘く申し上げたいのは、これはまさに宗侶必読の書であるということである。

所謂、道元禅師のご生涯は、他の鎌倉期の祖師方と異なり、”ドラマティックではない”ということがよく言われる。もちろん、ドラマティックであれば良いのではなく、これは映画化や、小説化されるという前提での謂いであるが。
しかしながら、ごく一般的な宗侶、また檀家さま含め、道元禅師のご生涯は、その”ドラマティック”なさゆえ、わずか数シーンのみハイライトがあたり、その他のご行跡については、ほとんどが知られざるのが常である。
それは僅かに、「母の死に会い、発心したこと」「入宋の折、椎茸典座の話」「如浄禅師との出会い」「波多野義重公の手引きによる入越(大仏寺・永平寺開創)」「鎌倉下向」などと言えよう。
特に永平寺(大仏寺)に入られてからは、”鎌倉下向”を除けば、何もなくただ淡々と坐禅をされているかのごとく思われている。
また、大雑把に言って、ご生涯を研究する意志があり、実際参究したものでなければ、道元禅師のご生涯はあまりにその著述に比して無関心で、謎めいているように見える。
例えば、何故道元禅師の父が元来、久我通親公であり、近年の研究で通具公とされるようになったのか。或いは、母が伊子とされてきたが、その根拠となる典籍は何か等々。
そうした意味で、まさに不毛地帯であった道元禅師のご生涯を詳らかにするという事において、宗門もようやく重い腰を上げたというべきか。しかし、発心に早い遅いがないように、またこの事業も、菅原師を待ってようやく実現したと、私はもろ手を挙げて称賛したい。
厚顔を承知で申し上げるが、従来の道元禅師伝は、どのようにして組まれたものか、よく分からない。がしかし、師の文にあるようにこの道元禅師伝は、今まで考慮されなかった『永平広録』や瑩山禅師の『伝光録』をふんだんに取り入れて書かれている。
逆説的に言えば、それらは”今までの道元禅師の伝記には顧慮されてこなかった”ことになる。『永平広録』が道元禅師の上堂の記録であり、道元禅師をお慕いし時代的にもさほど下ることのない瑩山禅師のご提唱が『伝光録』であるとするならば、従来の研究方法(たぶん明治以来の”合理的”文献学)は、上辺だけを撫でたような、甚だお粗末なものと言わねばならない。
内容について、私自身が感銘を受けたのは、もちろん『正法眼蔵』や『随聞記』は言うに及ばず、何といっても上堂の記録『永平広録』を何度も挿入し、あたかも禅師の上堂を目の当たりにいているかのような生き生きとした印象を受けることである。
この本を読まれた方は「どこにそんな文学的表現があるのか。これは小説ではないのに」と言われるだろう。私の言わんとするところは、そんなことではない。
道元禅師の行跡に合わせ、『弁道話』など(『正法眼蔵』はいわずもがな)の著述、つまり禅師の宗教的思想に触れていること、そして『永平広録』をただの上堂語として、また禅境の深さを指し示すメルクマールとしてのみならず、上堂それ自体が道元禅師の面目として描かれていることである。また或いは、『宝慶記』という正に如浄禅師との仏法についてのやり取りを通して、我々は道元禅師の”求道の生き方”を見るのである。
また、当然のことながら『正法眼蔵』はご生涯を掛けられた著作であるので、その折々の思想的変遷も見逃せない。(そうした”変遷”がなく、とかく宗祖は”初めからずっと真理を悟っていた”と見る向きもないではない)
そこにも、”生きた道元禅師”が見えるのである。
こうした書き様は、変なたとえだが、篆刻の”白文”と”朱文”を想起させる。
即ち、白文とは印の漢字の部分を掘り込み、漢字が白い線で浮き出る印影の彫り方。朱文はその逆で、漢字の周りを彫って字を朱にするものある。
今まであまたある道元禅師伝が、その著者自身の一刀による白文であるとするならば、今回の『道元禅師伝』は対照的に、あらゆる伝記や時代考察が可能な書籍に当るだけではなく、禅師ご自身の手になる『正法眼蔵』や懐奘禅師の『随聞記』を織り込み、彫りこまれ、あたかも道元禅師のご生涯が浮き上がる(即ち朱文)であるかのごとくである。
もちろん、著者である菅原師自身が述べられているように、”道元禅師のご生涯については、研究者同士、百家争鳴的状況である”が、しかし”伝記を明らかにする困難さを示すため、敢えてその議論を議論のまま記述”されている。
そうであるから、文中にもたびたび、”他にも〇〇という説もある”というように、すべからく断定ではない。また研究され、引用されている典籍が曹洞宗系ばかりではないがゆえに、より一層、その伝記的地盤は強固ではない。しかし、これは”勝手な想像による道元禅師像”ではなく、さまざまな考証・典籍の渉猟を経て作り上げられた証左であり、それが一際、この『道元禅師伝』を魅力的にさせているのである。
逆にそこが私には新鮮で、なおかつ著者の面目躍如であると思っている。
始めに述べたように、これは宗侶必読の本である。私も折に触れて勉強させていただきたいと思う。
― この本の著者であり、私の大先輩である菅原研州師に感謝の気持ちと更なるご活躍を祈念して 泰明九拝―
第一に、強く感じ、弘く申し上げたいのは、これはまさに宗侶必読の書であるということである。

所謂、道元禅師のご生涯は、他の鎌倉期の祖師方と異なり、”ドラマティックではない”ということがよく言われる。もちろん、ドラマティックであれば良いのではなく、これは映画化や、小説化されるという前提での謂いであるが。
しかしながら、ごく一般的な宗侶、また檀家さま含め、道元禅師のご生涯は、その”ドラマティック”なさゆえ、わずか数シーンのみハイライトがあたり、その他のご行跡については、ほとんどが知られざるのが常である。
それは僅かに、「母の死に会い、発心したこと」「入宋の折、椎茸典座の話」「如浄禅師との出会い」「波多野義重公の手引きによる入越(大仏寺・永平寺開創)」「鎌倉下向」などと言えよう。
特に永平寺(大仏寺)に入られてからは、”鎌倉下向”を除けば、何もなくただ淡々と坐禅をされているかのごとく思われている。
また、大雑把に言って、ご生涯を研究する意志があり、実際参究したものでなければ、道元禅師のご生涯はあまりにその著述に比して無関心で、謎めいているように見える。
例えば、何故道元禅師の父が元来、久我通親公であり、近年の研究で通具公とされるようになったのか。或いは、母が伊子とされてきたが、その根拠となる典籍は何か等々。
そうした意味で、まさに不毛地帯であった道元禅師のご生涯を詳らかにするという事において、宗門もようやく重い腰を上げたというべきか。しかし、発心に早い遅いがないように、またこの事業も、菅原師を待ってようやく実現したと、私はもろ手を挙げて称賛したい。
厚顔を承知で申し上げるが、従来の道元禅師伝は、どのようにして組まれたものか、よく分からない。がしかし、師の文にあるようにこの道元禅師伝は、今まで考慮されなかった『永平広録』や瑩山禅師の『伝光録』をふんだんに取り入れて書かれている。
逆説的に言えば、それらは”今までの道元禅師の伝記には顧慮されてこなかった”ことになる。『永平広録』が道元禅師の上堂の記録であり、道元禅師をお慕いし時代的にもさほど下ることのない瑩山禅師のご提唱が『伝光録』であるとするならば、従来の研究方法(たぶん明治以来の”合理的”文献学)は、上辺だけを撫でたような、甚だお粗末なものと言わねばならない。
内容について、私自身が感銘を受けたのは、もちろん『正法眼蔵』や『随聞記』は言うに及ばず、何といっても上堂の記録『永平広録』を何度も挿入し、あたかも禅師の上堂を目の当たりにいているかのような生き生きとした印象を受けることである。
この本を読まれた方は「どこにそんな文学的表現があるのか。これは小説ではないのに」と言われるだろう。私の言わんとするところは、そんなことではない。
道元禅師の行跡に合わせ、『弁道話』など(『正法眼蔵』はいわずもがな)の著述、つまり禅師の宗教的思想に触れていること、そして『永平広録』をただの上堂語として、また禅境の深さを指し示すメルクマールとしてのみならず、上堂それ自体が道元禅師の面目として描かれていることである。また或いは、『宝慶記』という正に如浄禅師との仏法についてのやり取りを通して、我々は道元禅師の”求道の生き方”を見るのである。
また、当然のことながら『正法眼蔵』はご生涯を掛けられた著作であるので、その折々の思想的変遷も見逃せない。(そうした”変遷”がなく、とかく宗祖は”初めからずっと真理を悟っていた”と見る向きもないではない)
そこにも、”生きた道元禅師”が見えるのである。
こうした書き様は、変なたとえだが、篆刻の”白文”と”朱文”を想起させる。
即ち、白文とは印の漢字の部分を掘り込み、漢字が白い線で浮き出る印影の彫り方。朱文はその逆で、漢字の周りを彫って字を朱にするものある。
今まであまたある道元禅師伝が、その著者自身の一刀による白文であるとするならば、今回の『道元禅師伝』は対照的に、あらゆる伝記や時代考察が可能な書籍に当るだけではなく、禅師ご自身の手になる『正法眼蔵』や懐奘禅師の『随聞記』を織り込み、彫りこまれ、あたかも道元禅師のご生涯が浮き上がる(即ち朱文)であるかのごとくである。
もちろん、著者である菅原師自身が述べられているように、”道元禅師のご生涯については、研究者同士、百家争鳴的状況である”が、しかし”伝記を明らかにする困難さを示すため、敢えてその議論を議論のまま記述”されている。
そうであるから、文中にもたびたび、”他にも〇〇という説もある”というように、すべからく断定ではない。また研究され、引用されている典籍が曹洞宗系ばかりではないがゆえに、より一層、その伝記的地盤は強固ではない。しかし、これは”勝手な想像による道元禅師像”ではなく、さまざまな考証・典籍の渉猟を経て作り上げられた証左であり、それが一際、この『道元禅師伝』を魅力的にさせているのである。
逆にそこが私には新鮮で、なおかつ著者の面目躍如であると思っている。
始めに述べたように、これは宗侶必読の本である。私も折に触れて勉強させていただきたいと思う。
― この本の著者であり、私の大先輩である菅原研州師に感謝の気持ちと更なるご活躍を祈念して 泰明九拝―
タグ :道元禅師伝
2011年07月27日
子ども参禅会@永平寺で得られたもの
・・・せっかく書いた文章が消えてしまいました・・・(涙)
前回の記事では、永平寺子ども参禅会の研修風景を中心にお送りしました。今日は、私が子ども参禅会を通して思ったことなどを書いてみます。

「目にはさやかに 見えねども・・・」
古今和歌集の有名な歌ですね。目にははっきり見えなくても、という事で、今回の研修を通してたぶん子供たち自身”目にははっきり見えないけれど”成長があったと思います。
というのも、日程の前半はほとんど遊び。だから子どもたちも子どもたちらしく目いっぱい遊んで(暴れて?)ました。いつの世も子供は宝。元気に遊びまわっている姿は、一人の親としてうれしいものです。
しかし、ひとたび永平寺に入ると、帰るその瞬間まで作法やルールに従わなければなりません。何でこんなことしなきゃいけないんだ、と子供たちも口にします。その中には、今の世の中とは逆行するようなこともあるでしょう。
しかし、そこできちんと行う事、自分の好き嫌いに関わらず従う事が、ともすれば自己中だらけの世の中で、新たな価値を与えてくれるのかもしれません。
そこまで大げさではなくても、子供たちは実際、きちんと手を合わせ、決まり通りに坐禅をし、そして作法に則り食事をいただく。始めはできなかったり、反抗したり、口答えします。しかし、私たちや修行僧の姿を見、何度も行うことによって、身についていく。身に着くと、自然に自分勝手な振る舞いが少なくなっていく。この連続が、”目にはさやかに見えねども”何かしらの糧を子どもたちに与えているような気がしてなりません。
それこそが仏教だ、ともそれは仏教ではない、とも私は言い切れませんが、ともあれ、仏教は世法(世の中の常識やルール)とは違ったところで成立しています。数値に現れたり、はっきり目に見えることだけが評価される現代社会とは違って当然。
逆にハッキリ見て取れることもあります。それは坐禅。
最初子供たちはまったく坐禅ができません。当たり前です。普段やっていないんですから。しかし、何度の坐禅を通して、何も言われなくてもきちんと座ることができる。何より、姿勢が美しい。これは実際目の当たりにすると、結構感動します。
きちんと座る。ただそれだけのことが、実は行ってみると案外難しかったりする。それをいとも簡単に子供たちはクリアします。
子どもたちが遊園地や公園で走り回ったり騒いだりすることも確かにいいでしょう。しかし、永平寺のこの生活はそれだけではない”何か”がきっとあると思います。それは何か、と端的に表現することはできないのですが、それでも、複数回参加している子どもたちも多くいるところを見ると、きっと普段の生活では得られない”何か”があるのでしょう。
また来年も行われる予定です。ご興味のある親御さんは詳しい日程や参加費などお知らせしますので、どうぞお気軽にお尋ねください。(対象はほぼ小学生~中学生です。お寺の子どもではなく、ほとんどが一般のご家庭ばかりです)
前回の記事では、永平寺子ども参禅会の研修風景を中心にお送りしました。今日は、私が子ども参禅会を通して思ったことなどを書いてみます。
「目にはさやかに 見えねども・・・」
古今和歌集の有名な歌ですね。目にははっきり見えなくても、という事で、今回の研修を通してたぶん子供たち自身”目にははっきり見えないけれど”成長があったと思います。
というのも、日程の前半はほとんど遊び。だから子どもたちも子どもたちらしく目いっぱい遊んで(暴れて?)ました。いつの世も子供は宝。元気に遊びまわっている姿は、一人の親としてうれしいものです。
しかし、ひとたび永平寺に入ると、帰るその瞬間まで作法やルールに従わなければなりません。何でこんなことしなきゃいけないんだ、と子供たちも口にします。その中には、今の世の中とは逆行するようなこともあるでしょう。
しかし、そこできちんと行う事、自分の好き嫌いに関わらず従う事が、ともすれば自己中だらけの世の中で、新たな価値を与えてくれるのかもしれません。
そこまで大げさではなくても、子供たちは実際、きちんと手を合わせ、決まり通りに坐禅をし、そして作法に則り食事をいただく。始めはできなかったり、反抗したり、口答えします。しかし、私たちや修行僧の姿を見、何度も行うことによって、身についていく。身に着くと、自然に自分勝手な振る舞いが少なくなっていく。この連続が、”目にはさやかに見えねども”何かしらの糧を子どもたちに与えているような気がしてなりません。
それこそが仏教だ、ともそれは仏教ではない、とも私は言い切れませんが、ともあれ、仏教は世法(世の中の常識やルール)とは違ったところで成立しています。数値に現れたり、はっきり目に見えることだけが評価される現代社会とは違って当然。
逆にハッキリ見て取れることもあります。それは坐禅。
最初子供たちはまったく坐禅ができません。当たり前です。普段やっていないんですから。しかし、何度の坐禅を通して、何も言われなくてもきちんと座ることができる。何より、姿勢が美しい。これは実際目の当たりにすると、結構感動します。
きちんと座る。ただそれだけのことが、実は行ってみると案外難しかったりする。それをいとも簡単に子供たちはクリアします。
子どもたちが遊園地や公園で走り回ったり騒いだりすることも確かにいいでしょう。しかし、永平寺のこの生活はそれだけではない”何か”がきっとあると思います。それは何か、と端的に表現することはできないのですが、それでも、複数回参加している子どもたちも多くいるところを見ると、きっと普段の生活では得られない”何か”があるのでしょう。
また来年も行われる予定です。ご興味のある親御さんは詳しい日程や参加費などお知らせしますので、どうぞお気軽にお尋ねください。(対象はほぼ小学生~中学生です。お寺の子どもではなく、ほとんどが一般のご家庭ばかりです)
2011年07月25日
子ども参禅会@永平寺に行ってきました。
遅くなってゴメンナサイ。
さる7月21日~23日の3日間、福井県にある大本山永平寺に行ってきました。
今回は、子ども参禅会のスタッフ(引率)として参加しました。
この参禅会は、今年で39回目(!)という大変に歴史ある(?)子ども参禅会で、毎年、曹洞宗東海管区教化センター(名古屋市熱田区にある機関)が主催しています。
参加するのは、ほとんどが一般のお子さんで、下は小学1年生から上は中学2年生くらいまで。今回はちょっと参加者数が少なくて40名ほど。かつては200名ほどの子供が参加していたそうです。(すごい)
同行のスタッフは教化センターの職員さん(全員僧侶です)4名と、私のような外部から参加の若手僧侶4名。他に数名の僧侶と添乗員さんなどなど。
さて、この記事ではこの旅行のサマリーを。次回の記事では参禅会を通して私が感じたことなどを書き留めてみたいと思います。
ちなみに、今回は写真をバシャバシャ撮ってきましたが、こうした写真は貴重かもしれません。なぜなら、観光で永平寺に行くと建物を写せるのみで、実際の研修風景とかは撮影できないからです。どうぞご高覧ください
[7/21(木)・1日目]
8:30教化センターがある熱田区圓通寺を出発。一路福井県へ。
バスの中でスタッフの紹介や、永平寺での注意点を説明します。
永平寺では私語を慎むべき3箇所(三黙道場、と言い、トイレ・浴室・食事の場所と決められています)の説明や、基本的な3つの手の所作(三進退、と言い、合掌・叉手=歩くとき ・法界定印=坐禅の時の手の組み方)を覚えてもらいます。
また開講式や食事の初めと終わりに読む短いお経なども練習します。
エンゼルランド福井にて昼食・自由時間(ここは広い芝生と遊具があり、プラネタリウムや南極の温度が体験できる建物を擁する施設。簡単に言えばココニコと自然史博物館を足してダウンサイジングしたような施設・・・ローカルネタですみません )
)
エンゼルランドを出発し、永平寺門前の旅館、ほっきょ荘へ。
夕食後、近くのだだっぴろい駐車場でキャンプファイヤー。(永平寺はド田舎です。)キャンプファイヤーでは、専門のスタッフ(子供対象の体育教室や、子供の研修旅行を引率する専門の会社から2名の女性がスタッフとして参加してくれました)がゲームや踊りをリード。子どもたちは楽しそうでした。
終了後、就寝。
[7/22(金)・2日目]
起床。毎回行っているラジオ体操は雨天のため、できませんでした。朝食後、バスに乗車。
バスで15分ほど走ったところにあるカマボコ工場でかまぼこ作り体験。(これが結構おもしろい!)
その後、永平寺町の文化施設「四季の森文化館」へ。
ここは、公園と歴史民俗博物館があり、中でも永平寺にあった傘松閣という、絵天井で有名な建物も移築されています。
ここで勾玉(まがたま)作りと火おこし体験。そして昼食。

(火おこし体験)
昼食後はいよいよ永平寺へ。

13時ころに永平寺に到着すると、すぐに雲水(永平寺にいる修行僧)から宿泊の注意点や説明があり、終わって開講式。
子どもたちは、修行道場が醸し出す厳粛な雰囲気に押されたのか、それまでのはしゃいだ様子がなりをひそめました。
開講式後はすぐに坐禅指導。私たち若手僧侶が坐禅を1から説明します。最初は全くできなくても、この研修では全部で3回の坐禅があるので、自然にできるように。

子どもは体が柔らかいからなのか、心が素直なのか(たぶん両方)、非常に美しい姿勢で坐禅をします。上の写真、中々様になってますよね。

坐禅の後は掃除。修行僧が実際に毎朝掃除している山門(さんもん、永平寺の表玄関)を特別に掃除させてもらえます。これは修行僧でなければ絶対にできない、貴重な体験です。ただし、数十メートルある廊下を何往復もするので、実際かなりきつい
掃除後は入浴。その後、精進料理の夕食。夕食は薬石(やくせき)と言います。

よく勘違いされる方がいますが、修行僧はこんなご馳走は食べていません。朝はごま塩とおかゆとたくあん。昼と夜は所謂一汁一菜が基本です。
ただ、きちんと作法を守って食事をいただくのは修行僧と同じ。もちろん、一切の私語は禁止です。
夕食後に自分たちが寝る布団を自分たちで敷き、終わるとまた坐禅。段々慣れてきて、無駄口をたたかなくなってきます。
坐禅の後は法話と短い映画(と言っても、仏教関係のアニメ)。終わって就寝。

(布団ももちろん自分たちで)
[7/23(土)・3日目]
朝4時起床。(修行僧はもっと早いです)
身支度をして、法堂(はっとう)と呼ばれる本堂へ朝のおつとめに参ります。永平寺は山の斜面に建てられており、いくつもある堂宇の中で、法堂は一番上に位置するので、歩いて階段を上るだけで汗が噴き出、息が上がります。(思い起こせば、修行中は楽勝だったのに・・・身体がなまっています・・・反省)

(これが法堂。中は撮影禁止ですが、いつ訪れてもこの空気には圧倒されます。百聞は一見に如かず、ですよ!!)
朝のおつとめの後は、修行僧が永平寺の建物を案内・説明してくれます。


それが終わると朝の坐禅。元気の塊のような子どもたちも流石にちょっと疲れ&寝不足なご様子。
朝の坐禅の後には朝食。これを小食(しょうじき)と言います。

朝食が済むと、今度は3日間の感想文。やっぱりみんな「永平寺に行ったよ」とか「足が痛かった坐禅」といったタイトルが並びます。

閉講式をして、雲水さんや永平寺の先生(修行僧を指導・監督する僧侶)にお礼のご挨拶をして出発。
越前陶芸村へ向かいます。ここで陶芸教室。電動ロクロこそないものの、中々本格的で、子供たちの中には自分で作ったこの作品を夏休みの自由課題にして提出することもあるんだとか。なかなかしたたかですね(笑)
陶芸村を後にして昼食。ここからは一気に帰途につきます。
夕刻、また熱田の教化センターへ。
今回もけがや病気をする子がおらず、無事に戻ってくることができました。こうして円成できたのも、みんなで揃ってお経を読んだり、きちんと合掌してお参りしたお蔭かもしれませんね。
さる7月21日~23日の3日間、福井県にある大本山永平寺に行ってきました。
今回は、子ども参禅会のスタッフ(引率)として参加しました。
この参禅会は、今年で39回目(!)という大変に歴史ある(?)子ども参禅会で、毎年、曹洞宗東海管区教化センター(名古屋市熱田区にある機関)が主催しています。
参加するのは、ほとんどが一般のお子さんで、下は小学1年生から上は中学2年生くらいまで。今回はちょっと参加者数が少なくて40名ほど。かつては200名ほどの子供が参加していたそうです。(すごい)
同行のスタッフは教化センターの職員さん(全員僧侶です)4名と、私のような外部から参加の若手僧侶4名。他に数名の僧侶と添乗員さんなどなど。
さて、この記事ではこの旅行のサマリーを。次回の記事では参禅会を通して私が感じたことなどを書き留めてみたいと思います。
ちなみに、今回は写真をバシャバシャ撮ってきましたが、こうした写真は貴重かもしれません。なぜなら、観光で永平寺に行くと建物を写せるのみで、実際の研修風景とかは撮影できないからです。どうぞご高覧ください

[7/21(木)・1日目]
8:30教化センターがある熱田区圓通寺を出発。一路福井県へ。
バスの中でスタッフの紹介や、永平寺での注意点を説明します。
永平寺では私語を慎むべき3箇所(三黙道場、と言い、トイレ・浴室・食事の場所と決められています)の説明や、基本的な3つの手の所作(三進退、と言い、合掌・叉手=歩くとき ・法界定印=坐禅の時の手の組み方)を覚えてもらいます。
また開講式や食事の初めと終わりに読む短いお経なども練習します。
エンゼルランド福井にて昼食・自由時間(ここは広い芝生と遊具があり、プラネタリウムや南極の温度が体験できる建物を擁する施設。簡単に言えばココニコと自然史博物館を足してダウンサイジングしたような施設・・・ローカルネタですみません
 )
)エンゼルランドを出発し、永平寺門前の旅館、ほっきょ荘へ。
夕食後、近くのだだっぴろい駐車場でキャンプファイヤー。(永平寺はド田舎です。)キャンプファイヤーでは、専門のスタッフ(子供対象の体育教室や、子供の研修旅行を引率する専門の会社から2名の女性がスタッフとして参加してくれました)がゲームや踊りをリード。子どもたちは楽しそうでした。
終了後、就寝。
[7/22(金)・2日目]
起床。毎回行っているラジオ体操は雨天のため、できませんでした。朝食後、バスに乗車。
バスで15分ほど走ったところにあるカマボコ工場でかまぼこ作り体験。(これが結構おもしろい!)
その後、永平寺町の文化施設「四季の森文化館」へ。
ここは、公園と歴史民俗博物館があり、中でも永平寺にあった傘松閣という、絵天井で有名な建物も移築されています。
ここで勾玉(まがたま)作りと火おこし体験。そして昼食。
(火おこし体験)
昼食後はいよいよ永平寺へ。
13時ころに永平寺に到着すると、すぐに雲水(永平寺にいる修行僧)から宿泊の注意点や説明があり、終わって開講式。
子どもたちは、修行道場が醸し出す厳粛な雰囲気に押されたのか、それまでのはしゃいだ様子がなりをひそめました。
開講式後はすぐに坐禅指導。私たち若手僧侶が坐禅を1から説明します。最初は全くできなくても、この研修では全部で3回の坐禅があるので、自然にできるように。
子どもは体が柔らかいからなのか、心が素直なのか(たぶん両方)、非常に美しい姿勢で坐禅をします。上の写真、中々様になってますよね。
坐禅の後は掃除。修行僧が実際に毎朝掃除している山門(さんもん、永平寺の表玄関)を特別に掃除させてもらえます。これは修行僧でなければ絶対にできない、貴重な体験です。ただし、数十メートルある廊下を何往復もするので、実際かなりきつい

掃除後は入浴。その後、精進料理の夕食。夕食は薬石(やくせき)と言います。
よく勘違いされる方がいますが、修行僧はこんなご馳走は食べていません。朝はごま塩とおかゆとたくあん。昼と夜は所謂一汁一菜が基本です。
ただ、きちんと作法を守って食事をいただくのは修行僧と同じ。もちろん、一切の私語は禁止です。
夕食後に自分たちが寝る布団を自分たちで敷き、終わるとまた坐禅。段々慣れてきて、無駄口をたたかなくなってきます。
坐禅の後は法話と短い映画(と言っても、仏教関係のアニメ)。終わって就寝。
(布団ももちろん自分たちで)
[7/23(土)・3日目]
朝4時起床。(修行僧はもっと早いです)
身支度をして、法堂(はっとう)と呼ばれる本堂へ朝のおつとめに参ります。永平寺は山の斜面に建てられており、いくつもある堂宇の中で、法堂は一番上に位置するので、歩いて階段を上るだけで汗が噴き出、息が上がります。(思い起こせば、修行中は楽勝だったのに・・・身体がなまっています・・・反省)
(これが法堂。中は撮影禁止ですが、いつ訪れてもこの空気には圧倒されます。百聞は一見に如かず、ですよ!!)
朝のおつとめの後は、修行僧が永平寺の建物を案内・説明してくれます。
それが終わると朝の坐禅。元気の塊のような子どもたちも流石にちょっと疲れ&寝不足なご様子。
朝の坐禅の後には朝食。これを小食(しょうじき)と言います。
朝食が済むと、今度は3日間の感想文。やっぱりみんな「永平寺に行ったよ」とか「足が痛かった坐禅」といったタイトルが並びます。
閉講式をして、雲水さんや永平寺の先生(修行僧を指導・監督する僧侶)にお礼のご挨拶をして出発。
越前陶芸村へ向かいます。ここで陶芸教室。電動ロクロこそないものの、中々本格的で、子供たちの中には自分で作ったこの作品を夏休みの自由課題にして提出することもあるんだとか。なかなかしたたかですね(笑)
陶芸村を後にして昼食。ここからは一気に帰途につきます。
夕刻、また熱田の教化センターへ。
今回もけがや病気をする子がおらず、無事に戻ってくることができました。こうして円成できたのも、みんなで揃ってお経を読んだり、きちんと合掌してお参りしたお蔭かもしれませんね。
2011年07月15日
雲のように、水のように
暑いですね~。みなさん、お元気でいらっしゃいますか?
泰明は本格的に夏バテ気味です。食欲はないし、ボーっとしてるし(年中か?)大丈夫かな。
身体を動かすのもけだるいので、道元禅師の語録(通称『永平略録』)をパラパラと読んでました。いい言葉を発見したので、記してみます。

”人間の日常も、雲や水のようでなければならぬ”かぁ。そうですね~。
「暑いときは暑いように。寒いときは寒いように。」昔、大学の授業で、ある先生が言ってました。
この自由無礙なる心が禅の本質なのかもしれませんね。
ただ、気を付けなけければならないのは、”自由だから何をやってもいい”ということではないんですよね。どうしても、我々現代人がこの文章だけを読むと、そんな印象を受けますが、これは全然違うと思います。
あくまでその「”自由”をむさぼる心」からも自由になった”雲のように、水のように”という境涯。素敵な教えですね。
・・・あ、花火が鳴った。そういや今日明日は祇園ですね。忘れてた。
泰明は本格的に夏バテ気味です。食欲はないし、ボーっとしてるし(年中か?)大丈夫かな。
身体を動かすのもけだるいので、道元禅師の語録(通称『永平略録』)をパラパラと読んでました。いい言葉を発見したので、記してみます。

31.海に入りて沙を算う
上堂。海に入りて沙(いさご)を算う、空しく自ら力を費やす。塼を磨いて鏡と作す、枉に工夫を用う。君見ずや高高たる山上の雲、自ずから巻き自ずから舒ぶ。滔滔たる澗下の水、曲に随い直に随う。衆生の日用は雲水のごとし。雲水は自由なれども人は爾らず。もし爾ることを得ば、三界の輪廻、何の処よりか起こらん。
【訳文】
仏法を学ぶのに教学を究めて仏法の悟りにいたろうとするのは、海に入って沙を数えるような空しい努力である。かといって、教学を捨てて、悟りをめあてに修行するのは、瓦を磨いて鏡とするように、これまた空しい工夫である。
高い山の上の雲を見るがよい。雲は、何のはからいもなく、自然とちぢんだり延びたりしている。滔々と流れる谷川の水を見るがよい。水は、何のはからいもなく、曲がったところは曲がり、まっすぐなところはまっすぐに流れている。
人間の日常も、雲や水ようでなければならぬ、雲や水は自由無礙であるが、人間はそうはいかない。もし雲や水のようであれば、人間が三界に流転生死することも、起こりようがないのである。
『道元禅師語録』鏡島元隆・講談社学術文庫 P74~75
”人間の日常も、雲や水のようでなければならぬ”かぁ。そうですね~。
「暑いときは暑いように。寒いときは寒いように。」昔、大学の授業で、ある先生が言ってました。
この自由無礙なる心が禅の本質なのかもしれませんね。
ただ、気を付けなけければならないのは、”自由だから何をやってもいい”ということではないんですよね。どうしても、我々現代人がこの文章だけを読むと、そんな印象を受けますが、これは全然違うと思います。
あくまでその「”自由”をむさぼる心」からも自由になった”雲のように、水のように”という境涯。素敵な教えですね。
・・・あ、花火が鳴った。そういや今日明日は祇園ですね。忘れてた。
2011年05月01日
掃除のスペシャリストたち
先日、田原市赤羽根町のお寺に、法要の準備会に行ってきました。
来月、5月下旬に大きな法要があるので、そのための打ち合わせ&準備です。
↓これ、なんだと思いますか?

そう、”お籠”です。このお寺は由緒正しき古刹で、なんと自前のお籠があります。もちろん、現在使っているわけではありませんが、昔は自家用車のように大きなお寺は自前のお籠があったそうです。
このお籠はいつ頃のものかは分かりませんが、現在は完璧にメンテナンス(再塗装・リペア)されていて新品同様。それに通常は近くの資料館で保存・展示されているので、実際に乗ることもできます。
(余計なことですが、このお籠、ため息が出るほどに無駄のない機能性を兼ね備えていて、天井部分はガルウィング式に跳ね上がり、赤い簾の部分はスライドします。しかも簾の部分はまるでシトロエンの2CVの窓のように半分上げることができ、内部は折りたたみの小さな机もあります。現代の高級車も真っ青な機能美を備えていました。昔の日本人の美的センスと職人芸に脱帽です。)
で、今回の法要でこの”お籠”に新住職が乗ってお寺に入ります。
どういう事かと言いますと、来月の法要、大きくは2つのパートに分かれていて、前半は「晋山式」(しんさんしき)という式をします。
これは新住職の就任式なのですが、ただの式典(辞令交付)とは違います。
昔々、大昔に思いを馳せてみてください。車も電気もない時代。
新しく住職の辞令を受けた僧侶は、今までいたお寺を去り、新たに住職として(世襲ではないので)、別のお寺に入ります。車もない時代ですから、当然歩いていくわけです。その間、お寺の檀家さんたちは、新しい住職を迎えるために、宿の手配をしたり、お寺を修理したり、ごちそうを作ったりと「おもてなし」の準備に余念がありません。
住職としても、もしかしたら初めて”住職”としてお寺に入るかもしれず、気持ちを新たに旅を進めます。
で、ここからが「晋山式」のスタートです。お寺に入る直前、「親元」と呼ばれるお寺の近くの檀家さんの家に新住職は泊めてもらい、そこで一夜を過ごします。翌朝、お礼の気持ちを込めて、その家のご先祖様に供養のお経を上げ、正式な衣に着替えます。そして、まさに”初めて”その赴任先のお寺に入るのです。
これが、本来の晋山式です。
「親元」のお檀家さんのお宅から、このお籠に乗って、お寺の門である、山門に到着します。山門に到着すると、新しい住職を迎えるため、近隣の(本来はそのお寺にいる修行僧も、でしょう)お寺が列をなしてお待ちしています。そこで、新住職はお香を焚き、自らの心中、決意をしたためた短い漢文を読み上げます。こうしていよいよお寺の本堂に向かうのですが・・・全部説明すると、ど長くなりそうなので、今日はこの辺で(笑)
とにもかくにも、住職の一世一代の大舞台であり、檀信徒の方にとっては新しい住職をお迎えするという祝賀会でもあります。私も昨年の5月1日に(あ、ちょうど一年前だ)この「晋山式」をさせてもらいましたが、大勢の僧侶とお寺のお檀家さんのご協力をいただき、無事におつとめができました。本当に感動的な式典でもあります。

閑話休題。
この日の準備会は主に法要に必要な仏具や機材の確認と、掃除。
そこで”なるほど”と思わされることがありました。
それは、掃除。
一軒、長屋のようなお部屋を掃除したのですが、若手僧侶がチームを組むと、自然とチームワークが生まれて、しかも、”掃除のツボ”を全員が共有しているかのようでした。誰も何にも言わなくても”共通のゴール”(=掃除完了)に向かって、どのような”各人のプロセス”(=掃除方法)をすればよいのか、無意識に了解しているように感じました。
つらつら考えてみるに、これはひとえに修行の成果ではなかろうか、と。その時、私含めて8名ほどの僧侶が一緒に掃除していたのですが、後から考えたら、7人が永平寺で1人が総持寺。ともに曹洞宗の大本山です。
何というか・・・別にプロの掃除屋さんと向こうを張ろうとか、誰よりも綺麗にできるとか、そういう意味ではなく、掃除に限らず、年代は違えど、”修行をして体に刻まれた共通認識”、というのが出来上がるのではないか、と思った次第です。
横山行敬さん(新城市議にして曹洞宗の僧侶にして、どすごいブロガー)もご自身のブログで触れられていましたが、やはり「平常時にはそれほど目立たなくても、有事の際の動き方については、すでに体にプログラミングされたものがあ」るのでしょうね。まぁ、今回はお掃除なので、有事とはちょっと違いますが、妙に納得してしまいました。
次回の打ち合わせ+会議は10日。素晴らしい儀礼・式典になるように、私も微力ながら精進していきたいと思います。 合掌
来月、5月下旬に大きな法要があるので、そのための打ち合わせ&準備です。
↓これ、なんだと思いますか?

そう、”お籠”です。このお寺は由緒正しき古刹で、なんと自前のお籠があります。もちろん、現在使っているわけではありませんが、昔は自家用車のように大きなお寺は自前のお籠があったそうです。
このお籠はいつ頃のものかは分かりませんが、現在は完璧にメンテナンス(再塗装・リペア)されていて新品同様。それに通常は近くの資料館で保存・展示されているので、実際に乗ることもできます。
(余計なことですが、このお籠、ため息が出るほどに無駄のない機能性を兼ね備えていて、天井部分はガルウィング式に跳ね上がり、赤い簾の部分はスライドします。しかも簾の部分はまるでシトロエンの2CVの窓のように半分上げることができ、内部は折りたたみの小さな机もあります。現代の高級車も真っ青な機能美を備えていました。昔の日本人の美的センスと職人芸に脱帽です。)
で、今回の法要でこの”お籠”に新住職が乗ってお寺に入ります。
どういう事かと言いますと、来月の法要、大きくは2つのパートに分かれていて、前半は「晋山式」(しんさんしき)という式をします。
これは新住職の就任式なのですが、ただの式典(辞令交付)とは違います。
昔々、大昔に思いを馳せてみてください。車も電気もない時代。
新しく住職の辞令を受けた僧侶は、今までいたお寺を去り、新たに住職として(世襲ではないので)、別のお寺に入ります。車もない時代ですから、当然歩いていくわけです。その間、お寺の檀家さんたちは、新しい住職を迎えるために、宿の手配をしたり、お寺を修理したり、ごちそうを作ったりと「おもてなし」の準備に余念がありません。
住職としても、もしかしたら初めて”住職”としてお寺に入るかもしれず、気持ちを新たに旅を進めます。
で、ここからが「晋山式」のスタートです。お寺に入る直前、「親元」と呼ばれるお寺の近くの檀家さんの家に新住職は泊めてもらい、そこで一夜を過ごします。翌朝、お礼の気持ちを込めて、その家のご先祖様に供養のお経を上げ、正式な衣に着替えます。そして、まさに”初めて”その赴任先のお寺に入るのです。
これが、本来の晋山式です。
「親元」のお檀家さんのお宅から、このお籠に乗って、お寺の門である、山門に到着します。山門に到着すると、新しい住職を迎えるため、近隣の(本来はそのお寺にいる修行僧も、でしょう)お寺が列をなしてお待ちしています。そこで、新住職はお香を焚き、自らの心中、決意をしたためた短い漢文を読み上げます。こうしていよいよお寺の本堂に向かうのですが・・・全部説明すると、ど長くなりそうなので、今日はこの辺で(笑)
とにもかくにも、住職の一世一代の大舞台であり、檀信徒の方にとっては新しい住職をお迎えするという祝賀会でもあります。私も昨年の5月1日に(あ、ちょうど一年前だ)この「晋山式」をさせてもらいましたが、大勢の僧侶とお寺のお檀家さんのご協力をいただき、無事におつとめができました。本当に感動的な式典でもあります。

閑話休題。
この日の準備会は主に法要に必要な仏具や機材の確認と、掃除。
そこで”なるほど”と思わされることがありました。
それは、掃除。
一軒、長屋のようなお部屋を掃除したのですが、若手僧侶がチームを組むと、自然とチームワークが生まれて、しかも、”掃除のツボ”を全員が共有しているかのようでした。誰も何にも言わなくても”共通のゴール”(=掃除完了)に向かって、どのような”各人のプロセス”(=掃除方法)をすればよいのか、無意識に了解しているように感じました。
つらつら考えてみるに、これはひとえに修行の成果ではなかろうか、と。その時、私含めて8名ほどの僧侶が一緒に掃除していたのですが、後から考えたら、7人が永平寺で1人が総持寺。ともに曹洞宗の大本山です。
何というか・・・別にプロの掃除屋さんと向こうを張ろうとか、誰よりも綺麗にできるとか、そういう意味ではなく、掃除に限らず、年代は違えど、”修行をして体に刻まれた共通認識”、というのが出来上がるのではないか、と思った次第です。
横山行敬さん(新城市議にして曹洞宗の僧侶にして、どすごいブロガー)もご自身のブログで触れられていましたが、やはり「平常時にはそれほど目立たなくても、有事の際の動き方については、すでに体にプログラミングされたものがあ」るのでしょうね。まぁ、今回はお掃除なので、有事とはちょっと違いますが、妙に納得してしまいました。
次回の打ち合わせ+会議は10日。素晴らしい儀礼・式典になるように、私も微力ながら精進していきたいと思います。 合掌
2011年04月29日
静かで、厳かで、有り難い(山頭火)
ちょっと遅くなりました。
ようやくこの記事が書けます。
先日(4月25,26日)と曹洞宗の大本山、福井県の永平寺に行ってきました。
今回は、永平寺の住職(禅師)の三十七回忌の法要に参列するための上山でした。このエリアから14名ほどの僧侶が参列しました。
なにぶんにも、到着してからというもの、慌ただしくしてしまい、ゆっくり写真を撮ったりもできなかったので、せっかくの精進料理とか、法要とかそういったショットは皆無です(ゴメンナサイ)

さて、到着して受付を済ませて、まず控室へ。ここで着替えをして正装(お袈裟を付ける)します。
その後、すぐに現在の住職さま(前豊川稲荷 妙厳寺の住職)にごあいさつ。この住職様が起居される場所は「不老閣(ふろうかく)」と言われ、永平寺の最北東に位置しています。ちなみに控室の場所は最南西・・・。永平寺に行かれた方はご存じだと思いますが、かなり距離があります。
雪が平然と残っている、うすら寒い永平寺においても、これだけの距離を歩くと(しかも斜面に建っているから軽く山登り )息は切れるし、汗が出てきます(笑)
)息は切れるし、汗が出てきます(笑)
禅師さま、お元気そうで何よりです。ご挨拶をして、みんなで写真撮影。やはり地元の僧侶ばかりで行ったので、禅師さまとも皆、旧知の仲。ということで、朗らかな笑顔が何度も拝見できて、よかったです。
そして不老閣から、法要会場である法堂へ。ここは「はっとう」と読み、所謂お寺の本堂にあたるところで、388畳もの大伽藍。あんな山の斜面に、あれほどの規模の建築物があるかと思うと(しかも当然木造)、人間の知恵・技術力・信仰心に驚きます。
自分の修行時代を通して、いつ来ても、いつあの場所に立っていても、その荘厳さ、ピーンと張りつめた圧倒的な厳粛さ、清冽な空気感には圧倒されます。自分もこの法堂で7年前に法要の黒子役(準備係)をしていたことを、昨日の事のように思い出します。大変だったなぁ・・・朝1時半起き(正確には”夜”ですよね)で、一人であのでかい法堂を掃除したり、全ての畳にぞうきんがけをしたり(涙)
で、荘厳極まる法要も無事に終わり、参列の僧侶で記念撮影。その後は、客殿で立派は精進料理をいただきました。これは特別な時に特別な方にしかお出ししない精進料理で(写真なしです。ごめんなさい)、2の膳が付いたスペシャルなもの。
全部で9品ほどが漆黒に永平寺の寺紋(久我竜胆:こがりんどう)をあしらった器に飾られており、食べるのが勿体ないほどでした。でも、美味しかった(笑)

唯一の誤算は、想像以上に寒かったこと。と、いうか永平寺自体はそんなに寒くないのですが、法要会場である法堂は常に薄暗く、ストーブもエアコンもなし。だからそこだけ底冷えがして、風邪ひきそうでした
地元のお寺から修行に行っている何人かの修行僧に会うこともでき、また偶然にも私の修行仲間(同期)がたまたま別の法要で来ていてばったり会ったりと、うれしいサプライズもありました。

何はともあれ、故禅師さまの法要に参列させていただき、また無事に帰ってこられたことを感謝しつつ、今日はこの辺で。
ようやくこの記事が書けます。
先日(4月25,26日)と曹洞宗の大本山、福井県の永平寺に行ってきました。
今回は、永平寺の住職(禅師)の三十七回忌の法要に参列するための上山でした。このエリアから14名ほどの僧侶が参列しました。
なにぶんにも、到着してからというもの、慌ただしくしてしまい、ゆっくり写真を撮ったりもできなかったので、せっかくの精進料理とか、法要とかそういったショットは皆無です(ゴメンナサイ)

さて、到着して受付を済ませて、まず控室へ。ここで着替えをして正装(お袈裟を付ける)します。
その後、すぐに現在の住職さま(前豊川稲荷 妙厳寺の住職)にごあいさつ。この住職様が起居される場所は「不老閣(ふろうかく)」と言われ、永平寺の最北東に位置しています。ちなみに控室の場所は最南西・・・。永平寺に行かれた方はご存じだと思いますが、かなり距離があります。
雪が平然と残っている、うすら寒い永平寺においても、これだけの距離を歩くと(しかも斜面に建っているから軽く山登り
 )息は切れるし、汗が出てきます(笑)
)息は切れるし、汗が出てきます(笑)禅師さま、お元気そうで何よりです。ご挨拶をして、みんなで写真撮影。やはり地元の僧侶ばかりで行ったので、禅師さまとも皆、旧知の仲。ということで、朗らかな笑顔が何度も拝見できて、よかったです。
そして不老閣から、法要会場である法堂へ。ここは「はっとう」と読み、所謂お寺の本堂にあたるところで、388畳もの大伽藍。あんな山の斜面に、あれほどの規模の建築物があるかと思うと(しかも当然木造)、人間の知恵・技術力・信仰心に驚きます。
自分の修行時代を通して、いつ来ても、いつあの場所に立っていても、その荘厳さ、ピーンと張りつめた圧倒的な厳粛さ、清冽な空気感には圧倒されます。自分もこの法堂で7年前に法要の黒子役(準備係)をしていたことを、昨日の事のように思い出します。大変だったなぁ・・・朝1時半起き(正確には”夜”ですよね)で、一人であのでかい法堂を掃除したり、全ての畳にぞうきんがけをしたり(涙)
で、荘厳極まる法要も無事に終わり、参列の僧侶で記念撮影。その後は、客殿で立派は精進料理をいただきました。これは特別な時に特別な方にしかお出ししない精進料理で(写真なしです。ごめんなさい)、2の膳が付いたスペシャルなもの。
全部で9品ほどが漆黒に永平寺の寺紋(久我竜胆:こがりんどう)をあしらった器に飾られており、食べるのが勿体ないほどでした。でも、美味しかった(笑)

唯一の誤算は、想像以上に寒かったこと。と、いうか永平寺自体はそんなに寒くないのですが、法要会場である法堂は常に薄暗く、ストーブもエアコンもなし。だからそこだけ底冷えがして、風邪ひきそうでした

地元のお寺から修行に行っている何人かの修行僧に会うこともでき、また偶然にも私の修行仲間(同期)がたまたま別の法要で来ていてばったり会ったりと、うれしいサプライズもありました。

何はともあれ、故禅師さまの法要に参列させていただき、また無事に帰ってこられたことを感謝しつつ、今日はこの辺で。