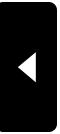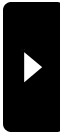2012年04月11日
人間らしく働くと言うことについて
さて、前回からの続きです。
http://saikouji.dosugoi.net/e343420.html
日本の会社の99%を占める中小企業をフィールドワークしてきた法政大学大学院教授 坂本光司さんのインタビュー、後半です。

全く話しは変わりますが、最後の段「新興国に価格競争で勝てるはずがない・・・」ということと、だからこその「人本主義」というのは、たまたま今読んでいる佐伯啓思氏の『日本という「価値」』にかなり近いことが書かれています。
佐伯氏は、ご専門が社会経済学と経済思想史でありますが、それらにまるで無知の私でさえ、ところどころ非常に腹オチする、腑に落ちるところ多い名文を書かれます。
同書では、トピックが多岐に渡り、本当のところ、私も全く理解できない部分も(不勉強だから)ありますが、反面、同じ意図のものを、表現を変え、懇切丁寧に記してあります。
一言で言えば、現代の経済(というか金)至上主義は、結果的には何の制約も制限もなく(これは“自己責任”とか“自由”という問題にも絡む)、節度もない。しかし、その考えが蔓延した結果、いわば実体のない金融という世界に資本が流入し、それが肥大化しすぎた。まるでコントロールの効かない怪物のように、それはリーマンショックやギリシャの金融破綻を引き起こし、今なお、その指針となる解決策が生み出されない、というようなことでしょうか。
_______________
(以下、抜粋)
今日の「グローバル経済競争」は、価値の確かな基準を放棄するという点がある。徹底した価値相対主義といってもよいが、(中略)グローバル市場においては、ともかくも売れればよく、利益が上がればよい。「勝てばよい」のであり「儲かればよい」のである。それ以外の基準はない。これはまぎれもなきニヒリズムである。
_______________
この後で、佐伯氏は、だからこそ日本は「武士道」に表されるような、倫理的規範・・・それは仏教の無常観や、儒教的孝順心、神道などの自然観・・・が、必要であり、さもなければ、“金があるかないか”だけの、ニーチェの言う“力への意思”だけが基準となる、空恐ろしいニヒリズムの世界から抜け出すことは出来ない、と警鐘を鳴らします。
翻って、坂本氏の主張「人本主義」も当に同じ事を指摘されます。つまりは、“コストを下げれば良い”という価値だけで物事を推し進めようとした場合、かならず限界が来て、その限界は生身の人間に降りかかります。そして行き過ぎた結果・・・書くまでもないでしょう。先進国でありながら、自死者が3万人を超えるのは日本だけだと聞きます。内戦や戦争の起こっている国でさえ、滅多にこの数に届くことはない、とも。
朝日土曜版の他のコラムも多々仕事についての悩みや相談事が書かれていますが、およそ信じられない劣悪な勤務環境が赤裸々に綴られていたりします。
私は、全ての事柄を、宗教や仏教だけで解決できるとは微塵も思っていませんが、少なくとも宗教学者ではない、経済学が専門の佐伯氏のこの文章は、宗教者として非常に重く受け止めるべきことであります。そして、それが為に、それを解決するために、この世界に提供すべき事が宗教者には必ずあると思うし、同時にそれは我々に課せられたひとつの使命なのではないかと、今は感じています。
http://saikouji.dosugoi.net/e343420.html
日本の会社の99%を占める中小企業をフィールドワークしてきた法政大学大学院教授 坂本光司さんのインタビュー、後半です。

全く話しは変わりますが、最後の段「新興国に価格競争で勝てるはずがない・・・」ということと、だからこその「人本主義」というのは、たまたま今読んでいる佐伯啓思氏の『日本という「価値」』にかなり近いことが書かれています。
佐伯氏は、ご専門が社会経済学と経済思想史でありますが、それらにまるで無知の私でさえ、ところどころ非常に腹オチする、腑に落ちるところ多い名文を書かれます。
同書では、トピックが多岐に渡り、本当のところ、私も全く理解できない部分も(不勉強だから)ありますが、反面、同じ意図のものを、表現を変え、懇切丁寧に記してあります。
一言で言えば、現代の経済(というか金)至上主義は、結果的には何の制約も制限もなく(これは“自己責任”とか“自由”という問題にも絡む)、節度もない。しかし、その考えが蔓延した結果、いわば実体のない金融という世界に資本が流入し、それが肥大化しすぎた。まるでコントロールの効かない怪物のように、それはリーマンショックやギリシャの金融破綻を引き起こし、今なお、その指針となる解決策が生み出されない、というようなことでしょうか。
_______________
(以下、抜粋)
今日の「グローバル経済競争」は、価値の確かな基準を放棄するという点がある。徹底した価値相対主義といってもよいが、(中略)グローバル市場においては、ともかくも売れればよく、利益が上がればよい。「勝てばよい」のであり「儲かればよい」のである。それ以外の基準はない。これはまぎれもなきニヒリズムである。
_______________
この後で、佐伯氏は、だからこそ日本は「武士道」に表されるような、倫理的規範・・・それは仏教の無常観や、儒教的孝順心、神道などの自然観・・・が、必要であり、さもなければ、“金があるかないか”だけの、ニーチェの言う“力への意思”だけが基準となる、空恐ろしいニヒリズムの世界から抜け出すことは出来ない、と警鐘を鳴らします。
翻って、坂本氏の主張「人本主義」も当に同じ事を指摘されます。つまりは、“コストを下げれば良い”という価値だけで物事を推し進めようとした場合、かならず限界が来て、その限界は生身の人間に降りかかります。そして行き過ぎた結果・・・書くまでもないでしょう。先進国でありながら、自死者が3万人を超えるのは日本だけだと聞きます。内戦や戦争の起こっている国でさえ、滅多にこの数に届くことはない、とも。
朝日土曜版の他のコラムも多々仕事についての悩みや相談事が書かれていますが、およそ信じられない劣悪な勤務環境が赤裸々に綴られていたりします。
私は、全ての事柄を、宗教や仏教だけで解決できるとは微塵も思っていませんが、少なくとも宗教学者ではない、経済学が専門の佐伯氏のこの文章は、宗教者として非常に重く受け止めるべきことであります。そして、それが為に、それを解決するために、この世界に提供すべき事が宗教者には必ずあると思うし、同時にそれは我々に課せられたひとつの使命なのではないかと、今は感じています。
2012年04月09日
1260年前の今日
今から1260年前の今日、4月9日に奈良東大寺の大仏が完成したそうです。
先日も採り上げましたが、『禅グラフ』(西光寺の本堂で配布中)誌の、西山厚氏(奈良国立博物館学芸部長)のインタビューで、聖武天皇の大仏建立の背景について、語られています。
________________
(以下、文意を取りながら抜粋)
聖武天皇のお父さんは25で亡くなった。お母さんは聖武天皇を産んだ後、心を病んで人前に出られなくなった。聖武天皇が初めてお母さんに会ったのは37の時です。ちなみに祖父は28で亡くなっている。
そういう家系ですから、20代で亡くなっても不思議はない。
聖武天皇の時代は惨憺たる時代でもありました。飢饉、干ばつ、地震に天然痘の流行。今だったら、雨が降らなくても人間は簡単に死なない。でも昔は雨が降らないだけで人は死んだんです。
聖武天皇はそれを自分のせいだと受け止めた。私の政治が悪いからだと。天皇は若い頃から体が弱くて病気がちだった。しかし、心は強い。精神力で生きていたような方です。
苦しんで苦しんで、苦しんだ末に、大仏を造ることを思いつく。そのとき、大きな力やたくさんの富は、むしろ有害無用なものになる。
小さな力を無数に集めることにこそ価値がある。大仏を生み出したのは、聖武天皇の苦悩です。その苦悩に近づかないと、大仏のことは理解できません。
大きな力で造るな、たくさんの富で造るなと聖武天皇は言った。
極端に言えば、大仏は出来なくてもいいのかもしれない。大仏造りにかかわる人は心の中に大仏を造れ、と言っておられます。
そして、日に三度、大仏を礼拝せよとも言われます。できていないのに、どうするのか。それは心の中の大仏様を礼拝するのです。
自分の力を誇示するため聖武天皇は大仏を造ったという人がたくさんいます。その人は本当に苦しんだことがないのではないでしょうか。みなの幸せを本気で願ったことがないのではないでしょうか。だから苦悩する人の気持ちが分からない。
しかし、一方で苦悩は悪いことではない。法然上人や道元禅師も比叡山でエリートコースにおられたわけですが、それを許さない苦悩があって比叡山をおりた。苦悩した人にしか分からない世界があって、そういう人たちだけが、苦悩する人も苦悩していない人も共に幸せになる世界をつくり出す可能性をもてるのではないでしょうか。_____________
仏教を学んでいるという一般の方は、往々にして“歴史としての仏教”しか見ていないように思います。史実(←こういう概念も怪しいけどね)をのみ仏教として見ている、というか。もちろん、これ自体は悪いことではありませんが、その見方でしか仏教を見ないと、大変に偏狭な理解になってしまいます。

いきなり話が飛躍しますが、最近、内田樹氏のブログを拝読していて、この話と全く違うようでいて、妙に合点のいく、ぼんやりと合致するような文章がありました。
国旗掲揚と、君が代の斉唱についての文章です。全文はコチラから。
http://blog.tatsuru.com/2012/04/04_1251.php
___________
______________
全く以て、同感であります。ただ、まぁ、今回の聖武天皇と大仏建立の背景とは、かなり論点がずれているところもあります。それは自覚しています。ただ、結局、歴史としての仏教とか、史実としてだけの信仰とかってことを考えると、トピックこそまるで違いますが、あながち大ハズレでもないような印象を強く受けます。
つまり、「法律だけ(“科学的な実証”)がすべてである。それ以外の価値は認めない。」というのは、一見まったくその通りなのでありますが、だからといって、それを“人間性”すべてに適応できるかと言えば、そんなこと不可能なのであります。
あ、あたり前ですが、法律を無視しろということではないですよ。逆に、法律に従え、という話しでも。(当たり前ですので)
そうではなくて、それで人格の形成が出来るかと言えば、甚だ怪しいし、もっといえば、それで縛り付けられると思っている方が短絡的で、めでたい発想だ、と思えるということです。そして、内田氏の論点もそこではないでしょうか。
仏教的にいえば、戒律も同じで、戒律さえ守れば、そのまますぐに悟れるのか、とういう疑問も出てくるし、他方で“守っていること”を堂々と公言して、それを誇ることの方がずっと問題ではないのかという疑念もわいてきます。いや、これも短絡的に“禅は無の境地だから何をやっても良いんだ”という馬鹿げた僧侶もいたって話しも聞くし・・・。
もし、守りさえすれば・・・という発想なら、世の“引きこもり”と言われている人々は、どうなるんでしょうか・・・。
ちょっと話しが大きくなってしまったし、私もよく分からないことが多いので、今日はこの辺で止めておきます。
先日も採り上げましたが、『禅グラフ』(西光寺の本堂で配布中)誌の、西山厚氏(奈良国立博物館学芸部長)のインタビューで、聖武天皇の大仏建立の背景について、語られています。
________________
(以下、文意を取りながら抜粋)
聖武天皇のお父さんは25で亡くなった。お母さんは聖武天皇を産んだ後、心を病んで人前に出られなくなった。聖武天皇が初めてお母さんに会ったのは37の時です。ちなみに祖父は28で亡くなっている。
そういう家系ですから、20代で亡くなっても不思議はない。
聖武天皇の時代は惨憺たる時代でもありました。飢饉、干ばつ、地震に天然痘の流行。今だったら、雨が降らなくても人間は簡単に死なない。でも昔は雨が降らないだけで人は死んだんです。
聖武天皇はそれを自分のせいだと受け止めた。私の政治が悪いからだと。天皇は若い頃から体が弱くて病気がちだった。しかし、心は強い。精神力で生きていたような方です。
苦しんで苦しんで、苦しんだ末に、大仏を造ることを思いつく。そのとき、大きな力やたくさんの富は、むしろ有害無用なものになる。
小さな力を無数に集めることにこそ価値がある。大仏を生み出したのは、聖武天皇の苦悩です。その苦悩に近づかないと、大仏のことは理解できません。
大きな力で造るな、たくさんの富で造るなと聖武天皇は言った。
極端に言えば、大仏は出来なくてもいいのかもしれない。大仏造りにかかわる人は心の中に大仏を造れ、と言っておられます。
そして、日に三度、大仏を礼拝せよとも言われます。できていないのに、どうするのか。それは心の中の大仏様を礼拝するのです。
自分の力を誇示するため聖武天皇は大仏を造ったという人がたくさんいます。その人は本当に苦しんだことがないのではないでしょうか。みなの幸せを本気で願ったことがないのではないでしょうか。だから苦悩する人の気持ちが分からない。
しかし、一方で苦悩は悪いことではない。法然上人や道元禅師も比叡山でエリートコースにおられたわけですが、それを許さない苦悩があって比叡山をおりた。苦悩した人にしか分からない世界があって、そういう人たちだけが、苦悩する人も苦悩していない人も共に幸せになる世界をつくり出す可能性をもてるのではないでしょうか。_____________
仏教を学んでいるという一般の方は、往々にして“歴史としての仏教”しか見ていないように思います。史実(←こういう概念も怪しいけどね)をのみ仏教として見ている、というか。もちろん、これ自体は悪いことではありませんが、その見方でしか仏教を見ないと、大変に偏狭な理解になってしまいます。

いきなり話が飛躍しますが、最近、内田樹氏のブログを拝読していて、この話と全く違うようでいて、妙に合点のいく、ぼんやりと合致するような文章がありました。
国旗掲揚と、君が代の斉唱についての文章です。全文はコチラから。
http://blog.tatsuru.com/2012/04/04_1251.php
___________
もし、「この憲法前文を書いたのが実際には何人かのアメリカ人であるという歴史的事実」というにとどまって、「だからこんなものはナンセンスだ」という「リアリスト」がいたら、彼は「戦争に勝った国の人間は敗戦国民にどのような無理難題も押しつけることができる」という命題を「現実的」だと思っていることになる。
けれども、そのときにこの「リアリスト」もまた「戦争に勝ったアメリカ人たち」にはある種の「集合的な意思」があると思っているし、「敗戦国民」には全員に共通する「負け犬的メンタリティ-」が内在していると思っている。
彼もまた「国民」という集合的な意思や感情が存在するということは無批判に前提しているのである。
この「リアリスト」が未成熟なのは、「欲望や支配欲や卑屈や弱さ」は集合的性格でありうるが「できるだけフェアで住みやすい統治システムをめざす意思」が集合的に共有されるということは「ありえない」と信じているからである。
「色と欲」だけがリアルであり、「きれいごと」はフェイクだというのは、その人のパーソナルな経験が生み出した私見であり、一般性を要求できるようなものではない。
けれども、多くの自称「リアリスト」はこの水準から出ることがない。
______________
全く以て、同感であります。ただ、まぁ、今回の聖武天皇と大仏建立の背景とは、かなり論点がずれているところもあります。それは自覚しています。ただ、結局、歴史としての仏教とか、史実としてだけの信仰とかってことを考えると、トピックこそまるで違いますが、あながち大ハズレでもないような印象を強く受けます。
つまり、「法律だけ(“科学的な実証”)がすべてである。それ以外の価値は認めない。」というのは、一見まったくその通りなのでありますが、だからといって、それを“人間性”すべてに適応できるかと言えば、そんなこと不可能なのであります。
あ、あたり前ですが、法律を無視しろということではないですよ。逆に、法律に従え、という話しでも。(当たり前ですので)
そうではなくて、それで人格の形成が出来るかと言えば、甚だ怪しいし、もっといえば、それで縛り付けられると思っている方が短絡的で、めでたい発想だ、と思えるということです。そして、内田氏の論点もそこではないでしょうか。
仏教的にいえば、戒律も同じで、戒律さえ守れば、そのまますぐに悟れるのか、とういう疑問も出てくるし、他方で“守っていること”を堂々と公言して、それを誇ることの方がずっと問題ではないのかという疑念もわいてきます。いや、これも短絡的に“禅は無の境地だから何をやっても良いんだ”という馬鹿げた僧侶もいたって話しも聞くし・・・。
もし、守りさえすれば・・・という発想なら、世の“引きこもり”と言われている人々は、どうなるんでしょうか・・・。
ちょっと話しが大きくなってしまったし、私もよく分からないことが多いので、今日はこの辺で止めておきます。
2012年04月07日
え?!今日がクリスマスイブ????
ちょっと釣り的タイトルですが・・・(笑)
明日、4月8日は、「花まつり」です。つまり、仏教の開祖、お釈迦様(ブッダ)のお生まれになった日とされています。
私たち仏教徒にとって、重要な3つの日の1つ。
花御堂(はなみどう)という、ブッダの生誕を祝し、それを模した小さなお堂を組み立て、そこへたくさんの花を添えて、彩ります。
現在制作中。

(これは花御堂の屋根)
そして!プレゼントもあります★
小さなお子様にお持ち帰り頂けるように、「花まつり」セットもご用意しました!
これ、面白いのは、「甘茶のティーバッグ」が入っていること。
甘茶、というのはアジサイのような木らしいですが、字の通り、見た目はお茶なのに甘い。もちろん、砂糖などは添加せずに、です。
ブッダが生まれたとき、それを祝して竜が天から降りてきて、甘露(かんろ・・・甘い雨)を降らせた、との伝説に基づく物です。
かつては、甘味は大変貴重なものでした(どうように、お餅も) であるからこそ、お供えをするのです。
ともあれ、この甘茶、結構飲み慣れるとクセになる味なので、ご賞味ください!
この機会にお寺にお出かけいただき、ブッダのご生誕をお祝いしましょう。

あ、明日はここ大手町のお花見もあります。これから準備に出かけます。イベント目白押し(?)の週末になりそうです。
明日、4月8日は、「花まつり」です。つまり、仏教の開祖、お釈迦様(ブッダ)のお生まれになった日とされています。
私たち仏教徒にとって、重要な3つの日の1つ。
花御堂(はなみどう)という、ブッダの生誕を祝し、それを模した小さなお堂を組み立て、そこへたくさんの花を添えて、彩ります。
現在制作中。
(これは花御堂の屋根)
そして!プレゼントもあります★
小さなお子様にお持ち帰り頂けるように、「花まつり」セットもご用意しました!
これ、面白いのは、「甘茶のティーバッグ」が入っていること。
甘茶、というのはアジサイのような木らしいですが、字の通り、見た目はお茶なのに甘い。もちろん、砂糖などは添加せずに、です。
ブッダが生まれたとき、それを祝して竜が天から降りてきて、甘露(かんろ・・・甘い雨)を降らせた、との伝説に基づく物です。
かつては、甘味は大変貴重なものでした(どうように、お餅も) であるからこそ、お供えをするのです。
ともあれ、この甘茶、結構飲み慣れるとクセになる味なので、ご賞味ください!
この機会にお寺にお出かけいただき、ブッダのご生誕をお祝いしましょう。

あ、明日はここ大手町のお花見もあります。これから準備に出かけます。イベント目白押し(?)の週末になりそうです。
2012年03月30日
奈良東大寺の大仏はどうして造られたのか?
同じく『曹洞禅グラフ』にあったインタビュー。奈良国立博物館学芸部長の西山 厚氏へのインタビューです。
「東大寺の大仏は何故作られたのか?」
このあと、聖武天皇の生い立ちや時代背景、大仏建立の物語が語られているのですが、ここでは触れません。(それはそれで面白いのです)
私が大切だと思えるのは、引用した最後の文。アンダーラインを引いた箇所です。
全く話は変わりますが、曹洞宗に限らず、広く読まれているお経に『妙法蓮華経観世音菩薩普門品偈』というのがあります。一言で言えば、観音様の無限のお力を信じ、そしてその広大無辺な慈悲の力を、詩で賛嘆し綴るもの、と言えましょう。

当初、このお経の意味をちょっと調べているとき、あまりにも非科学的な、それこそSF的な挿話(例えば・・・火が燃えさかる抗に突き落とされそうになったとき、観音様のお力を念じると、たちまち火は消え、水となり池となって助かる・・・とか)に、バカバカしさというか、変な気持ちになったのを覚えています。
仏教は生き方を教えてくれるものではないのか、もっと哲学的で、もっと実践的なことがお経には書いてないのか、とそのときは思ったものです。
が、しかし、その後学びを進めるにつれ、或いは信仰というものをおぼろげながら考えるとき、この考えは、ひどく偏狭な物に思えてきました。
この経典が設立した時代、そして中国に将来された過程。翻訳され、どれほどの人々の信仰を集め、安寧を与えてきたのか・・・きっと現代人は想像もつかないほどの労苦と、信仰心に裏打ちされた驚異的な実行力があり、数々の弾圧もあったでしょう。そして、そうした状況で、必死で安寧を祈り、読誦し書写し、後世に伝えてきた人々の事を思うとき、“現代の”目でしか見られない自分の判断というのは、ひどく滑稽なものに思えてきました。
何より大切なのは、こうした非科学的なことを馬鹿にする自分は、“合理的で科学的な”ものだ、そして古くからの信仰や風習を“役に立たない物”と思い込む、その愚かさに気付いたことでした。
そんな“自分”など、苦労を知らず、絶望を味わったことがなく、“宗教など非科学的な価値のないもの”と思っている。だがしかし、そんな“自分”でさえ、ものすごく脆くて、危なっかしい自己なのだということに気がついたからです。
以来、このお経はマイフェイバリット(笑)になっていますが、歴史に限らず、こうした思いを読み取り、自らのものとして思いを馳せると言うことが、どれほど大切なことなのか、気付かされたのでした。
「東大寺の大仏は何故作られたのか?」
聖武天皇が何故、大仏を作られたのか、それを正確に知る人は少ないのではないか?
例えば、学校の試験なら「聖武天皇は仏教の力で国を守り、みなを幸せにしようと考え、大仏を作った」と答えれば、多分100点をくれるだろう。しかし、本当のところはそうではない。
「大仏造立の詔」にそれがある。そこには「万代の副業を修めて、動植ことごとく栄えむとす」、つまり、すべての動植物が共に栄える世の中を作りたい、これが大仏造立を決意した理由である。
通常、動物も植物も共に栄える世界などあり得ないという理由で、研究者はその部分をとばしてしまう。しかし、それではおかしい。聖武天皇の思いに近づくべき。
大仏を作るのは、未曾有の大事業。であればこそ、莫大な労力とお金がかかる。それなのに、天皇はおかしなことを言う。“大きな力で作るな。たくさんの富で造るな。一本の草・一握りの土を持ってやって来て大仏造営を手伝いたいという人があれば、その人に手伝って貰いなさい”と。
なぜ、こんな役にも立たないような小さな力で、あの大仏を立てられたのか。何を考えていたのか。聖武天皇がどうして、そのような気持ちを抱くに至ったか、これをかんがえるのが大事。それなしに結論を急ぐのは、歴史上の出来事なんか、所詮は他人事だからでしょう。
このあと、聖武天皇の生い立ちや時代背景、大仏建立の物語が語られているのですが、ここでは触れません。(それはそれで面白いのです)
私が大切だと思えるのは、引用した最後の文。アンダーラインを引いた箇所です。
全く話は変わりますが、曹洞宗に限らず、広く読まれているお経に『妙法蓮華経観世音菩薩普門品偈』というのがあります。一言で言えば、観音様の無限のお力を信じ、そしてその広大無辺な慈悲の力を、詩で賛嘆し綴るもの、と言えましょう。

当初、このお経の意味をちょっと調べているとき、あまりにも非科学的な、それこそSF的な挿話(例えば・・・火が燃えさかる抗に突き落とされそうになったとき、観音様のお力を念じると、たちまち火は消え、水となり池となって助かる・・・とか)に、バカバカしさというか、変な気持ちになったのを覚えています。
仏教は生き方を教えてくれるものではないのか、もっと哲学的で、もっと実践的なことがお経には書いてないのか、とそのときは思ったものです。
が、しかし、その後学びを進めるにつれ、或いは信仰というものをおぼろげながら考えるとき、この考えは、ひどく偏狭な物に思えてきました。
この経典が設立した時代、そして中国に将来された過程。翻訳され、どれほどの人々の信仰を集め、安寧を与えてきたのか・・・きっと現代人は想像もつかないほどの労苦と、信仰心に裏打ちされた驚異的な実行力があり、数々の弾圧もあったでしょう。そして、そうした状況で、必死で安寧を祈り、読誦し書写し、後世に伝えてきた人々の事を思うとき、“現代の”目でしか見られない自分の判断というのは、ひどく滑稽なものに思えてきました。
何より大切なのは、こうした非科学的なことを馬鹿にする自分は、“合理的で科学的な”ものだ、そして古くからの信仰や風習を“役に立たない物”と思い込む、その愚かさに気付いたことでした。
そんな“自分”など、苦労を知らず、絶望を味わったことがなく、“宗教など非科学的な価値のないもの”と思っている。だがしかし、そんな“自分”でさえ、ものすごく脆くて、危なっかしい自己なのだということに気がついたからです。
以来、このお経はマイフェイバリット(笑)になっていますが、歴史に限らず、こうした思いを読み取り、自らのものとして思いを馳せると言うことが、どれほど大切なことなのか、気付かされたのでした。
2012年03月28日
”無事”は良いこと?悪いこと?
『曹洞禅グラフ』という仏教企画社が発行している小冊子があります。季刊で、西光寺の本堂でお檀家さんにお配りしているのですが、この小冊子、泰明は結構好きで拝読しています。今月号にも、中々興味深い文があったので、ご紹介したいと思います。
哲学者、立教大学の教授である内山節氏の寄稿、「無事な春」と題されたものより。
(以下、適宜抄出)
とても分かりやすくて、心に染みる、淡々として、しかも確実に訴える氏の文章でした。全文はご紹介できませんが、まだ西光寺の本堂にございますので、どうぞお持ち下さい。
さて、この“無事”という言葉、すっかり日本語に定着していますが、禅学大辞典によれば「1.問題がない。事が起こらない。」という、所謂一般的な意味もありますが、他方「2.寂静無為の境涯。本来の自己に立ち還った安らかさ」とあります。
この“本来の自己に立ち還った”ということを考えるとき、現代に生きる我々は、あまりもその“自己”を取り違え、はき違えて生きているような気がしてなりません。
端的に言えば、文中にある“人間の欲望の全面的な肯定”を実行することが“自己表現”だと勘違いし、それを実行できる“自由”を最上の価値として盲信することが現代人の“自己”そしてそれを邁進してきた結果が、この現代の社会ではないか。
例えば、これは佐伯啓思氏が繰り返し仰っていることですが、自由とはそもそも自明の権利ではなく、単純にその時の社会・政治・状況が許しただけの中での“自由”であり、かつ(現代では、それがさも最上の真理であるかのように思われているが)最上に据え置くべき価値・目標ではなく、自らが信じうる価値への“ただの手段”が“自由”である、ということ。
そして、その自由のはき違えが、「新自由主義」を生みだし、「構造改革」の名の下に推し進められ、隠蔽され続けてきた、格差社会・生産要素の市場化、ひいては市場中心主義を増大させてしまった、ということです。
だいぶ話しを端折っているので、この文意も的確ではないのですが、つまり我々は“自由だ”とか“これこそが至上の価値だ”とか、ある意味、普遍的真理のように思っていることって、実際、大したことのない、極めて脆弱で、不確かな社会の価値だったりします。
そこを気がつかずに、“世間の常識”が真理であるかの如く信奉する態度、これが仏教的に言うところの“無明”であります。
一つだけ言えるのは、こうした無明を抑え、解くために仏教の智慧があるのであり、たぶん仏教に限らず、宗教や道徳や哲学や芸術と言った、近代化の中で価値を置かれなかったものの中に、或いはその複合体の中に、その答えがあるということ。そして、それを“自らが実行する”ことが、重要ではないでしょうか。
哲学者、立教大学の教授である内山節氏の寄稿、「無事な春」と題されたものより。
(以下、適宜抄出)
自然は毎年同じ事を繰り返している。かつては、人々も基本的には毎年同じことを繰り返していた。そこには自然と人間が時空を共有していた時代が展開していた。
この時代の人々は「無事」を尊んでいたように思う。日常会話のなかでも「無事なだけの人生で」と人々は自分の過去を振り返り、無事に過ごすことができたことに感謝した。「無事が何より」だったのである。
無事に一年を過ごすことができれば、秋にはお米が収穫でき、お盆には先祖たちを、正月には神様を迎えることができた。やり過ごしたことのない一年だったと感じられる日常のなかに、無事への感謝が込められていた。
現代社会が否定したのは、こんな人間たちの生き方だったように思う。無事な生き方は進歩のない生き方とみなされるようになり、私たちは日々向上しなければいけなくなった。
もちろんどんな時代でも、人間たちに向上したいという思いはあったことだろう。しかし以前の向上心というのは、技を深めていくとか、真理がわかるようになるというところにあったのであって、ひたすら新しいものを獲得しようとした近代以降のそれとは質の違うものであった。近代以降の向上心は、人間の欲望の全面的な肯定とともに展開する。
気がつけば、無事ではない自分自身と社会が広がっていた。
原発事故はその象徴である。長期にわたって無事を取り戻すことのできない地域が発生し、得体の知れない放射性物質という不安と共存する生き方を強制されてしまった。
一方で、津波の被害を受けた地域では、それを応援するさまざまな人々と連携しながら、「無事が何より」といえるような地域をつくる試みが始まっている。
とても分かりやすくて、心に染みる、淡々として、しかも確実に訴える氏の文章でした。全文はご紹介できませんが、まだ西光寺の本堂にございますので、どうぞお持ち下さい。
さて、この“無事”という言葉、すっかり日本語に定着していますが、禅学大辞典によれば「1.問題がない。事が起こらない。」という、所謂一般的な意味もありますが、他方「2.寂静無為の境涯。本来の自己に立ち還った安らかさ」とあります。
この“本来の自己に立ち還った”ということを考えるとき、現代に生きる我々は、あまりもその“自己”を取り違え、はき違えて生きているような気がしてなりません。
端的に言えば、文中にある“人間の欲望の全面的な肯定”を実行することが“自己表現”だと勘違いし、それを実行できる“自由”を最上の価値として盲信することが現代人の“自己”そしてそれを邁進してきた結果が、この現代の社会ではないか。
例えば、これは佐伯啓思氏が繰り返し仰っていることですが、自由とはそもそも自明の権利ではなく、単純にその時の社会・政治・状況が許しただけの中での“自由”であり、かつ(現代では、それがさも最上の真理であるかのように思われているが)最上に据え置くべき価値・目標ではなく、自らが信じうる価値への“ただの手段”が“自由”である、ということ。
そして、その自由のはき違えが、「新自由主義」を生みだし、「構造改革」の名の下に推し進められ、隠蔽され続けてきた、格差社会・生産要素の市場化、ひいては市場中心主義を増大させてしまった、ということです。
だいぶ話しを端折っているので、この文意も的確ではないのですが、つまり我々は“自由だ”とか“これこそが至上の価値だ”とか、ある意味、普遍的真理のように思っていることって、実際、大したことのない、極めて脆弱で、不確かな社会の価値だったりします。
そこを気がつかずに、“世間の常識”が真理であるかの如く信奉する態度、これが仏教的に言うところの“無明”であります。
一つだけ言えるのは、こうした無明を抑え、解くために仏教の智慧があるのであり、たぶん仏教に限らず、宗教や道徳や哲学や芸術と言った、近代化の中で価値を置かれなかったものの中に、或いはその複合体の中に、その答えがあるということ。そして、それを“自らが実行する”ことが、重要ではないでしょうか。
2012年02月15日
自分、僧侶ですから・・・【涅槃会】
今日、2月15日は仏教徒にとって非常に重要な3つの日のひとつ、「涅槃会」(ねはんえ)です。
涅槃とは、本来、煩悩を消し去った後の安楽なる状態を言うのですが、これが転じてお釈迦様のご命日とされています。もう少し言えば、ブッダは“死”というものを以て、安楽なることを示されたということで、「涅槃」という言葉が使われています。

さて、今日はせっかくなので、『佛垂般涅槃略説教誡経』を採り上げてみたいと思います。長いタイトルですが、ずばりこれはお釈迦様が亡くなる前に、最後に遺した言葉・教えのお経とされています。ちなみに読み方は「ぶっすいはつねはんりゃくせつきょうかいきょう」もしくは「ぶっしはつねはんりゃくせつきょうかいきょう」、略して“遺経”(ゆいきょう)とか、“遺教経”とか言われています。まぁ文字通り「最後に遺されたお経」ということですね。(以下、「遺経」と書きます)
ある説に依れば、このお経は“偽経”と言われ、俗に言う所の「中国で後世に作られた偽物」という事なんですが、言ってしまえば、元々ブッダは、教えをただの1つも文字として遺されていない(これはイエスも同じと言われていますね)訳で、そう言う意味では「パリニッバーナ」だって同じようなものです。なんでもかんでも、「北伝(中国や日本に伝わる仏教)は偽物で、南伝(スリランカやタイなどの仏教)こそ本物だ!」と主張する人がいますが・・・このことについて詳しく書くと、とんでもなく長くなりそうなので割愛します。
が、とにかく、泰明は個人的にこの「遺経」が非常に気に入っています。西光寺ではお通夜にこのお経をおつとめするので、年に何十回も読むから、ということもありますが、「死の直前」という臨場感あふれる描写と、教えが割と平易で、身に染みる感じがするからです。
実際はとても長いお経なので、この中からごくの一部分だけを書きます。今日は終わりに近いこの部分。
「当に知るべし、世は皆無常なり、会うものは必ず離るることあり。憂悩を懐くこと勿れ、世相是の如し。当に勤めて精進して早く解脱を求め、智慧の明を以て、諸の痴暗を滅すべし。世は実に危脆なり、牢強なる者なし。」
あまり難しい言葉ではないのですが、一応現代語風にいうなら・・・
「(ブッダは弟子達に伝えた)・・・まさに知っておきなさい。世の中はみな無常です。会った人とは必ず別れがくるのです。(しかしだからといって)いたずらに悩み憂いを持つことはありません。世相がこのようなものだから。
だからこそ、しっかり勤め励み精進をして、解脱(さとり)を求め、正しい智慧(見方・考え方)という“明かり”をもって、この愚かさの“暗さ”を滅しなさい。
世の中は、実にもろく、危ういのだから、堅剛なものなどありません。」
ま、だいたいこんな感じでしょうか。この遺経も、最後の最後の段になると、殊更に臨場感あふれ、本当に死を前にした人間が、遺された人に伝えたい最後の思いを吐露するような文が続きます。
無常、というと、何か寂寥感が込み上げてくるような面持ちがしますが、仏教的にいえば、これが基本理念であります。どうしても我々は“世の中ははかないものだから”といい、怠惰をむさぼり、楽な方楽な方へと流れがち。
しかし、だからこそ、ブッダは「悲しむことはない、これが世の掟だから」と言い、「怠ることなく、修行を完成させなさい」(このフレーズはパリニッバーナにある)と最後に言い残すのです。ま、これは言ってみれば弟子たちに伝えた言葉であるので、たぶんに“僧侶向け”な教えではありますが。とはいうものの、一般の方が読んでも「なるほど~」と仰っていただけるんじゃないかと思って紹介しました。
涅槃とは、本来、煩悩を消し去った後の安楽なる状態を言うのですが、これが転じてお釈迦様のご命日とされています。もう少し言えば、ブッダは“死”というものを以て、安楽なることを示されたということで、「涅槃」という言葉が使われています。

さて、今日はせっかくなので、『佛垂般涅槃略説教誡経』を採り上げてみたいと思います。長いタイトルですが、ずばりこれはお釈迦様が亡くなる前に、最後に遺した言葉・教えのお経とされています。ちなみに読み方は「ぶっすいはつねはんりゃくせつきょうかいきょう」もしくは「ぶっしはつねはんりゃくせつきょうかいきょう」、略して“遺経”(ゆいきょう)とか、“遺教経”とか言われています。まぁ文字通り「最後に遺されたお経」ということですね。(以下、「遺経」と書きます)
ある説に依れば、このお経は“偽経”と言われ、俗に言う所の「中国で後世に作られた偽物」という事なんですが、言ってしまえば、元々ブッダは、教えをただの1つも文字として遺されていない(これはイエスも同じと言われていますね)訳で、そう言う意味では「パリニッバーナ」だって同じようなものです。なんでもかんでも、「北伝(中国や日本に伝わる仏教)は偽物で、南伝(スリランカやタイなどの仏教)こそ本物だ!」と主張する人がいますが・・・このことについて詳しく書くと、とんでもなく長くなりそうなので割愛します。
が、とにかく、泰明は個人的にこの「遺経」が非常に気に入っています。西光寺ではお通夜にこのお経をおつとめするので、年に何十回も読むから、ということもありますが、「死の直前」という臨場感あふれる描写と、教えが割と平易で、身に染みる感じがするからです。
実際はとても長いお経なので、この中からごくの一部分だけを書きます。今日は終わりに近いこの部分。
「当に知るべし、世は皆無常なり、会うものは必ず離るることあり。憂悩を懐くこと勿れ、世相是の如し。当に勤めて精進して早く解脱を求め、智慧の明を以て、諸の痴暗を滅すべし。世は実に危脆なり、牢強なる者なし。」
あまり難しい言葉ではないのですが、一応現代語風にいうなら・・・
「(ブッダは弟子達に伝えた)・・・まさに知っておきなさい。世の中はみな無常です。会った人とは必ず別れがくるのです。(しかしだからといって)いたずらに悩み憂いを持つことはありません。世相がこのようなものだから。
だからこそ、しっかり勤め励み精進をして、解脱(さとり)を求め、正しい智慧(見方・考え方)という“明かり”をもって、この愚かさの“暗さ”を滅しなさい。
世の中は、実にもろく、危ういのだから、堅剛なものなどありません。」
ま、だいたいこんな感じでしょうか。この遺経も、最後の最後の段になると、殊更に臨場感あふれ、本当に死を前にした人間が、遺された人に伝えたい最後の思いを吐露するような文が続きます。
無常、というと、何か寂寥感が込み上げてくるような面持ちがしますが、仏教的にいえば、これが基本理念であります。どうしても我々は“世の中ははかないものだから”といい、怠惰をむさぼり、楽な方楽な方へと流れがち。
しかし、だからこそ、ブッダは「悲しむことはない、これが世の掟だから」と言い、「怠ることなく、修行を完成させなさい」(このフレーズはパリニッバーナにある)と最後に言い残すのです。ま、これは言ってみれば弟子たちに伝えた言葉であるので、たぶんに“僧侶向け”な教えではありますが。とはいうものの、一般の方が読んでも「なるほど~」と仰っていただけるんじゃないかと思って紹介しました。