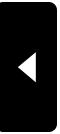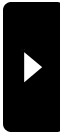2012年03月02日
坊主はホントに丸儲けか?こつこつe-tax完了!!
やった~~~~~~~!(というのも変だけど)確定申告終了!!
今年もe-taxでしたが、ちょっと苦戦を強いられた。
思い起こせば4,5年前、必要に迫られて開始したe-tax。今ほどはまだ普及していなくて、あまり参考になるサイトもなく、さらに税に関してまったく無知だった私。そもそも市役所でカードを作ったのに、電子証明と住民台帳の有効期限が異なっていることも知らず、ICカードリーダーが必要なのも知らず、いきなり“飛び込んだ”状態だったのです。(リーダーも売ってなくて電気屋をハシゴ)
今でも忘れませんが、初年度は本当に苦労した。申請サイトも読みづらい(今もだけど)し、何を言っているのか不明な所も多々あり、しかも、初めてだったから何度も何度もIDを打ち込まされて、仕舞いには16桁のIDを暗記してしまった(笑)
ということで、今年もやって参りましたこの季節。
今年は電子証明の更新を忘れていて、若干焦る。しかも、更新するとカードはそのままなのに、e-taxの登録が一端リセットされるらしく、今回は最後の最後、申告書を送信する段でエラーメッセージ。はじめから言ってよ。
毎度思うのですが、e-taxって一番トップページはさも“簡単ですよ”と言わんばかりの分かりやすいレイアウト、デザインになっているのに、徐々にそのセンスが薄れていき、最後は非常に重要な文言も見落としがち。それは何でかと言えば、色を使いすぎているんですね。だからどこに重要な文章があるのか、いまいちよく分からん。(もっとも、税を預かる非常に重要なことだから、当たり前だし、そもそも電子申請に踏み切ったこと自体、大変なことです。ここは感謝)
でもね、「23年度の申告を始める」という最初のページに「必要なもの」というPCの環境やらセットアップの確認があるんですが、実はそれだけでは今回のように不十分。
何というか、RPGで言うなら、“ラスボスの所まで来たことは来たんだけど、序段で取るべきアイテムがなくて、倒せない”みたいな。だから最初まで戻らないといけない。(あぅ、分かりづらいか)
あ、グチグチしてすみません!!(汗)

で、今日の本題は、税金にからめて、「坊主は丸儲けか?」ということ。
いつかは書こうと思っていたこのテーマなんですが、昨日の「彼岸寺」(超宗派によるインターネットヴァーチャル寺院)の記事で、バッチリなことが書かれていました。
ここにも書いてありますが、坊さんって、結局サラリーマンなんです。たとえ「お寺で使ってください」と100万円寄附(布施)があっても、そのまま僧侶の懐には入りません。一端お寺(宗教法人)に入り、僧侶はそこから決まったサラリーが出る。まったくサラリーマンと同じ。だから当然所得税も納めます。(みなさん、知っていましたか?)よく知りもしないのに、“坊主は丸儲けだ”とよくも言えるよなぁ、と私なんかは思いますけど。
話しはそれましたが、この「お布施のゆくえ」と題された記事、非常に簡にして要を得ているので、引用させて頂きます。(全文お読み頂きたいくらいです)
「お布施のゆくえ」彼岸寺 松島靖朗師
http://www.higan.net/bizplan/2012/02/post-32.html
*****************
「坊主丸儲け」という言葉があります。お寺やお坊さんに関する世間話は、なにかと話題に事欠きませんが、その中でも一番関心が集まるのはお金のお話でしょう。
(中略)
冒頭の「坊主丸儲け」という言葉。人々が口にする背景には、短いお経を読んで高いお布施を懐に入れて帰っていく姿を見たといった経験や、お坊さんは税金を払わなくていい、といった流言が存在しているからだと思います。
実際のところはどうなのでしょうか?
まず短いお経に高いお布施を...というものですが、これはきっと「お布施」というものに対する誤解や説明不足が原因であると思います。お布施とは本来、お金の執着から離れるために喜んでお金を捨てることで(これを喜捨といいます。またお金を施すということから財施といいます。)、そのお金を仏道修行に励むお坊さんに施すというものです。これに対して、お坊さんはお経を読むことで仏教の教えを施すのです(これを法施といいます。)。お経を読むだけでなく、お経に書かれた意味や法要の意味をお伝えすることも法施の一つです。この相互にお布施をしあう関係において、財と法が移動することが本来のお布施の流れなのです。
(中略)
そして、二つ目の「お坊さんは税金を払わなくていい」というものですが、これは間違いです。正確には宗教法人には一部の収入※を除いて、法人税が課税されないのです。お坊さんはお布施を懐に入れ、そのまま飲み食いしているのではなく(いらっしゃるかもしれませんが...)、所属するお寺から給与を受け取っています。宗教法人から給与を支給されるお坊さん個人には、会社で働いている方々と同様に所得税や住民税が課税されており、国民年金や国民健康保険にも加入する必要があります。お坊さんも買い物をすれば消費税を払い、自動車に乗れば自動車税を払います。お坊さんも皆さんと同じ納税者なのです。
註:※駐車場の運営や物販販売など、宗教行為によらない収入に対しては所得税が課税されます。(ただしこれも、一般企業と比較すると税率などの面で優遇措置があります。)
**************
布施、というのは、六波羅蜜(ろくはらみつ、ろっぱらみつ)という、彼岸(安らぎの世界)に行くための菩薩が行う6つの徳目・修行項目の第一です。この6つの徳目を実行することが大乗仏教徒にとって重要だとされています。ちなみに、6つの項目は、布施・持戒・忍辱・精進・静慮(禅定)・智慧の6つです。
ちなみに波羅蜜は、元々“パーラミタ”の音写で、“到彼岸”とか訳されます。
松島師の文にはありませんが、この布施を積むことは、すなわち布施をした本人に見えない功徳が積まれる、ということです。
昔、ある僧侶から聞いたことですが、その僧侶のお寺の先々代住職という方が、中々豪傑な方だったそうで、檀家さんが御布施を持ってきても、「ありがとう」のただの一言も言わなかったそうです。
理由は「布施を持ってきた檀家にこそ、功徳が積まれる。功徳を積ませる機会を与える僧侶が“ありがとう”ではおかしい」と常々言っていたとか。
今の経済至上主義・資本主義社会では全く理解できないかもしれません。何でお金持ってきて“ありがとう”の一言もないんだろう、と思うのが普通です。でも、その“当たり前”という感覚を一回ご破算にして、この布施ということを考えると、見えてくるものがあります。例えば「だから“御布施は決まりがないのか”」とかね。読経料でも、御礼でもなく、布施をして利があるのは仏教的に見て本来は、僧侶ではなく施主そのものだからです。
こう考えると、布施は読経料ではないのですから、僧侶が「ありがとう」というのも教義的にはおかしいのです。ちなみに私は「お納めさせて頂きます」と言っていますが。
今日は思わず長文になってしまいました。最後までお読み頂き、ありがとうございました。
今年もe-taxでしたが、ちょっと苦戦を強いられた。
思い起こせば4,5年前、必要に迫られて開始したe-tax。今ほどはまだ普及していなくて、あまり参考になるサイトもなく、さらに税に関してまったく無知だった私。そもそも市役所でカードを作ったのに、電子証明と住民台帳の有効期限が異なっていることも知らず、ICカードリーダーが必要なのも知らず、いきなり“飛び込んだ”状態だったのです。(リーダーも売ってなくて電気屋をハシゴ)
今でも忘れませんが、初年度は本当に苦労した。申請サイトも読みづらい(今もだけど)し、何を言っているのか不明な所も多々あり、しかも、初めてだったから何度も何度もIDを打ち込まされて、仕舞いには16桁のIDを暗記してしまった(笑)
ということで、今年もやって参りましたこの季節。
今年は電子証明の更新を忘れていて、若干焦る。しかも、更新するとカードはそのままなのに、e-taxの登録が一端リセットされるらしく、今回は最後の最後、申告書を送信する段でエラーメッセージ。はじめから言ってよ。
毎度思うのですが、e-taxって一番トップページはさも“簡単ですよ”と言わんばかりの分かりやすいレイアウト、デザインになっているのに、徐々にそのセンスが薄れていき、最後は非常に重要な文言も見落としがち。それは何でかと言えば、色を使いすぎているんですね。だからどこに重要な文章があるのか、いまいちよく分からん。(もっとも、税を預かる非常に重要なことだから、当たり前だし、そもそも電子申請に踏み切ったこと自体、大変なことです。ここは感謝)
でもね、「23年度の申告を始める」という最初のページに「必要なもの」というPCの環境やらセットアップの確認があるんですが、実はそれだけでは今回のように不十分。
何というか、RPGで言うなら、“ラスボスの所まで来たことは来たんだけど、序段で取るべきアイテムがなくて、倒せない”みたいな。だから最初まで戻らないといけない。(あぅ、分かりづらいか)
あ、グチグチしてすみません!!(汗)

で、今日の本題は、税金にからめて、「坊主は丸儲けか?」ということ。
いつかは書こうと思っていたこのテーマなんですが、昨日の「彼岸寺」(超宗派によるインターネットヴァーチャル寺院)の記事で、バッチリなことが書かれていました。
ここにも書いてありますが、坊さんって、結局サラリーマンなんです。たとえ「お寺で使ってください」と100万円寄附(布施)があっても、そのまま僧侶の懐には入りません。一端お寺(宗教法人)に入り、僧侶はそこから決まったサラリーが出る。まったくサラリーマンと同じ。だから当然所得税も納めます。(みなさん、知っていましたか?)よく知りもしないのに、“坊主は丸儲けだ”とよくも言えるよなぁ、と私なんかは思いますけど。
話しはそれましたが、この「お布施のゆくえ」と題された記事、非常に簡にして要を得ているので、引用させて頂きます。(全文お読み頂きたいくらいです)
「お布施のゆくえ」彼岸寺 松島靖朗師
http://www.higan.net/bizplan/2012/02/post-32.html
*****************
「坊主丸儲け」という言葉があります。お寺やお坊さんに関する世間話は、なにかと話題に事欠きませんが、その中でも一番関心が集まるのはお金のお話でしょう。
(中略)
冒頭の「坊主丸儲け」という言葉。人々が口にする背景には、短いお経を読んで高いお布施を懐に入れて帰っていく姿を見たといった経験や、お坊さんは税金を払わなくていい、といった流言が存在しているからだと思います。
実際のところはどうなのでしょうか?
まず短いお経に高いお布施を...というものですが、これはきっと「お布施」というものに対する誤解や説明不足が原因であると思います。お布施とは本来、お金の執着から離れるために喜んでお金を捨てることで(これを喜捨といいます。またお金を施すということから財施といいます。)、そのお金を仏道修行に励むお坊さんに施すというものです。これに対して、お坊さんはお経を読むことで仏教の教えを施すのです(これを法施といいます。)。お経を読むだけでなく、お経に書かれた意味や法要の意味をお伝えすることも法施の一つです。この相互にお布施をしあう関係において、財と法が移動することが本来のお布施の流れなのです。
(中略)
そして、二つ目の「お坊さんは税金を払わなくていい」というものですが、これは間違いです。正確には宗教法人には一部の収入※を除いて、法人税が課税されないのです。お坊さんはお布施を懐に入れ、そのまま飲み食いしているのではなく(いらっしゃるかもしれませんが...)、所属するお寺から給与を受け取っています。宗教法人から給与を支給されるお坊さん個人には、会社で働いている方々と同様に所得税や住民税が課税されており、国民年金や国民健康保険にも加入する必要があります。お坊さんも買い物をすれば消費税を払い、自動車に乗れば自動車税を払います。お坊さんも皆さんと同じ納税者なのです。
註:※駐車場の運営や物販販売など、宗教行為によらない収入に対しては所得税が課税されます。(ただしこれも、一般企業と比較すると税率などの面で優遇措置があります。)
**************
布施、というのは、六波羅蜜(ろくはらみつ、ろっぱらみつ)という、彼岸(安らぎの世界)に行くための菩薩が行う6つの徳目・修行項目の第一です。この6つの徳目を実行することが大乗仏教徒にとって重要だとされています。ちなみに、6つの項目は、布施・持戒・忍辱・精進・静慮(禅定)・智慧の6つです。
ちなみに波羅蜜は、元々“パーラミタ”の音写で、“到彼岸”とか訳されます。
松島師の文にはありませんが、この布施を積むことは、すなわち布施をした本人に見えない功徳が積まれる、ということです。
昔、ある僧侶から聞いたことですが、その僧侶のお寺の先々代住職という方が、中々豪傑な方だったそうで、檀家さんが御布施を持ってきても、「ありがとう」のただの一言も言わなかったそうです。
理由は「布施を持ってきた檀家にこそ、功徳が積まれる。功徳を積ませる機会を与える僧侶が“ありがとう”ではおかしい」と常々言っていたとか。
今の経済至上主義・資本主義社会では全く理解できないかもしれません。何でお金持ってきて“ありがとう”の一言もないんだろう、と思うのが普通です。でも、その“当たり前”という感覚を一回ご破算にして、この布施ということを考えると、見えてくるものがあります。例えば「だから“御布施は決まりがないのか”」とかね。読経料でも、御礼でもなく、布施をして利があるのは仏教的に見て本来は、僧侶ではなく施主そのものだからです。
こう考えると、布施は読経料ではないのですから、僧侶が「ありがとう」というのも教義的にはおかしいのです。ちなみに私は「お納めさせて頂きます」と言っていますが。
今日は思わず長文になってしまいました。最後までお読み頂き、ありがとうございました。
2012年02月24日
自慢の自慢の
こんばんは。
雨が降ったり、急に気温が上がったり、春の前触れですね。まさに「雨水」(二十四節気)ですね。
「雨水」で思い出しましたが、ウチのお檀家さんが日本料理アカデミー主催の全国料理人コンクールで準優勝されました!!!すごい!どすごい!!地方新聞や中日新聞の県内版にも載っていましたね。
ご存じの方も多いでしょう。駅前にある「むぎとろ」の黒柳さんです。ホントにおめでとうございます
で、この「雨水」というタイトル(ちょうど決勝戦の日が“雨水”だった)を据えてのお料理だったそう。

さて私事ですが、ここ数日は葬儀に奔走し、また春のお彼岸の案内状を作るためにパソコンにかじりつき、まったく余力なく過ごしていました。ちょうど一息つきました。一週間弱空いてしまったんですね。楽しみにされてたかた、ごめんなさい。
あ、そうそう、西光寺が誇る(?)お檀家さんネタをもう一つ。
超絶カレーを通販のみで作られている福井さんが、サンドウィッチマンのラジオ番組にとどまらず、様々なメディアで紹介されています。福井さんから、最新の掲載についてメールをいただきましたので、ご紹介させて頂きます。
「河北新報」
http://flat.kahoku.co.jp/u/volunteer16/6lYAp3B59JfeF2grhoEI/
この方の文章がちょっとおもしろいので、こっそり転載します。
*************
(フクイのカレー 辛口について)
辛口カレーは、最も話題となりました。ある人は「あまりに辛く、人生で初めてカレーを飲む経験をした」と語り、またある人は「まだまだですよ、あの辛さ(笑)」と豪語しました。私にとって、あの味は、ど真ん中ストライクの辛口でした。
(中略)
つぶつぶに細かく砕かれた香辛料そのものが、味わう前に襲い来る辛さを予感させ、その通りにじわじわと口と喉に刺激を与えてくれます。
これは素晴らしいボディーブローを叩き込まれて、痛みと同時に相手を賞賛したくなる衝動を抑えきれない感覚と似ているかもしれません。作り手は元プロボクサーの福井英史氏。「さすが!」。あったこともない名シェフに、思わず拍手喝さいです。煮込まれたチキンは、辛さを邪魔せずあっさりとした味を与えています。
**********
フクイのカレーは本当においしいです。どうおいしいかと言えば、とにかく“味の凝縮度が半端ない!”ことと、“家庭の味を究極化してる”ことです。良い意味で、どんな方のお口にも合うんですね。でもそうかといって、食べやすいだけじゃない。奥深さがあるんです。
(前も書いたけど、大事なことなので再掲↓)
福井さんは、昨年の大震災発生直後より積極的な支援活動を展開され、現在でもなお様々な活動を通し、被災地に支援をされています。まったく「身を粉にする」という表現がピッタリくるほど、妥協がなく真っ直ぐに支援をされています。本当に頭が下がる。
被災地の食材をふんだんに使用してカレーを作られているので、このカレーを購入されることでも支援になります。ご興味のある方は、是非一度お電話を!!!(オーダーは電話のみです)
フクイのカレー(福井さん)電話:0532-61-4269
PS・・・ステマじゃなくて、ホントに美味しいんですって!!Believe me !
雨が降ったり、急に気温が上がったり、春の前触れですね。まさに「雨水」(二十四節気)ですね。
「雨水」で思い出しましたが、ウチのお檀家さんが日本料理アカデミー主催の全国料理人コンクールで準優勝されました!!!すごい!どすごい!!地方新聞や中日新聞の県内版にも載っていましたね。
ご存じの方も多いでしょう。駅前にある「むぎとろ」の黒柳さんです。ホントにおめでとうございます

で、この「雨水」というタイトル(ちょうど決勝戦の日が“雨水”だった)を据えてのお料理だったそう。

さて私事ですが、ここ数日は葬儀に奔走し、また春のお彼岸の案内状を作るためにパソコンにかじりつき、まったく余力なく過ごしていました。ちょうど一息つきました。一週間弱空いてしまったんですね。楽しみにされてたかた、ごめんなさい。
あ、そうそう、西光寺が誇る(?)お檀家さんネタをもう一つ。
超絶カレーを通販のみで作られている福井さんが、サンドウィッチマンのラジオ番組にとどまらず、様々なメディアで紹介されています。福井さんから、最新の掲載についてメールをいただきましたので、ご紹介させて頂きます。
「河北新報」
http://flat.kahoku.co.jp/u/volunteer16/6lYAp3B59JfeF2grhoEI/
この方の文章がちょっとおもしろいので、こっそり転載します。
*************
(フクイのカレー 辛口について)
辛口カレーは、最も話題となりました。ある人は「あまりに辛く、人生で初めてカレーを飲む経験をした」と語り、またある人は「まだまだですよ、あの辛さ(笑)」と豪語しました。私にとって、あの味は、ど真ん中ストライクの辛口でした。
(中略)
つぶつぶに細かく砕かれた香辛料そのものが、味わう前に襲い来る辛さを予感させ、その通りにじわじわと口と喉に刺激を与えてくれます。
これは素晴らしいボディーブローを叩き込まれて、痛みと同時に相手を賞賛したくなる衝動を抑えきれない感覚と似ているかもしれません。作り手は元プロボクサーの福井英史氏。「さすが!」。あったこともない名シェフに、思わず拍手喝さいです。煮込まれたチキンは、辛さを邪魔せずあっさりとした味を与えています。
**********
フクイのカレーは本当においしいです。どうおいしいかと言えば、とにかく“味の凝縮度が半端ない!”ことと、“家庭の味を究極化してる”ことです。良い意味で、どんな方のお口にも合うんですね。でもそうかといって、食べやすいだけじゃない。奥深さがあるんです。
(前も書いたけど、大事なことなので再掲↓)
福井さんは、昨年の大震災発生直後より積極的な支援活動を展開され、現在でもなお様々な活動を通し、被災地に支援をされています。まったく「身を粉にする」という表現がピッタリくるほど、妥協がなく真っ直ぐに支援をされています。本当に頭が下がる。
被災地の食材をふんだんに使用してカレーを作られているので、このカレーを購入されることでも支援になります。ご興味のある方は、是非一度お電話を!!!(オーダーは電話のみです)
フクイのカレー(福井さん)電話:0532-61-4269
PS・・・ステマじゃなくて、ホントに美味しいんですって!!Believe me !
2012年02月05日
ご厚意の茵に抱かれて
昨日は西光寺の恒例行事、大般若祈祷会(だいはんにゃきとうえ)がありました。
これは檀家さまの一年の無事・家内安全を祈る法要で、多くのお寺は正月に行っているもの。伝統的には、今から1300年ほど前から宮中で始められたとされています。西光寺は毎年、立春(2月4日)に行います。
「大般若」とは、西遊記でおなじみ、三蔵法師(この方のモデルと言われているのが実在の僧侶“玄奘”げんじょう、という名です)がインドから中国に持ち帰り、翻訳した600巻もあるお経のことです。
ちなみに三蔵(さんぞう)とは、本来、「経」・「律」・「論」の3つの事柄を指し、それぞれ“ブッダの教え”、“教団のルールブック”“ブッダの教えの注釈”なのですが、これら3つに精通した僧侶を尊敬の念をこめて“三蔵”と言います。尊称ですね。

さて、前日までとてつもなく寒かったので(当日もストーブをつけに本堂へ行ったら5℃だった)、果たして檀家さんはお越しいただけるのか?と内心心配していましたが、結果的に200名を超えるお檀家さんにお越しいただき、無事におつとめできました。
実は今日書きたかったことは、無事におつとめできたことでも、大般若祈祷の解説でもありません。
今日書きたかったのは、護持会役員さんのご厚意が身にしみるほど有り難かったこと。
この法要にあたり、役員さん数名の方より、事前にお電話をいただき「何か手伝えることはない?」とご連絡頂きました。この自発的な善意が本当にありがたく、うれしかった。
そして当日、多くの役員さんたちが受付や、甘酒(法要後に檀家さんに振る舞う)の準備や接待・片づけを手伝ってくださいました。
・・・この文章だけでは、ごく普通のことに聞こえるかもしれません。私が感激した理由が分からないでしょう。ちょっと回りくどいですが、聞いてください。
護持会(ごじかい)というのは、何度も書いているとおり、檀家さん全員でお寺を守り、維持していく会のことで、西光寺では現在26名の役員さんがいらっしゃいます。正直、昨年まで、まったく活動をしていなかった。
昨年末に12名の方に新たに役員さんになっていただきました。
当初、新役員さん方には「年に数回の会議に出席してください」とお願いをしました。
それはつまり、現状の護持会は、それ以外にはやることがなかったのです。唯一の役務は法要の受付なのですが、これも従来、同じメンバーがやってくださっていました。
では何故、別に増やさなくてもよさそうな護持会役員をこの時期に増員したかと言えば、これからのために、です。
これから、大本山の旅行や、写経会や落語会・お経を読む会などの行事を企画し、実施にご協力頂こうと思っての増員でした。
しかし、とはいうものの、今までずっと活動休止状態の護持会。
役員さんたちはもちろん、私の中でも、何をどのようにしていったらいいのか、不安な面もかなりあった。だからいきおい慎重にならざるを得ず、手探りで行事を企画し、まずは年に1~3個の護持会企画を実施していけたら、くらいのヴィジョンでありました。それで、これから2年くらいかけて徐々に活動のテンポを上げていけたら、と思っていました。(それにいきなりアクセル全開!!では、ついていく檀家さんは当然のこと、自分も一度広げた大風呂敷をしまうのが大変・・・)
と言うわけで、当面は新役員さんたちにも受付業務をちょっとずつお願いしようか、くらいにのんびり思っていた矢先に、新役員さんたちからのお電話。だから、その善意がめちゃくちゃ嬉しかった。法要の準備や片づけからくる疲れも吹き飛ぶような、心のあたたかさを感じました。
ただ、逆に言えば、役員さんたちには申し訳ないことをした、と猛省もしています。
もっとちゃんと「受け入れ態勢」をきちんとしておくべきだった。せっかくの役員さんたちのご厚意に応えられなかった。控え室の確保、輪袈裟(わげさ・・・信徒が着けるお袈裟のようなもの)の準備、流れの説明、お茶すら差し上げられなかった・・・これは大反省。
でも、今回の失敗を活かし、次回へ。役員さんたちのご厚意が、私を奮い立たせてくれた気がします。なんだかやる気がメラメラ湧いてきた!よ~し、今年はがんばるぞ!
***オマケ***
昨日の法要。ウチの子、法要に参列した私と同じ年代の若手僧侶にむかって「パパ!パパ!」と言いながらくっついてった。しかも2人・・・。パパが3人もいるってこと???誰でもいいのだろうか(笑)
これは檀家さまの一年の無事・家内安全を祈る法要で、多くのお寺は正月に行っているもの。伝統的には、今から1300年ほど前から宮中で始められたとされています。西光寺は毎年、立春(2月4日)に行います。
「大般若」とは、西遊記でおなじみ、三蔵法師(この方のモデルと言われているのが実在の僧侶“玄奘”げんじょう、という名です)がインドから中国に持ち帰り、翻訳した600巻もあるお経のことです。
ちなみに三蔵(さんぞう)とは、本来、「経」・「律」・「論」の3つの事柄を指し、それぞれ“ブッダの教え”、“教団のルールブック”“ブッダの教えの注釈”なのですが、これら3つに精通した僧侶を尊敬の念をこめて“三蔵”と言います。尊称ですね。

さて、前日までとてつもなく寒かったので(当日もストーブをつけに本堂へ行ったら5℃だった)、果たして檀家さんはお越しいただけるのか?と内心心配していましたが、結果的に200名を超えるお檀家さんにお越しいただき、無事におつとめできました。
実は今日書きたかったことは、無事におつとめできたことでも、大般若祈祷の解説でもありません。
今日書きたかったのは、護持会役員さんのご厚意が身にしみるほど有り難かったこと。
この法要にあたり、役員さん数名の方より、事前にお電話をいただき「何か手伝えることはない?」とご連絡頂きました。この自発的な善意が本当にありがたく、うれしかった。
そして当日、多くの役員さんたちが受付や、甘酒(法要後に檀家さんに振る舞う)の準備や接待・片づけを手伝ってくださいました。
・・・この文章だけでは、ごく普通のことに聞こえるかもしれません。私が感激した理由が分からないでしょう。ちょっと回りくどいですが、聞いてください。
護持会(ごじかい)というのは、何度も書いているとおり、檀家さん全員でお寺を守り、維持していく会のことで、西光寺では現在26名の役員さんがいらっしゃいます。正直、昨年まで、まったく活動をしていなかった。
昨年末に12名の方に新たに役員さんになっていただきました。
当初、新役員さん方には「年に数回の会議に出席してください」とお願いをしました。
それはつまり、現状の護持会は、それ以外にはやることがなかったのです。唯一の役務は法要の受付なのですが、これも従来、同じメンバーがやってくださっていました。
では何故、別に増やさなくてもよさそうな護持会役員をこの時期に増員したかと言えば、これからのために、です。
これから、大本山の旅行や、写経会や落語会・お経を読む会などの行事を企画し、実施にご協力頂こうと思っての増員でした。
しかし、とはいうものの、今までずっと活動休止状態の護持会。
役員さんたちはもちろん、私の中でも、何をどのようにしていったらいいのか、不安な面もかなりあった。だからいきおい慎重にならざるを得ず、手探りで行事を企画し、まずは年に1~3個の護持会企画を実施していけたら、くらいのヴィジョンでありました。それで、これから2年くらいかけて徐々に活動のテンポを上げていけたら、と思っていました。(それにいきなりアクセル全開!!では、ついていく檀家さんは当然のこと、自分も一度広げた大風呂敷をしまうのが大変・・・)
と言うわけで、当面は新役員さんたちにも受付業務をちょっとずつお願いしようか、くらいにのんびり思っていた矢先に、新役員さんたちからのお電話。だから、その善意がめちゃくちゃ嬉しかった。法要の準備や片づけからくる疲れも吹き飛ぶような、心のあたたかさを感じました。
ただ、逆に言えば、役員さんたちには申し訳ないことをした、と猛省もしています。
もっとちゃんと「受け入れ態勢」をきちんとしておくべきだった。せっかくの役員さんたちのご厚意に応えられなかった。控え室の確保、輪袈裟(わげさ・・・信徒が着けるお袈裟のようなもの)の準備、流れの説明、お茶すら差し上げられなかった・・・これは大反省。
でも、今回の失敗を活かし、次回へ。役員さんたちのご厚意が、私を奮い立たせてくれた気がします。なんだかやる気がメラメラ湧いてきた!よ~し、今年はがんばるぞ!
***オマケ***
昨日の法要。ウチの子、法要に参列した私と同じ年代の若手僧侶にむかって「パパ!パパ!」と言いながらくっついてった。しかも2人・・・。パパが3人もいるってこと???誰でもいいのだろうか(笑)
2012年01月11日
僧侶の本分・本懐 -1-
(前回からの続きです。)
役員会のあと、珍しく神経が高ぶっていたようで、寝付けなかった、というお話です。その時考えていたことについて。
新しく護持会役員を承諾してくださった方には、本当に感謝しています。
そして、有名無実のままの状態でずっと待ってくださっていた旧来の役員さんには、それ以上に感謝しています。
だから、もっともっと努力してうまくこの護持会を機能させたいと切実に思います。
しかし、同時に思うこともあるのです。ここから結構重要ですが、はっきり言って、「今やっていることは、言ってみれば組織の立ち上げであって、これは僧侶の本分なのかな?」、と自問自答しないでもないのです。
「おいおい、なんだそりゃ。じゃあ、やってもらっている方に失礼だろ」と思われるかもしれません。確かにそうなのですが、ちょっとそんなに単細胞な話ではありません。
私が思う護持会の在り方は、現在こそ僧侶中心・先導でやっていますが、ゆくゆくはもう少し護持会役員主導で動いて頂きたいと思うのです。
つまり、今は黎明期でありますので、そこは住職なり私なりが微力ながらお手伝いをさせていただいて、規約を決めたり、活動内容をサジェストしたりとしていますが、最終的にはもう少し独立性のある、つまりは互いに僧侶として、或いは在家(一般の方)としての立場にのっとって、うまいバランスをとりながら会がまわっていくと良いな、と思っているのです。
僧侶-護持会役員-一般檀家というトップダウンではなく、もう少し三権分立的と申しましょうか、それぞれが上手く調和しているような組織、これが理想かなと思っています。
何故そう思うのかというと、やはり「僧侶の本分」とは何か、ということを考えさせられるから。もっと言えば、最近とみに己の仏教の不勉強さを恥じることが多いからです。
”僧侶の本分”という書き方をしましたが、これについて皆さん誤解されている。
つまり、ごく一般的なイメージ(事実ではなく“イメージ”)として、僧侶は「葬式と法事をする人」に終始しています。「坊さんって葬式と法事をすることが仕事でしょ?」と思っていませんか?
それはあくまで一面に過ぎません。
すべての基本は、仏道を行じること。即ち、仏教を学び、実践し(修行し)、わが曹洞宗においては行持道環(発心・修行・菩提・涅槃)が回り続けることこそが、出家者の意義であり、僧侶の本分だと強く思っています。
その過程で、僧侶としての「慈悲心」(=他者への思いやりの心)が基盤となって葬祭行事を行うべきなのです。
もっと分かりやすく言えば、何で坊さんが葬式をやっているのかといえば、「悲しんでいる人をほってはおけないから」です。他人の悲しみを少しでも和らげたい、故人に安らかに眠って欲しい、その気持ちが僧侶をして葬儀をさせしめている。これが全てのはじまりです。
役員会のあと、珍しく神経が高ぶっていたようで、寝付けなかった、というお話です。その時考えていたことについて。
新しく護持会役員を承諾してくださった方には、本当に感謝しています。
そして、有名無実のままの状態でずっと待ってくださっていた旧来の役員さんには、それ以上に感謝しています。
だから、もっともっと努力してうまくこの護持会を機能させたいと切実に思います。
しかし、同時に思うこともあるのです。ここから結構重要ですが、はっきり言って、「今やっていることは、言ってみれば組織の立ち上げであって、これは僧侶の本分なのかな?」、と自問自答しないでもないのです。
「おいおい、なんだそりゃ。じゃあ、やってもらっている方に失礼だろ」と思われるかもしれません。確かにそうなのですが、ちょっとそんなに単細胞な話ではありません。
私が思う護持会の在り方は、現在こそ僧侶中心・先導でやっていますが、ゆくゆくはもう少し護持会役員主導で動いて頂きたいと思うのです。
つまり、今は黎明期でありますので、そこは住職なり私なりが微力ながらお手伝いをさせていただいて、規約を決めたり、活動内容をサジェストしたりとしていますが、最終的にはもう少し独立性のある、つまりは互いに僧侶として、或いは在家(一般の方)としての立場にのっとって、うまいバランスをとりながら会がまわっていくと良いな、と思っているのです。
僧侶-護持会役員-一般檀家というトップダウンではなく、もう少し三権分立的と申しましょうか、それぞれが上手く調和しているような組織、これが理想かなと思っています。
何故そう思うのかというと、やはり「僧侶の本分」とは何か、ということを考えさせられるから。もっと言えば、最近とみに己の仏教の不勉強さを恥じることが多いからです。
”僧侶の本分”という書き方をしましたが、これについて皆さん誤解されている。
つまり、ごく一般的なイメージ(事実ではなく“イメージ”)として、僧侶は「葬式と法事をする人」に終始しています。「坊さんって葬式と法事をすることが仕事でしょ?」と思っていませんか?
それはあくまで一面に過ぎません。
すべての基本は、仏道を行じること。即ち、仏教を学び、実践し(修行し)、わが曹洞宗においては行持道環(発心・修行・菩提・涅槃)が回り続けることこそが、出家者の意義であり、僧侶の本分だと強く思っています。
その過程で、僧侶としての「慈悲心」(=他者への思いやりの心)が基盤となって葬祭行事を行うべきなのです。
もっと分かりやすく言えば、何で坊さんが葬式をやっているのかといえば、「悲しんでいる人をほってはおけないから」です。他人の悲しみを少しでも和らげたい、故人に安らかに眠って欲しい、その気持ちが僧侶をして葬儀をさせしめている。これが全てのはじまりです。
2012年01月10日
「お寺」と「野球」
昨日の拙記事、『生きている人のためのお寺へ』にコメントを頂戴しました。ありがとうございます。
「野球とお寺の比喩、どんなものだか気になります」と言うことで、折角なので、恥ずかしながらその資料を抜粋・補足して掲載します。
呉々も申し上げますが、これはあくまで「たとえ話」に過ぎません。そもそも比較する対象が異なっているために、上手く説明することもできません。
ですから、簡単なイメージとしてお読み頂ければ幸いです。
それから、この資料は西光寺の護持会役員さんにお配りしたものですから、他のお寺に通用するわけではないですし、そう言う意味では何ら普遍性があるわけではないのです。悪しからずご了承下さい。
ついでにもう一つ。これは護持会の話なので、言うなればあんまり仏教の教義とは関係ありません。とどのつまり「組織論」であります。
長い言い訳になりましたが、ここを読み間違えられてしまうと、まったく筋が通らなくなるので・・・蛇足でした。
**********(資料抜粋)************
(1)「護持会」とは・・・
檀家(檀信徒)同士が協力して、先祖が眠る場所・仏教の拠り所としてのお寺を守り(=「護」)、建物を保守・維持(=「持」)していく会のこと。
(2)「護持会役員」の役割は・・・
一般檀家と僧侶(お寺)との橋渡し役として、お寺をより深く理解し、僧侶と協力して法要・行事などを実施・補助する。また檀家の先頭に立って、よりよいお寺にするべく、中心となって活動する。
(お寺により名称が異なるが、いわゆる「総代」「世話役」「世話人」と呼ばれる役)
*「野球」と「お寺」の対比イメージ*
スポーツ< >宗教
野球< >仏教
球団< >お寺
球場(ホーム)< >お寺(建物)
監督< >住職
選手< >僧侶(含 住職)
試合< >法要
練習< >修行
慈善事業・ファンイベント< >護持会行事
ファンクラブ役員< >護持会役員
ファン< >檀家(護持会)
●野球選手・・・練習をして、試合をする(勝利する)ことが本分。
◆野球ファン・・・試合やファンイベントへ足を運び、野球や選手に親しみ、球団はその入場料などで球団(スタジアムの保守や選手の年俸)を存続していく。
●僧侶・・・仏教を学び、修行をし(仏道を行じること)、その上で檀信徒に対して法要・布教をすることが本分。
◆護持会(檀家)・・・法要や護持会行事へ参加し、仏教やお寺について深く理解して、信心を深め、お寺は檀家よりの布施(寄附)によって仏教、お寺を存続させていく。
(3)現在のお寺の問題点
***野球になぞらえると***
・勝つための試合をひたすらするだけ(監督や勝利投手などのインタビューもなし、野球中継やキャンプ情報、宣伝もしない→ファンは選手や監督の素顔、本音、素性を知り得ない)
・ファンイベント(=プロの選手に触れあえる機会・・・少年野球教室など)や試合外の活動(慈善事業・学校などへの講演)を一切しない
=ファンと球団との接点が少なく、試合のみの姿しか見えない。マスコミによる偏った報道により、ファンが本当の野球・球団・選手の姿・形を見ることがなく偏見を持っている。真の野球の魅力を感じることができない。
**********************
というのが、「お寺と野球」の比喩です。
いかがでしたか?イメージしづらいですよね。会議の時は私は一人で喋りまくっていたので、もう少し解りやすかったかもしれません。
実はこの役員会議が終わった晩、何となく神経が高ぶっていたのか珍しく寝付けませんでした。思うがままに、よしなしごとを考えていました。
(次回の記事に続きます)
「野球とお寺の比喩、どんなものだか気になります」と言うことで、折角なので、恥ずかしながらその資料を抜粋・補足して掲載します。
呉々も申し上げますが、これはあくまで「たとえ話」に過ぎません。そもそも比較する対象が異なっているために、上手く説明することもできません。
ですから、簡単なイメージとしてお読み頂ければ幸いです。
それから、この資料は西光寺の護持会役員さんにお配りしたものですから、他のお寺に通用するわけではないですし、そう言う意味では何ら普遍性があるわけではないのです。悪しからずご了承下さい。
ついでにもう一つ。これは護持会の話なので、言うなればあんまり仏教の教義とは関係ありません。とどのつまり「組織論」であります。
長い言い訳になりましたが、ここを読み間違えられてしまうと、まったく筋が通らなくなるので・・・蛇足でした。
**********(資料抜粋)************
(1)「護持会」とは・・・
檀家(檀信徒)同士が協力して、先祖が眠る場所・仏教の拠り所としてのお寺を守り(=「護」)、建物を保守・維持(=「持」)していく会のこと。
(2)「護持会役員」の役割は・・・
一般檀家と僧侶(お寺)との橋渡し役として、お寺をより深く理解し、僧侶と協力して法要・行事などを実施・補助する。また檀家の先頭に立って、よりよいお寺にするべく、中心となって活動する。
(お寺により名称が異なるが、いわゆる「総代」「世話役」「世話人」と呼ばれる役)
*「野球」と「お寺」の対比イメージ*
スポーツ< >宗教
野球< >仏教
球団< >お寺
球場(ホーム)< >お寺(建物)
監督< >住職
選手< >僧侶(含 住職)
試合< >法要
練習< >修行
慈善事業・ファンイベント< >護持会行事
ファンクラブ役員< >護持会役員
ファン< >檀家(護持会)
●野球選手・・・練習をして、試合をする(勝利する)ことが本分。
◆野球ファン・・・試合やファンイベントへ足を運び、野球や選手に親しみ、球団はその入場料などで球団(スタジアムの保守や選手の年俸)を存続していく。
●僧侶・・・仏教を学び、修行をし(仏道を行じること)、その上で檀信徒に対して法要・布教をすることが本分。
◆護持会(檀家)・・・法要や護持会行事へ参加し、仏教やお寺について深く理解して、信心を深め、お寺は檀家よりの布施(寄附)によって仏教、お寺を存続させていく。
(3)現在のお寺の問題点
***野球になぞらえると***
・勝つための試合をひたすらするだけ(監督や勝利投手などのインタビューもなし、野球中継やキャンプ情報、宣伝もしない→ファンは選手や監督の素顔、本音、素性を知り得ない)
・ファンイベント(=プロの選手に触れあえる機会・・・少年野球教室など)や試合外の活動(慈善事業・学校などへの講演)を一切しない
=ファンと球団との接点が少なく、試合のみの姿しか見えない。マスコミによる偏った報道により、ファンが本当の野球・球団・選手の姿・形を見ることがなく偏見を持っている。真の野球の魅力を感じることができない。
**********************
というのが、「お寺と野球」の比喩です。
いかがでしたか?イメージしづらいですよね。会議の時は私は一人で喋りまくっていたので、もう少し解りやすかったかもしれません。
実はこの役員会議が終わった晩、何となく神経が高ぶっていたのか珍しく寝付けませんでした。思うがままに、よしなしごとを考えていました。
(次回の記事に続きます)
2012年01月08日
生きている人のためのお寺へ
お正月も終わり、早8日になりましたね。
昨日はみなさん、七草粥はお召し上がりになりましたか?私は今年もいただきました。
西光寺は毎年作っています。子どもの頃は本当に嫌で嫌で(笑)、“何でこんなものを”と内心思っておりましたが、永平寺での修行(基本毎朝玄米の粥)と、齢を重ねたことでか、おかゆが美味しく感じられるようになりました。
それにしても、お正月のご馳走で疲弊した胃腸、人によっては溜まった疲れもありましょうが、それらをそっと癒して、体をリセットする“七草粥”、いやはや先人の知恵というのは誠にありがたいものです。(特に今年は元旦からウィルスに感染されていたので、お粥が真に美味しかった。おかげさまで、体調は8割方回復です。ご心配をお掛け致しました。)
さて、昨日は“決戦は土曜日”でした。
え?金曜じゃなくて?
そう、ドリカムは金曜ですが、土曜日です。

昨夜は18時より西光寺の護持会役員会でした。しかも、新役員さんをお迎えして初の会議。私のこの会議に対する気合いの入りようといったら、ちょっとなかった。
それは何故か。
(あまり良いことではないので、書かない方が良いのかもしれませんが、)隠さず書けば、それは「開店休業状態」だった護持会役員会(簡単に言えば、総代会とか世話人会のようなもの)を、十数年ぶりに(もしかしたらもっとかもしれません)再興し、動き出したのが、まだ去年のこと。
役員も過去の名簿からすると半減(亡くなられているので)し、当然の如くその分、役員も年齢を重ねているわけで、まさに組織として息も絶え絶えだった去年。そこから、新役員候補を選考し、お願いに上がり、昨年末ついに当初の14名から26名に増員したのでした。
ですから、昨夜の会議はただ単に「新入役員さんをお迎えして」という以上に、「ここが護持会のリスタート・リユニオン」というべき、やや記念的会議でありました。
自分で云うのも何ですが、かなり時間をかけて資料を作り、わずかA4・3枚ですが、その限られた中に、自分の思いを込めました。
今回の資料はずばり、「護持会と護持会役員について」。護持会の意味や意義、役員の在り方について。
さらには、今後お寺をどうしていきたいのか、或いは現在、何が問題で、どのようにしたいのかを自分なりに考えて書いたつもりです。
分かりやすくするために、「お寺」を「プロ野球」になぞらえて資料を作りました。これは結構よくできた(笑)
もちろん、お寺と野球は並列で語れるものではないので、齟齬はありますが、分かりやすくするために敢えての「野球」です。結果、役員会が終わった後に、新役員さんの一人から「説明も資料もすごく分かりやすくて、よく理解できました」とのお言葉を頂戴しました。有り難いことです。
後で考えてみれば、40分間、一人でずっと語っていた・・・。それも自分の親以上の世代の方に・・・。昨日寝る時に、お布団の中で考えていたんですが、自分の人生で、こんな長い時間一人でしゃべっていたのは、初めてでした。
きっと、今まで思ってきたこと、考えていたことが、一気に溢れ出したのだと思います。それほど思いが強かったのかもしれません。そうじゃきゃ、とてもこんな時間、独演できない。(泰明は元々人前で一方的に話すのが好きではない)何かに突き動かされるような、デイドリームの40分でした。
誠に有り難いことに、新旧の役員さんは皆素晴らしい方ばかりで、加えて、お互いに顔見知りだったり、仕事でのつながりがあったりと、あちこちで「おお、あんたもいたのか」的な挨拶が飛び交っていました。狙ってやった訳ではない(基本的にお人柄で選んでいるので交友関係までは知らない)ので、うれしい誤算でした。
さて、ここまでは順風満帆。西光寺は檀家さんに恵まれてる!さあ、今年が勝負です!がんばります。
昨日はみなさん、七草粥はお召し上がりになりましたか?私は今年もいただきました。
西光寺は毎年作っています。子どもの頃は本当に嫌で嫌で(笑)、“何でこんなものを”と内心思っておりましたが、永平寺での修行(基本毎朝玄米の粥)と、齢を重ねたことでか、おかゆが美味しく感じられるようになりました。
それにしても、お正月のご馳走で疲弊した胃腸、人によっては溜まった疲れもありましょうが、それらをそっと癒して、体をリセットする“七草粥”、いやはや先人の知恵というのは誠にありがたいものです。(特に今年は元旦からウィルスに感染されていたので、お粥が真に美味しかった。おかげさまで、体調は8割方回復です。ご心配をお掛け致しました。)
さて、昨日は“決戦は土曜日”でした。
え?金曜じゃなくて?
そう、ドリカムは金曜ですが、土曜日です。
昨夜は18時より西光寺の護持会役員会でした。しかも、新役員さんをお迎えして初の会議。私のこの会議に対する気合いの入りようといったら、ちょっとなかった。
それは何故か。
(あまり良いことではないので、書かない方が良いのかもしれませんが、)隠さず書けば、それは「開店休業状態」だった護持会役員会(簡単に言えば、総代会とか世話人会のようなもの)を、十数年ぶりに(もしかしたらもっとかもしれません)再興し、動き出したのが、まだ去年のこと。
役員も過去の名簿からすると半減(亡くなられているので)し、当然の如くその分、役員も年齢を重ねているわけで、まさに組織として息も絶え絶えだった去年。そこから、新役員候補を選考し、お願いに上がり、昨年末ついに当初の14名から26名に増員したのでした。
ですから、昨夜の会議はただ単に「新入役員さんをお迎えして」という以上に、「ここが護持会のリスタート・リユニオン」というべき、やや記念的会議でありました。
自分で云うのも何ですが、かなり時間をかけて資料を作り、わずかA4・3枚ですが、その限られた中に、自分の思いを込めました。
今回の資料はずばり、「護持会と護持会役員について」。護持会の意味や意義、役員の在り方について。
さらには、今後お寺をどうしていきたいのか、或いは現在、何が問題で、どのようにしたいのかを自分なりに考えて書いたつもりです。
分かりやすくするために、「お寺」を「プロ野球」になぞらえて資料を作りました。これは結構よくできた(笑)
もちろん、お寺と野球は並列で語れるものではないので、齟齬はありますが、分かりやすくするために敢えての「野球」です。結果、役員会が終わった後に、新役員さんの一人から「説明も資料もすごく分かりやすくて、よく理解できました」とのお言葉を頂戴しました。有り難いことです。
後で考えてみれば、40分間、一人でずっと語っていた・・・。それも自分の親以上の世代の方に・・・。昨日寝る時に、お布団の中で考えていたんですが、自分の人生で、こんな長い時間一人でしゃべっていたのは、初めてでした。
きっと、今まで思ってきたこと、考えていたことが、一気に溢れ出したのだと思います。それほど思いが強かったのかもしれません。そうじゃきゃ、とてもこんな時間、独演できない。(泰明は元々人前で一方的に話すのが好きではない)何かに突き動かされるような、デイドリームの40分でした。
誠に有り難いことに、新旧の役員さんは皆素晴らしい方ばかりで、加えて、お互いに顔見知りだったり、仕事でのつながりがあったりと、あちこちで「おお、あんたもいたのか」的な挨拶が飛び交っていました。狙ってやった訳ではない(基本的にお人柄で選んでいるので交友関係までは知らない)ので、うれしい誤算でした。
さて、ここまでは順風満帆。西光寺は檀家さんに恵まれてる!さあ、今年が勝負です!がんばります。
タグ :七草粥