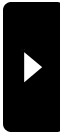2011年03月31日
〇〇が集まって話しをすると・・・
昨夜は永平寺の修行仲間の一人にお子さんがお生まれになったということで、ささやかな祝賀会をしました。私を含め、どすごいエリアから5人の僧侶が集まりました。お祝いはお祝いとして、素敵な会になったと思うのですが、実はそっちのけで(ゴメンナサイ)、別の話に花を咲かせました
率直に言って、「みんな悩んでいるんだな」ということ。
勿論、僧侶として、ということです。
同じ曹洞宗のそれも同年の、しかも同じ時に修行をした僧侶と言っても、現在の立場や置かれている境遇は千差万別。
大学の非常勤講師をしながら同時にお寺の法事に忙殺される僧侶。幼稚園を経営しつつお寺も維持していく僧侶。住職としての辞令を受けている者もいれば、そうでない者も(それだけでも全く立場や考え方が変わってくるような気がします)いるし、修行後に諸外国で布教に従事したものもいる。そして私のようにごく一般的な僧侶(笑)
切り口の違いはあれ、みな問題意識をもって、それぞれできることをやっている、というのが強く受けた印象でした。
特に今回の大震災に関しては、彼らが中心となって、石巻市まで送った物資を準備していたので、その時の話や、逆に全国曹洞宗青年会の役員である僧侶からは、全国規模で動くことの難しさ、とりわけ情報収集とその連絡方法、実際アクションを起こすまでの過程もチラリと聞き、支援も一様ではないし、一様にも出来ないという思いを新たにしたり。
後は、あれですかね・・・あんまり大っぴらに書けませんが(汗)・・・、教団や所属している会の批判というか・・・。まぁそれだけその会や団体に対して真剣に思っているからでしょうね。ただ、変えようと思っているんだったら、やっぱり痛みを伴ってもアクションを起こさないといけないのかな、とも感じました。ちょっと抽象的にしか書けなくてごめんなさい
と、いうことで、意外にも真面目な話に終始していたような会でした(笑)
「そうなの?」と驚かれるかもしれませんが、僧侶だってのうのうと暮らしているわけではありません。やはり自分の置かれている立場・境遇が如何なる具合においても、仏教を宣揚し、仏道を行じていくという芯(心、かも)は持ち続けるべきだし、それがなければ僧侶とは呼べないのかもしれません。そして、それがあるからこそ、また悩みもあるんでしょうね。
ともあれ、このような良き修行仲間が周りにいることを幸せに思います。有り難いことです。

率直に言って、「みんな悩んでいるんだな」ということ。
勿論、僧侶として、ということです。
同じ曹洞宗のそれも同年の、しかも同じ時に修行をした僧侶と言っても、現在の立場や置かれている境遇は千差万別。
大学の非常勤講師をしながら同時にお寺の法事に忙殺される僧侶。幼稚園を経営しつつお寺も維持していく僧侶。住職としての辞令を受けている者もいれば、そうでない者も(それだけでも全く立場や考え方が変わってくるような気がします)いるし、修行後に諸外国で布教に従事したものもいる。そして私のようにごく一般的な僧侶(笑)
切り口の違いはあれ、みな問題意識をもって、それぞれできることをやっている、というのが強く受けた印象でした。
特に今回の大震災に関しては、彼らが中心となって、石巻市まで送った物資を準備していたので、その時の話や、逆に全国曹洞宗青年会の役員である僧侶からは、全国規模で動くことの難しさ、とりわけ情報収集とその連絡方法、実際アクションを起こすまでの過程もチラリと聞き、支援も一様ではないし、一様にも出来ないという思いを新たにしたり。
後は、あれですかね・・・あんまり大っぴらに書けませんが(汗)・・・、教団や所属している会の批判というか・・・。まぁそれだけその会や団体に対して真剣に思っているからでしょうね。ただ、変えようと思っているんだったら、やっぱり痛みを伴ってもアクションを起こさないといけないのかな、とも感じました。ちょっと抽象的にしか書けなくてごめんなさい

と、いうことで、意外にも真面目な話に終始していたような会でした(笑)
「そうなの?」と驚かれるかもしれませんが、僧侶だってのうのうと暮らしているわけではありません。やはり自分の置かれている立場・境遇が如何なる具合においても、仏教を宣揚し、仏道を行じていくという芯(心、かも)は持ち続けるべきだし、それがなければ僧侶とは呼べないのかもしれません。そして、それがあるからこそ、また悩みもあるんでしょうね。
ともあれ、このような良き修行仲間が周りにいることを幸せに思います。有り難いことです。
2011年03月30日
カズはやっぱりキングだった
【時事ドットコム】
日本代表戦、視聴率22.5%
日本テレビが29日夜に放送したサッカー・日本代表-Jリーグ選抜(大阪・長居陸上競技場)の関東地区の平均視聴率は22.5%だった。この試合は、東日本大震災復興支援チャリティーマッチとして行われた。ビデオリサーチが30日、発表した。 (2011/03/30-12:58)
--------------------------------------------------------------------------------

昨日のサッカーご覧になりました?どすごいメンバーでしたね。特に前半。そしてカズ。あそこで点を決めるなんて・・・そしてカズダンス。ホントに涙腺緩みっぱなしでした。やっぱりキングですね。
何が良かったってメンバーもさることながら、その妥協なきプレー。
チャリティーという言葉が持つ、ある種の”ゆる~い慈善的”な(悪い意味ではありません)側面は微塵もなく、雌雄を決すると言いましょうか、とにかくオマケ的な変なプレーがなくて、いっそう感動しました。
真剣に、ひたむきにプレーすることこそが、サッカー選手にできる最高の支援だ、と確か遠藤選手も言ってましたが、その通りだと思います。その姿に感動し、その姿を見た我々が思いを新たにする。もちろん被災者の方々も元気づけられたことと思います。
個人的には遠藤選手が良かったですね。FKもさることながら、足もとまで相手を引き付けておいてフワッとボールを蹴り上げてかわした個人技にはぞくぞくしました。素晴らしかった。あとは小笠原選手の表情ですかね。何かを背負い、秘めた表情でプレーも鬼気迫るものがあったし。
最後に試合後のストイコビッチ監督の言葉です。
「忘れないでほしい、被災者の皆さん、あなた方は一人で歩んでいるんじゃない、我々がいることを」(英語だったので、もしかしたら違っているかも・・・)
日本代表戦、視聴率22.5%
日本テレビが29日夜に放送したサッカー・日本代表-Jリーグ選抜(大阪・長居陸上競技場)の関東地区の平均視聴率は22.5%だった。この試合は、東日本大震災復興支援チャリティーマッチとして行われた。ビデオリサーチが30日、発表した。 (2011/03/30-12:58)
--------------------------------------------------------------------------------

昨日のサッカーご覧になりました?どすごいメンバーでしたね。特に前半。そしてカズ。あそこで点を決めるなんて・・・そしてカズダンス。ホントに涙腺緩みっぱなしでした。やっぱりキングですね。
何が良かったってメンバーもさることながら、その妥協なきプレー。
チャリティーという言葉が持つ、ある種の”ゆる~い慈善的”な(悪い意味ではありません)側面は微塵もなく、雌雄を決すると言いましょうか、とにかくオマケ的な変なプレーがなくて、いっそう感動しました。
真剣に、ひたむきにプレーすることこそが、サッカー選手にできる最高の支援だ、と確か遠藤選手も言ってましたが、その通りだと思います。その姿に感動し、その姿を見た我々が思いを新たにする。もちろん被災者の方々も元気づけられたことと思います。
個人的には遠藤選手が良かったですね。FKもさることながら、足もとまで相手を引き付けておいてフワッとボールを蹴り上げてかわした個人技にはぞくぞくしました。素晴らしかった。あとは小笠原選手の表情ですかね。何かを背負い、秘めた表情でプレーも鬼気迫るものがあったし。
最後に試合後のストイコビッチ監督の言葉です。
「忘れないでほしい、被災者の皆さん、あなた方は一人で歩んでいるんじゃない、我々がいることを」(英語だったので、もしかしたら違っているかも・・・)
2011年03月29日
豊川閣妙厳寺開山忌逮夜随喜
漢字ばっかり並んでる・・・(笑)
日本語に直しますと”豊川閣妙厳寺(豊川稲荷)を開かれた初代住職のご命日に際し、前晩の供養(=お通夜みたいなもの)に参加してきました”ということです。
開山忌(かいさんき)というのはどこのお寺にもあるもので、初代住職様のご命日には特別な法要をします。大きなお寺などは逮夜(たいや、と読みます)と言って、前日の夕方にも法要をします。
ということで、行って参りました豊川稲荷!
前職場にも顔をだし・・・

法要は50名を超える僧侶で荘厳な雰囲気の中、粛々と行われました。とてもいい法要でした。儀式を型通りに行うという事が、どういうものなのか、久々にそれを感じることができた逮夜でした。
そして待ってました精進料理!(ってこれが目的かいっ、って突っ込まれそうですが…)豪華な精進料理です。これにおうどんが付きました。

豊川稲荷の精進料理ってもう何度も何度もいただいていますが、私は大好きです。味付けもしっかりしてあるし、ヴォリュームも満点。
フランス料理に例えると、永平寺のはクラシック、総持寺のはヌーヴェルキュイジーヌ、豊川稲荷のはビストロ、・・・って例えになっていないですね(汗)
豊川稲荷さんは、お寺の雰囲気やご祈祷の有り難さもさることながら、この精進料理、ホントにおいしいんです!皆さんも機会があれば是非お出かけください!!
日本語に直しますと”豊川閣妙厳寺(豊川稲荷)を開かれた初代住職のご命日に際し、前晩の供養(=お通夜みたいなもの)に参加してきました”ということです。
開山忌(かいさんき)というのはどこのお寺にもあるもので、初代住職様のご命日には特別な法要をします。大きなお寺などは逮夜(たいや、と読みます)と言って、前日の夕方にも法要をします。
ということで、行って参りました豊川稲荷!
前職場にも顔をだし・・・

法要は50名を超える僧侶で荘厳な雰囲気の中、粛々と行われました。とてもいい法要でした。儀式を型通りに行うという事が、どういうものなのか、久々にそれを感じることができた逮夜でした。
そして待ってました精進料理!(ってこれが目的かいっ、って突っ込まれそうですが…)豪華な精進料理です。これにおうどんが付きました。

豊川稲荷の精進料理ってもう何度も何度もいただいていますが、私は大好きです。味付けもしっかりしてあるし、ヴォリュームも満点。
フランス料理に例えると、永平寺のはクラシック、総持寺のはヌーヴェルキュイジーヌ、豊川稲荷のはビストロ、・・・って例えになっていないですね(汗)
豊川稲荷さんは、お寺の雰囲気やご祈祷の有り難さもさることながら、この精進料理、ホントにおいしいんです!皆さんも機会があれば是非お出かけください!!
2011年03月28日
There is no one like you.
今、facebookやっていたら、友達の投稿でこんなブログがあるのを知りました。
http://blog.goo.ne.jp/flower-wing
一気に全部読んでしまいました。何も言えませんが、とにかく必読です。
http://blog.goo.ne.jp/flower-wing
一気に全部読んでしまいました。何も言えませんが、とにかく必読です。
2011年03月27日
結構致命的な、ホントは隠したい私の弱点
泰明の苦手なもの・・・それは「法話」
坊さんなのに・・・
実は私は「法話」というものが苦手です・・・。
「法話」というのは要するに、仏教をからめて僧侶がするお話のことなんですが、自分自身が”有り難くない僧侶”(笑)だからか、どうにもこういう”ありがたい話”ってのが苦手で・・・。何か”お涙ちょうだいモノのドラマ”、みたいに感じちゃうんですよね。あ~~こんなこと書いたら偉大なるご先輩方に怒られるんだろうなぁ・・・。すみません、不謹慎で。
でも、一般の方にとっては、この”ありがたい話”こそ、僧侶に対するニーズってのも分かるんです。
何でこんなことを書いているかというと、昨日、葬儀を終えたばかりの檀家さんがお寺に来られました。四十九日(忌明け)の日程などを話して、その後で”中陰”(ちゅういん)の話になりました。「”中陰”というのは何か?」というのは難しい問題ですが、今はごく単純に”亡くなってから四十九日までの間”とご理解ください。
そこで檀家さんとしばらく話をさせてもらったのですが、つくづく自分は”1対1のトークが気楽にできるタイプ”だ、と気づきました。(自分で言うのも何ですが・・・)
どういう事かと言いますと、最初にお檀家さんが「四十九日って閻魔様の裁きを受ける日ですよね?」と聞いてこられたことで、”中陰”の会話がスタート。
もしこれが普通の僧侶なら、中陰についてきちんと勉強してますから、たぶん、学術的な説明(四有とか含め十王思想など)をしたり、或いは逆に「地獄ってのはこういうもので・・・云々」すると思うんですが、私の場合、どうしても知識が浅いというのも手伝って、一方的に滔々と自説を開陳することが出来ず、コール&レスポンス的トークになってしまいます。つまり、この場合、相手がどういう事象を信じているのか、どういうことを知りたくて、どういう事柄までを理解しているのかを、相手の表情や素振りを無意識に判断して話していると思うのです。かっこよく言えば、「相手に合わせて」話しているのでしょうが、たぶん、私の力不足がそうさせているのだと思います(笑)
前にも拙ブログで『魂ってあるの?ないの?』という記事を書きましたが、これなんかもそうで、結局、”ある”と信じている檀家さんにはそれ様に、”ない”と信じている檀家さんにもそれ様に話を変えると思うのです。このように書くと、すごく不誠実な感じがしますが、でも実際その存在の有無を議論しても意味がないというか、そこに本当の仏教があるとはどうしても私には思えないのです。つまり、これは実証実験でもなんでもなく、ただ単に信仰の問題なので、日常生活を送る上で度が過ぎてなければ、或いは他者に目に見えて被害をあたえていなければ”あってもなくても”どっちだっていい訳です。
話が飛びました・・・。今回は2人での会話ですが、もちろん、こうしたシチュエーションでも「法話」とは呼べます。ただ、普通「法話」と言った場合、檀家さん大勢の前でする話を指していて、(当たり前かもしれませんが)ほとんどの僧侶はそれができると思うんです。でも私は苦手。苦手というより敬遠しているというか。で、何でそうなんだろう?と自分で分析してみました。思い当たる節は3つ。
1.最大公約数的な話をしてしまう
・・・仏教の特色って、前にも書きましたが「対機説法」です。対機説法というのは、相手の立場に合わせて話の内容をコントロールして、順々に高度な思想を語っていくというブッダ以来の伝統的スタイルなんですが、逆に一般的な法話というのは不特定多数の前で話をします。
すると、”最大公約数”つまり、誰が聞いても当たり障りなく、まぁいい話が前提になってしまいます。これ、私苦手なんですよね。なんか胡散臭い気がしちゃうんです。
もちろん、そんな「いい話」なんてせずに、もっとディープだったり、観点が違ったりしている話もNGって訳じゃないと思うんです。でもね。やっぱりニーズってあるじゃないですか。それを無理に追うと苦しくなってしまうんです。
いつも思うのですが、私が好きなのはたぶん、マイケル・サンデルの授業みたいに「今日は”縁起”について話してみよう。身近な問題として”何故私は今ここに生きているのか?”を”縁起”の教えを通して考えてみたい」的な法話(法話と呼べるのか不明ですが)、すなわち定理(や教理)が前提としてあって、実践的にコール&レスポンスありの会話スタイルと申しましょうか・・・ま、でもとにかく私が勉強しないことには絵空事にすぎませんが・・・。
2.酔ってしまうことを恐れている
これは、もしかしたら司会をされている方とかもそうかもしれないんですが、大勢の前で自分だけ話をする(=アナウンスをする)というのは、みんなが聞いてくれることや、指示通りに動いてくれることに”自己陶酔”しやすいんじゃないかと思うのです。端的に言えば「私がしゃべったことをみんなが真剣に聞いてくれている。もっとしゃべらなきゃ」という感じ。(マイクも使っているから余計に)
真剣に聞いてくれていることに対して真摯に向き合うことは間違っていないんですが、それ以上の変な責任感に燃えるのは間違いだと思います。
だからこそ、それを自戒し警戒してそう思っています。
私事、何故か結婚式の二次会の司会とか幹事とか、今まで何度も何度もやっているんですが、どうしても自分にはその「司会をする(=大勢の前で話す)ことで得られる間違った自己陶酔」を僅かでも感じ取った過去があるので、余計にそう思うのかもしれません。
3.自分がそういう話を望んではいない、のかも。
これはそのまんまの意味です(笑)法話は、質問なしでただひたすら僧侶の話を聞く、というだけではナンセンスな気がしています。
つまり、仏教ってのは、「これこれこういう教理があって、こういう思想があって、こうすればこうなります」的な教えじゃないと感じています。そんな簡単なものだろうか?(違っている可能性大ですが・・・)
「これこれこういう教理があって、こういう思想があるから、今までこうしてきた。だから、とりあえず踏襲してこうしてみる。そして躓いたら考えてまたこうしてみる(以下繰り返し)」が仏教じゃないかと思うのです。(発心修行菩提涅槃というべきか・・・。)
あ・・・今回も偉そうなことをたくさん書きました。ごめんなさい。不説過戒を犯してしまった。反省。

坊さんなのに・・・

実は私は「法話」というものが苦手です・・・。
「法話」というのは要するに、仏教をからめて僧侶がするお話のことなんですが、自分自身が”有り難くない僧侶”(笑)だからか、どうにもこういう”ありがたい話”ってのが苦手で・・・。何か”お涙ちょうだいモノのドラマ”、みたいに感じちゃうんですよね。あ~~こんなこと書いたら偉大なるご先輩方に怒られるんだろうなぁ・・・。すみません、不謹慎で。
でも、一般の方にとっては、この”ありがたい話”こそ、僧侶に対するニーズってのも分かるんです。
何でこんなことを書いているかというと、昨日、葬儀を終えたばかりの檀家さんがお寺に来られました。四十九日(忌明け)の日程などを話して、その後で”中陰”(ちゅういん)の話になりました。「”中陰”というのは何か?」というのは難しい問題ですが、今はごく単純に”亡くなってから四十九日までの間”とご理解ください。
そこで檀家さんとしばらく話をさせてもらったのですが、つくづく自分は”1対1のトークが気楽にできるタイプ”だ、と気づきました。(自分で言うのも何ですが・・・)
どういう事かと言いますと、最初にお檀家さんが「四十九日って閻魔様の裁きを受ける日ですよね?」と聞いてこられたことで、”中陰”の会話がスタート。
もしこれが普通の僧侶なら、中陰についてきちんと勉強してますから、たぶん、学術的な説明(四有とか含め十王思想など)をしたり、或いは逆に「地獄ってのはこういうもので・・・云々」すると思うんですが、私の場合、どうしても知識が浅いというのも手伝って、一方的に滔々と自説を開陳することが出来ず、コール&レスポンス的トークになってしまいます。つまり、この場合、相手がどういう事象を信じているのか、どういうことを知りたくて、どういう事柄までを理解しているのかを、相手の表情や素振りを無意識に判断して話していると思うのです。かっこよく言えば、「相手に合わせて」話しているのでしょうが、たぶん、私の力不足がそうさせているのだと思います(笑)
前にも拙ブログで『魂ってあるの?ないの?』という記事を書きましたが、これなんかもそうで、結局、”ある”と信じている檀家さんにはそれ様に、”ない”と信じている檀家さんにもそれ様に話を変えると思うのです。このように書くと、すごく不誠実な感じがしますが、でも実際その存在の有無を議論しても意味がないというか、そこに本当の仏教があるとはどうしても私には思えないのです。つまり、これは実証実験でもなんでもなく、ただ単に信仰の問題なので、日常生活を送る上で度が過ぎてなければ、或いは他者に目に見えて被害をあたえていなければ”あってもなくても”どっちだっていい訳です。
話が飛びました・・・。今回は2人での会話ですが、もちろん、こうしたシチュエーションでも「法話」とは呼べます。ただ、普通「法話」と言った場合、檀家さん大勢の前でする話を指していて、(当たり前かもしれませんが)ほとんどの僧侶はそれができると思うんです。でも私は苦手。苦手というより敬遠しているというか。で、何でそうなんだろう?と自分で分析してみました。思い当たる節は3つ。
1.最大公約数的な話をしてしまう
・・・仏教の特色って、前にも書きましたが「対機説法」です。対機説法というのは、相手の立場に合わせて話の内容をコントロールして、順々に高度な思想を語っていくというブッダ以来の伝統的スタイルなんですが、逆に一般的な法話というのは不特定多数の前で話をします。
すると、”最大公約数”つまり、誰が聞いても当たり障りなく、まぁいい話が前提になってしまいます。これ、私苦手なんですよね。なんか胡散臭い気がしちゃうんです。
もちろん、そんな「いい話」なんてせずに、もっとディープだったり、観点が違ったりしている話もNGって訳じゃないと思うんです。でもね。やっぱりニーズってあるじゃないですか。それを無理に追うと苦しくなってしまうんです。
いつも思うのですが、私が好きなのはたぶん、マイケル・サンデルの授業みたいに「今日は”縁起”について話してみよう。身近な問題として”何故私は今ここに生きているのか?”を”縁起”の教えを通して考えてみたい」的な法話(法話と呼べるのか不明ですが)、すなわち定理(や教理)が前提としてあって、実践的にコール&レスポンスありの会話スタイルと申しましょうか・・・ま、でもとにかく私が勉強しないことには絵空事にすぎませんが・・・。
2.酔ってしまうことを恐れている
これは、もしかしたら司会をされている方とかもそうかもしれないんですが、大勢の前で自分だけ話をする(=アナウンスをする)というのは、みんなが聞いてくれることや、指示通りに動いてくれることに”自己陶酔”しやすいんじゃないかと思うのです。端的に言えば「私がしゃべったことをみんなが真剣に聞いてくれている。もっとしゃべらなきゃ」という感じ。(マイクも使っているから余計に)
真剣に聞いてくれていることに対して真摯に向き合うことは間違っていないんですが、それ以上の変な責任感に燃えるのは間違いだと思います。
だからこそ、それを自戒し警戒してそう思っています。
私事、何故か結婚式の二次会の司会とか幹事とか、今まで何度も何度もやっているんですが、どうしても自分にはその「司会をする(=大勢の前で話す)ことで得られる間違った自己陶酔」を僅かでも感じ取った過去があるので、余計にそう思うのかもしれません。
3.自分がそういう話を望んではいない、のかも。
これはそのまんまの意味です(笑)法話は、質問なしでただひたすら僧侶の話を聞く、というだけではナンセンスな気がしています。
つまり、仏教ってのは、「これこれこういう教理があって、こういう思想があって、こうすればこうなります」的な教えじゃないと感じています。そんな簡単なものだろうか?(違っている可能性大ですが・・・)
「これこれこういう教理があって、こういう思想があるから、今までこうしてきた。だから、とりあえず踏襲してこうしてみる。そして躓いたら考えてまたこうしてみる(以下繰り返し)」が仏教じゃないかと思うのです。(発心修行菩提涅槃というべきか・・・。)
あ・・・今回も偉そうなことをたくさん書きました。ごめんなさい。不説過戒を犯してしまった。反省。

2011年03月26日
ブログのタイトルを変える(捻る)とアクセス数倍増??
タイトルは、最近の私の疑問ですので、今回の内容とは全く関係ないです。ごめんなさい
さて、気分的に、しっかりした構成の文章が書けなさそうなので、昨日みたいに、種々雑感を記してみます。
ある意味、こういう文章が一番”おてライフ”(=僧侶の日常)っぽいかも・・・意外にこうした日記的なものって書きやすいですね。最近気が付きました(苦笑)
やはりテーマを決めて書くと、確かに頭も使うし、資料をあたったりと、それはそれで充実感があるのですが、今の自分には無理そうです。ご質問などくださった方には、本当に申し訳ないのですが、もう少しお時間ください。
◆すごいぞクロネコヤマト!!◆
一昨日の昼過ぎに仙台へ送った荷物が、もう昨日の夕方には若林区の修行仲間のお寺にとどいたそうです。正直、ビックリしました。彼からのメールは”取り急ぎ到着の報告まで”とあったので、災害に関する詳しい情報はなかったのですが(というか、悠長にメールを打っている暇はないでしょう)、それにしてもこのスピード、クロネコヤマトのスタッフには敬意を抱きます。ありがとうございました。
◆来週から朝日新聞土曜版Beが変わるみたい◆
震災の影響でお休みだった朝日新聞土曜版Beが今日復活しましたね。と、同時にユニクロを擁するファーストリテイリング会長兼社長 柳井正さんとジャーナリスト莫 邦富(モーバンフ)さんのコラムが終了し、来週から新たに3つのコラムが青Beに加わります。
名称も変更で、『青b』と『赤e』になるらしい。
新しいコラムは、【職場の理不尽Q&A】【結婚未満】【野遊び大全】の3つ。
どれも面白そう。やはりボーイスカウト経験者の私としては、九里徳泰さんと阿部夏丸さんが担当される「野遊び大全」に期待します。
九里さんは自転車で世界各地を横断・縦断されていた記憶があります。中高生の時、『Be-Pal』という老舗アウトドア雑誌を毎月買っていた時期があって、野田知祐さんとか田渕義雄さん(←大好きな作家です)とか魅力的な執筆陣で、その中に九里さんもいらっしゃいました。アウトドア熱が再燃しそう!(?)
◆「先入観」とこのブログ◆
今日も何件かご法事があり、おつとめをさせていただきました。
本堂での供養が終わり、お墓に行った時の事。そこでしばらくお若いお施主さまとお話をさせていただきました。
何かの拍子に私が「仏教って聞くと、みなさんほとんどは”葬式”とか”法事”をイメージされて、辛気臭いイメージがあるんですが、実はそれだけじゃないんですよね。本来は”どうやってこの苦しい世の中を生きていくか”っていう教えだと思うんです。でも、一般の方は”葬儀とか法事”という先入観があってそうした考えを受け入れてくださらない。」と申し上げたら、そのお施主様も「先入観、ってありますよね」と言われていました。
結構、これが障壁になるんですよね。仏教や宗教に限らず、あらゆる事象に対してそう。
因みに・・・お若いお施主様だからか、柔軟に、すんなりと私の発言をくみ取ってくださったみたいで、本当にうれしく、またありがたいことだと思いました。私自身は非力だけど、小水の岩を穿つが如くにやっていきます。
で、結局、そのお施主様に私が作ったブログのチラシ(西光寺においてあります、ってここで宣伝しても意味ないか…)をお渡しして、ちゃっかり宣伝しちゃったのですが(笑)、やはり、自分にとってこのブログを続ける原動力は、「葬式や法事だけじゃない仏教」という事を伝えたい、という思いなんです。勿論、それは”葬式”や”法事”を等閑にしているわけではありません。
でも、私が思うに、仏教がまだ生き続けているのは、そしてこれから生き続けるのは、こんな混迷を極める世の中でも、確かな生き方を説ける教えだからと、信じているからです。
まだまだ不勉強だからうまく言葉にできないけれど、少しずつ進めていきたいと思います。

にほんブログ村

さて、気分的に、しっかりした構成の文章が書けなさそうなので、昨日みたいに、種々雑感を記してみます。
ある意味、こういう文章が一番”おてライフ”(=僧侶の日常)っぽいかも・・・意外にこうした日記的なものって書きやすいですね。最近気が付きました(苦笑)
やはりテーマを決めて書くと、確かに頭も使うし、資料をあたったりと、それはそれで充実感があるのですが、今の自分には無理そうです。ご質問などくださった方には、本当に申し訳ないのですが、もう少しお時間ください。
◆すごいぞクロネコヤマト!!◆
一昨日の昼過ぎに仙台へ送った荷物が、もう昨日の夕方には若林区の修行仲間のお寺にとどいたそうです。正直、ビックリしました。彼からのメールは”取り急ぎ到着の報告まで”とあったので、災害に関する詳しい情報はなかったのですが(というか、悠長にメールを打っている暇はないでしょう)、それにしてもこのスピード、クロネコヤマトのスタッフには敬意を抱きます。ありがとうございました。
◆来週から朝日新聞土曜版Beが変わるみたい◆
震災の影響でお休みだった朝日新聞土曜版Beが今日復活しましたね。と、同時にユニクロを擁するファーストリテイリング会長兼社長 柳井正さんとジャーナリスト莫 邦富(モーバンフ)さんのコラムが終了し、来週から新たに3つのコラムが青Beに加わります。
名称も変更で、『青b』と『赤e』になるらしい。
新しいコラムは、【職場の理不尽Q&A】【結婚未満】【野遊び大全】の3つ。
どれも面白そう。やはりボーイスカウト経験者の私としては、九里徳泰さんと阿部夏丸さんが担当される「野遊び大全」に期待します。
九里さんは自転車で世界各地を横断・縦断されていた記憶があります。中高生の時、『Be-Pal』という老舗アウトドア雑誌を毎月買っていた時期があって、野田知祐さんとか田渕義雄さん(←大好きな作家です)とか魅力的な執筆陣で、その中に九里さんもいらっしゃいました。アウトドア熱が再燃しそう!(?)
◆「先入観」とこのブログ◆
今日も何件かご法事があり、おつとめをさせていただきました。
本堂での供養が終わり、お墓に行った時の事。そこでしばらくお若いお施主さまとお話をさせていただきました。
何かの拍子に私が「仏教って聞くと、みなさんほとんどは”葬式”とか”法事”をイメージされて、辛気臭いイメージがあるんですが、実はそれだけじゃないんですよね。本来は”どうやってこの苦しい世の中を生きていくか”っていう教えだと思うんです。でも、一般の方は”葬儀とか法事”という先入観があってそうした考えを受け入れてくださらない。」と申し上げたら、そのお施主様も「先入観、ってありますよね」と言われていました。
結構、これが障壁になるんですよね。仏教や宗教に限らず、あらゆる事象に対してそう。
因みに・・・お若いお施主様だからか、柔軟に、すんなりと私の発言をくみ取ってくださったみたいで、本当にうれしく、またありがたいことだと思いました。私自身は非力だけど、小水の岩を穿つが如くにやっていきます。
で、結局、そのお施主様に私が作ったブログのチラシ(西光寺においてあります、ってここで宣伝しても意味ないか…)をお渡しして、ちゃっかり宣伝しちゃったのですが(笑)、やはり、自分にとってこのブログを続ける原動力は、「葬式や法事だけじゃない仏教」という事を伝えたい、という思いなんです。勿論、それは”葬式”や”法事”を等閑にしているわけではありません。
でも、私が思うに、仏教がまだ生き続けているのは、そしてこれから生き続けるのは、こんな混迷を極める世の中でも、確かな生き方を説ける教えだからと、信じているからです。
まだまだ不勉強だからうまく言葉にできないけれど、少しずつ進めていきたいと思います。
にほんブログ村